2024年から始まった相続税増税の全貌! 税制改正の影響と対策を徹底解説
2025.05.04
2023年度の税制改正で相続税が大きく見直されました。相続税の加算期間延長や基礎控除の新設などがあり、厳しい財政事情を背景として増税志向が顕著となっています。
富裕層に対する課税強化の方向が明確となっていますので、まとまった相続財産が残る見込みの方は、今回の改正について理解しておく必要があります。
2023年の税制改正によって相続税の仕組みがどのように変わったのか、また不動産投資家にとってどのような節税対策が有効なのかについて、わかりやすく解説します。
▼この記事の内容
●2023年度に改正され、2024年から開始された改正相続税に注意する必要がある。相続税の加算期間が死亡前3年から7年に延長され、生前贈与による相続税節税を行うには、より計画性が求められるようになった。
●生前贈与時に発生する贈与税を相続時に精算する仕組みの「相続時精算課税制度」に基礎控除110万円が新設され、制度の利用がさらに柔軟になった。
●教育・結婚・子育て資金の一括贈与制度の期限が延長され、引き続き多くの人がこの制度を利用できるようになった。
●相続税は今回の改正の前、2015年に大改正があり、大幅増税となった。基礎控除額が引き下げられ、税率も引き上げられた。このことにより、相続税が課税される人が倍増した。
●賃貸不動産は実勢価格ではなく、相続税路線価・固定資産税評価額によって評価され、さらに借地権割合・借家権割合・賃貸割合によって割り引かれるため、相続税評価額が低く抑えられる。
目次
2024年から始まった税制改正のメリット・デメリットとは? 相続税が注目される理由

2023年度の税制改正によって相続税がどのように変わったのでしょうか。
今回の改正では相続税と関連する贈与税が主な対象となっています。改正が行なわれた社会的背景を含めて理解しておきましょう。
改正により注目される具体的なポイント
2023年度の相続税に関する改正点(開始は2024年1月1日から)をまとめると、以下の3つが大きな変更点となっています。
➀相続時精算課税における基礎控除の新設
②暦年課税の相続税加算期間の死亡前3年以内から7年以内への延長
③教育・結婚・子育て資金の一括贈与の期限延長
主に贈与税に関する改正が中心です。贈与税は相続税とも深く関連するため、相続税対策のうえでも重要な変更となっています。
活用方法が変わった制度もありますので、特に重要な3つの改正点について後ほど解説します。
高齢化と財政問題が背景に
今回の税制改正の背景には、少子高齢化社会による社会保障費の増加を背景とした財政のひっ迫と、滞留状態になりがちな高齢者の資産を次世代に移転させたいといった政策方針の意図があります。
これまであまり利用されなかった「相続時精算課税制度」の利用促進、生前贈与の加算期間延長による贈与税の実質的な課税強化などが注目すべき改正ポイントとなっています。
税の仕組みは従来より複雑化していますので、制度を理解したうえで、自分の状況にあった節税対策を準備しなければなりません。今後も細かな制度変更などは適宜実施される可能性があるため、情報をつねにアップデートしておく必要があります。
相続税加算期間が死亡前3年から7年に延長
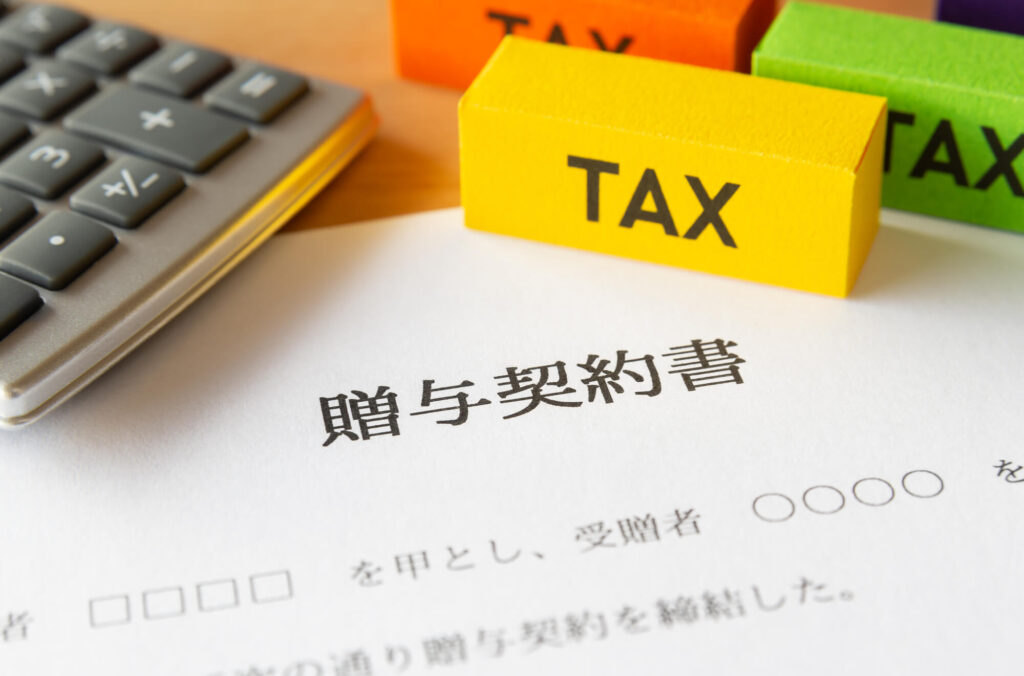
2023年の税制改正のうち、実質的な課税強化となっているのが生前贈与の相続税加算期間延長です。生前贈与を行う際にはこれまで以上に計画的なプランニングを行う必要性が増しました。
加算期間延長の具体的な内容
相続税の節税対策の1つに、生前贈与の利用があります。1年あたり110万円まで基礎控除枠となることを利用し、生前から毎年少額ずつの贈与を続け、来るべき相続財産を縮小させる方法です。
仮に生前贈与によって相続財産をすべて移転されてしまうと、相続税を徴収できなくなります。これは相続税を回避する行為なため、亡くなる3年前までに行われた贈与は相続財産に加算される、いわゆる「3年ルール」が設定されていました。
このルールが今回の改正によって、3年から7年までに延長されています。
具体的には、被相続人のなくなる3年前までの生前贈与は従来と同じく相続財産に加算されますが(贈与税の基礎控除である年間110万円分も含めて加算)、今回の変更対象となった4年から7年前までの贈与に関しては、該当期間中の贈与額から100万円を控除した額が加算の対象となっています。
例えば亡くなる7年前から毎年年間110万円の生前贈与があった場合、4~7年前の贈与分440万円から100万円を控除した340万円と、3年前までの贈与分330万円、合計670万円が相続財産に加わるということです。
従来は3年前までの330万円だけが加算されていたので、実質的に相続税の増税ともいえる変更です。
生前贈与に与える影響
相続財産に関する生前贈与の対象期間が延長され、死亡直前の一定期間に節税目的での財産贈与に対して制限がかかったといえます。
また、多額の相続財産を保有する方の場合、長期にわたって生前贈与の基礎控除額(年間110万円)内で資産を毎年移転する対策を取られていましたが、7年前から課税対象となる今回の改正で節税効果は薄れてしまっています。
うまく相続税対策を行うためには、これまで以上に早期の財産移転を開始する必要があります。その場合はかなり長期的なスパンで生前贈与を行わなければなりません。
なお、今回の税制改正の対象となる贈与は2024年1月1日以降の生前贈与です。それ以前の生前贈与については、従来と同じ3年以内の贈与が加算の対象となります。
計画的な贈与の重要性
このように生前贈与を利用して相続税対策を行う場合は、かなり早い段階から生前贈与の計画を立てる必要が生じています。税理士など専門家と相談し、長期的な視点から節税対策を講じなければなりません。
これから解説する教育・結婚・子育てを目的とした一括贈与や、相続時精算課税制度への移行も検討してみましょう。
相続財産の中身によっては生前贈与ではなく、相続税に関する各種控除の利用や、「小規模宅地等の特例」など、相続税に関する制度を活用したほうが大幅な節税になることもあります。他の制度とのバランスを見ながら、最適な方法を選択することが重要です。
相続時精算課税に基礎控除110万円が新設

今回の税制改正によって、従来より利用しやすくなったのが「相続時精算課税制度」です。これまではあえてこの制度を利用するメリット面が薄かったのですが、今回の改正で基礎控除枠110万円が新設されたことで、柔軟な制度運用が可能となっています。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、生前贈与で本来発生する贈与税支払い分を相続発生時に精算する課税制度です。いわば贈与税を相続時に後払いする仕組みといえます。
具体的には、贈与者から贈与された財産につき、2,500万円の特別控除枠までの贈与分については非課税となります(2,500万円以上の贈与分については一律20%の贈与税がかかります)。
非課税となった贈与税支払い分は消滅したのではなく、贈与者の死亡時に相続財産の一部へと持ち戻しされてしまうのです。贈与税の支払いを相続税の一括払いへと後ろ倒しできるに過ぎず、節税にはつながりませんでした。
贈与者は原則60歳以上の方に限られるので、若い世代の方は活用できないといったデメリットもありました。正直なところ、これまでは積極的に利用されたとは言い難い制度です。
基礎控除新設の意義
そこで2023年の税制改正において相続時精算課税制度の利用促進を目的に、基礎控除枠が新たに創設されました。基礎控除枠は年間110万円となり、従来からの特別控除枠の2,500万円とは別枠で新たな非課税枠が増えることになります。
具体的には、毎年の贈与財産から基礎控除110万円分を控除し、110万円を超える贈与財産は累計2,500万円まで特別控除枠が適用される流れとなります。特別控除枠を超える部分については一律20%の課税で、ここは従来と同じです。
申告の手間も軽減されています。これまでは少額であっても贈与財産があれば毎年申告を行なう必要がありましたが、改正後は基礎控除内での贈与に関しては申告が不要となりました。
これまでの利用されていた暦年贈与の仕組みを相続時精算課税制度に組み込んだかたちといえるでしょう。より柔軟に相続財産の移転を促進させるために、本制度の利用を促そうという政策意図が読み取れる改正です。
改正を活用した具体的な対策
仮に2年間、毎年500万円の贈与を行ってから贈与者が死亡したケースを想定し、従来の制度と比較してみましょう。
【従来の相続時精算課税制度の場合】
贈与税の対象額は1年間の贈与額(500万円)は特別控除枠(2,500万円)の対象となりますので、贈与税は非課税です。しかし2年間トータルでの贈与額1,000万円はそのまま相続財産に組み込まれます。
【改正後の相続時精算課税制度の場合】
贈与税対象額となる年間500万円から基礎控除110万円を差し引いた390万円が相続税対象額となります。もちろん特別控除枠(2,500万円)内に収まるので相続税は非課税です。さらに相続財産として組み込まれる相続財産は390万円×2年間で780万円となり、従来のケースであった1,000万円と比べると220万円分が非課税となったことがわかります。
このように基礎控除110万円の存在によって、長期間贈与を行えば行うほど相続財産に組み込まれる贈与税対象分を少額にできる仕組みとなりました。
ただし、制度を利用するには贈与者が60歳以上であることなどの要件を満たす必要があります。この点に変更はありません。
教育・結婚・子育て資金の一括贈与の期限延長

親から孫の教育資金のためにと子育て世代に対して贈与を行う際に、一定条件のもとで非課税となる特例制度があります。本特例制度は2024年3月31日までの期限が設定されていましたが、制度の適用期間が延長されることになりました。
制度の基本的な仕組み
「教育資金贈与に対する非課税特例」とは、直系尊属(祖父母や父母)から子どもの教育資金のために30歳未満の方が贈与を受けた場合に、贈与額1.500万円までを非課税とする制度です。教育資金には学校の授業料や教材費などが含まれます。
「結婚・子育て資金贈与に対する特例制度」は、18歳以上50歳未満でかつ所得額1,000万円以下の方が、直系尊属(祖父母や父母)から結婚資金や子育て資金のための贈与を受けた場合に、結婚資金は受贈者一人あたり300万円、子育て資金は受贈者一人あたり1,000万円までが非課税となる制度です。
結婚資金は挙式費用や新生活の準備費用、子育て資金には妊娠・出産などにかかる費用や保育所や幼稚園にかかる保育費用などが含まれます。
期限延長の背景と意義
税制改正の目的には相続財産を次世代へと積極的に移転させる意図があるため、教育や子育て、結婚費用のための贈与制度の利用拡大を狙った利用期限の延長が決定しました。
まず結婚・子育て資金の一括贈与に対する非課税特例は、本来2023年3月31日で終了する予定となっていましたが、2025年3月31日まで2年間延長されます。
また、教育資金のための一括贈与に対する非課税特例も同様の期限が迫っていましたが、こちらは3年間延長の2026年3月31日まで期限が延びました。
この非課税特例は、ある程度まとまった必要資金を一括で贈与しておきたい場合に有効となる制度です。ただし、細かな要件や税額の計算が複雑なので、利用するうえでは専門家と相談して計画的に活用する必要があります。
少額のお小遣い程度の援助ならそもそも贈与税がかかりませんので、興味のある方は本制度を利用する必要があるかも含めて検討してください。
制度を活用する際の注意点
本制度を利用する際には、贈与資金が適切に使用されていることを証明する書類が必要です。例えば結婚・子育て資金の一括贈与だと、金融機関と資金管理契約を結んだうえで専用口座を開設し、金融機関を通じて非課税申告書を作成しなければなりません。また、口座から引き出した資金については領収書を金融機関に提出する必要があります。
受贈者が50歳になった、あるいは死亡した、口座残高が0となって契約終了の合意をした場合も非課税特例の適用が終了します。贈与者となる父母や祖父母が途中で死亡した場合は、資金口座に残った残額分が相続税の課税対象額に組み込まれるケースも発生します。
ご家族の状態や資産状況に合わせて利用を検討する必要がありますが、気になる方は税理士などの専門家とよく相談して取り組みましょう。
富裕層だけではない! 相続税の大増税となった2015年の大改正
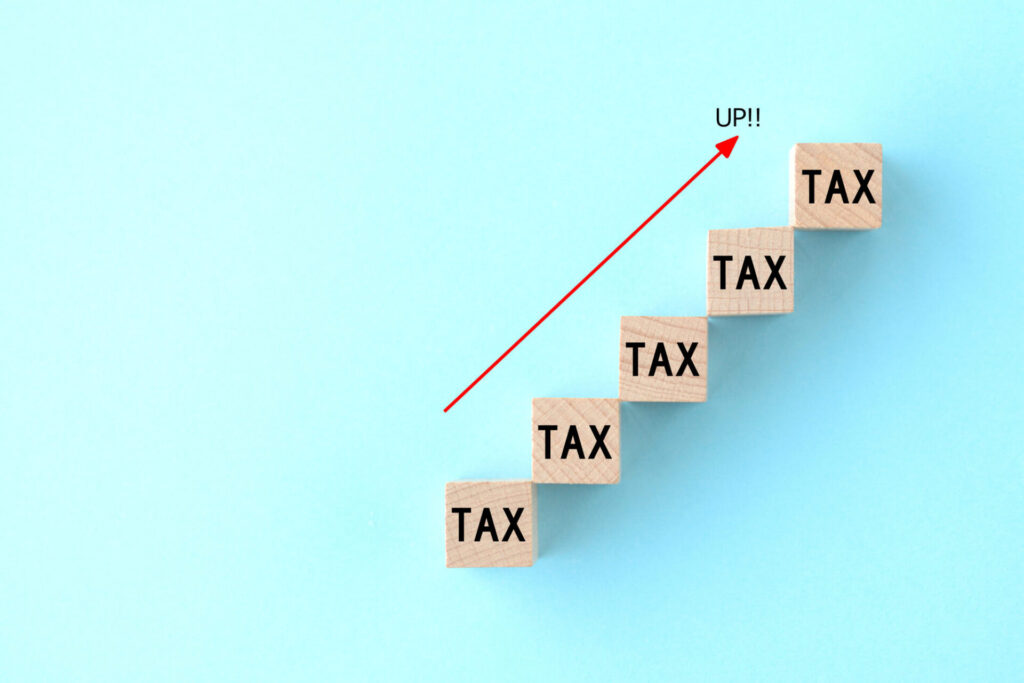
税制改正は毎年のように行われています。近年で大きな影響があったのが2015年の相続税の大改正です。あらためて2015年の相続税改正について解説します。
相続税が課税される人が倍増
国税庁の報告によると、税制改正が行われた2015年に課税対象となった被相続人の数が前年の56万人から103万人へと倍増していることがわかりました(※)。その大きな理由となったのが、相続税の課税対象とならない「基礎控除額」の引き下げです。これまで課税対象とならなかった層に対しても課税対象が拡大しました。
相続時精算課税や結婚・教育・子育て資金への一括贈与の非課税特例などを促進する一方で相続税の課税強化の方針は連動した動きとなっていますので、今後もこうした傾向は続くものと予想されます。
基礎控除額の引き下げ
相続税がかかるかどうか決定づけるのが基礎控除額の存在です。基礎控除額のラインは相続税計算ではきわめて重要です。
この基礎控除額は2015年の税制改正によって、以下のように引き下げられました。
改正前の基礎控除額:5,000万円+1,000万円×相続人
改正後の基礎控除額:3,000万円+600万円×相続人
仮に父・母・子ども2人の4人家族で、父がなくなり、母子3人の相続が発生したとします。
改正前の基礎控除額は
5,000万円+1,000万円×3=8,000万円
一方、改正後の基礎控除額は
3,000万円+600万円×3=4,800万円
となります。つまりこのケースでは改正前までは相続財産8,000万円までは相続税がかからなかったのですが、改正後は4,800万円まで控除額が縮小してしまったのです。
税率の引き上げ
さらに影響があったのが「相続税率の引き上げ」です。特に富裕層には大きな影響がある改定となっています。
改正後の相続税率・早見表
| 相続した取得金額 | 改正前の税率(2014年12月末) | 改正後の税率(2015年1月以降) | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | 10% | なし |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 30% | 30% | 700万円 |
| 1億円超~2億円以下 | 40% | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超~3億円以下 | 40% | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超~6億円以下 | 50% | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超~ | 50% | 55% | 7,200万円 |
出典:国税庁 相続税の税率
相続財産2億円超〜3億円以下の方が40%から45%に、6億円超の方が50%から55%に変更となりました。
相続税は、相続財産の価額が大きくなればなるほど税率が上がる「超過累進課税」です。超過累進課税とは、相続した取得金額が増えるにつれて、その増加分に対してのみ段階的に高い税率が適用される課税方式です。
超過累進課税は計算が複雑になるため、上記の早見表を使って計算します。相続した取得金額に税率を掛け、控除額を差し引くことで税額を求められます。
相続税の各人ごとの税額控除と加算
相続税には相続財産全体に対して適用される基礎控除のほか、法定相続人それぞれの要件ごとに適用される控除や特別加算の仕組みがあります。代表的な制度について解説します。
配偶者控除

1つめは「配偶者控除」です。被相続人(亡くなられた方)の配偶者(夫・妻)の相続税課税価格が「1億6,000万円」あるいは「法定相続分に相当する額」までの場合、相続税は非課税となります。
例えば夫が亡くなり、課税対象となる相続税課税価格が4億円とします。
妻の法定相続分は2億円です。これは配偶者控除枠1億6,000万円を上回っています。しかし、遺産分割協議などを経た後に妻の相続税課税価格が法定相続分2億円で決まった場合、「法定相続分に相当する額」までに相当するので相続税は非課税となるのです。
この配偶者控除枠は非常に強力で、相続人である配偶者が相続税を支払うケースは極めてまれといえます。ただし、支払う相続税額がゼロの場合でも相続税の申告そのものは必要です。
未成年者控除
相続で財産を取得した方が18歳未満である場合は、その方が18歳に達するまでの年数1年につき10万円が相続税額から控除されます。
例えば相続発生時に15歳6ヶ月だったとしましょう。
この場合、15歳6ヶ月を15歳として計算するので、
(18歳-15歳)×10万円=30万円
合計30万円が未成年控除額となります。
障害者控除
相続で財産を取得した方が障害者である場合、85歳に達するまでの年数1年につき10万円が控除額となります。
例えば相続人が相続時に15歳6ヶ月の普通障害者だった場合、相続税の控除額は
(85歳-15歳)×10万円=700万円
が控除額となります。
重度の障害をお持ちの特別障害者の場合は1年につき20万円の控除額です。
兄弟姉妹の2割加算
被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹が相続人となった場合、計算した相続税額にさらに20%を上乗せする2割加算の対象となります。
被相続人の兄弟が相続人となるケースは、被相続人に子どもや直系尊属(父や母、祖父母など)がいない事例です。法律上、兄弟姉妹は2親等にあたり、1親等内の血族(親や子ども)と比べて関係性が1段階違います。このことから、相続税の税負担の公平性を保つために兄弟姉妹の相続税額に対して2割加算を課しているのです。
注意したいのが、本来の相続人(被相続人の子どもなど)が相続放棄をした結果、兄弟姉妹が相続人となるケースです。
相続財産にマイナス資産が多い場合や、多額の相続税を支払えないなどの理由で相続人が相続放棄することがあります。次順位にあたる兄弟姉妹にとっては思いがけないタイミングで相続が発生することになりますが、このような事例でも兄弟姉妹に課される相続税は2割加算です。
相続放棄によって相続人となった場合は、その次順位の相続人が相続手続きを行わなければならないので、速やかに税理士などに相談して対応する必要があります。
孫の2割加算

孫については少し注意すべき事例があります。
本来、被相続人の孫が代襲相続する場合は2割加算の対象ではありません。しかし、相続前に被相続人が孫と養子縁組をする、いわゆる「孫養子」という事例には注意が必要です。孫との養子縁組とは、財産を子どもではなく直接孫に相続させたい場合に、孫を実子と相続順位が同じ「養子」にするために行う法的手続きです。
養子縁組をした「孫」が相続財産を承継する場合、相続税額2割加算の対象となります。孫を養子にしてしまうことで、実質的に被相続人の子どもへの相続を1段階スキップできてしまうことになるため、相続税負担の公平性を守るため孫養子への2割加算が設定されているのです。
他人に遺贈する場合の2割加算
2割加算の対象者は一親等内の血族と配偶者以外の方になりますので、血族関係にない方へ相続財産を移転する「遺贈」を受けた方は2割加算の対象となります。
よくあるケースは、内縁の妻など、実質的な夫婦生活を営んでいても法的な婚姻関係にない方です。内縁関係でも法律上は第三者と変わらないので、法定相続分はありません。
内縁関係にある方のほかにも、血族以外の方への遺贈や慈善団体などへの遺贈についても相続税は2割加算です。
相続税改正の対策は賃貸不動産で

相続税に関する税制改正は今後も行われる可能性は高く、方向性としては課税を強化する傾向が見られます。
仮に今後も相続税の課税が強化されたとしても、対応できる相続税対策が必要となります。数ある対策の中でも、賃貸不動産を活用した相続税対策は効果的といえます。
相続税評価額を圧縮できる
相続税は相続財産の相続税評価額をもとに算出されます。相続税評価額の計算では、現金や預貯金、有価証券などは時価100%そのままの金額が相続税評価額です。
不動産は実勢価格(時価)がそのまま相続税評価額になるのではなく、土地は相続税路線価、建物は固定資産税評価額をベースとした評価額で算定されます。
時価の6~7割ほどに抑えられることが多いため、実際の資産価値よりも低い評価額で相続税が計算される点が大きなポイント。この計算方法こそが不動産は相続税対策に強いとされる大きな理由です。
賃貸不動産の場合はこれに加えて借家権割合・借地権割合・賃貸割合という計算方法があるため、相続税評価額をさらに低く抑えられる可能性が高くなります。
土地部分の相続税評価額
土地部分の相続税評価額は「路線価方式」あるいは「倍率方式」で計算されます。一般的に市街地や住宅地で採用されるのが路線価方式で、土地の面している道路ごとに決められている1平米当たりの路線価をもとに、各種の補正率などを乗算して計算する方式です。
基本的な計算方法は次のとおりとなります。
•土地の相続税評価額の計算式(路線価方式の場合)
相続税評価額=路線価×各種補正率×土地面積
各種補正率とは、土地の形状や傾斜の程度、坂やがけの近くなどの周辺環境に応じて定められている補正率のことです。おおよそ土地部分の相続税評価額は時価の70%程度となります。
さらに賃貸不動産の土地部分に関しては「借家権割合・借地権割合」と「賃貸割合」といった補正を乗算します。
•賃貸不動産の土地部分の計算式
更地としての評価額×(1-借家権割合×借地権割合×賃貸割合)
路線価、あるいは倍率方式で計算した更地としての評価額に加え、借家権割合、借地権割合、賃貸割合による乗算によってさらに評価額を縮小させることが可能です。
借家権割合は一律で30%、借地権割合は30~90%、賃貸割合は物件の賃貸に出している割合に応じて決まります。
建物部分の相続税評価額
建物部分については再建築価格×減点補正率(経年劣化などを考慮した補正率)で固定資産税評価額が決まります。通常、建物部分についても時価の60~70%程度の価額です。
この固定資産評価額に次のような補正率を乗算し、建物の相続税評価額が計算されます。
・賃貸不動産の建物部分の計算式
建物の固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
ここでも借家権割合は一律で30%、賃貸割合は物件の賃貸に出している割合となります。
賃貸割合は、課税時に賃貸されている各独立部分の床面積の合計÷建物の各独立部分の床面積合計です。アパート一棟なら稼働中の部屋の床面積に全室の床面積の合計で割った数値となるので、仮に満室であれば100%となります。
ローンが債務控除になる
賃貸不動産の経営は通常、金融機関から融資を受けて運営します。不動産投資は、家賃収入から毎月のローン返済額や各種の経費を引いた残りが実質的な収益となります。
相続税の節税対策において真価を発揮するのが、金融機関からの不動産投資ローンです。相続財産には、プラスの資産だけでなく借金などのマイナス資産も計上されます。収益物件を新築、あるいは購入する際の金融機関からの債務残高もマイナス資産として相続財産に組み込まれるので、相続税の対象となる相続税評価額を大幅に縮小させることができるのです。
例えば、賃貸経営をされている方が次のような資産を残して亡くなった場合、
現金:1,000万円
保有する不動産の相続税評価額:1億円
不動産投資ローンの残高:3,000万円
相続税評価額は
1,000万円+1億円−3,000万円=8,000万円
となります。現金資産など他の財産も含めた相続財産から大幅な評価額の縮小につなげることが可能です。
まとめ

2023年度の相続税改正では、富裕層への課税強化の方向性が明確となっています。ある程度まとまった資産を保有する方にとって相続税対策は必須です。専門家のアドバイスを受けながら適切な対策を講じる必要があります。
相続税の節税対策には不動産投資が効果的です。信頼できる賃貸管理会社が味方につけば、相続税対策と資産拡大の両面で成功する確率が上がります。
管理戸数と賃貸仲介数の豊富な実績を誇る【リロの不動産】は、収益不動産の相続税対策についての知見も豊富です。あらゆる分野の専門家と連携し、オーナー様ひとりひとりにあった最適なプランをご提案しております。
相続税対策のために不動産投資をお考えの方は、ぜひ【リロの不動産】までご相談ください。
関連する記事はこちら
相続税を抑える決め手は?不動産評価制度の仕組みと注意点を解説
不動産の活用で相続税対策! 賃貸経営・アパート経営が効果的な理由と注意点
マンションの相続税を把握!評価額と節税対策の特例・注意点を解説
不動産購入が相続税対策になる理由!物件種類別の節税対策と注意点を解説
相続税が払えない地主になる前に!納税資金対策の物納・延納・生前対策を解説
不動産を相続するには誰に相談すればよいのか? 相続手続きの期限も解説
不動産物件を相続するときの手続きとは? 相続税を払えない場合はどうする?
アパートは相続税対策に有効! 相続税計算でメリットを検証・解説付き
アパート経営は相続対策に有効!資産管理会社の活用でメリット拡大
アパート相続の流れと注意点 賃貸経営継続か売却かの判断基準とは?
マンション相続の手続きとトラブル防止の事例!手順・税金計算も解説
相続した不動産の売却手順!売却基準や注意点・税金の特別控除も解説
おすすめのサービス
おすすめのお役立ち情報
この記事を書いた人
秋山領祐(編集長)
秋山領祐(編集長)
【生年月日】昭和55年10月28日。
【出身地】長野県上田市。
【趣味】子供を見守ること。料理。キャンプ。神社仏閣。
【担当・経験】
デジタルマーケティングとリブランディングを担当。
分譲地開発のPMや家業の土地活用などの経験を持つ。
リノベした自宅の縁の下に子ども達の夢が描かれている。





















