不動産相続で弁護士は必要?トラブル回避ポイント&弁護士依頼のメリット
2025.08.03
不動産を相続すると、遺産分割や相続税の納税など、さまざまな課題に直面します。相続人同士で意見がまとまらない場合や、法律の知識が必要な場面では、弁護士に依頼することで相続がスムーズに進められることもあります。
しかし、すべてのケースで弁護士が必要とは限らず、依頼のメリット・デメリットを理解したうえで判断する必要があります。
この記事では、不動産相続における弁護士の役割やトラブルを防ぐポイント、依頼する際の注意点について詳しく解説します。
▼この記事の内容
●弁護士に依頼する際の費用は、初回相談時にかかる費用、依頼時に発生する着手金、
成功報酬がある。弁護士によって費用は異なるが、かつての日本弁護士連合会報酬等基準が目安になる。
●不動産の相続を弁護士に依頼するメリットとしては、①遺産分割時など法律の専門知識を活かした適切なアドバイスを受けられる、②適正な不動産評価のサポートしてもらえる、③法的トラブルのリスクを回避できる、④登記申請や税務申告などの煩雑な相続手続きを代理で進めてもらえる、などがある。
●不動産の相続を弁護士に依頼するデメリットとしては、①弁護士費用が発生するためコストがかかる、②相続の状況によっては弁護士が不要なケースもある、などがある。
●弁護士依頼に関してトラブル回避のポイントとしては、①不動産相続に関する豊富な経験と実績を持つ弁護士を選ぶ、②収益物件の相続に詳しい弁護士を選ぶ、③税理士や司法書士との連携が可能か確認する、④料金体系が明確な弁護士を選ぶ、⑤法律の知識がない人にも丁寧に説明してくれるか確認する、⑥迅速な対応ができる弁護士を選ぶ、⑦複数の法律事務所を比較し相見積もりを取る、などがある。
目次
弁護士に依頼する際の費用
弁護士に依頼すると、相談料や着手金、報酬金などの費用が発生します。依頼内容や弁護士事務所によって金額が異なるため、事前に費用の仕組みを理解しておくことが大切です。ここでは、不動産相続で弁護士に依頼する際の費用の種類や注意点について解説します。
初回相談時にかかる費用を確認する
弁護士に相談する際、最初に確認すべきは相談料です。法律事務所ごとに料金が異なるため、事前に確認しておきましょう。
かつて、日本弁護士連合会は「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」という目安を定めており、弁護士の相談料や報酬額の基準がありました。旧基準では、初回の法律相談料は30分あたり5,000円〜1万円、一般的な法律相談では最大2万5,000円以下とされていました。現在はこの基準は廃止されていますが、一部の法律事務所では参考にして料金を設定している場合があります。
現在の相場としては、30分あたり5,500円(税込)が一般的です。ただし、法律事務所ごとに料金が異なり、初回相談を無料で受けられる事務所もあります。そのため、複数の事務所を比較し、相談しやすい弁護士を見つけるというのも選択肢の1つです。
依頼時に発生する着手金の相場を把握する

弁護士に正式に依頼する際、最初に支払うのが「着手金」です。これは、弁護士が具体的な業務に着手するための費用で、案件の複雑さや相続財産の規模によって金額が異なります。
着手金は、相続トラブルの代理交渉や遺産分割協議の進行を弁護士に依頼する際に発生し、一般的な相場は20万〜30万円程度とされています。ただし、遺産額が大きい場合や、相続人間の対立が深刻な場合は、それ以上の金額がかかることもあります。
かつて『(旧)日本弁護士連合会報酬等基準』で以下のように定められていました。
| 300万円以下 | 8% |
| 300万円超~3,000万円以下 | 5%+9万円 |
| 3,000万円超~3億円以下 | 3%+69万円 |
| 3億円超 | 2%+369万円 |
現在は法律事務所ごとに料金を自由に設定できるため、必ず事前に金額を確認しましょう。
成功報酬としての費用が発生するケースもある
弁護士に相続手続きを依頼した場合、相続が完了した際に「成功報酬」としての費用が発生することがあります。成功報酬の金額は、かつて「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」によって、以下のように決められていました。
| 300万円以下 | 16% |
| 300万円超~3,000万円以下 | 10%+18万円 |
| 3,000万円超~3億円以下 | 6%+138万円 |
| 3億円超 | 4%+738万円 |
現在はこの基準は廃止されていますが、今でも参考にする弁護士は多く、相場の目安となっています。
成功報酬は、銀行振込や現金手渡しのほか、弁護士が取得した金額から差し引かれる場合もあります。
不動産の相続を弁護士に依頼するメリット
不動産相続では、法的な手続きや相続人同士の調整が必要になり、対応を誤るとトラブルに発展することもあります。一方で、自分たちで解決できるのでは?と思う方もいるでしょう。ここでは、弁護士を依頼するメリットについて解説します。
遺産分割時など法律の専門知識を活かした適切なアドバイスを受けられる
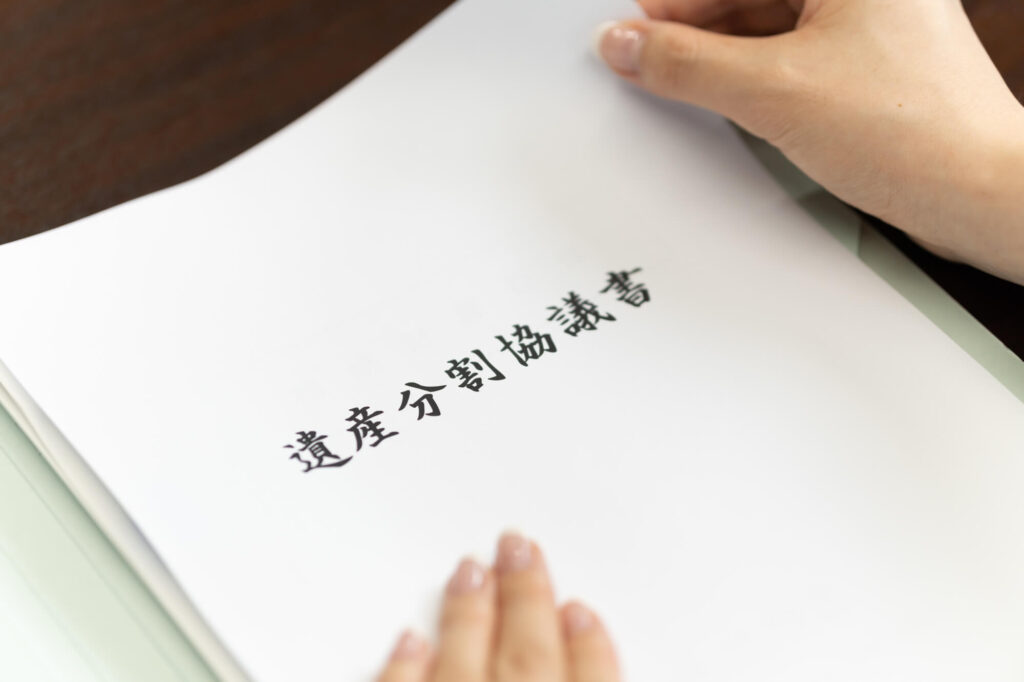
不動産を含む相続では、遺産の分け方をめぐって相続人同士の意見が対立し、トラブルに発展することが少なくありません。弁護士に依頼すれば、法律の専門知識をもとに、状況に応じた分割方法を提案してもらえます。
相続財産の分割方法には、主に以下の4つがあります。
| 現物分割 | 不動産や預貯金などをそのままの形で分ける方法(例:長女が不動産を、次女が預貯金を相続する) |
| 代償分割 | 特定の相続人が財産を取得し、他の相続人へ現金を支払う方法(例:兄が自宅を相続し、妹に代償金を支払う) |
| 換価分割 | 遺産を売却し、売却代金を分配する方法(例:空き家を売却し、売却益を相続人で分ける) |
| 共有分割 | 不動産を相続人の共有名義にする方法(例:兄妹で2分の1ずつ所有する) |
どの方法を選ぶかは、相続人の希望だけでなく、遺産の種類によっても異なります。また、分割方法によって相続税の負担が変わることもあるため、税金面を考慮したアドバイスを受けられる点も、弁護士に依頼するメリットの1つです。
適正な不動産評価のサポートをしてもらえる
不動産の価値は評価方法によって大きく変わるため、相続人同士で意見が合わないことも少なくありません。弁護士は不動産会社や税理士などと連携し、公正な評価のもとで相続人全員が納得した形で分割できるようサポートします。
不動産の評価方法には、主に以下の3種類があります。
| 土地:路線価方式 | 国税庁が定める路線価をもとに評価(市街地の土地に適用) |
| 土地:倍率方式 | 固定資産税評価額に一定の倍率をかけて算出(路線価が設定されていない土地に適用) |
| 建物:固定資産税評価額 | 建物の価値を決める基準として使用 |
不動産の相続税評価額は実勢価格よりも低くなります。そのため、相続人に不動産を相続する人と不動産以外の財産を相続する人がいる場合、相続税評価額と実勢価格に差が生じるため、相続人間のトラブルにつながることがあります。
弁護士は、相続人それぞれの意向を整理し、意見の食い違いを解決へ導く役割を担います。売却せずに不動産を相続する場合も、弁護士に依頼することで後のトラブルを防げる点はメリットといえるでしょう。
法的トラブルのリスクを回避できる

遺産の分け方や権利関係について意見が食い違うと、話し合いが進まず、感情的な対立につながることも少なくありません。法律の専門家である弁護士に依頼すれば、相続人同士の対立や第三者からの不当な請求を防ぐことができます。
収益不動産を含む相続では、家賃収入の配分や管理をめぐって争いが起こりやすい傾向があります。弁護士が間に入ることで、感情的な対立を避け、冷静に話し合いを進められるでしょう。
弁護士が法的な視点から解決策を示すことで、相続人全員が納得しやすくなるのも大きなメリットです。遺産分割協議や相続放棄などの手続きも正しく進められ、後から「手続きに不備があった」と問題になるリスクも減らせます。
相続は親族間の関係が関わるため、一度こじれると修復が難しく、長期化しやすい問題です。弁護士に相談することで、不要なトラブルを避けながら円滑に相続を進められるでしょう。
登記申請や税務申告などの煩雑な相続手続きを代理で進めてもらえる
不動産相続には、登記申請や税務申告など専門的な手続きが多く、必要書類の準備にも手間がかかります。相続人だけで対応するのは負担が大きいため、弁護士に相談することでスムーズに進められます。
弁護士自身が登記申請や税務申告を行うことはできませんが、信頼できる司法書士や税理士と連携し、手続きを一括して進めてもらえるでしょう。
不動産の名義変更を行う相続登記は、2024年4月から義務化されており、期限内に申請しないと過料が科される可能性があります。また、相続税の申告は相続発生を知った翌日から10ヶ月以内に行う必要があり、期限を過ぎると延滞税が発生することもあるため、早めに対応することが重要です。
相続手続きを円滑に進めるには、それぞれの専門家と連携することが欠かせません。弁護士に相談すれば、司法書士や税理士と連携したワンストップ対応が可能になり、複雑な手続きを一括して進められるため、相続に伴う負担を大きく軽減できるでしょう。
不動産の相続を弁護士に依頼するデメリット
弁護士に依頼することで相続の手続きを円滑に進められる一方で、注意すべき点もあります。依頼を検討する際は、メリットだけでなくデメリットも踏まえたうえで判断することが大切です。ここでは、弁護士に依頼する際のデメリットについて解説します。
弁護士費用が発生するためコストがかかる

弁護士に依頼すると、相談料や手数料が発生するため、一定のコストがかかります。特に、相続人間で争いが生じている場合や、相続財産の規模が大きい場合は、弁護士費用が高額になります。
弁護士費用は、相続財産から支払う場合や、相続人が分担して支払う場合が考えられます。相続財産が実物資産の場合は売却して現金化する必要がある点、相続人の弁護士費用分担にも不満が出る可能性がある点にも注意が必要です。
相続の状況によっては弁護士が不要なケースもある
相続人同士の関係が良好で、財産分割の話し合いがスムーズに進む場合は、弁護士に依頼せずに手続きを進められます。弁護士が不要であれば、その分の費用を削減できるため、コストを抑えられる点は大きなメリットです。
ただし、相続手続きには遺産分割協議書の作成や相続登記、税務申告など、専門知識が求められる場面が多々あります。自分たちで手続きを進めようとすると、多くの手間や時間がかかるため、司法書士や税理士へ依頼することも検討しましょう。
司法書士や税理士へ依頼することで、弁護士に依頼するより費用を抑えられる可能性があるため、状況に応じて選択するとよいでしょう。
弁護士に依頼する際にトラブルを回避するポイント
弁護士に依頼する際は、事前の確認が重要です。依頼後に「思っていたのと違った」とならないよう、トラブルを防ぐためのポイントを押さえておきましょう。ここでは、弁護士を選ぶ際に気をつけるべき点について解説します。
不動産相続に関する豊富な経験と実績を持つ弁護士を選ぶ
不動産相続の問題解決を弁護士に依頼する際は、相続問題を数多く扱っている弁護士を選びます。弁護士ごとに得意分野が異なり、相続に関する経験が少ない場合、的確な対応ができないことがあるためです。
相続人同士の意見が食い違っている場合や、遺言書の内容が不明確なときは、経験豊富な弁護士の力が必要になります。相続に関する法律や手続きに精通している弁護士なら、相続人同士の話し合いが円滑に進むように調整してもらえるため、相続時の余計なトラブルを避けられるだけでなく、手続きの負担を減らすことができます。
弁護士を選ぶ際は、公式サイトや口コミを確認し、相続案件の取り扱い実績が十分かどうかを見極めましょう。
収益物件の相続に詳しい弁護士を選ぶ
相続した不動産が収益物件の場合、複数の相続人の共有名義にしてしまうと、その後トラブルが発生しやすくなります。共有不動産は、売却などの処分行為は共有者全員の合意が必要であり、賃貸借契約などの管理行為は過半数の合意が必要です。
意見対立が発生すると賃貸経営が立ち行かなくなってしまいますので、共有名義を避けて一人の相続人が物件を相続するようにします。多くのケースでは、一人が不動産を相続する代わりに、他の相続人に金銭を支払う「代償分割」が利用されます。
収益物件の相続にあたって弁護士を選ぶ際は、これまでに収益物件の相続案件を担当した実績があるかを確認しましょう。また、賃貸管理会社と連携している弁護士であれば、相続後の管理や売却の手続きがスムーズに進み、余計な手間を減らせます。
税理士や司法書士との連携が可能か確認する
相続手続きを円滑に進めるためには、弁護士が税理士や司法書士と連携しているかを確認することが重要です。相続税の申告は税理士、不動産登記などは司法書士の専門分野であり、弁護士が単独で対応できる範囲には限りがあります。
相続税の申告が必要な場合、税理士と連携する弁護士であれば、相続税の負担も考慮した遺産分割が可能です。また、不動産の相続登記が必要なときも、弁護士が信頼できる司法書士を紹介できれば、手続きをスムーズに進めることができます。
相続手続きを包括的にサポートしてくれる弁護士に依頼できれば、依頼者自身が各専門家を探す手間が省けるため、相続に関する負担を軽減できるでしょう。弁護士を選ぶ際は、公式サイトを確認したり、初回相談の場で「税理士や司法書士と連携していますか?」と直接聞いたりすると安心です。
料金体系が明確な弁護士を選ぶ
弁護士に依頼する際は、料金体系が分かりやすい弁護士を選ぶようにします。費用の内訳が不明瞭なまま契約してしまうと、後から思わぬ高額請求を受ける可能性があります。依頼する前に、相談料・着手金・報酬金などの費用がどのように設定されているのか、詳しく確認しておきましょう。
弁護士費用は法律事務所ごとに異なり、料金の決め方もさまざまです。相談料が無料の事務所もあれば、30分ごとに費用が発生するところもあります。着手金についても、一律の金額を設定している場合と、相続財産の額に応じて変動する場合があります。成功報酬などの追加費用が発生することもあるため、契約前に支払いの条件を細かく確認し、予想外の出費を防ぐようにします。
法律の知識がない人にも丁寧に説明してくれるか確認する

法律用語は専門的で難解なものが多く、十分に理解できないまま契約を進めてしまうと、後になって「こんなはずではなかった」と後悔する可能性があります。そのため、法律の知識がない人にもわかりやすく説明してくれる弁護士に、依頼するようにしましょう。
法律用語は、日常的な言葉遣いとは違います。例えば、法律の世界では 「善意の第三者」という言葉がよく登場します。この「善意」も法律用語では「ある事柄について知らなかった」という意味になり、日常用語の感覚とは大きく異なります。
弁護士を選ぶ際は、初回相談での対応を確認し、質問に対して丁寧に答えてくれるか、専門用語をかみ砕いて説明してくれるかを見極めるようにします。依頼者に寄り添って説明してくれる弁護士なら、相続人が納得する形で相続手続きを進めてくれるでしょう。
迅速な対応ができる弁護士を選ぶ
相続手続きには期限があるため、迅速に対応できる弁護士を選ぶことが重要です。相続税の申告期限は、相続開始を知った翌日から10ヶ月以内と決まっており、相続登記も2024年から義務化されました。手続きを後回しにすると、必要書類の準備に手間取ったり、相続人同士の話し合いが長引いたりして、申告期限に間に合わなくなる可能性があります。
相続人が複数いる場合や、収益不動産を相続するケースでは、関係者との調整に時間がかかることもあります。迅速に対応できる弁護士であれば、相続人同士の話し合いを円滑に進め、余計なトラブルを防ぐことにもつながるでしょう。
弁護士を選ぶ際は、返信の速さや、質問に対する的確な回答があるかを確認すると安心です。メールや電話でのやり取りがスムーズな弁護士なら、手続きを進めるうえで余計なストレスを感じることなく、安心して依頼できます。
複数の法律事務所を比較し、相見積もりを取る
弁護士に依頼する際は、複数の法律事務所を比較し、相見積もりを取るようにします。弁護士費用は事務所ごとに異なり、料金体系やサービス内容にも違いがあります。1ヶ所の事務所だけで決めず、いくつかの弁護士と話をすることで、適正な価格で依頼できる可能性が高まります。
費用を比較する際は、相談料や着手金、成功報酬に加え、追加料金の有無や支払い方法も確認しましょう。無料相談を実施している事務所もあるため、事前に問い合わせて費用感を把握すると安心です。また、相続案件の実績が豊富な弁護士であれば、より的確なアドバイスを受けられるでしょう。
相続手続きでは何度もやり取りをするため、弁護士の対応の仕方も重要です。相談しやすい雰囲気か、説明がわかりやすいかも含めて比較すると、費用面だけでなく、安心して依頼できる弁護士を見つけやすくなります。
不動産の相続で弁護士以外に相談すべき専門家
不動産相続では、弁護士だけでなく、税理士や司法書士、不動産会社など、専門分野ごとのサポートが欠かせません。専門家への相談によって手続きの負担を減らし、円滑に相続を進められます。
税理士

相続税の申告や節税対策には、税理士のサポートが欠かせません。相続税は、相続した財産の総額に対して課税されるため、不動産以外にも現金や預貯金、株式などの資産がある場合は、税理士に依頼すると手続きがスムーズになります。
不動産を相続では、相続財産の評価方法も複雑なうえに特例や控除がある点も見逃せません。配偶者控除や未成年の税額控除、贈与税額控除などのほか、小規模宅地等の特例もあります。こうした制度が利用できるか否かで、相続税の納税額が大きく異なるため、早めに税理士に相談するとよいでしょう。
相続財産の種類が多い場合は、税額の計算だけでなく、遺産分割や申告の手順についても整理する必要があります。税理士に依頼すれば、全体の流れを把握しながら計画的に手続きを進められるため、余裕を持って相続税の申告を終えられるでしょう。
司法書士
不動産の相続登記は相続人自身でも手続き可能ですが、多くの書類を準備する必要があり、手間がかかります。遺産分割協議書や戸籍謄本などをそろえ、正しく申請しなければならず、慣れていないと大きな負担になるでしょう。
司法書士に依頼すれば、必要書類の確認や手続きの代行をしてもらえるため、相続登記にかかる労力を大幅に軽減できます。2024年4月から相続登記が義務化され、期限内に申請しないと過料の対象になる可能性があります。
さらに、裁判手続きに必要な書類の作成、相続財産の調査や名義変更といった遺産整理業務も、司法書士が対応可能です。
不動産会社

不動産を相続した際は、売却するのか、利用するのかを決める必要があります。その際、頼りになるのが不動産会社です。弁護士や税理士、司法書士、金融機関と連携しつつ、相続人の意向に沿った提案をしてくれます。
売却を希望する場合は、適正な査定や買い手探し、売却手続きのサポートを行います。所有を続ける場合は、リフォームの提案など資産価値を維持・向上させる方法についても相談可能です。
不動産会社を選ぶ際は、相続不動産の取り扱い実績があるかを確認するようにします。すでに売却や活用の方針が決まっている場合は、その分野に強い会社を選ぶとより的確なサポートを受けられるでしょう。
賃貸管理会社
収益不動産を相続した場合、今後の管理や運用をどのように進めるかを慎重に考える必要があります。賃貸経営を続けるのか、売却するのかによって、取るべき対応が大きく異なるためです。
賃貸経営を引き継ぐ場合、入居者対応や契約の管理、家賃の回収など、オーナー様としての業務が発生します。これらをすべて自身で行うのは大きな負担となるため、賃貸管理会社に委託することで、運営の手間を減らせます。
売却を検討する場合も、賃貸管理会社に相談すると、最適な売却タイミングについて具体的なアドバイスを受けられます。賃貸管理の実績が豊富な会社を選ぶことで、相続後の管理や売却も安心して進められるでしょう。
まとめ・収益不動産の相続は実績と信頼の【リロの不動産】へご相談を

不動産相続では、法律や税金、不動産の管理・売却など、多くの専門的な手続きが発生します。弁護士に依頼すれば、法的な問題を防ぎながら手続きを進められますが、それだけでは不十分な場合もあります。相続した不動産の活用や管理を考える際には、弁護士以外の専門家の力も必要になることが少なくありません。
不動産会社や賃貸管理会社は、相続人の意向を踏まえながら、弁護士や税理士、司法書士と連携し、適切な手続きを進めるコーディネーターとしての役割を果たします。相続時には弁護士だけでなく、不動産会社を窓口に専門家と連携し、総合的なサポートを受けることが重要です。
収益不動産の相続でお悩みの方は、実績と信頼のある【リロの不動産】にご相談ください。
関連する記事はこちら
相続税を抑える決め手は?不動産評価制度の仕組みと注意点を解説
不動産の活用で相続税対策! 賃貸経営・アパート経営が効果的な理由と注意点
不動産物件を相続するときの手続きとは? 相続税を払えない場合はどうする?
アパートは相続税対策に有効! 相続税計算でメリットを検証・解説付き
アパート経営は相続対策に有効!資産管理会社の活用でメリット拡大
マンションの相続税を把握!評価額と節税対策の特例・注意点を解説
不動産購入が相続税対策になる理由!物件種類別の節税対策と注意点を解説
相続税が払えない地主になる前に!納税資金対策の物納・延納・生前対策を解説
不動産を相続するには誰に相談すればよいのか? 相続手続きの期限も解説
2024年から始まる相続税増税の全貌! 税制改正の影響と対策を徹底解説
認知症の両親がいる時の不動産相続対策!遺言・家族信託・成年後見を解説
相続した土地の活用方法!困ったときの相談先や注意点とあわせて解説
相続税の基礎控除とは? 各種控除と賃貸不動産を活用した相続税対策
おすすめのサービス
おすすめのお役立ち情報
この記事を書いた人
秋山領祐(編集長)
秋山領祐(編集長)
【生年月日】昭和55年10月28日。
【出身地】長野県上田市。
【趣味】子供を見守ること。料理。キャンプ。神社仏閣。
【担当・経験】
デジタルマーケティングとリブランディングを担当。
分譲地開発のPMや家業の土地活用などの経験を持つ。
リノベした自宅の縁の下に子ども達の夢が描かれている。




















