空室保証で賃貸経営のリスクヘッジ!サブリース・家賃保証との違いも解説
2025.11.12
賃貸経営において最大のリスクとなる「空室リスク」。空室リスクに対応できる手法の一つに「空室保証」があります。空室保証とは空室が生じた場合でも一定以上の家賃収入が入るよう、保証会社に保証してもらうサービスのことです。
賃貸経営におけるリスクヘッジとして活用されるオーナー様が増加中で、そのスキームやメリット・デメリットを一通り理解しておくことが重要となっています。
今回の記事では空室保証とは何か、類似する仕組みである一括借上(サブリース)や家賃保証、滞納保証との違いも含めてわかりやすく解説しましょう。
▼この記事の内容
●空室保証とは、オーナー様が保証会社と契約を結び、物件に空室が出た場合、保証会社がオーナー様に一定の家賃相当額を支払うサービス。金額は満室家賃の8~9割程度が相場。
●混同されやすいものにサブリース(一括借上)がある。サブリース(一括借上)とは、オーナー様の所有する賃貸物件をサブリース会社に賃貸し、サブリース会社が入居者様とサブリース契約を結ぶことで賃貸経営を行う方式。
●空室保証は家賃保証(滞納保証)とも異なる。家賃保証は入居者様の家賃支払いが遅れた場合に、保証会社がかわりに家賃を立て替えて支払うサービス。
●空室保証については、空室リスクを最大限抑えたいオーナー様は利用したほうがよいが、入居者募集力がある物件には必要ない。いずれにしても、信頼できる賃貸管理会社との協力が重要になる。
目次
空室保証とはどういうものか
空室保証の仕組みについて解説します。ベースとなるスキームやメリット・デメリットを理解し、自分の状況にマッチし利用価値があるかをしっかり判断できるようにしましょう。
空室保証のスキーム
空室保証とは「空室の発生によって生じた家賃収入の減額分」について、保証会社がある一定程度の金額まで保証するサービスのことです。保証金額は満室賃料の8~9割程度が一般的ですので、満室賃料全てが保証されることはほとんどありません。また、各保証会社との契約内容によっても保証方法にかなり違いはあります。
オーナー様から保証会社に支払う保証料は毎月払いの定額制になるケースが多いです。定額制の場合、保証会社との契約締結後は物件の稼働率と関係なく、一定金額の保証金を毎月支払う必要があります。
空室保証は空室が発生した際の損失幅を最小限にとどめておくための手法といえるでしょう。例えば「空室保証80%」の契約を結ぶと、仮に空室が40%発生(入居率60%)だとしても、満室時の80%の家賃収入までは確保できます。イメージとしては掛け捨て型の保険に近いものがあり、空室の急激な増加などの緊急時に大いに役立ちます。
一方で空室率20%以下(入居率80%以上)といった満室に近い状態が続いている場合は、保証料を毎月支払うだけとなり、保証料負担は無駄なコストになってしまうでしょう。立地のいい物件など募集力のある物件では利用価値が低くなる傾向です。
なお、保証会社によっては空室保証を「空室補償」と表記している保証会社もありますが、基本的なスキームはほぼ共通とお考えください。
空室保証のメリット
次に空室保証のメリットを挙げておきましょう。
空室のリスクヘッジができて、最低収益を確定できる

空室保証は空室率の増減に関わらず、一定の家賃収入を確保することが可能です。例えば「家賃収入80%」の保証契約であれば、例えほとんど入居者がいない状態の物件であっても満額賃料の80%分は保証されます。入居者の入れ替え時や状況の急激な変化など、突然の収入減に対応できるため、リスクヘッジとしてはかなり心強いサービスです。
また、安定収益を得られることから金融機関からは損失の最大値が決まった物件と評価されますので、融資を取り付けやすくなるケースもあります。
稼働率がよければ家賃収入アップ
満室経営の稼働率であれば、空室保証の設定に関係なく家賃収入の全てはオーナー様に入ります。この点は後述する一括借上(サブリース)と大きく違う点です。空室保証が活用されるのはあくまでも家賃収入が減った場合ですので、稼働率が高ければ利用機会はなく、収入はすべてオーナー様の取り分となります。
空室保証のデメリット
空室保証のデメリット面についても挙げておきましょう。
月々の保証料の負担が増える

月々の保証料が発生し、経営上のランニングコストが増えてしまいます。しかも保証料を支払ったからといって満室時の賃料収入が保証されるわけではありません。高い入居率を維持できる物件の場合、保証料は単なる掛け捨てコストになりがちです。
保証会社とは別に賃貸管理会社との契約も必要
保証会社のサービス範囲は家賃収入の保証まで。賃貸管理などには関わりません。賃貸管理については別に賃貸管理会社との管理委託契約が必要となります。
滞納保証はない
空室保証は空室の増加に対する一定の保証ですので、入居者様の家賃滞納トラブルなどには対応していません。滞納保証ではない点にも注意しましょう。
立地や物件の状況が悪いと契約できない場合も
そもそも立地や物件の状態が悪く、資産価値としての評価の低い賃貸物件の場合、保証契約そのものを締結できないことがあります。保証会社もリスクを背負うことになるので、条件の悪い物件では不利な保証契約を提示されるケースも想定されるでしょう。
サブリース(一括借上)とはどう違うのか
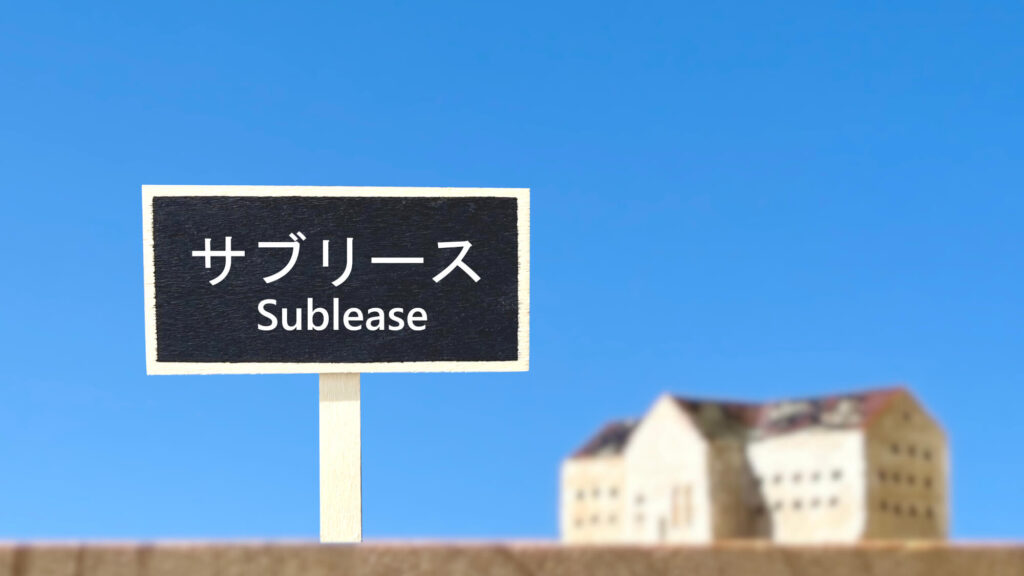
空室保証と混同されがちなのがサブリース(一括借上)です。サブリースとは、オーナー様が所有する収益物件をまるごとサブリース会社(不動産会社・賃貸管理会社)が一括で借り上げて、サブリース会社が借上した物件を入居者様に転貸するスキームの経営方式です。
サブリース(一括借上)の基本スキームやメリット・デメリット面について、空室保証との違いを意識しながら理解しておきましょう。
サブリースについては、以下の関連記事もご参照ください。
マスターリース契約とは? サブリースとの違いや活用ポイントを事例で解説
【事例付】サブリース新法を徹底解説! 契約時の注意点とメリット・デメリット
【事例付】一括借り上げとサブリースとの違いやメリット・デメリットを解説
サブリースのスキーム
サブリース(一括借上)とは、オーナー様の所有する賃貸物件をサブリース会社に賃貸し、サブリース会社が入居者様とサブリース契約を結ぶことで賃貸経営を行う方式です。賃貸管理実務はサブリース会社が行い、オーナー様は家賃収入としてサブリース賃料をサブリース会社から受け取るかたちとなります。
通常、サブリース賃料は満室時の家賃収入の80~90%程度に設定されますが、立地条件や物件価値の評価によって料率は違ってきます。空室保証との大きな違いは、サブリース賃料は空室の有無にかかわらず固定されるという点です。また、サブリース賃料は2年ごとに見直しが行われるのが通例です。予想を下回る入居率と判断されると賃料を下げる改定を求められることがあります。
一方、複雑で面倒な賃貸経営に関する業務はサブリース会社にほぼ丸投げできるため、オーナー様は特に何もしない状態でも収入だけが入ります。そのかわり、経営方針についてオーナー様がほとんど介入できなくなるため、積極的に賃貸経営に関わりたい方にとっては物足りない手法といえるでしょう。
▼サブリースの関連事例
大手からの転換!空室のみサブリースで安定収益を確保する賃貸経営!
サブリースから集金管理へ変更で収入が月額で約50000円増加!
不人気エリアでもサブリースで安定収入!退去、空室の心配から解放!
サブリース変更で収益アップ!需要を捉えたシミュレーションと入居者募集
サブリースのメリット
サブリースの代表的なメリットは次のようなものがあります。
安定した家賃収入
サブリースでは実際の賃貸物件の運営をサブリース会社が行いますので、オーナー様のほうで空室リスクや家賃滞納リスクを負うことがありません。入居率の状況がどうなろうと、サブリース契約時の家賃収入が入るため、安定した家賃収入を期待できます。
賃貸管理に関する業務を行う必要なし
賃貸管理業務はサブリース会社がすべて行うため、オーナー様が直接物件の管理運営に関わることはありません。賃貸管理業務は入居者の募集や物件の維持管理、入居者のクレーム対応や物件の修繕計画の策定など、かなり膨大な範囲に及びます。このような各種業務をサブリース会社に丸投げできるのは大きなメリット。オーナー様は手間をかけることなく家賃収入だけを受け取れます。
税金の計算が楽
家賃回収業務や税金の計算などもかなり簡略化できる点も大きなメリット。サブリース会社からの家賃収入に一本化されるうえ物件管理にかかる費用についてはサブリース会社が計算してまとめてくれますので、収入と支出の計算がシンプルです。税務申告時の煩雑さも大幅に減らすことができます。
融資が有利になる
サブリースは、賃貸物件の空室リスクや家賃滞納リスクをオーナー様に代わってサブリース会社が負担する仕組みです。金融機関からはローン契約者の収益の安定性が担保されていると見られるため、融資の審査が有利に働くケースがあります。不動産投資を始めたばかりの初心者や、自己資金が少ないオーナー様にとっては、返済能力の裏付けとしてサブリース契約がプラス評価となるのです。
サブリース契約では家賃収入の下限が明確に設定されるため、金融機関は事業計画の収支を見積もりやすくなります。金融機関の信頼を得やすくなるという点で、サブリースはオーナー様にとって強力な支援となるでしょう。
サブリースのデメリット
サブリースのデメリットとしては、以下のような点を挙げることができます。
収益上限は頭打ちになる
一括借上は稼働率の高い物件であっても家賃収入は定額のまま。どんなに入居率が上がっても満額分を受け取ることはできません。一般的には家賃収入の80~90%程度の料率設定が多く、入居者募集に強い人気物件であるほど、かえって損になることも少なくありません。
更新時に賃料の見直しがある
物件の稼働状況があまり良くない場合、サブリース会社から契約途中での家賃減額や中途解約を求められる可能性があります。契約更新は基本的に2年ごとで、この更新時期に家賃減額を要求される場合や依頼された工事対応をしなければならないことが原因でサブリース会社側とトラブルとなる事例も多いようです。
仮にサブリース会社側からの減額要求や中途解約が不満だとしても、オーナー様は法的に不利な立場となります。日本の法制度では貸主よりも借主の権利を保護する傾向にあるためです。例えばオーナー様側から契約解除したい場合でも、正当事由がなければできないルールがあります。
突然契約解除されるリスクがある
サブリース契約は家賃保証として安心材料になる一方、実は賃貸管理会社側から一方的に契約を解除されるリスクも潜んでいます。
賃貸需要が低下したり、物件の老朽化によって入居率が落ちたりした場合、サブリース会社が「収益性が合わない」と判断して契約解除を申し出ることがあります。契約書上に「一定の予告期間をもって解除できる」といった条項が記載されているケースもあり、オーナー様の意向にかかわらず法的に認められてしまうことが少なくありません。突然契約が解除されれば、家賃収入の見込みが立たず、ローン返済に支障が出るリスクもあります。
サブリース契約をする場合は、あらかじめ契約内容や解除条項をよく確認しておくことが重要です。
オーナー様からの契約解除が極めて困難
サブリース契約では、オーナー様側からの契約解除が非常に困難である点も大きなデメリットです。借地借家法では原則として賃借人が保護されますが、サブリース契約においてはサブリース会社が賃借人の立場となるためです。
サブリース契約は契約期間が数十年単位で設定されていることも多く、途中で解除しようとすると、高額な違約金を請求される場合があります。借地借家法上、契約解除には「正当事由」が必要とされ、家賃収入の低下では契約解除理由として認められないケースが多いのが実情です。
修繕・原状回復費用が割高になることがある

サブリース契約では、賃貸管理会社が入居者様との賃貸借契約を直接結ぶため、退去後の原状回復や修繕に関する費用も、サブリース会社の判断で行われます。
オーナー様にとっては「どの程度の修繕が必要か」「本当にその費用が妥当か」を確認しづらく、結果的に高額な費用を請求されるケースがあります。内装リフォームや設備交換においては、サブリース会社指定の工事会社への委託により中間マージンが上乗せされ、相場よりも割高になる事例もあります。
このようなトラブルを防ぐためには、契約時に「修繕費用の負担範囲」「原状回復の基準」などを確認しておくことが重要です。
家賃保証(滞納保証)とはどう違うのか
空室保証とよく似た仕組みに「家賃保証」があります。家賃保証は入居者様の家賃支払いが遅れた場合に、保証会社がかわりに家賃を立て替えて支払うサービスです。空室保証との違いに注目しながら、その基本スキームとメリット面・デメリット面を理解しておきましょう。
▼家賃保証(滞納保証)の関連記事
賃貸経営における滞納保証とは? 家賃保証や一括借上との違いを解説
家賃保証のスキーム

家賃保証とは、家賃保証会社が入居者様の保証人となる制度です。「滞納保証」と表記する場合もあります。入居者様が何らかの事情で家賃を滞納した場合に保証会社が未払い分の家賃を立替払いをするサービスのことで、「入居者様が保証会社と個別で契約締結」する仕組みです。保証料を支払うのは契約者である入居者様側となりますので、オーナー様の負担はありません。
オーナー様から見ると負担を増やすことなく家賃滞納リスクを防ぐことができるため、経営上のメリットは大きいです。入居者様との賃貸契約時に家賃保証を契約条件に含める事例も年々増加傾向にあります。
一方、入居者様にとってもメリットは多く、何らかの事情で連帯保証人を立てられない入居者様にとっては大いに役立つスキームとなっています。近年は家族や親族関係が希薄な方、周囲に連帯保証人になれる方がいない事例も少なくありません。支払い能力があるにもかかわらず連帯保証人を立てられないために、物件の選択肢が限定されているケースも増えているようです。
今後もこの様な傾向は続くものと予測されるので、家賃保証に対する需要はますます高まることでしょう。
▼家賃保証(滞納保証)の成功事例
初期費用なしのリノベーションで新品の設備!家賃保証で安定収入確保
疎遠だった親族の物件!家賃保証リフォームで賃料アップの空室改善!
入居者様にとってのメリット・デメリット
入居者様にとっての家賃保証のメリット面、デメリット面をあげておきましょう。
入居者様からみたメリット1:借りたい部屋を借りやすくなる
部屋を借りるときに大きなハードルとなるのが連帯保証人の問題です。基本的に賃貸契約締結時にはオーナー様側から連帯保証人が求められますが、連帯保証人が見つからない方は意外と多くいます。
そこで家賃保証会社の出番。連帯保証人の見つからない入居者様であっても家賃保証会社の保証があれば、オーナー様も安心して物件を貸すことができます。入居者様にとっても借りられる物件の選択肢が広がる点は大きなメリットです。
入居者様からみたメリット2:連帯保証人がいない人でも入居できる
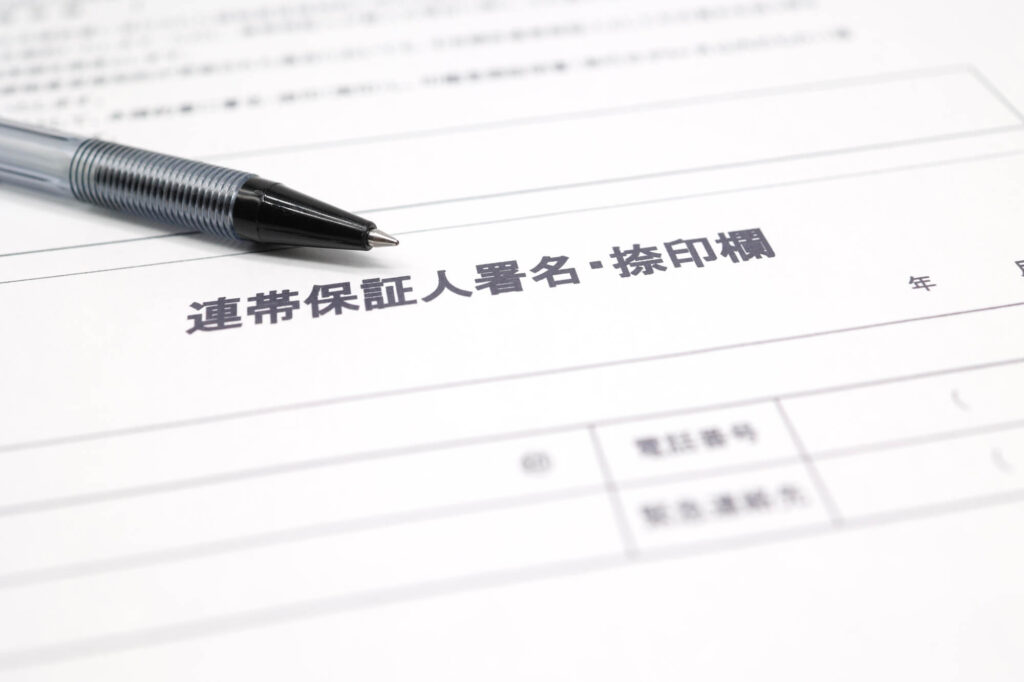
近年、高齢者の単身世帯や外国人、非正規雇用者など、連帯保証人を立てるのが難しい方が増えています。こうした背景の中、家賃保証会社を利用することで、連帯保証人がいなくてもスムーズに賃貸借契約ができる点は大きなメリットです。
身寄りが少ない方や、人間関係に頼らずに自立した生活を送りたい方にとって、保証会社の存在は安心材料になるでしょう。
入居者様からみたメリット3:連帯保証人を探す手間が省ける
連帯保証人を立てられる人がいたとしても、契約書に判子をもらいに行くなどの手間が生じます。親戚や会社の上司などが連帯保証人を引き受けてくれる場合も、実際には「お願いしづらい」「迷惑をかけたくない」という心理的な負担がつきまとうこともあるでしょう。
家賃保証会社を利用すれば、このような煩わしさや対人関係のストレスから解放され、スムーズに賃貸借契約を進められます。社会人になりたての方や、転勤・離婚後に新生活を始める方にとっては、保証人探しの時間や労力を省けるのは大きな魅力です。
入居者様からみたメリット4:病気やケガ、失業などの備えになる

人生には思いがけないトラブルがつきものです。病気やケガ、あるいは突然の失業などで一時的に収入が途絶えることもあります。
そのような万一の事態に備えて、家賃保証サービスを契約しておくと、支払いが困難になった際でも一定期間の猶予や支援を受けられるのは入居者様にとって大きなメリットといえます。
保証会社によっては、支払い相談窓口を設けており、分割払いや支払計画の見直しなど柔軟に対応してくれることもあります。オーナー様側も家賃滞納による損失をカバーできるため、入居者様との信頼関係が保たれやすく、追い出されるといった不安も軽減されるでしょう。
経済的リスクに対するセーフティネットとしての役割を果たしているのが家賃保証の大きな特徴です。
入居者様からみたデメリット1:保証料の負担が増える
家賃保証は入居者様と家賃保証会社との間での契約ですから、入居者様は家賃に加えて「保証料」を別途支払わなくてはなりません。保証料の相場は初回で1ヶ月の家賃分の50~100%分程度とされます。例えば家賃7万円のアパートを借りた場合は、保証料は3万5,000円から7万円の間ということです。
また、1年ごと(または2年ごと)に更新保証料が1万円前後かかります。入居者様にとっては意外と大きな負担となっています。
入居者様からみたデメリット2:立替金は後日支払う義務がある
家賃保証サービスは、入居者様が一時的に家賃を滞納した場合に、家賃保証会社がオーナー様に対して家賃を立て替えて支払ってくれる仕組みです。しかし、これはあくまで「立替払い」であるため、後日、入居者様が保証会社にその金額を返済しなければならないという義務が発生します。つまり、家賃の支払いが猶予されるだけで、最終的に支払わなければならない負担に変わりはありません。
返済の遅延が長引けば、遅延損害金が発生するケースもあり、支払総額が膨らむ可能性もあります。保証会社への支払いが遅れると信用情報に傷がつく可能性もあるため、一度立て替えてもらったからといって安心せずに速やかに支払う必要があります。
このように、家賃保証サービスは便利な一方で、入居者様にとって「返済義務を負う借金」が生じるという側面もあり、利用する際はそのリスクを理解しておく必要があります。
オーナー様にとってのメリット・デメリット
オーナー様からみた家賃保証のメリット・デメリットは次のようになります。
オーナー様からみたメリット1:家賃滞納リスクの減少
賃貸経営において、家賃滞納リスクは空室リスクと並んで非常にやっかいなものです。滞納者への支払い催促や取り立ては非常に骨の折れる業務ですし、支払いを確保できるまでは家賃収入がない状況が続きます。問題解決が長引くと賃貸経営上の大打撃となりかねません。
その点、家賃保証会社の保証があれば、問題が生じても家賃収入が途絶える状況をひとまずは回避することが可能です。また。支払い催促などの困難な業務も家賃保証会社がやってくれるため、余計な手間をかける必要もなくなります。
オーナー様からみたメリット2:入居者様の幅が広がり、入居者審査の質も向上する
家賃保証会社は入居者様と契約する際に、入居者様の信用審査を行います。信用審査の基準は各会社によって違いますが、おおむね家賃保証会社の審査に通った入居者様は家賃滞納リスクの低い方とみて間違いないでしょう。比較的優良な入居者様を集めやすくなる点はオーナー様にとっても大きなメリットです。
オーナー様からみたデメリット1:入居者様が敬遠することも
家賃保証会社の保証を条件に入居者様を集めると、思ったように入居希望者が集まらない場合も考えられます。やはり月々の保証料負担は大きなものとなるので、家賃保証を義務付けられると抵抗感を示す方も少なくないようです。家賃設定とのバランスのとれた契約条件を整える必要があるでしょう。
オーナー様からみたデメリット2:家賃保証会社の倒産リスク
家賃保証は、入居者が滞納した際に代わりに家賃を支払ってくれる便利な仕組みですが、その信頼性は保証会社の経営状況に依存しているともいえます。仮に保証会社が経営破綻した場合、家賃の立替払いや滞納時の対応などが突然停止されるおそれも否定できません。保証会社との契約があっても、倒産によってその効力が失われれば、オーナー様は本来得られるはずだった家賃を回収できない事態に直面します。
保証会社が倒産した場合、次の保証会社を探して再契約を結ぶ必要がありますが、再契約には入居者様の同意が必要なこともあり、スムーズに切り替えができないケースもあります。
保証会社の倒産はオーナーにとって極めて重大なリスクです。信頼できる保証会社を見極める目を持つことが不可欠であり、会社の財務状況や業界での実績などを慎重に調査することが望まれます。
【家賃保証会社を利用するメリット・デメリット】
| 入居者様 | オーナー様 | |
| メリット | ・借りたい部屋を借りやすくなる ・連帯保証人がいない人でも入居できる ・連帯保証人を探す手間が省ける ・病気やケガ、失業などの具になる | ・家賃滞納リスクの減少 ・入居者様の幅が広がり、入居者審査の質も向上する |
| デメリット | ・保証料の負担が増える ・立替金は後日支払う義務がある | ・入居者様が敬遠することも ・家賃保証会社の倒産リスク |
空室保証を利用すべきか
ここまで空室保証、一括借上(サブリース)、家賃保証の3つの制度について、基本的な特徴やメリット・デメリット面について解説しました。ここであらためて空室保証を利用したほうがいい場合や、利用の際に気をつけることについてまとめておきます。
空室リスクを最大限抑えたいオーナー様は利用したほうがよい
不動産投資において空室リスクは、収益の不安定化や資金繰り悪化を招く最大のリスク要因です。とくに、初めて賃貸経営やローン返済を抱えているオーナー様にとっては、数ヶ月の空室が大きな痛手となることもあります。そうした空室リスクに備える手段として有効なのが空室保証制度です。
空室保証を活用すれば、たとえ実際に入居者様がいない期間があっても、一定額の家賃が保証会社から支払われるため、安定したキャッシュフローの確保が可能です。結果として、ローン返済・固定資産税・修繕積立金などの支出を計画通りに進めやすくなり、経営に安心感をもたらします。
周辺地域の賃貸需要が不安定な場合や、築年数が経過している物件を所有している場合には、空室保証の導入がリスクヘッジとして有効です。
▼空室保証付きリノベーションの成功事例
近隣物件と差別化!初期費用は一切ない空室保証付きのリノベーション
半年以上続いた空室が完成と同時に成約!空室保証付きリノベーション
入居者募集力がある物件には必要ない
空室保証はあくまでも空室リスクのある物件に対するリスクヘッジです。せっかく月々の保証料を負担していても、満室に近い入居率を維持できる物件であればほとんど意味のないコストとなるでしょう。もともと立地条件がいい、物件の状態がいい、空室対策も万全な物件であれば空室保証は不必要なケースもあるため、収益予想とコストのバランスには注意して検討したいところです。
ただ、賃貸経営において空室リスクが0という物件は存在しません。現状で高い稼働率を維持できていたとしても、今後数十年にわたってそのまま安定するかは未知数です。競合物件の出現や立地環境に伴う入居者ニーズの変化、経年変化による物件のトラブル、入居者様の契約更新期が重なって一時的に空室が増えることなど、出口戦略を踏まえた中長期の視点をもって検討しなければならないでしょう。
特に不動産投資を始めたてのオーナー様や、収益状況がわからない新築の収益物件、さらに中古であっても契約の更新期が近づいている入居者様の多い物件などでは、空室保証がリスクヘッジとして大いに役立ちます。利回り上の余裕があれば、「保険」のつもりで利用すると将来的に安心です。
入居者募集の関連記事については、以下をご参照ください。
リーシング・空室対策に強い賃貸管理会社とは?入居者募集力と仲介力から確認
入居者募集のコツとは?契約形態別のメリット・デメリットを解説!
客付けでお困りの不動産オーナー様必見!仲介会社と上手に付き合うコツとは?
信頼できる賃貸管理会社との協力が重要

空室保証や一括借上は、空室の発生に対するリスクヘッジです。つまり空室保証を付けるかどうかの大前提として、まず物件の空室対策そのものが万全であるかどうかが大きな問題となります。空室の発生は立地条件などで決まると思われがちですが、実はそれ以外にも物件のニーズに合った入居者様を集める集客力、入居者様の満足度を上げる適切な賃貸管理が行われているかによって大きく変わります。
そこで空室保証を検討される際には、まずオーナー様の物件が適切な賃貸管理や空室対策がされているかどうかを再確認してみましょう。注目すべきは実際の集客業務や賃貸管理を行っている賃貸管理会社の仕事ぶりです。
賃貸管理会社の仕事ぶりを見極めるポイントは、入居希望者を集められる「募集力」と適正条件で契約締結する「仲介力」に、適切な「賃貸管理力」のバランスが重要です。この3つのポイントで優れたパフォーマンスを出す賃貸管理会社であれば、安定して高い入居率を維持できる可能性が高いでしょう。
仮に80%以上の入居率を安定して維持できる状態であれば、家賃保証や一括借上に頼ることなく賃貸経営を継続できます。
もしもの場合に備えて空室保証を利用したい場合でも、信頼できる賃貸管理会社がパートナーにいる場合はどのような契約内容がベストか相談してみてください。空室保証より一括借上のほうが費用対効果に優れる物件もありますので、プロ目線からアドバイスをもらうことが大切です。
まとめ

空室保証は不動産投資における保険のような立ち位置の制度です。どれだけ収益性の高い物件であっても空室リスクを完全に避けることはできませんので、一定のコストを払ってリスクヘッジをする判断も必要でしょう。
ただし、空室保証に頼る前に万全の空室対策が行われているか再検討することも重要です。そこで大きな役割を果たすのが経験と実績豊富な賃貸管理会社の存在。長期にわたって不動産を適切に管理し、高い稼働率を実現できる賃貸管理会社が味方につけば空室保証に頼らずに適正賃料で賃貸経営を続けられる可能性が高まります。
【リロの不動産】は全国トップクラスの管理実績はもちろん、建物管理業務のスペシャリストとしてこれまで数多くのオーナー様の賃貸経営をサポートして参りました。
特に「入居者募集力」「賃貸仲介力」「管理対応(入居者及び建物)」「工事対応」を重視した『4つの空室対策』のノウハウで、空室リスクの少ない客付け力のある物件に育てる自信があります。賃貸経営でお困りの場合は、ぜひ一度【リロの不動産】までご相談ください!
関連する記事はこちら
空室の原因を解決する『4つの空室対策』とは?14種類の手法を徹底解説!
賃貸経営における滞納保証とは? 家賃保証や一括借上との違いを解説
不動産投資の大敵・空室をなくす! 空室改善の方法をわかりやすく解説
無料インターネットで空室対策!管理会社が入居者ニーズの高い設備を紹介
おすすめのサービス
おすすめのお役立ち情報
この記事を書いた人
秋山領祐(編集長)
秋山領祐(編集長)
【生年月日】昭和55年10月28日。
【出身地】長野県上田市。
【趣味】子供を見守ること。料理。キャンプ。神社仏閣。
【担当・経験】
デジタルマーケティングとリブランディングを担当。
分譲地開発のPMや家業の土地活用などの経験を持つ。
リノベした自宅の縁の下に子ども達の夢が描かれている。





















