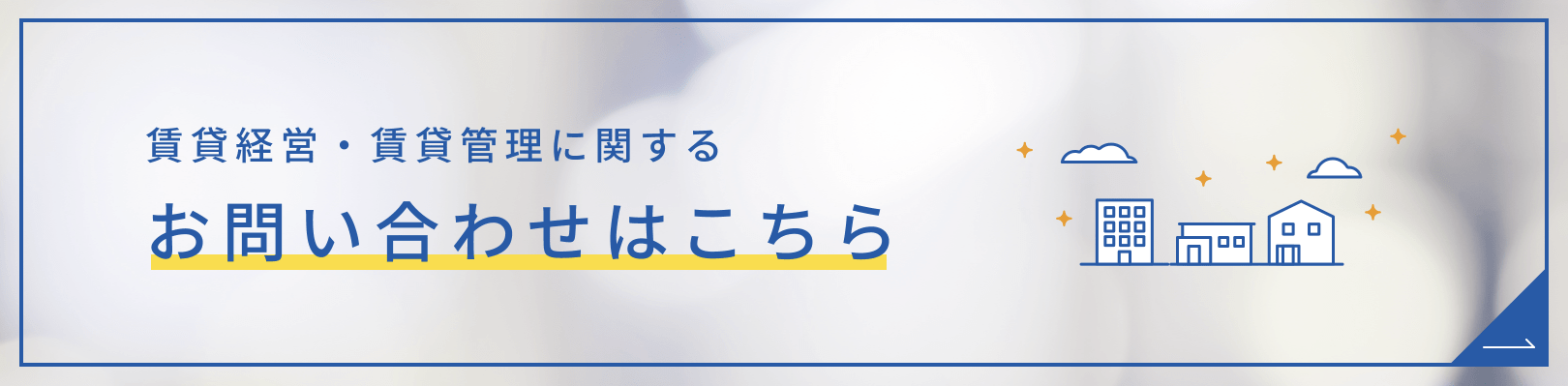アパートの相続税対策完全ガイド!シミュレーションで相続税の仕組みを解説
2025.07.27
アパートを所有している投資家・資産家にとって、将来的な相続の問題は頭の痛い問題の一つかもしれません。相続税は累進課税のため、所有する資産額が大きければ大きいほど税の負担も大きくなります。
一方で、アパート経営は相続税対策として有効な手段の一つとされ、適切な方法を取ることで評価額を圧縮し、相続税の負担軽減が可能です。
本記事では、アパートが相続税対策に有利とされる理由を詳しく解説するとともに、実際のシミュレーションを用いて仕組みを分かりやすく説明します。また、具体的な節税のポイントや注意点についても詳しく紹介し、相続対策を成功させるためのヒントをお伝えします。
将来的なトラブルを避けるためにも、今からしっかりと準備を進めておきましょう。
▼この記事の内容
●現金や預貯金、株式などは時価100%が相続税評価額となるが、アパートは評価額を圧縮できる。土地部分の評価方法は路線価方式と倍率方式の2つあり、小規模宅地等の特例もあるため、評価額を大幅に下げられる。建物部分の評価方法は、固定資産税評価額を基準に決定され、こちらも評価が下がる。
●アパートによる相続税対策のメリットとして、相続人が家賃収入を得られる、ローン残債が債務控除になる、インフレに強い実物資産を取得できるなどがあるが、デメリットとして、遺産が分割しにくくなる、アパート経営特有のリスクがある、アパート経営の承継者を決める必要があるなどがある。
●アパートを生前贈与するメリットとしては、分割贈与で相続税よりも節税できる、アパート経営の承継人を選べる、贈与する時期を選べる、家賃収入を受贈者が得られるなどがあるが、デメリットとして、贈与加算がある、アパートの名義変更に費用がかかる、「定期金に関する権利」と見なされる可能性がある、小規模宅地等の特例が使えなくなるなどがある。
●相続税計算の手順は、①法定相続人を確定、②正味の遺産総額を把握、③正味の総額から基礎控除を引き課税遺産総額を算出、④法定相続分に応ずる取得金額を算出、⑤相続税の総額を計算、⑥相続税の総額を取得割合に応じて按分、⑦税額控除などを適用して最終の納税額を確定の順番で行う。
目次
アパート(土地・建物)が相続税評価額を下げる

日本の相続税の税率は最大55%と定められており、相続資産が多い場合には多額の税金を納めなくてはならないケースがあります。現金や預貯金、株式などは時価100%が相続税評価額とされますが、相続資産の中に収益物件となるアパートがある場合は評価額を圧縮でき、直接的に節税対策となります。
ここでは、アパートの評価額を「土地部分」「建物部分」の2つに分類し、相続税評価額が下がる仕組みについて簡単に紹介します。
土地部分の相続税評価額
アパートの土地部分の評価方法としては、路線価方式と倍率方式の2つがあります。
まずは、アパートの土地部分の相続税評価額はどのように計算されるのか解説します。
路線価方式
路線価方式は、土地の相続税評価額を算出する一般的な方法で、市街地や住宅地など、国税庁が定める「路線価」が設定されている地域で適用されます。路線価とは、道路に面する土地の1平米あたりの価格を示したもので、毎年1月1日を評価時点として、国税庁が毎年7月に公表しています。
相続税評価額は、基本的に「路線価 × 土地の面積」で計算されます。例えば、ある土地の路線価が20万円/平方メートルで、土地の面積が100平方メートルの場合、相続税評価額は 20万円 × 100 = 2,000万円 となります。
路線価方式は、公示地価(時価)の約80%程度になることが多く、市場価格より低い評価額で相続税を計算できるため、結果として相続税の負担が軽くなります。
倍率方式
倍率方式は、路線価が設定されていない地域で適用される相続税評価額の算出方法です。この方法では、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価額を算出します。倍率は国税庁が定めており、土地の種類(宅地、農地、山林など)や地域ごとに異なります。
計算式はシンプルで、「土地の固定資産税評価額 × 倍率」で相続税評価額が決まります。
例えば、固定資産税評価額が1,000万円の土地で、倍率が1.2の場合、相続税評価額は1,000万円 × 1.2 = 1,200万円 となります。
固定資産税評価額は、市町村が公表する固定資産課税台帳で確認できます。一般的に、固定資産税評価額は市場価格の70%程度になることが多く、そこに倍率を掛けるため、結果として路線価方式と同様に市場価格よりも低い評価額になることが多いです。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、一定の条件を満たすと、相続税評価額を大幅に減額できる制度です。特に、相続財産の中に「自宅や賃貸アパートの土地」が含まれている場合、この特例を適用すると、最大で評価額を80%減額できるため、相続税の負担を大幅に軽減できます。
この特例には、主に以下の3つの適用区分があります。
・被相続人の居住用宅地(自宅):330平方メートルまでの土地について80%減額
・特定同族会社事業用宅地等に該当する土地:400平方メートルまでの土地について80%減額
・貸付事業用宅地(アパート経営など):200平方メートルまでの土地について評価額を50%減額
例えば、評価額1億円のアパート用地(200平方メートル)に貸付事業用宅地の特例が適用されると、評価額は5,000万円に圧縮され、その分相続税が大幅に軽減されます。
ただし、この特例は相続後も一定期間(原則として3年)土地の用途を変更しないなどの条件があるため、適用の可否を事前に確認することが重要です。特例の要件を満たすことで、大幅な節税が可能になるため、相続対策を考える際には必ず検討すべき制度です。
建物部分の相続税評価額
アパートなどの建物を相続する場合、その相続税評価額は、固定資産税評価額を基準に決定されます。
固定資産税評価額は、市町村が毎年公表する「固定資産税課税台帳」に記載されており、所有者は納税通知書で確認できます。この評価額は建物の種類や築年数、構造によって異なりますが、一般的に市場価格の50〜70%程度とされています。例えば、市場価格が5,000万円の物件でも、固定資産税評価額が3,000万円であれば、相続税評価額は3,000万円になります。
また、居住用の自宅などの場合は、前述の通り固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となります。一方で、アパートなどの賃貸用物件の場合は、実際の建物部分の相続税評価額は、固定資産税評価額に借地権割合などを加味した一定の倍率をかけた計算式で求められるため、さらに相続税の評価額は下がります。
このように、アパートなどの賃貸物件の建物部分の相続税評価額は、その他の不動産よりも低くなりやすく、大幅に相続税を軽減できる可能性があるといえます。
借地権割合・借家権割合
アパートの相続税評価額を算出する際、借地権割合と借家権割合が重要な要素となります。
借地権割合とは、土地の所有者(地主)と借地権者(借主)の権利関係を示すもので、土地の相続税評価額を決める際に使用されます。30%〜90%の間で設定されており、地域や用途によって異なります。
借地権が設定された土地を相続する場合、評価額は以下のように計算されます。
貸宅地の評価額 =(1 – 借地権割合)× 土地の相続税評価額
例えば、路線価が30万円で・面積100平方メートルの土地(評価額3,000万円)を持つ場合、借地権割合が60%であれば、3,000万円 ×(1 – 0.6)= 1,200万円となり、通常の土地よりも相続税評価額が低くなります。
建物部分の評価額に関連する借家権割合とは、建物を賃貸している場合に適用される割合で、全国一律30%とされています。アパートのような賃貸住宅では、所有者が自由に使用できないため、その価値が減額される仕組みになっています。さらに、アパートの相続税評価額の算出には賃貸割合も加味されます。
以上を踏まえて、貸家の評価額は、以下の計算式で求められます。
貸家の相続税評価額 = 固定資産税評価額 ×(1 – 借家権割合 × 賃貸割合)
例えば、固定資産税評価額が3,000万円のアパートで、借家権割合が30%、100%賃貸中の場合、3,000万円 ×(1-0.3 × 1.0) = 2,100万円となり、相続税評価額が30%減額されます。
相続対策として、所有する不動産の借地権割合や借家権割合を事前に把握し、適切な節税計画を立てることが重要です。
アパートによる相続税対策のメリット
アパートを相続した場合、相続税対策以外にも以下のような経済的なメリットがあります。
相続人が家賃収入を得られる

アパート経営を相続する最大のメリットの一つは、相続人が安定した家賃収入を得られることです。相続財産として親の自宅を受け継ぐ場合がありますが、それ自体は収益を生まないため、相続人が生活資金を確保するためには自宅を売却する必要が出てくることもあります。しかし、アパートは資産を保持しながら定期的な家賃収入を得られるため、長期的に安定した収益源となります。
家賃収入は景気や物価の動向に左右されにくく安定していることが特徴です。入居者様が継続的にいる限り、毎月一定の収入が見込めるため、生活費やローンの返済、固定資産税の支払いなどに充てることができ、さらには相続税納税の原資にもできます。
ローン残債が債務控除になる
相続税の計算において、アパートの購入や建築にともなうローンの残債は債務控除の対象となります。これは、相続財産からローンの残高を差し引ける仕組みであり、結果的に相続税の負担を軽減する効果があります。
例えば、評価額1億円のアパートを相続する場合、そのままでは1億円の資産として評価されて相続税が課税されます。しかし、ローン残債が5,000万円残っている場合、相続税の計算では1億円 – 5,000万円 = 5,000万円が相続財産として評価され、税負担が大幅に軽減されるのです。
相続人がローンを引き継ぐ際には、金融機関の承認が必要となる場合があるため、事前に融資条件を確認しておきます。
インフレに強い実物資産を取得できる

アパート経営は、相続人にとってインフレに強い実物資産を取得できるという大きなメリットがあります。インフレ(物価上昇)が進むと、現金や預貯金の価値は相対的に下がる一方で、不動産などの実物資産は価値を維持または上昇しやすい傾向があります。
例えば、1億円の現金をそのまま相続した場合、インフレが進むと実質的な価値が目減りしてしまいます。これが、1億円のアパートを相続した場合では、地価・不動産価格の上昇にともない、資産価値が維持または上昇する可能性があります。また、賃貸住宅の家賃は、長期的にはインフレとともに上昇する傾向があるため、実質的な資産の価値を守れるのです。
貨幣価値の変動に左右されない実物資産を取得できるという点において、アパートの相続は大きなメリットがあるといえるでしょう。
アパートによる相続税対策のデメリット
一方で、アパートによる相続税対策には、以下のようなデメリットも存在します。
遺産が分割しにくくなる
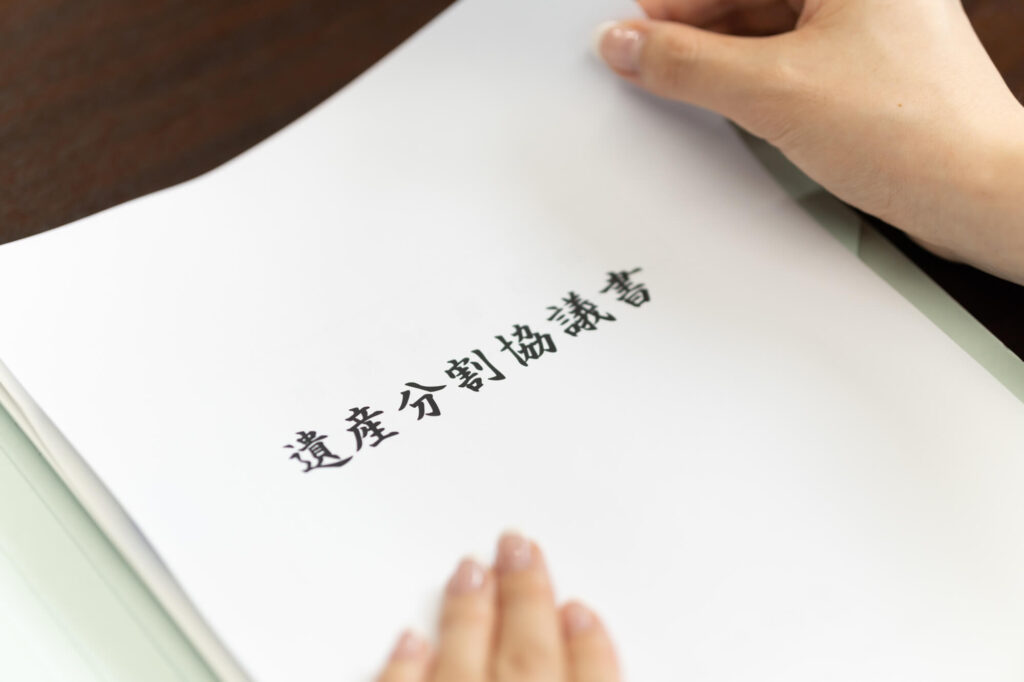
アパートのような不動産は現金や株式と異なり、物理的に分割しにくい資産です。そのため、複数の相続人がいる場合、相続の際にトラブルが発生しやすい点が大きなデメリットとなります。
相続財産として現金1億円を相続する場合は、相続人が2人いれば5,000万円ずつ分けることが容易です。しかし、1億円のアパートを相続する場合、均等に分割することは難しく、共有名義にすると運営方針や売却に関する意思決定が複雑になります。共有名義のままでは一部の相続人が売却を希望しても、他の相続人が反対すると売却できないケースも発生します。
遺産分割協議の際には、十分な協議が必要です。遺産をそのままの形で分割する「現物分割」が難しい場合には、特定の相続人にアパートを相続させる代わりに他の相続人に代償金を支払う「代償分割」を行うなどの方法が考えられます。
アパート経営特有のリスクがある
アパートを相続すると、経営に関するさまざまなリスクを引き継ぐことになります。これには、空室リスク、修繕リスクなどが含まれます。
空室リスクとは、入居者様が入らないために家賃収入が得られないリスクです。相続でローン債務を受け継いだ場合、このリスクは大きな負担となる可能性があります。立地条件の悪い物件や築年数の古い物件は空室になりやすい傾向にあり、安定した収益を確保するのが難しい場合があります。
建物の老朽化による修繕リスクも考慮すべき点です。築年数が進むと、外壁補修や水回り設備の交換などの修繕費用が必要になります。修繕費が不足すると、入居者様の満足度が低下し、さらに空室リスクが高まる悪循環に陥る可能性があります。
アパート経営の承継者を決める必要がある
アパートを相続する場合、経営を引き継ぐ人(承継者)を明確に決めておく必要があります。
アパート経営の相続は、その後の管理・運営が重要であり、経営の知識や経験がない相続人にとっては大きな負担となる可能性があります。相続人が経営を引き継ぐ準備ができていないと、空室が増えたり、修繕計画が適切に実施されなかったりするリスクがあります。
相続人が複数いる場合、アパート経営の承継者を決めておかないと、そのまま共有名義で相続するケースもありえます。共有名義のアパートは、運用方針や家賃収入の分配などをめぐって対立することも多く、売却するときも全員の合意が必要になります。
そのため、被相続人が生前に遺言書を作成し、誰が経営を引き継ぐのかを明確に決めておくことがおすすめです。
アパートを生前贈与するメリット

相続税対策として、アパートを生前贈与するという手段もあります。ここでは、アパートを生前贈与するメリットを4つ紹介します。
生前贈与については、以下の記事も参考にしてください。
■生前贈与に関連する記事
不動産を生前贈与したほうがいいケースとメリット・デメリットを解説
終活で考えるべき不動産の整理!自宅と収益物件のケースを徹底解説
分割贈与で相続税よりも節税できる
アパートを生前贈与する最大のメリットは、相続税よりも贈与税の負担を軽減できる可能性がある点です。特に、分割贈与を活用することで、贈与税の負担を大幅に抑えられます。
日本の相続税は累進課税で、相続財産の総額が大きいほど税率が高くなります。一方で、贈与税には110万円の基礎控除があり、毎年110万円以下の贈与であれば贈与税は発生しません。そのため、毎年少しずつアパートの持分を相続人に贈与することで、贈与税をかけずに資産移転が可能になります。子どもや孫に毎年110万円ずつ贈与すれば、長期間かけて大幅な節税が可能になるでしょう。
さらに、相続時精算課税制度を利用すれば、60歳以上の親が18歳以上の子どもに対して、2,500万円まで非課税で贈与できます。この制度を活用すれば、相続税の対象となる資産を減らしながら、将来的な税負担を軽減できるため、生前贈与は税対策として非常に有効です。
アパート経営の承継人を選べる

生前贈与のもう一つの大きなメリットは、アパート経営を引き継ぐ相続人を事前に選定できることです。通常の相続では、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がアパートを相続するかを決めるケースが多々あります。
アパートを生前に贈与すれば、特定の相続人にのみ確実に経営の承継が可能となります。例えば、長男がアパート経営に興味を持ち、他の兄弟姉妹は希望しない場合、生前贈与を活用すれば、将来的なトラブルを避けつつ、スムーズに事業承継を進められます。
アパート経営には一定のノウハウが必要なため、生前贈与で早めに承継人を決め、事前に経営のノウハウを学ばせることができます。こうした対策により、相続後の経営トラブルを未然に防ぐことが可能です。
贈与する時期を選べる
生前贈与の大きなメリットの一つとして、贈与するタイミングを自由に選べることも挙げられます。相続の場合は、被相続人が亡くなったタイミングで財産が移転するため、税制や市場状況を考慮する余裕がありません。生前贈与であれば、税制が有利な時期や不動産市場が好調なタイミングで贈与できます。
将来値上げが確実視される物件については、早めに生前贈与し、課税価格を抑制するのがおすすめです。
家賃収入を受贈者が得られる
アパートを生前贈与すると、受贈者(子どもや孫)が家賃収入を直接得られるようになります。これには、所得分散の効果があるため、家族全体の税負担を軽減するメリットがあります。
親が複数のアパートを所有していて、すべての家賃収入を得ると、高額所得者となり高額の所得税・住民税が課税される可能性が高まります。一部のアパートを子どもに贈与し、家賃収入を子どもが受け取るようにすれば、所得が分散され、税負担が軽減されます。
また、将来的な相続税発生を見込んで、納税のための原資とすることもできます。
アパートを生前贈与するデメリット

アパートを生前贈与することは、メリットばかりではありません。ここでは、生前贈与のデメリットをいくつか紹介します。
贈与加算がある
アパートを生前贈与する際に注意すべき点の一つが贈与加算の適用です。贈与加算とは、被相続人が死亡する前7年以内に行われた贈与については、相続財産に加算され、相続税の課税対象となるという制度です。
例えば、親が亡くなる5年前に子どもにアパートを贈与した場合、その贈与は相続税の計算上、相続財産として加算され、結果的に贈与税の節税効果がなくなる可能性があります。
生前贈与を計画する際は、被相続人の健康状態や年齢を考慮し、早めに実行することが重要です。
アパートの名義変更に費用がかかる
アパートを生前贈与する場合、所有権の移転登記が必要になり、その際に登録免許税・司法書士報酬などの費用が発生します。
贈与による所有権移転登記には登録免許税がかかり、固定資産税評価額の2%課税されます。一方、相続による名義変更の場合、登録免許税は0.4%と低く抑えられるため、生前贈与の方が名義変更コストが高いといえます。さらに、生前贈与を受けた際は不動産取得税の支払いも生じます。
相続税を節税できたとしても、移転登記にかかる諸費用で損失が出る恐れもあるため、事前にしっかりと資金計画を立てることが重要です。
「定期金に関する権利」と見なされる可能性がある
アパートを生前贈与する場合、贈与税の控除を受けるために毎年110万円以下の持分を暦年贈与するケースがあります。
しかし、毎年同時期に同じ金額を贈与し続けていると、「定期金に関する権利」を贈与したとみなされ、贈与額の合計額に対して贈与税が課税されるおそれがあります。
Q1
親から毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合には、各年の贈与財産の価額の合計額が110万円の基礎控除額以下ですので、贈与税がかからないことになりますか。
A1
定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、各年の贈与財産の価額の合計額が110万円以下であれば、暦年課税に係る基礎控除額または相続時精算課税に係る基礎控除額以下であるため、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約(約束)をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。
引用元:No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁
小規模宅地等の特例が使えなくなる
小規模宅地等の特例は、相続税の計算において大きな節税効果を持つ制度ですが、生前贈与を行うとこの特例を適用できなくなる点に注意が必要です。
小規模宅地等の特例は、被相続人が居住していた宅地や、アパート経営などに使用していた宅地について、一定の条件を満たせば相続税評価額を最大80%減額できる制度です。
しかし、生前贈与を行うと、この特例の適用対象外となってしまいます。生前にアパートを贈与すると、特例が適用されず、結果として税負担が重くなる可能性があります。
相続時に特例を適用できる場合は、生前贈与よりも相続で引き継いだ方が税負担を軽減できるケースもあるため、不動産の評価額や相続税のシミュレーションを行い、最適な方法を選択する必要があります。
相続税計算の手順

ここでは、アパートを相続する際にも利用できる相続税の計算手順を具体例を挙げながら解説します。
法定相続人を確定
相続税を計算するための第一歩は、法定相続人を確定することです。法定相続人とは、民法で定められた相続権を持つ人のことを指し、被相続人(亡くなった人)の家族構成によって順位と範囲が決まります。
配偶者は常に相続人となり、それ以外の親族の法定相続人の順位は以下の通りです。
●第1順位:子(直系卑属)
●第2順位:親(直系尊属)※子がいない場合
●第3順位:兄弟姉妹※子も親もいない場合
例えば、被相続人が亡くなり、配偶者と子2人がいる場合、法定相続人は3人(配偶者+子2人)となります。一方、子がいない場合、被相続人の親が存命であれば、法定相続人は配偶者と親となります。
被相続人に子どもがいる場合は、親や兄弟は相続人となれない点に注意しましょう。
正味の遺産総額を把握
次に、相続税の課税対象となる正味の遺産総額を計算します。正味の遺産総額とは、被相続人が所有していた財産(プラスの財産)から、負債や葬儀費用など(マイナスの財産)を差し引いた金額です。
相続税は、被相続人の遺産すべてが対象になるため、以下のようにプラスの財産とマイナスの財産を全て洗い出す必要があります。
| 分類 | 項目 |
| プラスの財産(課税対象) | ●土地・建物(不動産) ●預貯金・現金 ●株式・投資信託 ●生命保険(みなし相続財産として一部課税) |
| マイナスの財産(控除対象) | ●住宅ローンなどの負債 ●被相続人の未払い税金・医療費・ ●葬儀費用 |
また、祭祀用具、墓地などの非課税財産は遺産総額には含まれません。
正味の総額から基礎控除を引き課税遺産総額を算出
相続税には、基礎控除が適用され、一定額までは相続税が発生しません。基礎控除額の計算式は以下の通りです
3,000万円 +(法定相続人の数 × 600万円)
例えば、法定相続人が配偶者+子2人の場合、基礎控除額は3,000万円 +(3人 × 600万円) = 4,800万円となります。正味の遺産総額が1億円だった場合は、4,800万円を差し引いた5,200万円が課税遺産総額です。
法定相続分に応ずる取得金額を算出
法定相続分に基づき、各相続人が受け取る金額を算出します。民法上の法定相続分は以下の通りです。
| 相続人 | 割合 |
| 配偶者・子ども | ●配偶者:1/2 ●子ども:1/2(複数人いる場合は人数で等分) |
| 配偶者と父母 | ●配偶者:2/3 ●父母:1/3(複数人いる場合は人数で等分) |
| 配偶者と兄弟姉妹 | ●配偶者:3/4 ●兄弟姉妹:1/4(複数人いる場合は人数で等分) |
| 配偶者なし | ●相続順位の高い人が全て相続 |
例えば、課税遺産総額8,000万円で、配偶者と子ども2人の合計3人が相続人となった場合、
法定相続分に従った取得金額は以下のとおりです。
【計算例】
●配偶者:4,000万円(1/2)
●子A:2,000万円(1/4)
●子B:2,000万円(1/4)
この手順は、相続税の計算上必要であり、実際の遺産分割協議における分配とは異なります。
相続税の総額を計算
相続税の速算表を用いて、法定相続分に応じた取得金額に税率と控除額を適用し、相続税の総額を算出します。
相続税の速算表(抜粋):
●1,000万円以下 → 10%
●3,000万円以下 → 15%(控除額50万円)
●5,000万円以下 → 20%(控除額200万円)
たとえば、課税遺産総額8,000万円で、配偶者と子ども2人の合計3人が相続人となった場合、相続税は以下のように計算できます。
【計算例】
●配偶者(4,000万円):4,000万円 × 20% – 200万円 = 600万円
●子A(2,000万円):2,000万円 × 15% – 50万円 = 250万円
●子B(2,000万円):2,000万円 × 15% – 50万円 = 250万円
これにより、相続税の総額は、600万円 + 250万円 + 250万円 = 1,100万円となります。この段階では相続税の総額を算出しただけなので、実際にそれぞれの相続人がこの金額を負担するわけではありません。
参考:相続税の税率-国税庁
相続税の総額を取得割合に応じて按分
先程の行程で算出した相続税の総額を、遺産分割協議書の内容にもとづいて各相続人に按分します。
【計算例】
相続税の総額:1,100万円
配偶者:1,100万円 × 1/2 = 550万円
子A:1,100万円 × 1/4 = 225万円
子B:1,100万円 × 1/4 = 225万円
法定相続分とは異なる割合で遺産を分けた場合は、その分割割合に応じて税額が調整されます。
税額控除などを適用して最終の納税額を確定
最後に、各種税額控除を適用し、最終的な納税額を確定します。代表的な控除には、配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除などがあります。
たとえば、18歳未満の相続人には未成年者控除が適用され、控除額は(18 – 年齢)× 10万円です。もし子Aが15歳なら、(18 – 15)× 10万円 = 30万円が控除され、最終納税額は225 – 30 = 195万円になります。
また、配偶者には1億6千万円までが非課税となる配偶者控除が適用されるため、配偶者に相続税が発生することはほとんどありません。
このように、相続税の計算には複数のステップがあり、正確な計算と適用できる控除を理解することが重要です。
アパートの相続税計算シミュレーション

ここでは、アパートを相続した際の相続税を試算します。
相続人は配偶者と子ども2人(成人済み)の合計3人で、現金で相続した場合とアパートで相続した場合のそれぞれについて、シミュレーションを紹介します。
現金1億5,000万円のケース
前述の7つの手順に沿って、相続税を計算します。
① 法定相続人の確定
法定相続人は配偶者と子ども2人の計3人です。
② 正味の遺産総額を算出
遺産は現金1億5,000万円のみであり、負債がないため、そのまま課税対象となります。
③ 基礎控除額の計算
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人3人) = 4,800万円
課税遺産総額 = 1億5,000万円 – 4,800万円 = 1億200万円
④ 法定相続分に応じた取得金額を算出
配偶者 1/2(5,100万円)
子ども 1/4(2,550万円 × 2人)
⑤ 相続税の総額計算(速算表適用)
配偶者:5,100万円 × 30% – 700万円 = 830万円
子ども1人あたり:2,550万円 × 15% – 50万円 = 332.5万円
相続税の総額 = 830万円 + 332.5万円 × 2 = 1,495万円
⑥ 相続人ごとの取得割合に応じて按分
配偶者:1,495万円 × 1/2 = 747.5万円
子ども:1,495万円 × 1/4 = 373.75万円
⑦ 最終的な納税額
配偶者:0円(配偶者控除1億6,000万円以下が適用)
子ども:373.75万円
合計納税額:747.5万円
以上の計算により、子どもには1人あたり約371万円の相続税が発生します。
アパートを建築したケース

現金1億5,000万円のうち、1億円は現金のまま相続します。5,000万円の頭金と1億5,000万円の借入により、土地部分1億円(時価)、建物部分1億円(時価)のアパートを建築して相続した場合の相続税を計算します。
土地部分
アパートを建築する場合、土地部分の相続税評価額は時価ではなく、路線価方式または倍率方式を用いて計算されます。ここでは、路線価方式を採用すると仮定します。
土地の時価は1億円ですが、相続税評価額は時価の約80%程度になるため、土地の相続税評価額は8,000万円と仮定します。さらに、アパートを建築することで土地は貸家建付地となり、借地権割合と借家権割合による評価減を適用できます。
例えば、借地権割合が60%、借家権割合が30%とすると、評価額の計算式は以下の通りです。
貸家建付地の評価額 = 8,000万円 ×(1 – 借地権割合 × 借家権割合)
= 8,000万円 ×(1 – 0.6 × 0.3)
= 6,560万円
結果として、土地の相続税評価額は6,560万円となり、アパートを建てることで土地の評価額が減額され、相続税の負担を軽減できます。
建物部分
アパートの建物部分は、固定資産税評価額を基準に相続税が計算されます。一般的に、固定資産税評価額は時価の60%程度となるため、ここでは建物の時価1億円に対し、相続税評価額を6,000万円と仮定します。
さらに、アパートの建物部分は貸家として扱われるため、借家権割合(30%)による評価減が適用されます。賃貸割合が100%だとすると、評価額の計算式は以下の通りです。
貸家の相続税評価額 = 6,000万円 ×(1 – 借家権割合×賃貸割合)
= 6,000万円 ×(1 – 0.3×1)
= 4,200万円
結果として、建物の相続税評価額は4,200万円となり、賃貸アパートにすることでさらに評価額を抑えられます。
相続税を計算する
以上の土地部分と建物部分の評価額の計算結果を踏まえて、相続税を試算します。相続人は現金で相続した場合と同じく、配偶者と子ども2人の計3人です。
アパートの建築から10年後に相続が発生したとしてローン残高は1億3,000万円と仮定すると、遺産総額は以下のとおりです。
現金部分(相続財産としてそのまま相続する現金):1億円
土地部分の評価額:6,560万円(貸家建付地の評価額)
建物部分の評価額:4,200万円(貸家の評価額)
負債控除(借入金):1億3,000万円(銀行借入)
② 正味の遺産総額
= 1億円(現金) + 6,560万円(土地) + 4,200万円(建物) – 1億3,000万円(借入金)
= 7,760万円
③ 基礎控除額の計算
課税遺産総額 = 7,760万円 – 4,800万円(基礎控除額) = 2,960万円
④ 法定相続分ごとの取得額(法定相続割合適用)
配偶者:1,480万円(1/2)
子ども2人:730万円(1/4)
⑤ 相続税額の計算(速算表適用)
配偶者:1,480万円 × 15% - 50万円 = 172万円
子ども2人:740万円 × 10% = 74万円
相続税の総額 = 172万円 + 74万円 + 74万円 = 320万円
⑥ 相続税の総額を取得割合に応じて按分
配偶者:320万円 × 1/2 = 160万円
子ども2人:320万円 × 1/4 = 80万円
⑦ 最終納税額
配偶者:0円
子ども2人:80万円
合計納税額:80万円 × 2 = 160万円
以上の計算により、現金で相続した場合の合計納税額742.5万円と比較すると、およそ21%程度まで相続税額を抑えられます。
このように、アパートは相続税評価額が低くなるため、相続税の節税上有効な選択肢といえるでしょう。
まとめ

本記事では、アパートが相続税対策として有効な理由や、実際の相続税シミュレーションなどを詳しく解説しました。
アパートによる相続税対策は、節税や家賃収入といったメリットがある一方、遺産分割の難しさや経営リスクをともないます。計画的な準備とリスク管理のためには、信頼できる賃貸管理会社のサポートを受けることが重要です。
アパートの相続を検討している人は、ぜひ【リロの不動産】にご相談ください。
関連する記事はこちら
相続税を抑える決め手は?不動産評価制度の仕組みと注意点を解説
不動産の活用で相続税対策! 賃貸経営・アパート経営が効果的な理由と注意点
不動産物件を相続するときの手続きとは? 相続税を払えない場合はどうする?
アパートは相続税対策に有効! 相続税計算でメリットを検証・解説付き
アパート経営は相続対策に有効!資産管理会社の活用でメリット拡大
マンションの相続税を把握!評価額と節税対策の特例・注意点を解説
不動産購入が相続税対策になる理由!物件種類別の節税対策と注意点を解説
相続税が払えない地主になる前に!納税資金対策の物納・延納・生前対策を解説
両親のアパートを相続!売却か賃貸経営継続かを判断するポイントと注意点
2024年から始まる相続税増税の全貌! 税制改正の影響と対策を徹底解説
認知症の両親がいる時の不動産相続対策!遺言・家族信託・成年後見を解説
アパートローンの相続に関する注意点!債務者死亡時によくあるトラブルと対策
おすすめのサービス
おすすめのお役立ち情報
この記事を書いた人
秋山領祐(編集長)
秋山領祐(編集長)
【生年月日】昭和55年10月28日。
【出身地】長野県上田市。
【趣味】子供を見守ること。料理。キャンプ。神社仏閣。
【担当・経験】
デジタルマーケティングとリブランディングを担当。
分譲地開発のPMや家業の土地活用などの経験を持つ。
リノベした自宅の縁の下に子ども達の夢が描かれている。