アパート経営の節税戦略!減価償却・法人化・相続税対策の全てを解説
2025.08.10
アパート経営の大きなメリットの一つに節税があります。高額所得者にとっては頭の痛い税金対策ですが、アパート経営は節税に大きな力を発揮します。
アパート経営で節税できる税金は、主に所得税、住民税、相続税です。この記事では、アパート経営の節税戦略として、所得税・住民税対策と相続税対策に分け、それぞれの注意点を含めて詳しく解説します。
▼この記事の内容
●アパート経営で所得税・住民税の節税につながるのは、帳簿上の赤字幅を大きくでき、損益通算で課税所得を圧縮できる減価償却の活用。
●所得税・住民税対策としては、青色申告特別控除や小規模企業共済、iDeCoや生命保険料控除の活用も効果的。
●アパートなどの賃貸不動産は相続税評価額が圧縮され、相続税の節税になる。
●アパート経営の法人化は所得税・住民税節税にも、相続税の節税にも有効。
●節税目的でアパート経営を行うときは、収益性を無視した物件選びをしない、融資枠を無駄に使わない、出口戦略を意識する、デッドクロスの回避などの注意点がある。
目次
【所得税・住民税対策】減価償却を活用した節税
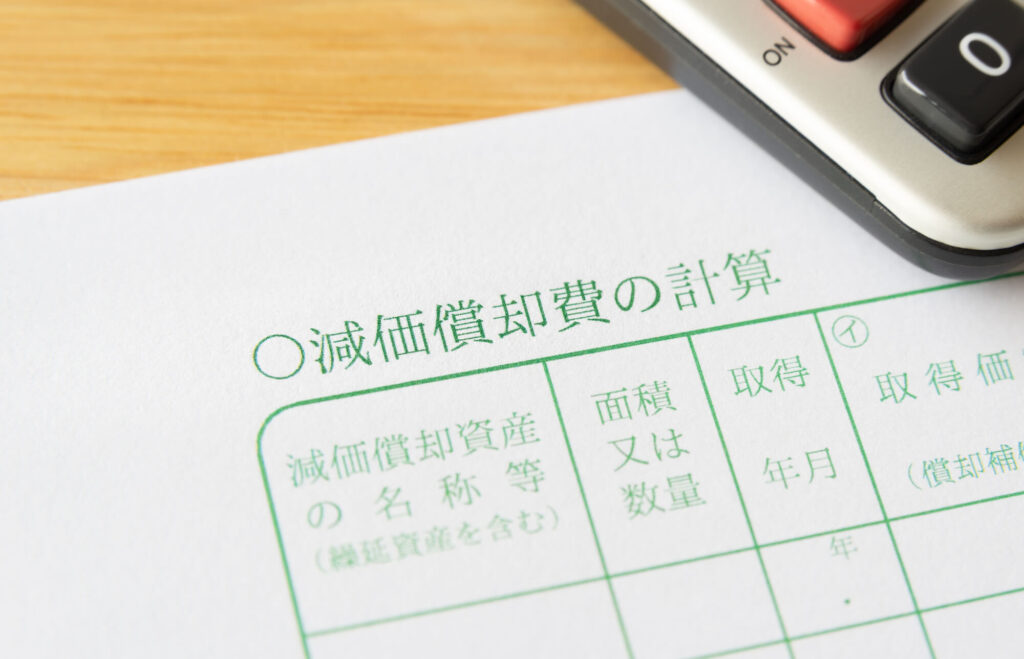
アパート経営が節税につながるのは、何といっても減価償却ができる点です。アパートのような固定資産は、購入した年に全額費用として計上しません。長期間にわたって使い続けるものであるため、一定の年数をかけて減価償却費として経費計上します。
アパート経営が節税になるのは、減価償却という会計処理によるところが大きいのです。なぜ減価償却を活用すると節税になるのか、その仕組みを解説します。
所得税・住民税対策については、以下の記事もご覧ください。
■所得税・住民税対策の記事
一棟アパート購入から始める不動産投資!成功者が確認する指標と利回りも解説
家賃収入にかかる税金はいくら?設備投資と損益通算で考える節税対策
【事例付】不動産売却の譲渡損失の損益通算!基本知識と注意点を解説
不動産所得は損益通算が可能
アパート経営をしていると不動産所得が発生するため、確定申告を行わなければなりません。申告が必要な税金には総合課税と分離課税という、2種類の課税方法があります。特定の所得に対して、他の所得とは分けて個別に税額を計算する方式を分離課税といい、複数の所得を合算して税額を計算する方式を総合課税といいます。
不動産所得は総合課税であり、ほかに給与所得や事業所得があれば損益通算ができます。複数の所得を合算することで課税所得が抑えられれば、それだけ所得税・住民税の納税金額も少なくなります。
不動産所得を得るようになると確定申告が義務付けられますが、損益通算で節税になる場合、源泉徴収されていた所得税が確定申告後に一部還付されます。
減価償却という会計処理

減価償却はアパートのような事業のために用いられる建物や建物付属設備、機械装置や車両運搬具など、何年にもわたって使えるものに対して使う経費計上の方式です。購入時の金額が大きく、一括で経費として計上すると、初年度にいきなり大きな赤字が出てしまいます。
減価償却資産である建物などは、何年もの間収益をもたらします。そこで、耐用年数に応じ、複数年にわたって経費計上しようとする仕組みが減価償却です。この減価償却という方式があるために、アパート経営で出た赤字をほかの所得と相殺し、課税所得の圧縮が可能になります。
減価償却では、実際はお金が出ていかないにもかかわらず帳簿上は減価償却費として経費計上されるため、キャッシュフローを得やすくなるメリットがあるのです。
なお、同じ不動産でも、土地は年数の経過で価値が減っていくものではないため、減価償却の対象にはなりません。
減価償却による節税では譲渡所得税に注意

アパート経営をしていると、最終的に物件を売却するタイミングが出てきます。物件を売却したときに出た売却益は、譲渡所得と呼ばれほかの所得と同じように、所得税や住民税が課税されます。また、2011年に発生した東日本大震災からの復興に必要な財源の確保として、2037年までの期間限定で創設された「復興特別所得税」も納めなければなりません。
譲渡所得税の税率は、売却するタイミングによっても変わります。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得の計算式は以下のとおりです。
譲渡所得=不動産の売却価格-(取得費+譲渡費用)
売却時に買主から譲渡日以降の固定資産税や都市計画税相当の支払いを受けている場合、その金額も計算式の売却価格に加えます。取得費は、物件の購入価格と取得にかかった費用の合計金額です。
物件の購入時には不動産取得税や登録免許税、印紙税などの各種税金がかかります。また、不動産仲介会社に支払う仲介手数料や、手続きを司法書士に依頼した場合は司法書士報酬など、さまざまな諸費用がかかっているでしょう。
取得費には以上の諸費用も含めて計算しますが、確定申告で減価償却費を計上している場合は、ここから所有していた期間の減価償却費を差し引きます。減価償却を多用していると取得費の金額が小さくなり、反対に譲渡所得は大きくなってしまうため、結果的に譲渡所得税も高くなります。
アパート経営における節税効果を最大限に得たい場合、売却時の譲渡所得税も考慮する必要があるのです。
譲渡所得税の税率
譲渡所得税の税率は、売却した物件の所有期間によって変わります。所有期間を決める基準日は、売却した年の1月1日です。基準日に所有期間が5年を超えている場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得となります。
長期譲渡所得の税率は、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%、合計20.315%です。一方、短期譲渡所得の税率は、所得税30%、住民税9%、復興特別所得税0.63%、合計39.63%となり、支払う税金の金額は倍近くになります。
売却するタイミングによっては、多くの譲渡所得税がかかるかもしれません。節税を優先するのであれば、売却する時期は所有期間が5年を超えてからにするといいでしょう。
アパート経営で節税になる年収の目安
アパート経営の節税メリットを説明してきましたが、所得税の税率を考えると、アパート経営で大きな節税効果を得られる目安は、課税所得が900万円(年収では約1,200万円)以上の方だといえます。
所得税の税率は所得が高くなるほど上がる超過累進課税となっているため、課税所得が高い高額所得者ほど節税メリットがあります。目安は、所得税の税率が33%になる課税所得900万円以上の方です。長期譲渡所得の譲渡所得税率20.315%を上回っており、さらに住民税10%が課税されるため、減価償却を利用していても、最終的に節税となる場合が多いからです。
アパート経営による節税シミュレーション

では、実際にアパート経営を行うことで、どのくらいの節税効果が得られるのでしょうか。ここからは具体的なケースを想定し、年間の節税額や売却時の譲渡所得税がどのくらい節税できるのか、シミュレーションをします。
アパートの物件概要
シミュレーションする物件の概要は以下のとおりです。シミュレーションを分かりやすくするために、物件は現金購入とし満室にて運営すると想定しています。また、各種所得控除、税額控除も考慮していません。
・築28年・軽量鉄骨造(厚み3㎜超4㎜以下)アパート
・減価償却期間 5年
・物件金額 1億円(土地3,000万円、建物7,000万円)
・現金購入
・年間満室想定賃料 700万円
・運営費用 200万円
以上の条件をもとに、次の段落からはアパート経営における年間の節税額と売却時の譲渡所得税を試算してみましょう。
アパート経営における年間の節税額を試算
まずは不動産所得の計算をしてみます。営業利益は年間満室想定賃料700万円から、運営費用の200万円を引いた500万円です。減価償却費は7,000万円で購入した建物を5年で償却するため、7,000万円÷5年で1,400万円となります。
課税所得は営業利益の500万円から減価償却費の1,400万円を差し引くため、-900万円です。オーナー様の給与年収を1,200万円(課税所得900万円)と仮定して損益通算すると、900万円-900万円=0万円となります。
課税所得900万円に対する所得税の税率は33%、控除額は153万6,000円であることから、所得税額は143万4,000円、住民税の所得割は10%で住民税額は90万円、合計すると233万円4,000円です。損益通算してトータルの課税所得が0円になるため、確定申告でこの233万円4,000円が還付されます。
売却時の譲渡所得税を試算
次に購入から5年後、20%値落ちしたアパート(土地・建物)を8,000万円で売却した場合の譲渡所得税の試算です。譲渡費用として、手数料などが200万円かかったとしたと仮定します。
譲渡所得は不動産の売却価格から取得費と譲渡費用を引いて算出するため、8,000万円-(1億円-7,000万円)-200万円で4,800万円です。所有期間は5年を経過しているため、長期譲渡所得の税率20.315%を適用して、譲渡所得税は4,800✕0.20315=975万1,000円になります。
前の段落で計算した1年間の節税分233万円4,000円✕5年分=1,167万円と比較してみましょう。1,167万円-985万円1,000円=191万9,000円となり、譲渡所得税を支払っても191万9,000円の節税となりました。なお、家賃収入は、所有していた5年間で合計2,500万円を得ています。
【所得税・住民税対策】青色申告特別控除

青色申告特別控除は、青色申告を行う事業者が受けられる税制上の特典です。要件を満たしていれば所得金額から一定の金額を差し引くことができる制度で、最大65万円の控除が受けられます。以下で詳しい要件を解説しますので参考にしてください。
65万円控除を受けるための要件
アパート経営で65万円の青色申告特別控除を受けるためには、以下で挙げる要件をクリアする必要があります。
・青色申告承認申請書を提出していること
・賃貸経営が事業的規模であること
・複式簿記で記帳していること
・青色申告を選択し、決算書の作成・提出していること
・現金主義ではないこと
・申告期限内に提出していること
・e-Taxによる申告、または電子帳簿保存に対応していること
65万円の控除を受けるためには、まず青色申告承認申請書を提出していなければなりません。また、白色申告では簡易簿記(単式簿記)でもかまいませんが、65万円の控除を受けるためには、複式簿記で日々の取引を記帳し、貸借対照表や損益計算書などの決算書も作成して確定申告の際に提出する必要もあります。
もちろん、確定申告は期限内に行わなければなりません。また、65万円の控除を受けるためには、e-Taxによる申告または電子帳簿保存に対応している必要もあります。対応していなければ65万円の控除は受けられず、55万円の青色申告特別控除が適用されるため注意してください。
10万円控除を受けるための要件
青色申告を選択していても、どれか一つでも上記の項目を満たさなかった場合は、10万円の特別控除が適用されます。例えば、簡易簿記による記帳を行っていても、現金主義用の青色決算書を作成して青色申告の手続きはできますが、上記の要件を満たしていないため、特別控除は10万円です。
また、65万円の控除を受けるための要件をほぼ満たしている状態でも、手続きが申告期限を過ぎてしまうと10万円の控除となるため注意してください。
【所得税・住民税対策】小規模企業共済
小規模企業共済は小規模企業の経営者や役員、個人事業主のための共済制度です。小規模企業の経営者や役員、個人事業主は、退職金制度が整った企業などに勤めている方とは違い、事業を廃業・退職した際の保証が十分ではありません。そこで、廃業・退職後の生活の安定や事業の再建を図るための資金を準備しておく共済制度として、1965年に始まりました。
小規模企業共済の掛金は全額が所得控除の対象になるため、節税効果があります。加入後に掛金の増額・減額ができるほか、受け取りは一括・分割のどちらも可能です。また、小規模企業共済の契約をしていると、掛金の範囲内で低金利の貸付制度を利用できるメリットもあるため、節税効果を得ながら備えておくのもおすすめです。
【所得税・住民税対策】iDeCo
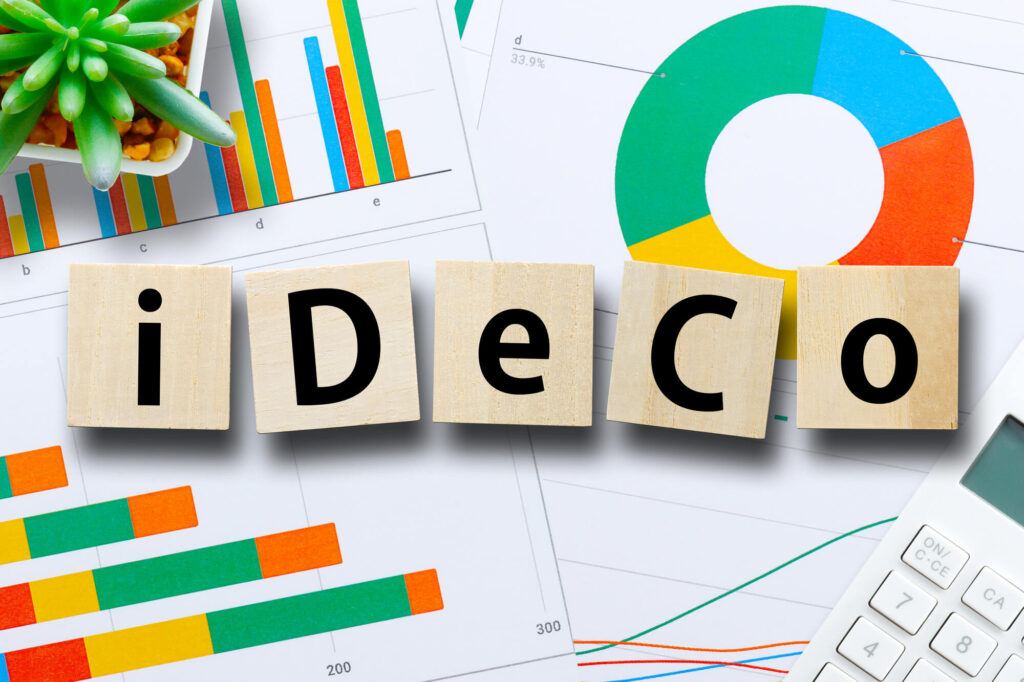
iDeCoと呼ばれる個人型確定拠出年金は、加入が任意の私的年金制度です。iDeCoでは掛金を自分で拠出して積み立て、運用も自分で行い、老後の資金として準備します。老後の資産形成を目的としていることから、税制が優遇されているのが特徴です。
掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となるため、毎年所得税や住民税の税金が軽減されます。また、通常は金融商品を運用したことで得られる運用益には課税されますが、iDeCoの運用益は非課税です。
受取方法は年金として受け取る方法と、一時金として受け取る方法を選択できます。年金として受け取る場合は公的年金等控除、一時金として受け取る場合は退職所得控除の対象になるため、ここでも節税効果があります。
【所得税・住民税対策】生命保険
生命保険料控除とは、支払った生命保険料に応じて一定の金額の控除が受けられる制度です。将来への備えとして、生命保険を掛けている方は多いのではないでしょうか。所得税や住民税の節税として、支払っている生命保険料などの掛金も控除の対象になるのはメリットです。
対象となるのは生命保険料のほか、介護医療保険料や個人年金保険料などがあります。生命保険料控除の控除額は、最高で12万円です。各種保険に加入しておくことで、自分が亡くなったときの遺族への補償や医療・介護への備え、老後の資金としての備えとして保険料を支払いつつ、節税にも役立ちます。
なお、2012年1月1日以降に締結した分と、2011年12月31日以前に締結した分では控除の取り扱いが異なるため注意してください。
【相続税対策】アパート経営による相続税評価額の圧縮

相続税を計算する際、現金や預貯金、株式などは相続税評価額が時価100%です。しかし、不動産の場合は、実際に不動産売買などで取引されている時価(実勢価格)では評価されません。
別の評価方法で相続税が評価されることで相続税評価額が下がるため、現金や預金、株式などよりも不動産を所有しているほうが相続税評価額を圧縮できます。不動産は土地部分と建物部分で、それぞれ分けて計算します。
土地は後述する路線価方式や倍率方式で評価され、相続税評価額は実勢価格のおおよそ80%です。建物は固定資産税評価額が相続税評価額になり、実勢価格の70%程度になります。
さらに賃貸不動産は他人に貸しているため、所有者の自由度が制限されると評価され、借地権割合・借家権割合が算定されるので、さらに相続税評価額が低くなります。アパート経営は相続税の節税対策として効果的です。
相続税対策については、以下の記事もご覧ください。
■相続税対策の記事
認知症の親御さんの不動産を売却する際の注意点!成年後見制度と売却の流れ
相続税を抑える決め手は?不動産評価制度の仕組みと注意点を解説
不動産を相続するには誰に相談すればよいのか? 相続手続きの期限も解説
知っておくべき相続税対策! 不動産を活用した節税の仕組みを解説
相続税の基礎控除とは? 各種控除と賃貸不動産を活用した相続税対策
不動産の相続税評価額の計算方法とは? 相続税が節税できる理由を解説
不動産売却時の税金を無料相談!譲渡所得税の基本知識と相談先の選び方を解説
土地部分の相続税評価額
土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式の2種類があります。また、居住用の土地や小規模の事業用の土地を相続した場合は、「小規模宅地等の特例」という制度があるため、相続税の減額になります。
路線価方式

路線価方式は毎年各国税局が作成している路線価図にもとづき、土地を評価する方式です。路線価とは、道路に面する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価額で、千円単位で表されています。路線価をもとにした評価額の計算式は以下のとおりです。
路線価 ×補正率・加算率 × 地積
土地は形状もさまざまだったり、一つの面の一部だけしか路線に接していなかったりなど、個別に条件が違っています。また、正面の路線だけではなく、側面や裏面の道路にも面している土地もあるでしょう。そのため、評価額を計算する際は、路線価に補正率や加算率も掛けて算出します。
路線価方式はほとんどの市街地で適用されており、国税庁が提供している「路線価図・評価倍率表」のページで調べることが可能です。
倍率方式
倍率方式は、路線価が定められていない地域にある土地の評価で採用される方式です。倍率方式では、土地の固定資産税評価額を用いて評価します。計算式は以下のとおりです。
固定資産税評価額 × 倍率
固定資産税評価額に掛ける倍率は、国税庁の「路線価図・評価倍率表」から各都道府県のページを開くと、市区町村別に倍率表が公表されています。倍率表には固定資産税評価額に掛ける倍率が宅地や田、畑、山林などの地目別に倍率が示されているほか、借地権割合も記載されています。
計算のもとになる固定資産税評価額は、対象の固定資産がある市区役所や町村役場、都税事務所などで確認してください。なお、路線価方式と倍率方式のどちらを評価方法として用いるのかは、土地によって決まっています。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、相続した土地の相続税評価額を算出する際、要件に応じて課税価格に算入する割合が最大80%減額される制度です。例えば、居住用の土地であれば、330m2までの部分について、80%の減額になります。また、特定同族会社事業用宅地等に該当する土地の場合も、400m2までの部分について80%の減額です。
賃貸事業用の土地の場合は、200m2までの部分について50%減額となります。この特例の対象となるのは特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等、特定居住用宅地等、貸付事業用宅地等の4つのうち、いずれかに該当するものです。
特例を受けるためには、小規模宅地等にかかる計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど、必要書類を添付して、相続税の申告の際に提供を受ける旨を記載しなければなりません。ただし、相続時精算課税に係る贈与によって取得した宅地等や、申告期限前に売却した宅地には特例が適用されないため、要件を確認する必要があります。
建物部分の相続税評価額
建物部分の相続税評価額は、固定資産税評価額で定められます。建物といっても、戸建て住宅やアパート・マンションなどいくつかのケースがありますが、被相続人が居住していたマイホーム(実需物件)の場合は、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額になります。計算式は以下のとおりです。
固定資産税評価額 × 1
固定資産税評価額は市区町村の役所・役場や都税事務所などで確認できるほか、毎年市区町村から送付されてくる固定資産税課税明細書の家屋の欄にも記載されています。マイホームとして使用されていた建物のケースで考えてみると、固定資産税課税明細書に記載されている金額が1,000万円であれば、相続税評価額もそのまま1,000万円となります。
借地権割合・借家権割合
アパートやマンションのような賃貸不動産の土地部分は、自宅として使用される自用地とは違い、貸家建付地といわれます。借地権は建物を建てることを目的として土地を借りる権利で、建物は建てた方が所有していますが、土地は借りているという状況です。借家権割合は入居者様が、その建物を借りる権利を意味します。
借地権割合と借家権割合も、国税庁の路線価図・評価倍率表で確認することが可能です。賃貸不動産の土地部分と建物部分は、それぞれ以下の計算式で評価されます。
土地部分:更地としての評価額×(1-借家権割合×借地権割合×賃貸割合)
建物部分:建物の固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
その場所で生活している入居者様がいる賃貸不動産は、所有者が自由に使える自用地に比べて売却なども簡単にはできず、価値が低いとされています。そのため、相続税評価額の計算においても、借地権や借家権が計算式に含まれているのです。借地権割合は30〜90%、借家権割合は一律で30%、賃貸割合は物件を賃貸に出している割合で計算します。
【所得税・住民税・相続税対策】アパート経営の法人を設立する

所得税・住民税と相続税の双方への対策として効果のある方法に、アパート経営を法人化するという選択肢があります。法人の設立にはメリットもデメリットもあるため、法人化を検討するのならば、どちらも把握しておくことが重要です。
アパート経営の法人化については、以下の記事もご覧ください。
■アパート経営法人化の記事
不動産投資は法人化がお得?節税対策につながるメリット・デメリット
【高額納税者必見】高所得者向け節税対策とは? 不動産投資と資産管理会社
アパート経営法人化のメリット
アパート経営を法人化することで、どのようなメリットが得られるのでしょうか。税金や経費、融資の面でメリットがあるほか、相続が発生した際に遺産分割がスムーズに進んだり、相続税の節税につながったりするのもメリットです。
所得税と法人税のギャップ
個人の収入にかかる所得税は、課税所得が高くなるほど税率も高くなる累進課税です。例えば課税所得が330万円から694万9,000円までの税率は20%、695万円から899万9,000円までは23%、900万円から1,799万9,000円になると33%になります。
一方、法人に対しては法人税がかかりますが、本社の所在地や所得金額によって異なるものの、実効税率は30数%程度です。個人でアパート経営をしている場合、課税所得が900万円以上になると税率は33%、さらに1,800万円以上になると40%になります。
課税所得が低いうちはそれほど税金面でのメリットはないかもしれませんが、900万円以上になれば法人化したほうが節税になるといえます。
経費計上の幅が広がる
個人でアパート経営をしているケースでは、経費として計上できる範囲が限定されていますが、法人化すれば経費計上の幅が広がり、節税につながるのも大きなメリットです。アパート経営に必要な費用は、基本的に経費として計上できます。経費として計上した分は収益から差し引けるため、課税所得を少なくできるという仕組みです。
個人事業主だとオーナー様に給与や役員報酬を経費計上できませんが、法人化すればそれも可能です。出張した場合、社長へ日当を支給できるため、経費としての計上が可能です。
また、個人事業主の場合、家族への給与は生計を一にしていると原則として経費化できません。法人化する際に家族を役員か従業員として据えていれば、家族にも役員報酬や給与の支払いができます。家族への報酬・給与は「所得の分散効果」があり、所得税と相続税の対策としても有効です。
融資の面で有利になる
一般的に法人のほうが、個人事業主に比べて社会的信用度は高いとされています。法人は登記されており、事業内容や資本金などが公開情報として確認できます。金融機関は企業の透明性を評価しやすく、信用度が高いと判断します。
また、法人になると複式簿記による帳簿付けを行う必要があり、決算の実施も義務付けられています。その分、法人は第三者の目からみても経営状況や財政状態を確認しやすいため、個人事業主よりも信用を得やすくなります。そのため、金融機関も融資にゴーサインを出しやすく、審査で有利に働く場合があります。
相続税の節税とスムーズな遺産分割
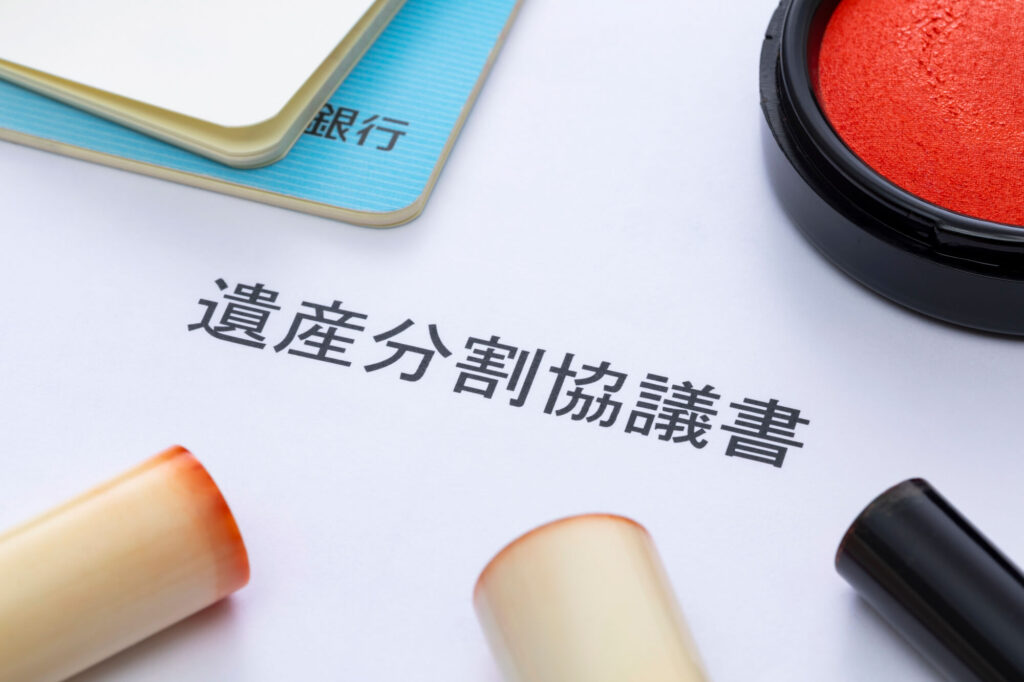
株式会社で法人化すれば、株式の資産価値を下げることで、相続税評価額も下げられます。
例えば、相続財産が現金だった場合は額面の金額がそのまま相続税評価額になりますが、アパートのような収益物件は相続税評価額を下げられます。設立した法人がアパートを保有した場合、3年経過すると個人の場合と同じ相続税評価額を適用できるようになります。結果的に、相続税の節税にもつながるのです。
また、個人でアパートを所有していると、相続が発生した際、当然ながら相続財産である不動産も遺産分割の対象になります。現金などと違い、簡単に分割できない不動産は、遺産分割協議で揉める原因にもなりかねません。
しかし、法人化で株式会社にしておくと、相続財産の分割は株式の分割で済みます。遺産分割が不平等になることも少なく、遺産分割協議もスムーズに進むでしょう。
アパート経営法人化のデメリット
アパート経営を法人化するメリットは複数ありますが、デメリットがないわけではありません。実際にアパート経営の法人化を検討する際は、以下の3つのデメリットもふまえる必要があります。
初期費用がかかる
法人を設立する際、初期費用がかかるのはデメリットの一つです。株式会社や合同会社など、会社形態によって費用の金額は異なりますが、法人登記関係や不動産登記関係の初期費用は最低限必要です。
例えば、株式会社を設立する登記では、資本金金額の0.7%、または15万円のどちらか高いほうの登録免許税がかかります。合同会社の登録免許税は資本金金額の0.7%、または6万円のどちらか高いほうです。また、法人を設立するためには定款を作成しなければなりませんが、株式会社の場合は資本金の金額に応じて定款の認証手数料も必要になります。
ほかにも法人の実印作成代や印鑑証明代、謄本手数料など、こまごまとした費用を用意しなければなりません。アパートをオーナー様の個人名義から法人の名義に変更すると、不動産の登録免許税や不動産取得税もかかります。さまざまな手続きを専門家に依頼した場合は、その報酬も費用として発生するため、法人の設立にはある程度の初期費用がかかることを考慮する必要があるでしょう。
維持費用がかかる
初期費用だけではなく、法人としてアパートを運営していくための維持費用や手間が増えるのもデメリットです。個人でアパート経営をしているときは、納める税金が所得税でしたが、法人になると法人税になります。先述したように、アパート経営がある程度の規模になれば、所得税よりも法人税のほうが税率を低くできるのはメリットでした。
法人化すると、あらたに個人が納める住民税とは異なる法人住民税が発生します。個人でアパート経営をしている場合、赤字ならば住民税を支払う必要がありません。しかし、法人住民税は資本金や従業員数に応じて計算される均等割の仕組みをとっており、赤字であっても納税する必要があります。
従業員を雇用するのであれば、社会保険にも加入しなければなりません。複式簿記による取引の記帳や決算・確定申告の手続きも専門的で複雑になるため、税理士に依頼する必要がでてくると、その分の費用も発生します。法人化する際は、維持費用を上回る節税効果が見込めるかどうかを判断する必要があるでしょう。
オーナー様でも資金を自由には使えない
個人の所有でアパート経営をしている場合、最低限アパート経営に必要な経費分を残しておけば、自分で稼いだお金は自由に使えます。しかし、アパート経営を法人化すると収益は法人の売上になるため、資金の使い方は自由度が下がります。オーナー様は法人の役員となり、役員報酬を受け取る立場になるからです。
オーナー様であっても法人の資金は自由に使えません。もし、勝手に法人としての資金を使ってしまうと、最悪の場合業務上横領に該当します。家族だけでアパート経営をしているから大丈夫だと思っていても、思わぬトラブルに発展することもありえます。個人で経営していたときの感覚のまま、法人のお金を勝手に動かさないようにしましょう。
節税目的でアパート経営を行うときの注意点
アパート経営を行う理由はオーナー様によって異なるかもしれませんが、節税目的の場合は気をつけておくべきポイントがあります。節税目的でアパート経営を行う際の注意点として、以下で挙げる4点には注意してください。
収益性を無視した物件選びはしない

アパート経営をしている方のなかには、節税が主目的だというケースもあるでしょう。しかし、節税ばかりに目を向けすぎて、収益物件としての事業計画が難しくなるようなら本末転倒となります。
アパート経営をする際は、事業計画が成り立たない物件には手を出さないことが重要です。例えば、木造のアパートは耐用年数が22年と定められていますが、耐用年数を超えた築年数の木造アパートは4年間で償却します。築古の木造アパートを投資先として選ぶと減価償却費を大きく取れるため、課税所得が圧縮されて節税効果が高い点はメリットです。
しかし、築年数が経過すると、空室率が高くなる可能性があります。周囲に魅力のある競合物件が増えると空室を埋めるのが難しくなり、経営が苦しくなることも考えられるでしょう。
節税のみを考えて赤字経営を続けていたとするならば、それは「節税」ではなく、ただの「損失」なのです。
融資枠を無駄に使わないようにする
金融機関による融資では、投資家の属性によって融資枠が決められているケースが多いため、融資枠を無駄に使わないことが大事です。アパートローンのような不動産投資向けの融資では、オーナー様の年齢や職業、収入や勤続年数などのほか、融資枠も意識されます。
融資を活用してアパート経営をするメリットの一つは、手持ちの資金が少なくても、レバレッジを効かせることにより、大きな利益を得られる点にあります。そのため、物件を買い進めるためにさらなる融資を追い求め、過剰な借り入れになるケースもあります。
将来的な事業拡大を見据えたうえで、融資額は適正化しておくようにしましょう。また、複数の金融機関と関係を結ぶなどして、融資枠を確保しておくことが重要です。
出口戦略を意識する
節税目的で築古の木造物件を取得した場合、いざ売却しようと思ったときに苦労することがあります。築年数が経過した物件は老朽化/修繕リスクが高まるうえ、競争力も低下する傾向です。金融機関の融資も下りにくいため、買主様も限定されます。
アパート経営では、いつか物件を手放すタイミングがやってきます。出口戦略を投資の始めから考えておくようにします。
アパート経営が最終的に成功したかどうかはっきりするのは、売却したときです。なぜなら、運営中は黒字を保っていても、売却時に大きな損失を出してしまうと、蓄積してきたインカムゲインが吹き飛んでしまうこともあるからです。
出口戦略のパターンは物件をそのまま売却するほか、更地にして土地を売却する、建て替えるなど、複数の選択肢があります。アパート経営では、必ず将来直面する出口戦略を意識しておくことが大事です。
出口戦略については、以下の記事もご覧ください。
■出口戦略の記事
【保存版】不動産投資の損益分岐点で着目するポイントは運用と売却!
収益物件を高値で売却する秘訣と注意点|出口戦略の立て方も解説!
デッドクロスが見えたら次の投資判断を
デッドクロスとは、ローンの元金返済額が減価償却費を上回った状態のことです。アパートの取得時から一定期間、減価償却費を経費として計上できることで、帳簿上は赤字が生じる可能性があります。不動産所得の赤字は給与所得や事業所得と損益通算できるため、課税所得を圧縮できるのがメリットです。
しかし、デッドクロスに入ると、現実のキャッシュフローは変わらないにもかかわらず、帳簿上は黒字になり、所得税や住民税が急激に上昇してしまいます。何も対策を施さずにいると資金繰りが悪化し、最悪、黒字倒産になる可能性もあるため、デッドクロスの発生はアパート経営を継続するかどうかの分岐点だといえるでしょう。
特に節税を目的としてアパート経営を行っている場合は、デッドクロスが見えてきた時点で対策を判断する必要があります。具体的な対策としては、①売却する、②新規物件を購入し新たな減価償却を取る、などの方法が考えられます。デッドクロスが見えてきたら、オーナー様の状況に合わせた対策を検討してください。
デッドクロスや減価償却については、以下の記事もご覧ください。
■デッドクロスと減価償却の記事
【事例付】アパート売却の流れと売却時期の見極め方!相続時の注意点も解説
【事例付】一棟アパート売却の成功術!売却時期と諸経費・税金を解説
不動産投資における減価償却とは?節税額の計算方法と注意点を解説!
まとめ

減価償却の活用は、アパート経営において強力な節税手段となります。ほかにも青色申告特別控除や小規模企業共済、iDeCoや生命保険料控除の活用などで、所得税や住民税の節税が可能です。
また、アパート経営を法人化すると所得税や住民税はもちろん、相続税対策にもなります。ただし、節税を目的としてアパート経営を行う場合は、譲渡所得税への備えや出口戦略、デッドクロスの回避といった長期的視点も重要です。
【リロの不動産】はリーシングや入居者管理・建物管理から、リフォームやリノベーション、相続対策や節税対策まで、賃貸経営に関わるさまざまなサポートに対応しています。節税や相続対策としてアパート経営を検討しているのなら、アパート経営をトータルでサポートする【リロの不動産】にお任せください。
関連する記事はこちら
不動産所得を節税するには?減価償却費など代表的な経費【一覧表】
家賃収入の確定申告は必要?必要経費を計上して節税対策を実施しよう
アパート経営は相続対策に有効!資産管理会社の活用でメリット拡大
家賃収入にかかる税金はいくら?設備投資と損益通算で考える節税対策
不動産投資は法人化がお得?節税対策につながるメリット・デメリット
不動産の活用で相続税対策! 賃貸経営・アパート経営が効果的な理由と注意点
アパートは相続税対策に有効! 相続税計算でメリットを検証・解説付き
不動産投資が相続税対策に選ばれている理由は?5つの節税対策も紹介
相続税を抑える決め手は?不動産評価制度の仕組みと注意点を解説
不動産購入が相続税対策になる理由!物件種類別の節税対策と注意点を解説
相続税が払えない地主になる前に!納税資金対策の物納・延納・生前対策を解説
2024年から始まる相続税増税の全貌! 税制改正の影響と対策を徹底解説
アパートローンの相続に関する注意点!債務者死亡時によくあるトラブルと対策
おすすめのサービス
おすすめのお役立ち情報
この記事を書いた人
秋山領祐(編集長)
秋山領祐(編集長)
【生年月日】昭和55年10月28日。
【出身地】長野県上田市。
【趣味】子供を見守ること。料理。キャンプ。神社仏閣。
【担当・経験】
デジタルマーケティングとリブランディングを担当。
分譲地開発のPMや家業の土地活用などの経験を持つ。
リノベした自宅の縁の下に子ども達の夢が描かれている。




















