家賃収入の確定申告は必要?必要経費を計上して節税対策を実施しよう
2024.12.26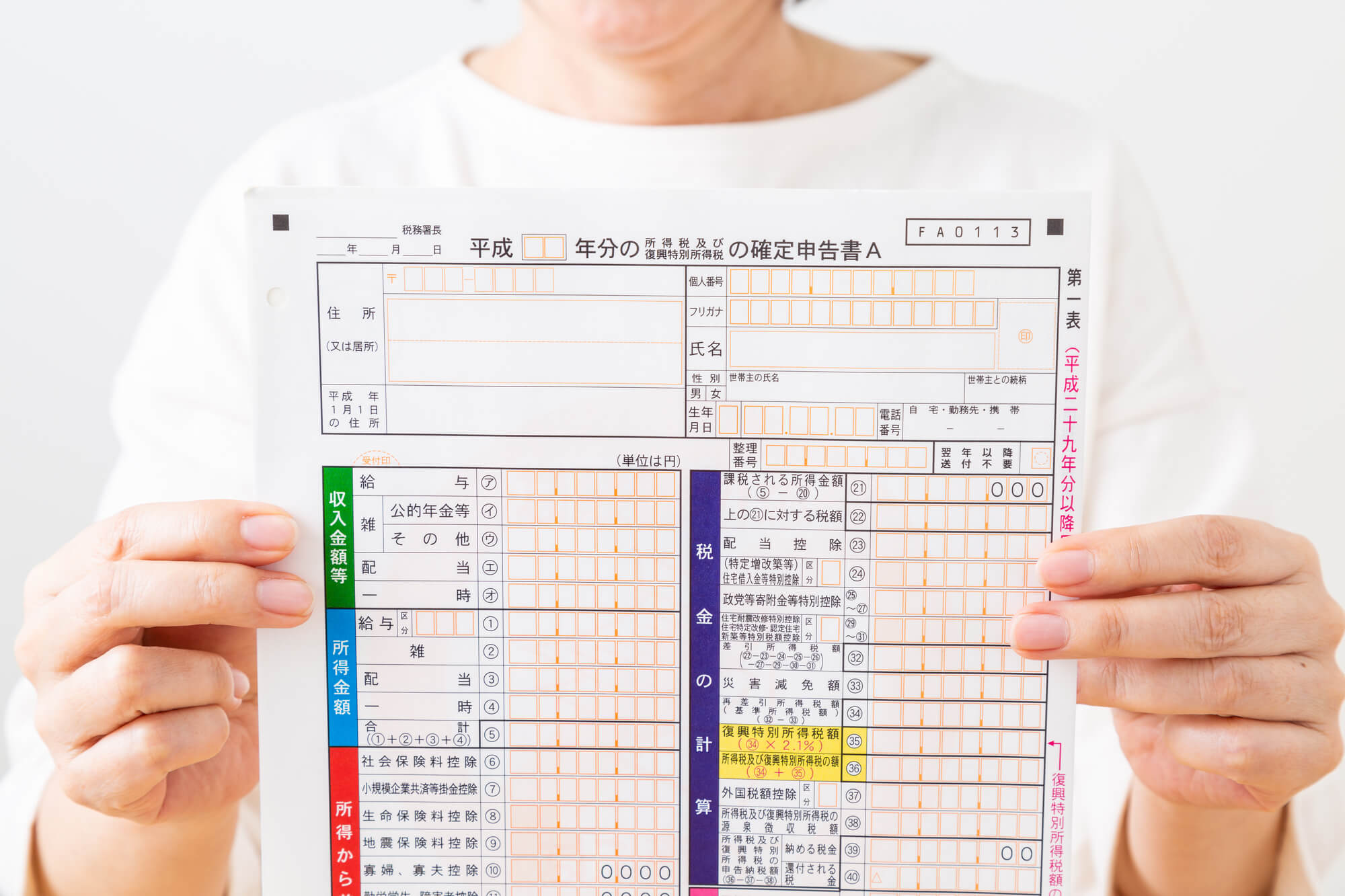
不動産賃貸経営を行っており、家賃収入がある場合、その収入に対する確定申告をどのように行うべきか、基本的なことが知りたいと思っている方もおられるでしょう。確定申告はもちろん、合わせて、節税対策にはどのようなものがあるのかを知っておくことも大切です。
本記事では、家賃収入がある場合の確定申告はどのように行なうのかといった基本的な情報を解説するとともに、賃貸経営における税金対策についても紹介します。
▼この記事の内容
●不動産所得が20万円超であれば確定申告が必要となるが、家賃収入がある人は損益通算によって節税できることがあるので、全員確定申告をするべき
●不動産収入とは、不動産の運用を通じて得られる収入の総称。不動産所得とは、不動産収入から賃貸経営に必要な経費を差し引いた金額。キャッシュフローとは、賃貸経営で実際に手元に残る現金
●賃貸経営に必要な経費としては、税金、管理手数料、修繕費、損害保険料、減価償却費、借入金の利子などがある
●確定申告は次の流れで行う。白色申告か青色申告かを決める、必要書類・添付書類を準備する、書類の作成・提出
目次
家賃収入の確定申告はいくらからするべき?

家賃収入があるときに確定申告が必要になるのは、一定の金額に達したときです。一定の金額の判断は、家賃収入の金額だけを見るのではなく、家賃収入から賃貸経営にかかる費用を差し引いた額で判断します。
結論から申し上げると、家賃収入がある方は全員確定申告をするべきです。以下でその理由を解説します。
不動産所得が20万円超であれば確定申告が必要
不動産賃貸経営における家賃収入は所得のうえでは不動産所得に該当します。そして、不動産所得の金額が20万円を超えた場合は確定申告が必要になります。ちなみに不動産所得の課税金額の求め方は、「総収入金額-必要経費」です。
家賃収入の合計額が20万円を超えたら確定申告が必要になるわけではなく、不動産所得金額が20万円を超えた場合に確定申告が必要になる点をしっかりと理解しておきましょう。
総収入金額には、家賃収入のほかに、以下のものも含まれます。
・名義書換料、承諾料、更新料など
・敷金や保証金などのうち、返還しないもの
・共益費としての電気代や水道代、掃除代など
また、必要経費として計上できるものには、「固定資産税」や「損害保険料」、「減価償却費」、「修繕費」などがあります。必要経費の詳細については後述します。
20万円以下なら確定申告は不要だがメリットも
では、総収入金額から必要経費を引いた不動産所得金額が20万円以下なら、確定申告は必要ないのでしょうか。不動産所得金額が20万円以下の場合、原則として確定申告は不要です。しかし、ケースによっては、確定申告を行なった方がよいケースもあります。
確定申告を行った方がよいケースとは、その年の不動産所得金額がマイナス(赤字)になった場合です。不動産所得が赤字になったときは、確定申告を行うことで、ほかの所得と損益通算を行うことができ、その結果、全体の所得金額を抑えることができるからです。さらに、確定申告を行うことで、納め過ぎた税金が還付されることもあります。
損益通算の仕組みについては、次で詳しく解説します。不動産所得の確定申告において重要な内容ですので、しっかりと理解しておきましょう。
損益通算の仕組み
損益通算とは、所得金額の計算において損失が発生した場合、一定の所得についてのみほかの所得金額から損失部分を控除できる仕組みです。損益通算が行える所得は「不動産所得」「事業所得」「譲渡所得」「山林所得」に限られており、不動産所得は損益通算の対象です。
サラリーマンで会社勤めをしており、副業として不動産経営を行っているなら、本来の収入は給与所得です。給与所得は、給与収入から給与所得控除を引いた額ですが、不動産所得金額がマイナスになっている場合は、確定申告を行うことにより、給与所得金額から不動産所得金額のマイナス分を差し引くことができるのです。
例えば、不動産経営を行っている中で修繕費が予想以上に大きくなってしまい、収入額を上回る結果になってしまった場合は、当然不動産所得金額がマイナスになります。その際、給与所得金額と損益通算することで、給与所得金額も減額されることになり、最終的な課税所得金額を抑えることになります。
家賃収入と不動産収入、不動産所得、キャッシュフロー

家賃収入と似た言葉に「不動産収入」「不動産所得」「キャッシュフロー」があります。ここではそれぞれの特徴と違いを解説します。
不動産収入
不動産収入とは、不動産の運用を通じて得られる収入の総称です。一般的なアパート・マンション経営においては、家賃収入と同義のものとして扱われています。
もっとも代表的なものとして家賃収入が知られていますが、不動産から得られる収入はそれだけではありません。以下で不動産収入の主な内訳を詳しく解説します。
不動産収入① 家賃収入
家賃収入は、契約にもとづいて入居者様がオーナー様に毎月支払うもので、居住用不動産の場合は居室の賃料、事業用不動産の場合は事務所やテナントの賃料がこれに該当します。
家賃収入は不動産収入の大半を占める重要な収入源のため、空室リスクの適切なコントロール、未納の把握と迅速な対処などを行う必要があります。
なお、賃貸管理会社に管理業務を委託すれば、家賃の徴収や督促に加え、空室時の客付けにも対応してくれます。
不動産収入② 礼金収入
礼金は契約時に入居者様からオーナー様に支払う「謝礼金」のようなものです。敷金とは異なり礼金には返還義務がないため、そのままオーナー様の収入となります。
礼金の相場は家賃の1〜2ヶ月程度が一般的ですが、商習慣や歴史的な背景の違いから、礼金を徴収しない地域も少なくありません。また、賃貸借契約締結に至りやすくするために、入居者様側の初期費用を軽減する目的で礼金を免除するケースが増加しています。
不動産収入③ 更新料による収入
不動産の賃貸借契約は2年契約が一般的であり、既存の契約を更新する際に入居者様からオーナー様に支払う費用が更新料です。
関東圏や京都府では家賃の半月分〜2ヶ月程度を徴収するのが一般的ですが、それ以外の地域では礼金同様に徴収しない地域が多いようです。
更新料の負担を理由に転居を考える入居者様も少なくないため、近年では更新料を設定しない、または廃止するケースも増えています。
不動産収入④ 管理費・共益費による収入
管理費・共益費は、物件の共用部分や設備を維持・管理するための費用であり、入居者様が毎月の家賃と合わせてオーナー様に支払うのが一般的です。
具体的な用途としては、共用部の電気代・水道代・清掃費・管理人の人件費などが挙げられますが、法的な定めはないため、用途や金額はオーナー様の裁量次第となります。
「管理費(共益費)込み」という家賃設定をしている場合もありますが、敷金や礼金は家賃が基準となることから、別立てした方が入居者様の負担を軽減できるという考え方もあります。
不動産収入⑤ 駐車場収入

収益物件に有料駐車場を併設して貸し出す場合の駐車場収入も不動産収入のひとつです。
入居者様専用駐車場とするケースが一般的ですが、入居者様に限らず対外的に月極駐車場やコインパーキングとして貸し出す場合もあります。
一方で、都市部に比べて利便性の低い郊外などでは、駐車場は無料で貸し出し、収入としては期待できないという地域も少なくありません。
不動産所得
「不動産収入」と「不動産所得」は混同されがちですが、異なる概念のため注意が必要です。
不動産所得とは、前述の不動産収入の合計から不動産経営に必要な経費を差し引いた金額であり、不動産経営における利益を指します。
「不動産経営に必要な経費」には、以下のようなものが挙げられます。
- 修繕費・水道光熱費
- 火災・地震保険料
- 賃貸管理会社に支払う委託費・管理手数料
- 仲介業者に支払う仲介手数料
- 支払利息
- 減価償却費
上記の経費を差し引いて算出した不動産所得から、さらに所得控除を差し引いた額が確定申告に用いられる「課税所得額」となります。
なお、敷金は預かり金にあたるため、不動産収入・不動産所得のいずれにも含まれません。
キャッシュフロー
不動産収入・不動産所得を考えるうえで特に注意したいのがキャッシュフローです。不動産収入・不動産所得はあくまで帳簿上の数字であり、実際の現金の動きや手元に残る金額とは異なるためです。
例えば、不動産所得を算出する際は減価償却費を差し引きますが、実際には現金の支出ではないため、手元に残る現金とは差が生じます。
また、不動産収入から経費やローン返済額を差し引いたものを「税引前キャッシュフロー」といい、税引前キャッシュフローから所得税・住民税を差し引いた金額を「税引後キャッシュフロー」と呼んで区別します。
なお、税引後キャッシュフローの金額が実際にオーナー様の手元に残る現金となります。
不動産所得に関係する必要経費とは

不動産所得を計算するうえで、経費として計上できる費用にはどのようなものがあるのでしょうか。基本的に経費として計上できるのは、事業(賃貸経営)に関係する費用のみです。自宅で使用した電気代などは原則として経費に含まれませんので注意してください。
固定資産税などの税金
固定資産税とは、毎年1月1日時点で不動産(土地や家屋)を所有している方に対して課税される地方税で、都市計画税と合わせて納付するのが通例となっています。課税主体は対象となる不動産が存在する市区町村ですので、徴収も市区町村が行います。
毎年4月~6月頃に不動産(土地や家屋)の所有者に対し、「納税通知書」および「課税明細書」が届きますので、納税額を確認し、納付します。納付は4回に分けて行いますが、1年分の固定資産税および都市計画税を一括前納することもできます。
固定資産税は、賃貸物件を保有するために発生する費用で、事業を行うにあたって必要な経費です。よって、不動産所得を計算するうえでの必要経費として認められます。さらに不動産を購入した際に支払った不動産取得税や登録免許税、収入印紙代についても取得した年の必要経費として計上できますので、忘れずに計上しましょう。
公租公課
公租公課は、国や地方公共団体が公共的な目的のために課す公的負担の総称です。公租とは、国や地方公共団体が国費や公費にあてる目的で個人や法人から徴収する金銭のことで、以下のものがあります。
・法方税
・消費税
・印紙税
・登録免許税
・事業税
・固定資産税
・自動車重量税
・不動産取得税
など
公課とは、国税や地方税以外に国や地方公共団体が徴収する金銭のことで、以下のものがあてはまります。
・賦課金
・加算金
・延滞金
・罰金
・過料
・社会保険料
・発行手数料
・公共サービス手数料
など
経費として扱われるものの、全てが認められるわけではなく、所得税や住民税は必要経費としては認められません。
賃貸管理会社へ支払う管理費
賃貸物件の管理を自主管理ではなく、賃貸管理会社に委託している場合は、その委託料が発生します。賃貸物件の管理は、業務を遂行する上で必要不可欠なものですので、必要経費として計上できます。
原状回復や維持管理にかかる修繕費
修繕費とは、建物や付属設備などを元の状態に戻す原状回復や維持管理のためにかかる費用です。原状回復や維持管理を行うことにより、入居者様の募集や賃貸契約の更新につながることから、修繕費は業務上必要な費用となり、必要経費に含めることができます。
ただし、耐震補強工事やフルリノベーションなど、現在の価値を高める工事については、費用ではなく資産として計上しなければなりませんので、費用としての計上はできない点に注意してください。
損害保険料(火災保険や地震保険)
賃貸物件に対して、火災保険や地震保険をかけている方もおられるでしょう。地震や火災などの損害から事業を守るためには、損害保険への加入は重要です。そして、損害保険料についても、こと業に関係する費用と見なされるため、必要経費に含めることができます。ただし、含めることができる額は、その年分の保険料のみです。
減価償却費(土地以外の建物など)
減価償却が認められているのは、事業の業務のために利用される建物や建物付帯設備などの資産です。土地は減価償却の対象外となることをまず理解しておきましょう。
減価償却は、購入した年に一括計上するのではなく、使用可能な期間に応じた額に計算し直して費用計上する必要があります。具体的には、「取得価格✕償却率」で求めますが、償却率は建物の構造や経過年数によって異なりますので、国税庁のサイトなどで確認しながら計算していきましょう。
不動産取得に係る借入金の利子
投資物件としての不動産を購入する際に、ローンを利用することもあります。その場合、ローンの利子分については、必要経費として計上できます。ただし、元金部分については計上できません。また、建物が完成してから賃貸を開始するまでの期間に相当する支払利息については、必要経費ではなく建物取得価額に参入されます。
注意していただきたいのは、不動産所得が赤字になる場合です。赤字の場合、土地の借入金の利子を必要経費に含めることはできません。借入金の利子と不動産所得の赤字のどちらか小さい額が損益通算の対象外になるため、、不動産所得が赤字の場合は、赤字の金額をほかの黒字の所得から差し引く(損益通算)ことができます。
そのほかの必要経費

そのほか、必要経費として計上できるものとしては、「会議費」や「車両費」のほか、弁護士や税理士に対する報酬などが挙げられます。
さらに、賃貸管理会社に家賃回収業務などを委託している際の賃貸管理代行手数料も必要経費として見なされます。ほかにも、交通費や通信費、接待交際費や消耗品費など、不応産賃貸経営を行うために使用したものであれば、必要経費として計上可能です。
確定申告の基本的なやり方

ここからは、家賃収入がある場合の確定申告のやり方を解説します。申告方法や必要書類などが異なるため、しっかり理解しておきましょう。
白色申告か青色申告かを決める
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があり、どちらの方法で申告するかを決める必要があります。
青色申告は確定申告で複式簿記の記帳を求められる申告方法です。後述する白色申告よりも手間はかかりますが、以下のように満たした条件に応じて10〜65万円の特別控除を受けられるのが大きなメリットです。
- 10万円控除:単式簿記で記帳し、損益計算書のみを提出
- 55万円控除:複式簿記で記帳し、期限内に貸借対照表と損益計算書を提出
- 65万円控除:55万円控除と同様の手続きを電子申告で行うか、電子帳簿保存を行う
一方、白色申告は複式簿記による記帳や事前申請などが不要であり、青色申告に比べて手間が少ない点が特徴です。作業負担が少ないかわりに、特別控除は設定されておらず、節税効果が望めないデメリットがあります。
近年は青色申告をサポートするサービスも増えているため、少しでも節税したい場合は青色申告を選択するのがおすすめです。
必要書類・添付書類を準備する
申告方法を決めたら、確定申告の必要書類と添付書類を準備しましょう。申告の種類によって多少添付書類が異なりますが、概ね以下のとおりです。
確定申告を行う際に作成する必要書類は以下の3点です。
- 確定申告書
- 収支内訳書または青色申告決算書
- 固定資産台帳
また、確定申告には以下の書類を添付する必要があります。
- 領収書・レシートや帳簿
- 源泉徴収票
- 保険料控除明細書
- 医療費控除の明細書
- 寄付金の受領証
- マイナンバーカード
- 金融機関の口座情報
準備する書類の種類が多いことに加えて、それぞれ入手先や入手までにかかる期間が異なる点に十分注意が必要です。
例えば、領収書やレシートは確定申告時期だけではなく、年間を通して日頃から集めて保管しておく必要があります。また、保険料控除明細書は保険料を支払っているそれぞれの企業から郵送で届くため、別途保管しておかなければなりません。
指定された期間内に滞りなく手続きを完了できるよう、あらかじめ必要書類を確認したうえで計画的に準備していくことが大切です。
書類の作成・提出
続いて、準備した書類にもとづいて確定申告の書類を作成します。書類の作成方法は大きく以下の4パターンです。
- 手書き
- 確定申告ソフト
- 確定申告書等作成コーナー
- 税理士へ依頼
このうち、1〜3は自分で作成する方法ですが、近年は「確定申告ソフト」や「確定申告書等作成コーナー」が使いやすく充実しており、自分で書類をつくるハードルが下がってきています。
書類が完成したら、以下のいずれかの方法で管轄の税務署に提出しましょう。
- e-Taxやスマホアプリによる電子申告
- 信書による郵送
- 税務署窓口への持参
- 税務署の時間外収集箱へ投函
このうち、税務署が推奨しているのは1の「電子申告」です。青色申告で65万円の特別控除を受けたい場合も、この電子申告で条件をひとつを満たせます。
自分で税務署に持ち込む場合は、職員に直接確認しながら手続きできる反面、確定申告時期には混雑するため注意が必要です。手続きに慣れている場合や持参が難しい場合などは、信書による郵送や時間外収集箱への投函を利用する方法もあります。
【リロの不動産】なら節税効果が見込める賃貸経営ができる

賃貸経営を行うことで家賃収入を得ることができますが、不動産所得金額によっては多額の所得税や住民税が発生します。そのため、節税対策も視野に入れた賃貸経営を考えることが必要です。そのためには、設備投資を行うことも一つの方法ですが、あまりに過剰な投資は禁物です。
【リロの不動産】【リロの賃貸】では、地域の特性と修繕実績など、賃貸経営データに基づき、オーナー様が保有している物件に合わせた最適な提案を行っています。
建て替えや資産活用サポート
築年数の経過による設備の入れ替えや、賃貸経営状況、および資産運用のご希望によっては建て替えの提案をさせていただくことがございます。合わせて、資産活用の問題に対しては、お手持ちの資産に関するご懸念点やご要望をお伺いし、最適な資産活用をご提案させて頂きます。
物件価格の査定や運用方法まで対応しているほか、提携する税理士や司法書士などの専門家などと、オーナー様の資産活用について包括的に伴走いたします。
特別条件の割賦工事
リロパートナーズグループの各社と管理契約をいただいているオーナー様には、特別利率・家賃収入でお支払いできる建物工事の割賦払いをご利用できます。老築化や、長期空室でお悩みのオーナー様、思い切ったリフォームや設備の入れ替えはしたいが、資金面でお困りのオーナー様もおられるのではないでしょうか。
『特別条件の割賦工事』では、月々の家賃収入からの相殺で持ち出しはありませんし、保証人や抵当権も不要でご利用可能です。
全力で満室経営をサポートしますので、お気軽にお問い合せください。
まとめ

【リロの不動産】【リロの賃貸】では、『4つの空室対策』により「募集力」「仲介力」「入居者様管理や建物管理」「設備投資対応力」の最適化を図ります。リログループの総合力と地域密着の老舗が持つ知見ときめ細かいサポートで、賃貸経営を包括的にサポートいたします。
設備投資についても過剰な投資にならないように、入居者様のニーズや競合物件と比較し、適切な設備投資を提案できます。【リロの満室パック】を利用すれば、『厳選されたリフォーム』を『割賦利用で実質0円』で対応し『借上利用により収益を確定』することも可能です。
賃貸経営において税金対策でお悩みのオーナー様は、賃貸経営の確かな実績を持ち、不動産に強い税理士パートナーがいる【リロの不動産】【リロの賃貸】にご相談ください。
関連する記事はこちら
家賃収入を増加するポイントとは?節税効果・確定申告・損益通算を知る
家賃収入にかかる税金はいくら?設備投資と損益通算で考える節税対策
【アパート経営・賃貸経営入門】メリット・リスク・成功の秘訣をわかりやすく解説!
アパートローンを上手に利用するコツと注意点|住宅ローンとの違いは?
【総集編】アパート経営の利回りの目安は?不動産投資の指標と注意点
アパート経営の失敗体験談9選と回避方法!よくある失敗事例から学ぼう
アパート経営に必要な自己資金はいくら? 成功に導く出口戦略と資金計画
アパート経営の年収と暮らしとは?アパート経営の収入を上げる方法
失敗しない中古アパート経営とは? メリット・リスク・対策方法を解説
公務員はアパート経営できる? 公務員が不動産投資を始める意外なメリット
不動産収入とは? 不動産所得と手取りの違い・収入を上げる方法も解説
賃貸経営サポートとは? 不動産投資の成功を左右する管理会社の実力
アパート経営の管理費って必要?自主管理と管理委託の大きな違いとは
おすすめのサービス
おすすめのお役立ち情報
この記事を書いた人
秋山領祐(編集長)
秋山領祐(編集長)
【生年月日】昭和55年10月28日。
【出身地】長野県上田市。
【趣味】子供を見守ること。料理。キャンプ。神社仏閣。
【担当・経験】
デジタルマーケティングとリブランディングを担当。
分譲地開発のPMや家業の土地活用などの経験を持つ。
リノベした自宅の縁の下に子ども達の夢が描かれている。




















