相続税の基礎控除とは? 各種控除と賃貸不動産を活用した相続税対策
2023.06.09
「自分には関係ない」と思わないでほしい、ご相続の事前準備。事前の対策で相続税の控除額は大きく変わるため、残される家族のために相続税対策を考えておく優しさが、次世代の未来をつくる大きな一助になります。相続税には一定の金額までは税金が課されない基礎控除があることに加え、相続人の状況によって各種控除も設けられています。
相続税対策をしっかり行うためには、各種控除について把握しておくことが大切です。この記事では相続税の仕組みと各種控除について詳しく解説するとともに、賃貸不動産を活用した相続対策についても紹介します。
相続税とはどのような税金か
相続税とは、人の死亡が原因で財産が移転することに対して課される税金です。なぜこのような税金があるのか、主に2つの理由があります。
富の再分配機能
相続税の制度が創設されたのは、100年以上前の1905年です。相続税制度ができる前の日本では元武士の士族や華族、地主など一部の層だけに富が集中していました。富は代々、子どもや孫などの子孫へと受け継がれるため、裕福な層は裕福であり続けます。
一方で、社会の制度が変わらないかぎり貧しい層に生まれた方はスタートから不利な状況にあり、いつまでたっても貧困に苦しむ生活から抜け出せません。
そこで設けられたのが「富の再分配機能」がある相続税制度です。相続税として国に納める税金は広く社会のために使われることになるため、結果的に生まれた家庭の経済状況による差を縮小させ、格差の固定化を防止する役割があります。つまり、高額の財産に対して多くの税負担をかけることで富を再分配し、次世代に引き継がれる財産の格差を少なくしていこうということです。
所得税の補完機能
相続税のもう一つの特徴に「所得税の補完機能」が挙げられます。相続人が相続することになる財産は、被相続人が生前に築いたものです。毎年なんらかの所得を得ていれば、通常は所得税が課税されます。ただ、所得税にはその時々によって、税法上の特典や軽減措置が設けられていることがあります。
所得税の補完機能といわれるのは、被相続人が生前に課税されなかった所得に対し、相続が発生した際に相続税として精算的に課税するという意味合いがあるからです。同時に、相続財産は相続人の資産を増加させることになるため、不動産投資や株式投資などと同じ一種の不労所得とみなされます。
相続で財産を得ているにもかかわらず、税金を課されないのは不公平に感じることもあるでしょう。その不公平感を解消するのも相続に税負担を求める理由の一つです。
相続税の基礎控除とは
相続税は被相続人から受け継いだ財産すべてに課されるわけではありません。相続税対策を考えるうえで、まずは基礎控除の仕組みと計算方法を把握しておきましょう。
基礎控除
相続税の基礎控除とは、被相続人が遺した財産の総額から一定額を控除できる仕組みです。相続税は受け継いだ財産すべてにかかるわけではありません。
預貯金や株式、不動産などプラスの財産から、債務や葬儀費用などマイナスの財産を差し引き、まず課税の対象となる合計額が決まります。そこから非課税枠として設けられている基礎控除額を差し引き、残りの分だけに課税されます。財産すべてに課税されるのに比べると、基礎控除がある分だけ相続税が減額される仕組みです。
基礎控除の算出方法
基礎控除の算出方法は「基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算され、法定相続人の数で金額が変わってきます。法定相続人が配偶者と子ども1人の合計2人なら、基礎控除は「3,000万円+(600万円×2)=4,200万円」です。法定相続人が配偶者と子ども2人で合計3人の場合は、「3,000万円+(600万円×3)=4,800万円」となり、法定相続人の数が増えるほど基礎控除額も多くなります。
もし、相続財産が同じ4,500万円でも、法定相続人の人数で相続税がかかるかどうかが違ってくる場合があります。例えば法定相続人が3人なら基礎控除額4,800万円以内に収まるため、相続税は発生しません。一方で2人では「相続財産4,500万円-基礎控除額4,200万円=300万円」となり、基礎控除額を差し引いた残りの300万円に対して相続税がかかります。
相続税の法定相続人とは
では、相続税の控除を考えるうえで必要になる法定相続人とは、具体的にどのような範囲になるのでしょうか。
配偶者相続人

民法では遺産の継承を受けられる人物として、相続人が指定されています。相続人には大きく分けて2種類に大別されます。その一つが配偶者相続人です。名称からも推察できるように、配偶者相続人は夫や妻などの配偶者を指します。
ただし、相続における配偶者相続人は、あくまでも法律上、婚姻関係にある夫または妻です。どれだけ長年夫婦同然に生活していたとしても、内縁の夫や妻、事実婚のパートナーはこの配偶者相続人に該当しません。もし、内縁の夫・妻や事実婚のパートナーに財産を残したい場合は、あらかじめ遺言を残しておくなど対策が必要です。
被相続人に配偶者がいた場合、配偶者は生きていればつねに相続人となります。配偶者以外に後述する血族相続人がいる場合、どの人物がともに相続人となるのかで法定相続分が変わってきます。例えば、相続人が配偶者と子どもなら配偶者の法定相続分は2分の1、配偶者と父母や祖父母なら3分の2、配偶者と兄弟姉妹なら4分の3です。
血族相続人
民法で配偶者相続人とともに、相続人として指定されているのが血族相続人です。血族相続人はさらに父母や祖父母などの「直系尊属」と子や孫などの「直系卑属」、「兄弟姉妹」の3つがあります。
ただし、血族相続人には相続の優先順位があり、第1順位は直系卑属、第2順位は直系尊属、第3順位は兄弟姉妹です。なお、養子は血のつながりがありませんが、正式に養子縁組を行っていれば相続税の計算をする際、一定の人数まで法定相続人として認められます。
配偶者相続人はつねに相続人となりますが、血族相続人は高い順位の者が相続人となれば、低い順位の者には相続の権利がなくなります。例えば、子どもが生きていれば子どもが相続人となり、親や祖父母、兄弟姉妹は相続人にはなれません。
子どもがいない場合は親や祖父母が相続人となり、さらに親や祖父母もいなければ次は兄弟姉妹が相続人になります。ただ、子どもが亡くなっているケースで、その子ども(孫)が生きているケースでは、孫が代襲相続として第1順位の相続人になるため、親や祖父母、兄弟姉妹は相続人にはなりません。
相続税の計算方法
ここからは、どのようにして相続税が算出されるのか、5つのステップに分けて順番に計算方法を解説していきます。
課税価格を計算する

相続税がどのくらいになるか計算する前に、まずは課税対象となる財産の価格を算出する必要があります。課税価格はプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた金額です。プラスの財産は現金や預貯金、株や不動産など「金銭的に見積もることができる経済的価値のあるものすべて」と定義されています。宝石や貴金属、金銭債権や借地権などもプラスの相続財産です。
また、生命保険金や被相続人が支給されるはずだった退職手当金など、被相続人が死亡したことによって受け取ったお金は「みなし相続財産」と呼ばれています。みなし相続財産は法的には相続したものではないものの、実質的には相続と同じ経済的な効果を生むものとしてプラスの財産扱いになります。
被相続人から3年以内に贈与された財産がある場合は、その財産分もプラスし、債務や葬儀費用を引いた額が最終的な課税価格です。
課税遺産総額を計算する
相続税は被相続人が遺したプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた課税価格、すべてにかかってくるわけではありません。課税価格を計算したら、次は実際に課税される課税遺産総額を算出します。そこで必要になってくるのが、先述した基礎控除額です。
課税遺産総額は「課税価格-基礎控除額」で求められます。課税遺産総額という言葉は相続税法上の用語に過ぎませんが、相続税課税のもとになる大事な金額です。
具体的に法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人、課税価格が9,600万円のケースでみてみると、基礎控除額は3,000万円+(600万円×3)で4,800万円です。課税遺産総額は課税価格9,600万円-基礎控除額4,800万円で、4,800万円となります。
相続税額の総額を計算する
課税遺産総額を計算してプラスになった場合、まずはいったん相続人全員で納める相続税の総額を算出します。この段階では実際どのように相続財産を分けるかどうかは関係なく、民法による法定相続分の割合で計算を行うことがポイントです。例えば、相続人の構成が配偶者と子ども2人の場合、法定相続分は配偶者と子どもで2分の1ずつになります。
課税遺産総額が4,800万円だったケースで考えてみると、配偶者は2,400万円、子ども2人はそれぞれ1,200万円です。相続税の税率は、法定相続分に応ずる取得金額によって変わってきます。
相続税の速算表によると1,000万円を超えて3,000万円以下では税率が15%、控除額は50万円となっているため、配偶者分の仮の相続税額は310万円です。子どもの仮の相続税額は1人130万円ずつです。相続税をすべて合計した相続税の総額は570万円となります。
相続税の総額を実際の相続分で按分する
納めるべき総相続額が計算できたら、次は実際に相続する割合に合わせて相続人ごとに按分します。按分割合は「各相続人が実際に相続した財産の課税価格÷相続税の課税価格の総額」でそれぞれ求めます。
課税価格の総額が4,800万円、配偶者の相続分が2,400万円、子ども2人がそれぞれ1,200万円相続し、総相続税額が570万円の場合、配偶者の按分割合は2,400万円÷4,800万円で0.5です。子どもの按分割合は1,200万円÷4,800万円で、それぞれ0.25になります。
按分割合が割り切れない場合、相続人が全員納得していれば調整して合計が「1」になれば問題ありません。通常は四捨五入して、小数点以下第2位までになるよう調整します。次に各相続人の相続税額を「相続税の総額×各相続人の按分割合」で計算します。上記の例では配偶者の相続税額が570万円×0.5で285万円、子ども2人の相続税額は142万5,000円です。
各種税額控除・加算を行う
実際の相続税額の算出には、按分した相続額に各種控除や加算を行う必要があります。もともと課税遺産総額を計算する際には基礎控除額を差し引いていますが、各相続人の個別の事情によって、基礎控除以外にも別の控除が適用される場合があります。例えば、配偶者に対する相続税額の軽減や相続人が未成年の場合の未成年者控除、障害者控除、贈与税額控除などです。
個別の相続税額の算出では、加算されるケースもあります。加算の対象となるのは、配偶者と一親等以外の血族が相続する場合です。加算の対象となる相続人には、2割が加算されます。ただし、被相続人の子どもを越えて孫が相続する場合は2割が加算されますが、子どもがすでに亡くなり、孫が代襲相続する場合は加算の対象にはなりません。
基礎控除以外の控除枠
各相続人の個別の事情を鑑みて設けられている基礎控除以外の控除枠は、以下で解説する配偶者控除と未成年者控除、障害者控除、贈与税額控除の4つです。
配偶者控除
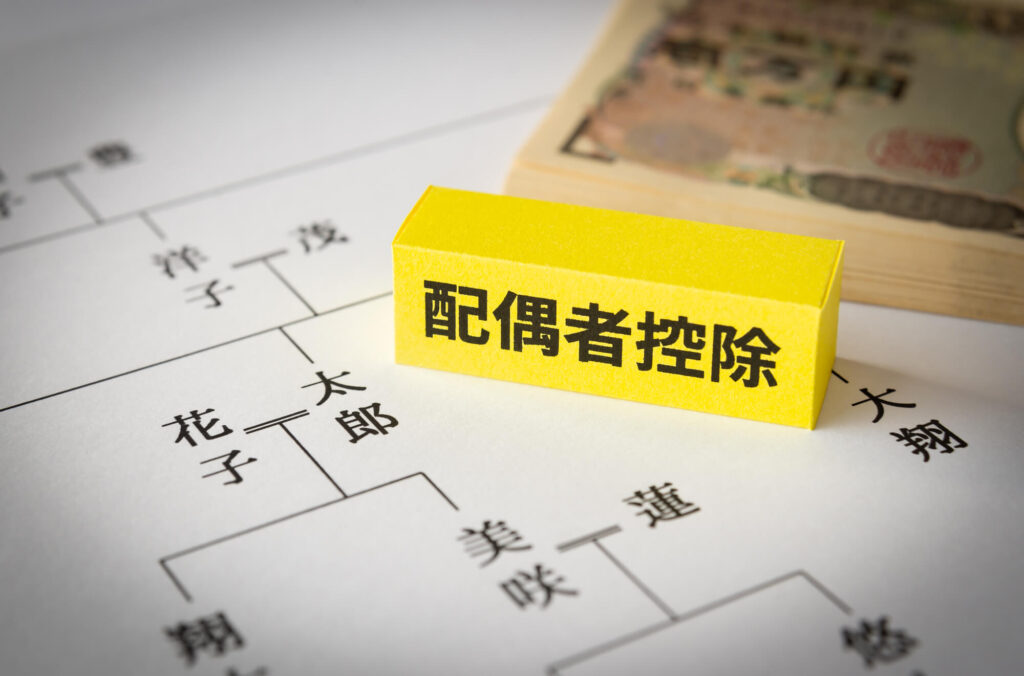
配偶者控除は相続税額を算定する際、被相続人の配偶者が負担する税額を軽減する制度です。具体的には配偶者の法定相続分相当額または、1億6,000万円のどちらか多い金額までは非課税になります。配偶者控除が適用されるのは戸籍上の配偶者だけで、内縁の夫や妻などは対象に入りません。
配偶者控除を受けるためには、ほかにも条件があります。一つは、相続税の申告書を税務署に提出することです。相続税額がゼロになるケースでも配偶者控除を受けるためには申告が必要になるため、相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に申告しましょう。
また、配偶者控除は遺産分割などの結果、実際に取得した相続財産に対して適用されます。基本的には相続税の申告期限までに遺産分割が完了していなければ、配偶者控除を受けられません。
未成年者控除

未成年者控除は、相続人が未成年者の場合に相続税額を控除できる制度です。未成年であっても、親や祖父母などから財産を相続すれば、相続税を納める必要があります。しかし、成人するまでには養育費や教育費など、まだまだお金がかかるでしょう。そこで未成年者の生活をサポートするために、未成年者控除が設けられています。
未成年者控除を受けるための要件の一つが、相続開始日に未成年であることです。2022年4月1日に成人年齢が18歳に引き下げられてからは、18歳未満であれば制度を利用できます。ただし、法定相続人であることや相続開始日に日本国内に住所があることなど、ほかにもいくつかの要件があります。未成年者控除の額は、満18歳になるまでの年数1年につき10万円です。
障害者控除
障害者控除は相続人が85歳未満の障害者の場合、障害の程度に応じて一定の金額控除が受けられる制度です。未成年者控除と同様に、被相続人が亡くなったことで障害のある相続人の生活に支障がでないよう設けられています。障害者控除を受けるためには、相続で財産を取得したときに日本国内に住所があることや、法定相続人であることなどの要件を満たしていなければなりません。
障害者控除の対象となる障害者は、一般障害者と特別障害者の2つに分けられます。特別障害者は重度の知的障害者とされた者や精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級、身体障害者手帳が1級または2級など、より障害が重い方です。障害者控除の額は相続人である障害者が満85歳になるまでの間、1年につき一般障害者は10万円、特別障害者は20万円として計算します。
贈与税額控除
贈与額税控除は、すでに納めた贈与税分を相続税から控除する制度です。生前に被相続人から贈与された財産がある場合、相続が発生した際に行われる相続税の計算で、すでに受け取った贈与財産が足されるケースがあります。それでは贈与税と相続税の二重課税になってしまうため、すでに支払っている贈与税の分については控除できる仕組みになっているのです。
贈与の方法には暦年贈与と相続時精算課税制度という2種類があります。暦年贈与は1年に110万円までの贈与は贈与税がかからない制度です。110万円を超える分には贈与を受けた時点で贈与税を納めます。
ただ、相続が開始される3年以内に贈与された財産については相続財産の対象として加算されるため、相続税の算出時に贈与税額控除で差し引くことが可能です。なお、2023年度の税制改正で、この「3年」が「7年」に変更されます。
不動産投資は相続税対策に最適
不動産投資が相続税対策として最適だといわれる理由の一つは、賃貸不動産に相続税節税の効果があるからです。そこで不動産投資が節税になる仕組みと、それ以外のメリットについて解説します。
メリット1・相続税評価額の圧縮

不動産投資が相続税対策になるのは、相続税評価額を圧縮できるところにあります。同じ財産として所有しているのでも、現金などの状態で保有している場合とは、相続税評価額自体が異なるからです。次に不動産の相続税評価方法、および賃貸不動産が節税になる理由も詳しく解説します。
不動産の相続税評価方法
現金や預貯金などの相続税評価額は額面そのままですが、不動産は時価がそのまま相続税評価額となるわけではありません。土地の評価方法には路線価方式と倍率方式の2種類があります。
路線価方式で用いられる路線価は毎年1月1日時点での道路に面する土地1平方メートルあたりの評価額で、もともと土地売買の価格の目安とされる地価公示の価格の8割程度です。倍率方式で用いられる固定資産税評価額も地価公示の7割程度であり、それだけでも不動産として財産を所有しているほうが、相続税評価額を圧縮できることが分かるでしょう。
また、一定の条件に当てはまれば、評価額を減額できる小規模宅地等の特例もあります。被相続人が住んでいた土地は特定居住用住宅等に該当し、330平方メートルまでは80%減額されるほか、事業用の宅地等も条件によって50~80%の減額が可能です。建物部分の相続税評価額は固定資産税評価額をもとに定められ、自宅は固定資産税評価額そのままの金額が相続税評価額となります。
賃貸不動産はさらに有利
不動産がアパートやマンション、戸建て賃貸住宅などの賃貸不動産の場合は、さらに相続税の圧縮効果が高くなります。更地や被相続人が自宅として使っていた土地とは異なり、賃貸不動産は借主様にとって「生活の場」になります。
生活している借主様の居住空間を守るために、たとえオーナー様の所有する土地や建物であっても、なんでも自由にすることはできません。賃貸不動産が建っている土地は、自由度が低いため、貸家建付地として相続税評価額をさらに低減させる仕組みがあります。
相続税評価額を計算する際は、借地権割合や借家権割合、賃貸割合などの考え方によって、借主様の存在を反映させます。計算式は「更地としての評価額×(1-借家権割合×借地権割合×賃貸割合)」です。
借家権は土地の上に建っている建物を借主が利用する権利で、借家権割合は一律30%と定められています。借地権は建物を建てることを目的として土地を借りる権利を指し、借地権割合は対象の土地のうち借地が占める割合です。借地権割合は地域によって異なり、30~90%の間で決められています。賃貸割合は建物の床面積のうち、貸し出されている割合です。
メリット2・長期・安定収入を得られる

賃貸不動産を相続するメリットは、何も相続税が節税になるだけではありません。賃貸不動産は入居者様からの家賃が毎月入ってくるため、賃貸経営が軌道に乗れば長期にわたってその後も安定的な収入を得られるのが大きなメリットです。
すでに相続した時点で賃貸経営がうまくいっている可能性もあるでしょう。同じ賃貸経営でも店舗やオフィスビルなどの事業系の物件もありますが、特にアパートやマンションのような住居系の物件は景気に左右されにくい特徴もメリットになります。
もともと会社員としての給与所得や自営業での事業所得などがある方も、本業での収入にプラスできる家賃収入があれば経済的に余裕を持てるようになります。誰にでも病気や怪我などで収入が途絶えるリスクがありますが、家賃収入という収入源があれば安心です。
家賃収入を貯蓄しておけば、老後の備えにもなるでしょう。短期的な面でいえば、相続税の資金が不足している場合にも、家賃収入を原資として納税できる特徴もあります。
メリット3・不動産投資ローン残高が債務控除になる
アパートやマンションなどの賃貸不動産を購入したり、新たに新築したりする場合、物件の規模が大きければ大きいほど、購入費用や建築費用も高くなります。多額の資産を保有している方でなければ、なかなか自己資金ですべての費用を賄うのは難しいでしょう。実際に賃貸不動産を取得する際は、不動産投資ローンを活用するケースが大多数になります。
被相続人が不動産投資ローンを組み、資金を借り入れた時点では相続税が減るわけではありません。しかし、返済の途中で亡くなった場合、ローンの残債も相続人に引き継がれます。ローンの残債はマイナスの財産として「債務控除」の対象となり、課税価格を計算する際には差し引かれるため相続税評価額を減らすことが可能です。
ただし、ローンを契約する際に団体信用生命保険(団信)に加入している場合、返済中に死亡すると保険金がローン残債に充当されます。そうなると残債はゼロになってしまうため、債務控除の対象にはなりません。
まとめ

相続税には配偶者控除や未成年者控除、障害者控除、贈与税額控除など、基礎控除以外にもいくつか控除があります。資産のある方にとって相続税の問題は重く、個人ごとにお悩みも異なるため、専門家に相談する必要があります。
不動産投資は相続税対策として有利になるため、相続対策を検討している方は賃貸経営を選択肢の一つにしてみてはいかがでしょうか。その際、心強いパートナーとなるのが経験豊富な賃貸管理会社です。
賃貸管理会社のサポート範囲にもよりますが、賃貸経営を最適化するために中立的な視点でオーナー様に近い感覚で伴走します。
ご相続でお悩みの方は、専門家とチームを組んで賃貸経営をトータルでサポートできる【リロの不動産】に、ぜひご相談ください。
関連する記事はこちら
知っておくべき相続税対策! 不動産を活用した節税の仕組みを解説
不動産を生前贈与したほうがいいケースとメリット・デメリットを解説
不動産投資が相続税対策に選ばれている理由は?5つの節税対策も紹介
アパートは相続税対策に有効! 相続税計算でメリットを検証・解説付き
土地の相続税はいくらかかる? 賃貸不動産を活用した相続対策も解説
ご生前に行う相続税対策とは? 賃貸不動産の認知症・遺産分割・節税・納税資金対策
不動産購入が相続税対策になる理由!物件種類別の節税対策と注意点を解説
【事例付】地主の相続対策はトラブル回避が重要!税金・争続・土地活用の注意点
おすすめのサービス
おすすめのお役立ち情報
この記事を書いた人
秋山領祐(編集長)
秋山領祐(編集長)
【生年月日】昭和55年10月28日。
【出身地】長野県上田市。
【趣味】子供を見守ること。料理。キャンプ。神社仏閣。
【担当・経験】
デジタルマーケティングとリブランディングを担当。
分譲地開発のPMや家業の土地活用などの経験を持つ。
リノベした自宅の縁の下に子ども達の夢が描かれている。





















