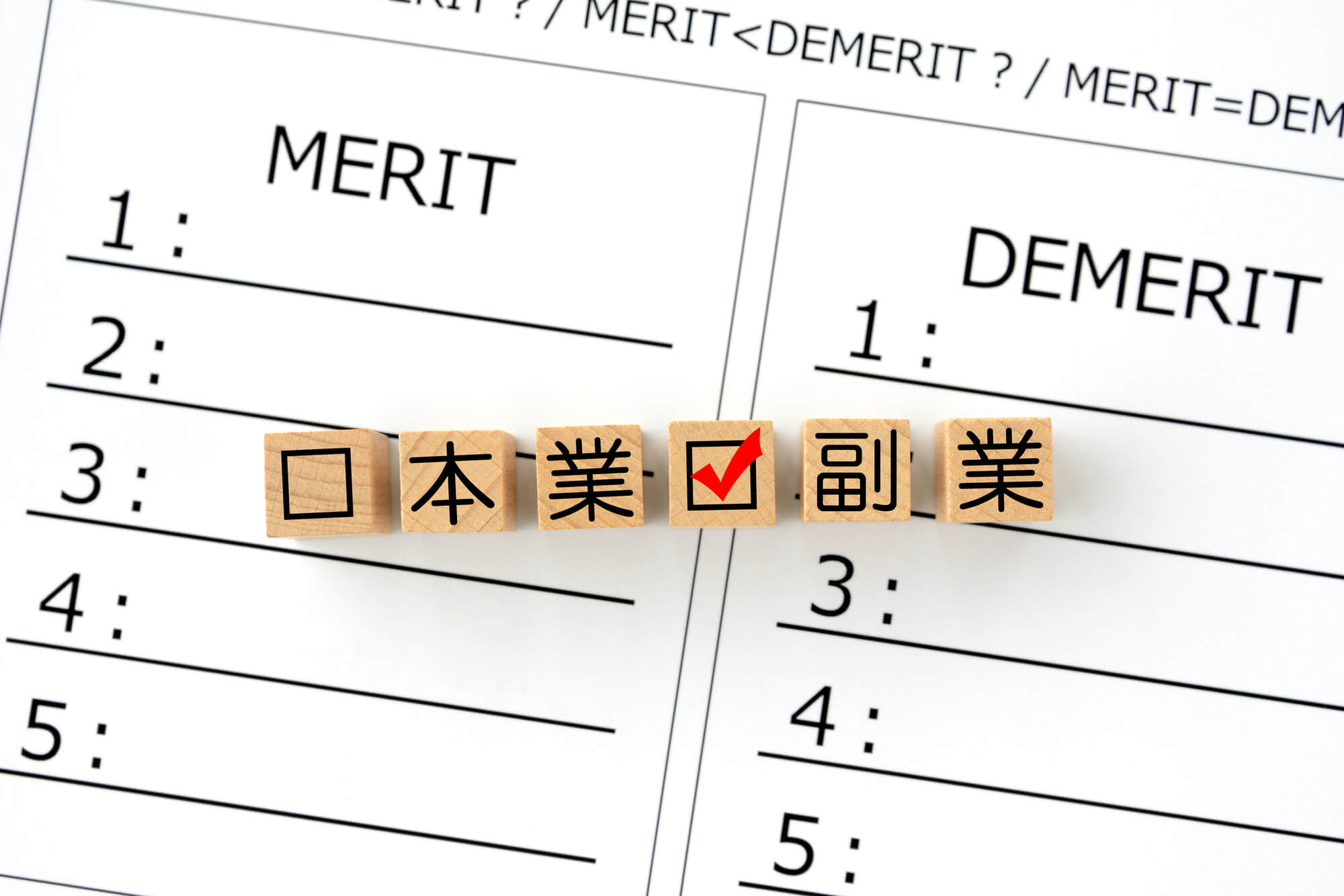アパート・マンション経営の管理費相場とは?収益を高める委託管理と自主管理の違い
2025.11.12
アパートの賃貸情報には、入居者様が負担すべき費用として家賃のほかに管理費や共益費が記載されています。これらの金額は物件ごとに異なり、家賃に含まれているケースも見られます。これといった基準がないため、管理費と共益費の違いや金額の決め方が分からず、お悩みのオーナー様もいるのではないでしょうか。
そこで、本記事では管理費・共益費とは何かを説明するとともに、アパート管理の重要性について解説します。
▼この記事の内容
●アパートの管理には、大きく分けて自主管理と管理委託の2種類がある。自主管理とはオーナー様が自分で管理する方法で、入居者様との距離が近い、賃貸管理のノウハウが身につくなどのメリットがある。一方、管理業務に忙殺される、管理を怠ると資産価値が下がる、専門的な知識が必要なときがあるなどのデメリットがある。
●管理委託とは賃貸管理会社に管理を委託する方法で、遠方の物件の所有が可能、リスクヘッジができるなどのメリットがある一方、管理手数料がかかる、賃貸管理会社を見極める目が必要というデメリットがある。
●管理委託契約の一種にサブリース(一括借上)契約がある。サブリースのメリットとしては、空室リスク・家賃滞納リスク対策になる、融資が有利になるなどがあるが、通常より家賃収入が減少する、家賃減額を請求されることがある、オーナー様からの契約解除が難しい、修繕・原状回復工事費用が割高になることがあるなどのデメリットがある。
●アパートの入居者様が支払うものとして、管理費がある。似たものに管理手数料があるが、管理費は共用施設の点検や維持管理に使われる費用なのに対して、管理手数料は管理業務の対価としてオーナー様から賃貸管理会社に支払う費用。
●また、修繕積立金というものがある。修繕積立金は定期的に実施される大規模修繕に充てられる費用で、賃貸アパートではオーナー様が負担する費用になる。
●管理費とは別に共益費というものもある。賃貸アパート・賃貸マンションでは共益費という言葉が適当とされるが、管理費と共益費は厳密な区別なく使用されている。
目次
アパート経営における自主管理と管理委託
賃貸物件のオーナー様には所有する物件を「管理」する義務があります。管理には2つの方法があり、「自主管理」または「管理委託」のいずれかを選択します。まずはそれぞれの違いを把握していきましょう。
アパート経営についての関連記事は、こちらもご参照ください。
【アパート経営・賃貸経営入門】メリット・リスク・成功の秘訣をわかりやすく解説!
【総集編】アパート経営の利回りの目安は?不動産投資の指標と注意点
失敗しない中古アパート経営とは? メリット・リスク・対策方法を解説
自主管理とは

自主管理とは、オーナー様が自分で建物管理ならびに入居者管理を行う方法です。具体的には次のような業務を行います。
【建物管理】
● 敷地内や共用部分の清掃
● 共用設備の定期点検や修繕の手配
● 大規模修繕工事の計画、実施 など
【入居者管理】
● 入居者募集
● 賃貸借契約の締結
● 家賃の回収、入金管理
● 家賃滞納者への督促
● 入居者様や近隣住民からのクレーム対応
● 退去時の立ち会い など
管理委託とは
管理委託とは、文字どおり管理業務を第三者に委託することをいいます。建物管理や入居者管理は専門的な知識・ノウハウを必要とするものもあり、賃貸管理会社に委託するのが一般的です。
管理委託については、こちらもご参照ください。
【事例付】管理委託契約とは? 委託管理と賃貸管理会社の選定方法!
賃貸経営サポートとは? 不動産投資の成功を左右する管理会社の実力
賃貸経営の核心となる不動産の賃貸管理! 管理会社の対応力と長期視点が大事
自主管理のメリット
自主管理には主に次の3つのメリットがあります。
● 管理手数料が抑えられる
● 入居者様との距離が近い
● 賃貸管理のノウハウが身につく
具体的に解説します。
管理手数料が抑えられる
管理業務を賃貸管理会社に委託した場合、月々の管理手数料が発生します。自主管理では管理手数料を支払う必要がないため、手数料分のコストが抑えられるのが一番のメリットになります。
入居者様との距離が近い
自主管理ではクレーム対応などもオーナー様が行うため、入居者様からの声をダイレクトに聞くことができます。クレームや問い合わせに迅速かつ的確に対処できれば、オーナー様への信頼感は高まります。住みやすいアパートと評価され、高い入居率がキープできるでしょう。また、入居者様と接する時間が増えるので、コミュニケーションが生まれやすいという点もメリットです。
賃貸管理のノウハウが身につく
建物や設備の点検・修繕などは、オーナー様が専門業者を選定して発注することになります。不動産仲介会社をはじめ設備会社や清掃会社などとの接点ができ、自然とさまざまな知識が得られるでしょう。数多くの業者と直接やり取りする中で相場観なども養われ、賃貸管理のノウハウが身につきます。
自主管理のデメリット
自主管理のデメリットは主に次の3つです。
● 管理業務に忙殺される
● 管理を怠ると資産価値が下がる
● 専門的な知識が必要なときがある
それぞれ具体的に見ていきましょう。
管理業務に忙殺される
先述のとおり、賃貸経営における管理業務は多岐にわたります。入居者様から寄せられる連絡には、雨漏りや設備の故障など緊急度の高いものも含まれるため、基本的に365日・24時間体制で対応しなくてはなりません。
当然ながら所有する物件数が多くなるほどクレームやトラブルの発生頻度は高くなり、管理業務に忙殺されることになります。物件数が少ないとしても、集中すべき本業を持ち、副業として賃貸経営をしている方には自主管理は難しいといえるでしょう。
管理を怠ると資産価値が下がる

建物は築年数が経つにつれて徐々に劣化していきます。資産価値を維持するためには定期的な修繕やメンテナンスが欠かせません。また、快適な住環境を保つには共用部分のこまめな清掃も必要です。
こうした管理に手が回らないと建物の資産価値は下がり、空室の発生や家賃の下落を招きます。メンテナンスや清掃が行き届かず荒れた印象のアパートは、新規の入居募集者にも避けられがちです。収益が下がり、修繕などにかける費用が捻出できず建物はますます劣化するという悪循環に陥ります。
専門的な知識が必要なときがある
アパートを所有していれば誰でも賃貸経営ができますが、自主管理を行う場合、ある程度は不動産取引や建築についての知識が必要になります。トラブル対応では法律が関わるケースも少なくありません。
民法では「賃貸人は賃料を受け取るかわりに、賃借人に建物を使用収益させる義務を負う」と規定されています。つまり、オーナー様は入居者様が住まいとして使用できるよう、管理にも責任を持たなくてはならないのです。
例えば、深夜の騒音など迷惑行為が目立つ入居者様がいたとします。この方にアパートから出て行ってもらえばほかの入居者様の使用収益は守られますが、賃借人の権利は借地借家法で保護されているため、退去を迫るのは簡単ではありません。こうしたトラブルやアクシデントに備え、自主管理のオーナー様には賃貸経営について学び続ける必要があるといえるでしょう。
管理委託のメリット
次に、管理委託した場合のメリットを紹介します。主には次の3つが挙げられます。
● 手間が省ける
● 遠方の物件の所有が可能
● リスクヘッジができる
詳しく見ていきましょう。
手間が省ける

賃貸管理会社に管理を委託すれば、オーナー様は面倒な管理業務から解放されます。空いた時間は新規に買い増す物件を探したり、賃貸経営の勉強に充てたりなど、オーナー業に専念できるでしょう。別に本業を持つ方なら、管理について意識することなく本業に集中できます。
遠方の物件の所有が可能
管理を委託してしまえば、自主管理では不可能だった遠方の物件への投資も可能になります。資産規模の拡大を目指すオーナー様こそ管理委託を選ぶべきといえるでしょう。
先述のとおり、所有する物件数が多くなると自分では管理に手が回らなくなりがちです。空室が増えれば経営悪化につながり、売却するにしても資産価値の下がったアパートは高く売れません。その点、管理のプロに委託してしまえば安心です。建物の管理はもちろん、入居付けに強い賃貸管理会社なら入居率の維持向上が期待できます。
リスクヘッジができる
賃貸経営にはさまざまなリスクがありますが、賃貸管理のノウハウを持つ賃貸管理会社に管理委託することがリスクヘッジにつながります。
空室リスクと入居者募集対応・仲介対応
空室期間中は当然ながら家賃収入が得られません。空室による家賃収入が得られない状況を「空室リスク」といい、賃貸経営における最大のリスクとされています。空室が増えるほど、また空室期間が長引くほど減収の幅は大きくなり、経営状態は悪化します。
こうした状況を防ぐには、空室期間をできるだけ短くするために退去が出たら迅速に行動することが大切です。退去後は速やかに原状回復工事の手配を行い、工事完了後にすぐに入居できるよう並行して入居者募集を行います。状況によっては水回り設備を新しくするなどのリフォームも必要になるかもしれません。
これら一連の流れはオーナー様が一人で行うよりも、実績豊富な賃貸管理会社が行ったほうがはるかに効率的といえるでしょう。特に入居者募集対応・仲介対応の業務に長けた賃貸管理会社であれば、入居者募集のノウハウやネットワークを持っています。
空室発生の代表的な要因を解決するフレームワークである『4つの空室対策(募集/仲介/入居者管理/設備・工事)』を意識するとともに、そのノウハウを持った賃貸管理会社のサポートを得られれば心強いものになります。
成功事例については、こちらもご参照ください。
自主管理時代に数年続いた空室とも、おさらば!入居者募集の違いを実感
自主管理オーナー様の代替わり、海外在住でもバッチリサポート!
入居者トラブルリスクと「入居者管理」

すべての入居者様がマナーを順守するとはかぎりません。ゴミ出しのルールを守らない、深夜にもかかわらず大きな音をたてるなどの迷惑行為やルール違反があると、アパートにお住いの入居者様のコミュニティにおける共通認識が崩れてしまい、賃貸管理の品質が低下します。
入居者様や近隣住民からのクレームにはオーナー様が対応しなくてはならず、精神的な負担は大きなものになるでしょう。また、ほかの入居者様が住環境に不満を抱き、退去してしまう可能性もあります。
このような入居者トラブルへの対策のひとつに、契約前の厳格な入居者審査が挙げられます。実際の審査は、日頃から数多くの入居者様・入居希望者様とやり取りをしている賃貸管理会社に任せるのがよいでしょう。
また、あらかじめ説明をしておくことでトラブルを未然に防げることもあります。既存の入居者様の顧客満足度を向上させる賃貸管理により、長くお住まい頂ける環境をつくることが空室対策にもなるのです。
成功事例については、こちらもご参照ください。
物件内に管理委託と自主管理が混在、管理移管とあわせて全部委託したい!
家賃滞納リスクと「入居者審査・保証会社」
厳格な入居者審査は家賃滞納リスクを減らすことにもつながります。同時に家賃保証会社を利用することで、より確実なリスクヘッジが可能です。
家賃保証会社では、滞納があった際に入居者様に代わって家賃をオーナー様に支払い、後日入居者様から立て替えた家賃を回収します。オーナー様にとっては予定どおり家賃が得られるうえ、督促などの労力から解放される心強い存在です。近年、家賃保証会社を利用する賃貸住宅は、全国で約8割にのぼるともいわれています。新規の入居者募集の際、検討してみてはいかがでしょうか。
成功事例については、こちらもご参照ください。
建物と外構の管理リスクと「建物管理(清掃・メンテナンス)」
建物の外観や駐輪場・ゴミ置き場など共有施設の状態は、アパート全体の印象を左右します。見学に来た方の入居意思決定にも関わるため、日頃からこまめな清掃とメンテナンスを継続することが大切です。
しかしながら、本業を持つオーナー様がアパート清掃のために定期的に通うのは現実的ではありません。専業のオーナー様でも所有物件が複数あると手が回らないでしょう。清掃業務や点検・メンテナンスを含め、賃貸管理会社に委託すれば安心して賃貸経営が行えます。
建物とお部屋の老朽化リスクと「設備・工事・修繕対応」
建物は実物資産である以上、年数が経つにつれて老朽化していくことを避けることはできません。経年劣化に伴う対策を放置したままでは資産価値が低下する一方のため、定期的な大規模修繕工事によって建物の状態を維持する必要があります。また、建物の躯体や競合物件の状況に応じて入居者様のニーズに応えられるようなリフォームやリノベーションを計画・実施することも大切です。
ただし、高額な費用をかけたからといって相場よりも高い家賃を設定してしまうと、逆に近隣相場からかけ離れてしまい、入居付けが難しくなる可能性があります。適切なコストで効果的な工事を行うには、賃貸市場のニーズを把握している賃貸管理会社にアドバイスしてもらうのがよいでしょう。
成功事例については、こちらもご参照ください。
自主管理で6部屋の空室を原状回復のみで2カ月で満室経営に改善!
賃貸経営のサポートが受けられる
賃貸管理会社に依頼できる業務は、大きく分けると「入居者管理」と「建物管理」の2つです。賃貸管理会社には定形的な管理業務だけにとどまらず、より幅広い賃貸経営のサポートまでカバーしてくれるところもあります。
オーナー様の中には、いつか物件を売却することを検討している方もいます。賃貸経営では出口戦略を間違えると、せっかく運用時に得た家賃収入(=インカムゲイン)が吹き飛び、大きな損失を出す場合もあります。
売却する際は適切なタイミングで、いかに高く売り、どれだけ売却益(=キャピタルゲイン)を得られるかが重要です。出口戦略を見据えたアドバイスをくれる賃貸管理会社であれば心強く、賃貸経営を始めるときから相談もできます。
また、節税で悩みを抱えている方や、不動産投資を拡大したいと考えている方、将来子どもや孫などに物件を相続させたいと考えていらっしゃる方もいるでしょう。幅広い業務に対応している賃貸管理会社なら、税務相談や複数棟の購入、相続などのサポートも受けられます。
成功事例については、こちらもご参照ください。
【売却実績】自宅から1時間かけて自主管理をしていた一棟アパート!体力の限界が来る前に終活の一環として売却を決意!
管理委託のデメリット
管理委託で注意したいデメリットは、次の2つです。
● 管理手数料がかかる
● 賃貸管理会社を見極める目が必要
以下にて詳しく解説します。
管理手数料がかかる

賃貸管理会社に管理を委託すると、管理手数料というコストが発生するのはデメリットです。管理手数料の設定は会社によって異なるほか、業務内容によっても違いがあります。管理手数料が安ければ費用を抑えることができますが、その分、適切な管理やメンテナンスができなければ本末転倒です。
管理手数料を出し渋ったばかりに物件の資産価値が下がり、将来売却しようとしたときに思ったほどの価格で売れないことも考えられます。それでは出口戦略で損失を出し、最終的にオーナー様の賃貸経営が失敗する結果になりかねません。
一般的な管理手数料の相場は、家賃の5%程度です。管理手数料を相場よりも低く設定している賃貸管理会社の中には、システム利用料などのほかの名目で費用請求をするケースもあるため注意してください。
賃貸管理会社に委託する管理業務の適正化によって、管理手数料は削減できることもあります。管理内容を把握したうえでオーナー様が自分で対応できることを見極め、できない部分だけを賃貸管理会社に委託するのも方法のひとつです。
成功事例については、こちらもご参照ください。
管理費削減による収支の改善と賃料アップによる賃貸経営の改善!
築浅物件のサービス見直しで管理費削減!月々3万円のコストダウン
賃貸管理会社を見極める目が必要
賃貸管理の良し悪しはそのまま物件の良し悪しに、さらにはオーナー様の評判にも直結します。管理委託の場合、実際に入居者様とやり取りをするのは賃貸管理会社です。クレームやトラブルに迅速・的確に対応できるか、入居者様が安心できるような対応ができるかなど細かくチェックし、良質な賃貸管理会社を見極める目が求められます。
賃貸管理会社の選び方については、こちらもご参照ください。
賃貸経営を成功に導く不動産管理とは? 信頼できる管理会社の選び方を解説
賃貸管理会社の探し方と6つのポイント!賃貸経営の収支を握る管理とは
【必読】賃貸管理会社の選び方!運用益と出口戦略を見据える賃貸管理
【賃貸管理会社】大手と地域密着型のどっちがおすすめ?選び方とは
賃貸管理会社の選定基準は手数料の安さか、収益性を高める管理か
管理会社の変更はあり?賃貸経営安定化のためにオーナー様がなすべきこと
サブリースのメリット
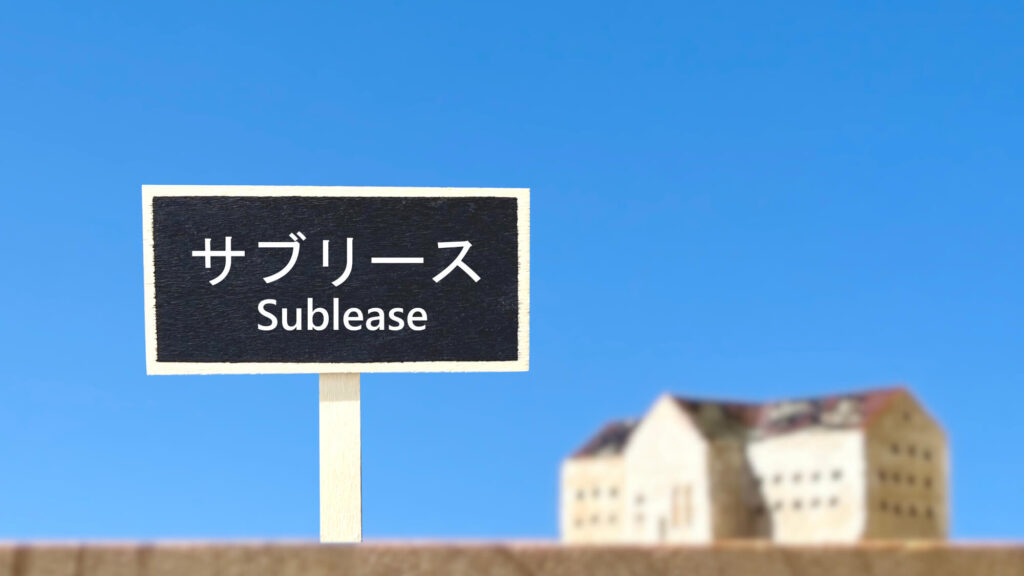
管理委託契約の一種に、サブリース(一括借上)契約という方法もあります。この仕組みは、オーナー様にとって複数のメリットがあります。空室リスク・家賃滞納リスクへの対策、および融資が有利になりやすいという2つのメリットについて、さらに詳しく掘り下げます。
サブリース契約については、こちらもご参照ください。
サブリースとは?不動産経営や賃貸経営で損しないサブリースの注意点
【事例付】サブリース新法を徹底解説! 契約時の注意点とメリット・デメリット
【事例付】一括借り上げとサブリースとの違いやメリット・デメリットを解説
マスターリース契約とは? サブリースとの違いや活用ポイントを事例で解説
空室リスク・家賃滞納リスク対策になる
サブリース契約は賃貸管理会社が物件を一括して借り上げるため、オーナー様にとっては空室や家賃滞納の影響を受けにくいのがメリットです。サブリース契約では、仮に空室や家賃の滞納が発生しても、オーナー様は賃貸管理会社から一定の金額を支払ってもらえます。
一般的な賃貸経営では、多かれ少なかれ空室が発生するリスクや入居者様が家賃を滞納するリスクがあります。家賃収入が途絶えた分、賃貸経営を圧迫することになるため、リスクを気にせず、安定した収入を確保できる点は大きな利点です。
本業があるオーナー様は、賃貸経営を賃貸管理会社に任せて本業に専念できます。自分で管理をしにくい遠方の物件であっても、サブリース契約であれば投資しやすいでしょう。
融資が有利になる

サブリース契約を結ぶことにより、一般的な賃貸経営に比べて空室リスクや家賃滞納リスクが軽減されます。収入の安定性が担保されれば、金融機関の評価が高まりやすくなるのもメリットです。
金融機関が融資するかどうかを決定する際に重視するポイントのひとつが、融資先の返済能力です。サブリース契約を結んでいると、入居率や市場の変動にかかわらず一定の家賃収入が保証されているため、収益性が高いと判断されやすくなります。結果としてローンの審査に通りやすくなる可能性も高まるでしょう。
新たに収益物件を一棟購入し、投資を拡大したいというケースでも、サブリース契約の物件を保有していることで金融機関の評価が有利に働き、新たな融資を受けやすくなる傾向です。
サブリースのデメリット
一方で、サブリース契約には注意すべきデメリットも存在します。後になって、思っていたほどの家賃収入が得られない、契約解除ができないなどのトラブルに直面しないよう、契約を検討する際にはリスクを理解しておくことが不可欠です。
通常より家賃収入が減少する
サブリース契約は一定額の安定した収入を得られる点がメリットですが、直接貸し出す場合に比べると家賃収入が少なくなるデメリットがあります。サブリース会社は入居者様から得た家賃収入から一定の料率を差し引いた額をオーナー様に支払うからです。
例えば、サブリース会社が入居者様から受け取った家賃収入が月額で合計100万円あったとしても、その10〜20%が差し引かれ、オーナー様には80〜90万円程度しか入りません。一般的な管理委託では、賃貸管理会社に支払う管理手数料はせいぜい5%程度です。
空室リスクや家賃滞納リスクは軽減されるものの、長期的に10〜20%家賃収入が減少し続けると、利益が圧迫される可能性もあります。サブリース契約を検討する際は、長期的な利益が減少することも理解しておいてください。
家賃減額を請求されることがある
サブリース契約で安定した収益を確保できるのは大きなメリットではあるものの、最初の契約内容が長期継続するとはかぎりません。収入のもとになる家賃は、市場の状況変化や需要の変化などで見直しが図られるケースがあります。
サブリース契約では2年ごとに契約条件が見直される場合が多く、家賃の減額交渉を受けることがあります。オーナー様にとっては家賃収入が減ることは受け入れがたい状況ですが、周辺の家賃相場と不釣り合いな場合や経済情勢の変化があった場合などには、オーナー様はサブリース会社に家賃の減額請求をされることがあります。
借地借家法は賃借人の立場を守る法体系となっています。サブリース契約ではサブリース会社が賃借人の立場になるため、どんなに大きな法人であっても法的に「守られる」立ち位置にあるのです。
サブリース契約においては、将来的な家賃減額のリスクも考慮して収支計画を立てておくことが重要です。
オーナー様からの契約解除が難しい
サブリース契約では、オーナー様側の都合で契約を解除することが極めて難しいのも大きなデメリットです。前述したとおり、サブリース契約はオーナー様が賃貸人、サブリース会社が賃借人という立場となるため、オーナー様側から契約解除を申し出る場合は「正当事由」が必要になります。
正当事由としては「老朽化で取り壊す必要がある」、「賃貸人が自分で使用する事情がある」、「賃借人が信頼関係を破壊する行為をした」などが挙げられます。
単に「サブリース会社の管理業務に不満がある」、「経営方針が変わった」などのオーナー様都合の理由での契約解除はできないのが現実です。「合意解約」といった形で認められたとしても、多額の違約金を支払わなければならないケースも珍しくありません。一般的な賃貸経営とは違い、柔軟な運用ができなくなる点には十分に注意してください。
修繕・原状回復工事費用が割高になることがある

サブリース契約はサブリース会社が入居者様に居室を転貸している形態であり、あくまでも物件の所有者はオーナー様です。そのため、サブリース契約の物件にかかる修繕や原状回復工事にかかる費用は、サブリース契約の内容によって詳細は決まりますがオーナー様負担が生じます。
サブリース契約の場合、工事の依頼先はサブリース会社が指定する施工会社になることがほとんどです。もし、オーナー様が個人的にお付き合いのある施工会社やお世話になったことがある施工会社に依頼したいと思っても、認められない可能性があります。その結果、工事費用にサブリース会社のマージンが上乗せされて、相場よりも高い費用を負担することにもなりかねません。
修繕や原状回復工事にかかる費用負担については、サブリース契約の内容によっても違いがあります。修繕・原状回復工事の費用があまりにも高額になってしまうと、将来にわたる修繕計画も立てにくくなるでしょう。サブリース契約を結ぶ際は契約内容をしっかり確認し、不安や疑問点があれば確認するようにしてください。
管理費の相場・目安は
ソフト面の入居者管理や、ハード面の建物管理など、賃貸管理の全体像を押さえたところで、次に入居者様から徴収する管理費について見ていきましょう。
管理費の全国的な平均相場
管理費は、主に共用施設の維持管理や点検、修繕などに充てられる費用です。金額の設定については法的な決まりはなく、オーナー様の意向で決められます。ちなみに国土交通省の調査では、2021年度の民間賃貸住宅における共益費(管理費)の平均は月額5,362円と発表されています。基本的には近隣の競合物件と返りが少ない管理費設定をしますが、物件により各種調整を入れることが多い項目です。
管理手数料との違いとは
管理料と管理手数料は似た言葉ですが、まったく別のものです。先述したように管理費は建物の維持管理のために使われるもので、オーナー様が入居者様から徴収する費用です。金額はオーナー様が任意で決められます。
管理費は共用施設の点検や維持管理に使われる費用であり、そこで生活する入居者様にとっては欠かせません。安全かつ、快適に暮らすために重要な費用として、入居者様にも負担していただいています。
一方で、管理手数料は管理業務の対価としてオーナー様から賃貸管理会社に支払う費用であり、金額は賃貸管理会社が決めます。一般的な相場は家賃の5%程度ですが、賃貸管理会社や業務内容によって違いがあるため注意してください。
修繕積立金との違いとは
修繕積立金は定期的に実施される大規模修繕に充てられる費用として、区分マンションの所有者が積み立てるものです。区分所有法に基づき、区分所有者が支払う義務を負っています。大規模修繕は日常的な点検やメンテナンスとは違い、大きな費用が発生するため、マンションの所有者全員が少しずつ積み立てを行っているのです。
同じように複数の居住スペースが設けられているアパートやマンションも、見た目は区分所有マンションと変わりありません。しかし、収益物件の場合、入居者様はあくまでも借りているだけで、所有者はオーナー様です。
賃貸マンションやアパートでは、そこに住んでいる入居者様が大規模修繕に備える修繕積立金を負担する義務はなく、修繕の義務はオーナー様にあります。アパートやマンションなどの建物は日頃からしっかり維持管理を行っていても、時間の経過とともに劣化が進んでいくのは避けられません。
そのため、実物資産を所有している以上、いつかは大規模修繕を実施する時期がやってきます。そのため、オーナー様には、毎月の収益の中から積み立てておく必要があります。
共益費との違いは
管理費に似たものに「共益費」があります。共益費も管理費と同じく、集合住宅の共用施設を維持管理するのに充てられる費用ですが、どのように使い分けるのか疑問に感じる方は多いのではないでしょうか。ここからは公的機関の資料を参考に、管理費と共益費の違いを解説します。
管理費とは?
不動産公正取引協議会連合会の資料では、管理費についての表示規約として以下のように定めています。
(41)管理費(マンションの事務を処理し、設備その他共用部分の維持及び管理をするために必要とされる費用をいい、共用部分の公租公課等を含み、修繕積立金を含まない。)については、1戸当たりの月額(予定額であるときは、その旨)を表示すること。
ただし、住戸により管理費の額が異なる場合において、その全ての住宅の管理費を示すことが困難であるときは、最低額及び最高額のみで表示することができる。
冒頭に「マンションの」という文言が含まれていますが、国土交通省の「マンション標準管理規約」には次の記載が見られます。
第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
一 管理費
二 修繕積立金
共益費とは?

共益費について、不動産公正取引協議会連合会の資料では次のように定義しています。
(42) 共益費(借家人が共同して使用又は利用する設備又は施設の運営及び維持に関する費用をいう。)については、1戸当たりの月額(予定額であるときは、その旨)を表示すること。ただし、住戸により共益費の額が異なる場合において、その全ての住宅の共益費を示すことが困難であるときは、最低額及び最高額のみで表示することができる。
また、国土交通省が提示する「賃貸住宅標準契約書」には、次のような記載があります。
第5条 乙(借主)は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費等(以下この条において「維持管理費」という。)に充てるため、共益費を甲(貸主)に支払うものとする。
ここには「共益費」とはっきり記載されていますが、建物の構造についての制限はありません。マンションでもアパートでも賃貸住宅に関しては「共益費」という言葉が適当かと思われますが、実際には厳密に区別することなく使用されています。
管理費を設けて家賃を下げることで空室対策になる
分譲マンションの区分所有者が支払う管理費の額は管理規約に定められているため、各自自由に決めることはできません。一方、賃貸住宅の管理費(共益費)は、家賃も含めオーナー様が自由に決められます。
住宅情報サイト(SUUMO・HOME‘S・at-home)などを見てみると「管理費込み」「共益費込み」としている物件もありますが、家賃とは別にしたほうが入居希望者様の目に留まりやすいかもしれません。
例えば、6万円台の家賃で検索しているお客様には家賃7万円の物件は表示されませんが、家賃6万5,000円にすれば検索結果に表示されます。別途管理費として5,000円を徴収すれば、結果的には月7万円の家賃収入になります。より多くのお客様に情報が届くことが空室対策にもなるため、試してみてはいかがでしょうか。
まとめ

賃貸経営において管理は肝といえるものです。優れた賃貸経営のノウハウを持つ賃貸管理会社に管理を委託することが、賃貸経営の成功に結びつくといっても過言ではありません。
【リロの不動産】は、大手不動産会社と地域密着型不動産会社の強みを併せ持つハイブリッド型の賃貸管理会社です。『4つの空室対策(募集/仲介/入居者管理/設備・工事)』を徹底した賃貸管理、老朽化による長期空室をサポートする『リロの満室パック』や費用対効果の高い『賃貸経営リノベーション』のご提案など、賃貸経営のパートナーとして出口戦略までオーナー様をしっかりサポートします。
管理についてお悩みのオーナー様は、ぜひ一度【リロの不動産】にご相談ください。
関連する記事はこちら
不動産収入とは? 不動産所得と手取りの違い・収入を上げる方法も解説
不動産運用は資産形成の王道! リスクを抑えメリットを活かす不動産投資
賃貸経営サポートとは? 不動産投資の成功を左右する管理会社の実力
【必読】不動産投資・賃貸経営の目的が明確なほど成功確率が上がる理由
家賃収入を増加するポイントとは?節税効果・確定申告・損益通算を知る
不動産投資成功の鍵はリフォームにある! 戦略的なリフォーム投資で資産価値向上を
【事例付き】地主のアパート経営が資産保全・税金対策に有利な理由と注意点を解説
【総集編】アパート経営の利回りの目安は?不動産投資の指標と注意点
不動産所得を節税するには?減価償却費など代表的な経費【一覧表】
【アパート経営・賃貸経営入門】メリット・リスク・成功の秘訣をわかりやすく解説!
アパートローンを上手に利用するコツと注意点|住宅ローンとの違いは?
アパート経営に必要な自己資金はいくら? 成功に導く出口戦略と資金計画
家賃収入にかかる税金はいくら?設備投資と損益通算で考える節税対策
おすすめのサービス
おすすめのお役立ち情報
この記事を書いた人
秋山領祐(編集長)
秋山領祐(編集長)
【生年月日】昭和55年10月28日。
【出身地】長野県上田市。
【趣味】子供を見守ること。料理。キャンプ。神社仏閣。
【担当・経験】
デジタルマーケティングとリブランディングを担当。
分譲地開発のPMや家業の土地活用などの経験を持つ。
リノベした自宅の縁の下に子ども達の夢が描かれている。