不動産投資の減価償却と節税の仕組み!節税額の計算方法と注意点を事例で解説
2026.01.01
不動産投資について調べると、減価償却が節税に有利だと聞いたことがある方も多いでしょう。事業を営むうえで不動産のような固定資産を購入すると、会計処理で減価償却を行う必要があります。
この記事では不動産投資における減価償却について、計算方法や節税目的で不動産投資を行う注意点も含めて、具体的にわかりやすく解説します。
▼この記事の内容
●減価償却は、固定資産の購入費用を購入した単年度にすべて費用計上せず、使用可能期間で分割し、一定の期間にわたって毎年計上する会計処理。
●減価償却という会計処理によって、不動産所得は帳簿上赤字にできるケースが多い。不動産所得は給与所得や事業所得などとの損益通算が可能なため、課税所得を圧縮できる。その結果、所得税や住民税の節税につながる。
●減価償却での節税では、物件売却時の譲渡所得税には注意が必要。物件売却時の譲渡所得の計算では、取得費から減価償却費分を差し引く必要がある。そうすると、譲渡所得は大きくなるため、譲渡所得税も高くなる。
●不動産投資では、課税所得900万円以上の人は効果が高いとされる。課税所得900万円未満の人は、節税を主目的にするよりも収益第一の不動産投資を目指すこと、確定申告を青色申告にすることが必要。
●節税目的で不動産投資を行うときは、築古の一棟物件を選択する、新築区分マンションを選ばないようにする、建物価格の大きいものにする、売却は所有期間が5年超になってから行う、収益性を無視した物件選びはしない、融資枠を無駄に使わないようにする、出口戦略を意識する、デッドクロスが見えたら次の投資判断を行う、などが求められる。
目次
不動産投資における減価償却の基本
詳しい計算方法をみていく前に、まずは減価償却の基本を把握しておきましょう。減価償却を知るうえで大切な減価償却資産や、耐用年数などの考え方について解説します。
減価償却とは
減価償却は固定資産の購入費用を購入した単年度にすべて費用計上するのではなく、使用可能期間で分割し、一定の期間にわたって毎年計上する会計処理です。購入価格が10万円以上で耐久性のある資産に関しては、会計上、購入した年に資産として計上されます。一方で費用の処理は、減価償却する分だけを後述する耐用年数に応じて1年ずつ計上する仕組みです。
複数年にわたって使用し続けるにもかかわらず、購入した年にすべて費用計上すれば収支のバランスが取れません。減価償却によって適正な費用配分を行えば、期間の損益を正確に算定できます。ただし、業務で使用するものであっても、購入価格が10万円未満、使用期間が1年未満のものについては、全額購入した年の必要経費とします。
なお、不動産に含まれる資産のうち、土地は経年や使用によって価値が減らないとされるため、減価償却の対象になりません。同じ物件でも、減価償却できるのは建物や設備などに限られ、土地については費用配分の考え方が異なる点を押さえておく必要があります。
減価償却資産

減価償却資産とは、減価償却の対象となる資産です。具体的には建物や建物の附属設備、パソコンなどの機械装置や備品、車両運搬具などの資産が該当します。
また、特許権や商標権、ソフトウェアなども無形固定資産として、減価償却の対象です。減価償却資産は、一般的に時間の経過によって資産価値が減少していくものが対象となり、資産の耐用年数に応じて毎年費用計上をしていきます。
ただし、固定資産であればすべて減価償却できるわけではなく、減価償却の対象となるのはあくまでも事業に使用されるものにかぎられます。ちなみに、骨董品のように時間が経過しても価値が下がるどころか、むしろより価値が上がる可能性もある物品は減価償却資産に入りません。
耐用年数
耐用年数とは、資産を使用できる期間のことです。建物にしても、車両や備品にしても、使っているうちに劣化してくる経年変化は避けられません。いつかは資産が本来持っている価値がなくなる時期が訪れます。税法では、減価償却資産の種類ごとに使用可能な期間を耐用年数として規定しています。
ご紹介する耐用年数は法的に定められている年数であって、対象の減価償却資産を製造したメーカーなどが公表している耐久年数ではありません。費用として処理するための減価償却費を求めるためには、国が定めた耐用年数をもとに計算する必要があります。ただ、同じ不動産でも、土地は年月の経過で価値が下がるようなものではないため減価償却資産としては扱われず、耐用年数もありません。
建物の構造と法定耐用年数
不動産の減価償却資産である「建物」は構造や用途ごとに分けられた種類ごとに法定耐用年数が定められています。住宅として使用される建物で代表的な構造別の耐用年数をみてみると、木造は22年、木骨モルタル造は20年になります。
木造建築は日本古来の建築方法にみられるように、梁や柱、筋交いなどを木材で作っていることを指します。木骨モルタル造は骨組みを木で造り、モルタルで外壁を形成している造りです。鉄骨鉄筋コンクリート造や鉄筋コンクリート造は、法定耐用年数が長く、住宅用では47年となっています。
レンガ造や石造、ブロック造も鉄骨鉄筋コンクリート造や鉄筋コンクリート造ほどではありませんが、比較的長い38年です。鉄骨のような金属造のものは骨格材の厚さによって法定耐用年数が異なり、3mm以下の鉄骨は木造よりも短い19年になっています。3mmを超えて4mm以下の鉄骨では27年、4mmを超えると34年です。
同じ構造の建物であっても、住宅用や事務所用、旅館・ホテル用・病院用など、用途によっても法定耐用年数が異なるため注意が必要です。
不動産投資で減価償却が所得税・住民税の節税に有利な仕組み
では、減価償却が節税になるといわれるのはなぜでしょうか。次に所得税や住民税の節税に有利になる仕組みを解説します。
不動産所得は損益通算が可能

不動産投資としてアパートやマンションなどの収益物件を保有していると、不動産所得が発生します。所得にはさまざまな種類があり、課税方法は大きく分けて総合課税と分離課税の2種類があります。
不動産所得は給与所得や事業所得と同じ総合課税の対象となる所得になります。分離課税は所得の種類ごとに税率が決まっているため、合算することはできません。一方、総合課税では対象の所得を1年間分すべて合計した金額が課税の対象になるため、給与所得や事業所得などとの損益通算が可能です。
つまり、不動産所得が帳簿上赤字であれば、給与所得や事業所得と合わせることで課税所得を圧縮できます。課税所得が圧縮された結果、所得税や住民税の節税につながります。
会社員として給与所得を得ている方は年末調整で税金を支払っていますが、不動産所得を得ていれば確定申告を行わなければなりません。不動産所得で赤字が発生していれば損失分が相殺されて課税対象額も減るため、支払いすぎた税金が還付されます。
減価償却費は実際にはお金が出ていかない支出
不動産は減価償却という会計処理によって、法定耐用年数に応じた年数に分けて費用計上ができます。不動産所得は家賃収入などの収益から、かかった必要経費を差し引いた金額になります。不動産は金額が大きい分、減価償却費に計上できる金額も大きくなります。そのため、帳簿上赤字になる、もしくは赤字幅を大きくできる特徴があります。
しかも、支払い自体は物件の購入時に済んでいるため、帳簿上は費用として計上されていても、実際にはお金が出ていきません。同じ費用でも事務用品の購入や水道光熱費、交際費などの日常的に発生する費用は、実際に支払った金額を計上します。
減価償却では支出がないにもかかわらず、法定耐用年数が残っている期間は課税所得の圧縮が可能です。しかも、収益が手元に残るところは、ほかの投資にはない不動産投資ならではのメリットでしょう。
不動産投資における減価償却費の計算方法
ここからは不動産投資における具体的な減価償却費の計算方法について、計算式や各項目を詳しく解説します。
減価償却費の計算式
減価償却費の計算式は「減価償却費=取得価格×耐用年数に応じた償却率」です。減価償却費を算出するためには取得価格や耐用年数はもちろん、償却率も大事な要素になります。
実際に減価償却資産の会計処理する方法は定額法と定率法の2種類があり、固定資産の種類によってどちらの方法が選択されるのかが決まっています。減価償却費の計算では、残存耐用年数も大事なポイントのひとつです。以下の段落では、さらに減価償却費の計算に関わる要素をそれぞれ解説します。
取得価格
土地は年数によって価値が下がるものではないため、減価償却の対象にはなりません。そのため、減価償却費の計算のもとになる取得価格は、不動産の取得価格から土地部分を除き、建物だけの取得価格を求める必要があります。
ただし、取得価格は購入代金だけではなく、購入時にかかった付随費用も含むことがポイントです。不動産取得税などの租税公課や登記費用など一部含められない費用もありますが、仲介手数料や固定資産税の清算金などは取得価格に含められます。
残存耐用年数
減価償却費を決める要素となる償却率は、耐用年数で決まります。新築物件の場合は法定耐用年数がそのまま使われますが、中古物件では築年数を用いて残存耐用年数を求めます。建物は法定耐用年数を過ぎると、資産価値がなくなるというのが税法上の考え方です。
しかし、実際には建物自体は存在し、使われています。そこで減価償却では現実的な状況を反映させ、帳簿上は資産としての価値が残るようにされているのです。
簡便法での残存耐用年数の計算方法は以下のとおりです。まだ法定耐用年数の一部しか経過していない物件の場合は、「残存耐用年数=(法定耐用年数-築年数)+築年数×20%」です。例えば、法定耐用年数が22年の建物で、築年数が10年だったとすると、残存耐用年数は「(22年-10年)+10年×20%」で、14年となります。
築年数が法定耐用年数を超えている中古物件では、「残存耐用年数=築年数×20%」で計算されます。同じ法定耐用年数22年で築年数が30年の築戸物件では「22年×20%」となり、残存耐用年数は4年です。
定額法と定率法
減価償却の算出方法には、定額法と定率法の2種類があります。定額法は、毎年一定の金額を減価償却費として計上する方法です。「取得価格×定額法の償却率」で計算され、原則として減価償却費は毎年同じ金額になります。
定率法は最初に大きな減価償却費を計上し、使用していくうちに減価が少なくなると仮定する償却方法で、特に物件購入後の早い時期に節税効果があります。減価償却費の計算式は「未償却残高(初年度は取得価格)×定率法の償却率」です。
2007年の税制改正で減価償却資産は1円まで償却されることとなり、償却保証額や調整前償却額、改定取得価額、改定償却率が設けられました。そのため、償却額が償却保証額に満たなくなった年以降の分は「改定取得価格×改定償却率」で計算され、毎年同額になります。
ただし、減価償却の方法はこれまで何度も改正が行われており、1998年4月の改正では、以降に取得した建物の償却方法は定額法のみ適用されるようになりました。また、2016年4月以降に取得した建物附属設備も定率法が廃止され、定額法だけになっています。
償却率の表
国税庁では償却率を一覧にした表が公開されています。2007年には税制が改正され、償却率が変わっています。2007年3月31日以前に用いられていた償却方法は旧定額法・旧定率法と呼ばれるようになりました。
定額法はそれほど大きな違いはないものの、多少異なっている部分があります。2007年の改正では1円まで償却することになったのがポイントのひとつです。定率法では年数が経つと減価が少なくなるため、1円になるまでの年数が長くかかります。
そこで、償却保証額を設け、この金額を下回ると、改定取得価格に改定償却率をかけて償却額を算出するように計算方法が変わります。減価償却費を計算する際は、その「減価償却資産の償却率表」で確認してください。
収益物件を売却する際の譲渡所得税に注意!

節税目的で減価償却の費用計上を行う際は、売却時の譲渡所得税には注意が必要です。そこで、譲渡所得についても計算方法や税率を含めて解説します。
譲渡所得とは
譲渡所得とは、不動産などの資産を売却したときに生じる所得です。土地や建物などの不動産のほか、株式やゴルフ会員権なども譲渡して売却益が発生すれば譲渡所得になります。ただし、不動産でも山林の譲渡で得たものは譲渡所得になりません。譲渡所得に対して所得税や住民税、2037年までは所得税に対して2.1%の復興特別所得税などの譲渡所得税がかかります。
確定申告の際は給与所得や事業所得など、ほかの所得と合わせて行いますが、譲渡所得税は分離課税です。同じ不動産にかかわる所得でも、収益物件を所有することで得られる家賃収入は不動産所得として給与所得や事業所得と損益通算ができます。一方、譲渡所得は損益通算ができないため、別々に計算することになります。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得の計算式は「譲渡所得=不動産の売却価格-(取得費+譲渡費用)」です。譲渡所得は実際に土地や建物の売却代金として買主から受け取った売却価格から、取得費や譲渡費用、特別控除額があればその分も差し引いて求めます。
取得費はその物件を購入したときの代金や新築の場合は建築代金、不動産取得税や印紙税などの購入にかかった手数料を合計した金額です。譲渡費用は売却する際に支払った印紙税や仲介手数料など、売却するために直接かかった費用が該当します。
ただし、確定申告で減価償却費を計上している場合、取得費の計算で減価償却費分を差し引く必要があります。減価償却は不動産を保有しているときは節税効果が期待できますが、多用していると譲渡所得の計算時には取得費が小さくなることに注意が必要です。
取得費が小さくなれば、反対に譲渡所得は大きくなるため、譲渡所得税も高くなってしまいます。この計算方法を知らなければ減価償却で節税できても、後々物件を売却する際の譲渡所得税で帳消しになってしまいます。
譲渡所得税の税率

譲渡所得税の税率は、売却した物件を所有していた期間で変わります。所有していた期間が5年を超過した1月1日を基準日として、超えていれば長期譲渡所得、それ以下の期間なら短期譲渡所得に区分されています。長期譲渡所得の税率は「所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%=20.315%」、短期譲渡所得の税率は「所得税30%+住民税9%+復興特別所得税0.63%=39.63%」です。
長期譲渡所得と短期譲渡所得では税率が倍近くも異なるため、売却時期が少し違っただけでも負担する税金が大きくなる可能性があります。不動産投資では、減価償却を計上し節税を図ったうえで、長期譲渡所得になってから売却するのが出口戦略の基本です。
減価償却の期間が終了すると所得税や住民税の負担が大きくなり、建物や設備の劣化が進むと修繕コストもかかってきます。減価償却を行っている間の課税対象額を圧縮できるメリット、長期譲渡所得で売却時の税率が低くなるメリットをうまく活用し、トータルで税金の負担を抑えることがポイントです。
不動産投資では年収によって節税効果は変化する

不動産投資の節税は、減価償却の使い方だけでなく、投資家の年収によって効果の大きさが変わります。どの所得帯に当てはまるかで、得られるメリットや重視すべきポイントが異なるため、まずは年収ごとの違いを整理しておきましょう。
課税所得900万円以上の人は効果が高い
不動産投資で得られる節税効果は、投資家の年収によって大きく変わります。日本は累進課税制度のため、所得が高いほど税率も上がる仕組みです。特に効果が出やすいのが、課税所得900万円(年収の目安はおよそ1,200万円)を超える層で、この水準になると所得税33%と住民税10%を合わせた合計税率は43%になります。
減価償却費などを使って不動産所得が赤字になると、その赤字は給与所得と損益通算できます。例えば不動産所得で100万円の赤字を計上した場合、課税所得が100万円圧縮されます。税率43%の方と税率30%の方では、同じ100万円の圧縮でも節税額が変わります。そのため、高所得層ほど節税の恩恵を受けやすくなるのです。
ただし、減価償却が進むと簿価が下がり、売却時に利益が大きくなりやすい点は押さえておきます。
課税所得900万円未満の人が行うべきこと
課税所得が900万円に満たない場合、減価償却による節税効果はどうしても小さくなります。そのため、高所得者向けのような節税型の不動産投資とはあまり相性がよくないといえます。
では何を重視すればいいのかというと、運用でどれだけ手元に残るか、そして長く続けられる収支かどうかです。ここからは、節税に依存せず、堅実に資産を育てるための考え方と、実際の手続き面で押さえておきたいポイントを順番に紹介していきます。
収益第一の不動産投資を目指す
課税所得が900万円未満の方は、節税を主目的にするよりも、まず収益性を軸にした不動産投資を意識したいところです。減価償却による節税効果が大きくなりにくいため、判断の中心は税引き後のキャッシュフローになります。
表面利回りや節税額だけではなく、空室リスク、長期保有で必要になる修繕費、家賃の下落といった要素をふまえた実質利回りや、最終的にどれだけ手残りがあるかを基準に物件を選びます。
減価償却は補助的に働く場面がありますが、投資判断の軸にはせず、安定して手残りを確保できるかが優先される視点です。収支の内容をしっかり確認して物件を選べば、無理のない運用ができ、長期的な資産形成につながります。
確定申告を青色申告にする

不動産所得の確定申告では、節税メリットが大きい「青色申告」を選ぶことをおすすめします。青色申告の特徴は、要件に応じて10万円、55万円、最大65万円の青色申告特別控除を受けられる点です。経費とは別に課税所得から直接差し引ける仕組みのため、所得税と住民税の負担を安定して抑えられます。日々の収支を整理するほど、青色申告特別控除の効果も実感しやすくなります。
最大65万円の控除を受ける場合は、複式簿記による記帳と e-Tax を使った電子申告(または条件を満たす電子帳簿保存)が必要です。紙で申告する場合は55万円が上限ですが、それでも節税効果としては十分大きい水準です。
青色申告にはそのほかにも、不動産所得が赤字になった際に翌年以降3年間繰り越せる「純損失の繰越控除」や、一定の条件を満たせば家族に支払う給与を経費として計上できる「青色事業専従者給与」などの制度があります。複数の仕組みを合わせて使うことで、不動産投資の税負担を継続的に軽くしやすくなります。
出典:国税庁 A1-4 純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求手続
不動産投資の減価償却による節税シミュレーション

減価償却を活用すると、どの程度の節税効果が期待できるのでしょうか。ここでは「課税所得2,000万円」と「課税所得4,000万円」の2つの事例をもとに、築古物件の減価償却を行った場合と行わなかった場合の税額の差をシミュレーションします。
事例1
【概要】
| 建物価格 | 4,000万円 |
| 物件総額 | 8,500万円(土地価格・諸費用込) |
| 構造 | 木造(法定耐用年数22年) |
| 築年数 | 25年 |
| 総収益率(FCR) | 4% |
| オーナー様の属性 | 課税所得2,000万円の会社員 |
【① 減価償却なし】
所得税:(2,000万円 × 40%)- 2,796,000円 = 520万4,000円
復興特別所得税:520万4,000円 × 2.1% = 10万9,284円
住民税:2,000万円 × 10%= 200万円
所得税+住民税=約731万円
【② 減価償却あり】
年間CF:8,500万円×0.04=340万円
減価償却費:4,000万円÷4=1,000万円
不動産所得:340万円−1,000万円=−660万円
課税所得:2,000万円−660万円=1,340万円
所得税:1,340万円×33%−153万6,000円=288万6,000円
復興特別所得税:288万6,000円×2.1%=6万606円
住民税:1,340万円×10%=134万円
合計:約428万円
減価償却を行わない場合の税額は約731万円、減価償却を行った場合は約428万円となり、年間で約303万円の節税となります。
事例2
【概要】
| 建物価格 | 7,000万円 |
| 物件総額 | 1億1,500万円(土地価格・諸費用込) |
| 構造 | 軽量鉄骨(法定耐用年数27年) |
| 築年数 | 27年 |
| 総収益率(FCR) | 3.8% |
| オーナー様の属性 | 課税所得4,000万円の企業経営者 |
【① 減価償却なし】
所得税:(4,000万円 × 45%)− 4,796,000円 = 1,320万4,000円
復興特別所得税:1,320万4,000円 × 2.1% = 27万7,284円
住民税:4,000万円 × 10%= 400万円
所得税+住民税=約1,748万円
【② 減価償却あり】
年間CF:1億1,500万円 × 0.038 = 437万円
減価償却費:7,000万円 ÷ 5 = 1,400万円
不動産所得:437万円 − 1,400万円 = −963万円
課税所得:4,000万円 − 963万円 = 3,037万円
所得税:3,037万円 × 40% − 279万6,000円 = 935万2,000円
復興特別所得税:935万2,000円 × 2.1% = 19万6,392円
住民税:3,037万円 × 10% = 303万7,000円
合計:約1,258万円
減価償却を行わない場合の税額は約1,748万円、減価償却を行った場合は約1,258万円となり、年間で約490万円の節税となります。
節税目的で不動産投資を行うときの注意点
節税目的で不動産投資を行うときは、ほかにも注意すべきポイントがあります。以下の内容についても把握しておいてください。
築古の一棟物件を選択する
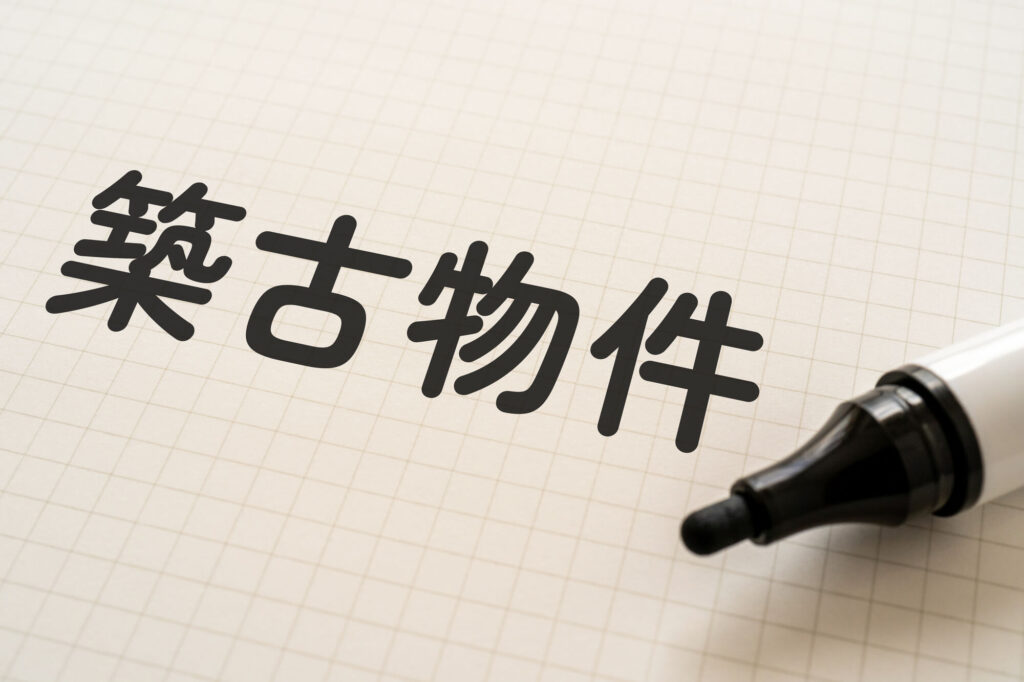
減価償却による節税効果を高めるには、毎年どれだけ大きく減価償却費を計上できるかが重要です。そこで候補に入れたいのが、法定耐用年数をすでに超えた築古の一棟アパートです。
耐用年数を全て経過した建物は「簡便法」という計算方法を使うことができ、木造であれば4年、軽量鉄骨の場合は5年という短い期間で建物価格を償却できます。短い年数で費用を大きく計上できるため、不動産所得が会計上赤字になりやすく、給与所得などとの損益通算による節税効果を得やすい点が大きなメリットです。
一方で、築古物件は設備の交換や外装工事など、突発的な修繕費が発生する可能性があります。節税額だけに注目して購入すると、想定以上の支出が重なり、キャッシュフローが圧迫されるリスクがあります。築古の一棟物件を選ぶ際は、減価償却のメリットと同時に、維持管理にどれくらい費用がかかるかも必ず確認し、長期の収支を踏まえて検討することが大切です。
■収益物件の中古アパート購入事例
ヴェンヴェール日吉の購入事例|不動産投資・投資用不動産・収益物件
西荻窪アパートの購入事例|不動産投資・投資用不動産・収益物件
方南町アパートの購入事例|不動産投資・投資用不動産・収益物件
西川口1棟アパートの購入事例|不動産投資・投資用不動産・収益物件
駒澤大学アパートの購入事例|不動産投資・投資用不動産・収益物件
新築区分マンションを選ばないようにする
節税目的で不動産投資を行う場合、新築の区分マンションは選ばないほうが賢明です。理由は、節税の中心となる減価償却費をほとんど計上できず、所得を圧縮する効果が非常に小さいためです。
多くの区分マンションは鉄筋コンクリート造で、法定耐用年数は47年と長く設定されています。減価償却費は法定耐用年数で按分されるため、新築物件を47年で償却すると、1年あたりに経費として計上できる金額はごく小さくなります。長期間にわたって少額ずつしか償却できないため、所得を大きく圧縮することが難しく、減価償却を節税の軸にしづらいということです。
上記の理由から、新築区分マンションは節税を目的とした不動産投資との相性が悪く、節税効果を期待して購入する物件としては適していないといえます。
建物価格の大きいものにする
不動産投資の節税効果を高めるには、物件価格のうち「建物価格」の割合が大きい物件を選ぶことが重要です。
不動産の価格は建物と土地で構成されますが、減価償却の対象になるのは建物だけです。土地は経年で価値が下がらない資産とされており、経費として扱えません。つまり、建物価格が大きいほど償却できる総額が増え、会計上の所得を抑えやすくなるのです。
どれだけ償却できるかは、土地と建物の按分がどのように設定されているかで決まります。そのため、物件を購入するときは、売買契約書や固定資産税評価証明書で土地と建物の区分を事前に確認するようにします。
建物価格を把握しておくことで、減価償却に使える金額が明確になり、物件ごとの節税効果も比較しやすくなります。
売却は所有期間が5年超になってから行う
不動産を売却する際は、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えてから手放すのが基本です。これは、譲渡所得にかかる税率が所有期間によって大きく変わるためです。5年以下なら短期譲渡所得扱いで税率は39.63%、5年を超えると長期譲渡所得扱いで20.315%となり、ほぼ半分の税率になります。売却益が出やすい不動産では、この差が実際の手取りに直結します。
築古物件で減価償却を多く取っているケースでは、帳簿上の建物価値が短期間で大きく下がり、その分だけ売却した際の利益が大きく計算されやすい特徴があります。実際のキャッシュが増えていなくても、帳簿上の数字だけが大きく動くため、短期の高い税率がかかると税額が想定以上に膨らむ可能性があるのです。
こうした仕組みを踏まえると、節税目的で物件を運用するなら、長期譲渡に該当する5年超まで保有し、その後に売却する流れを前提に考えておくと安心です。
収益性を無視した物件選びはしない

不動産投資で節税を考えるのは大事です。しかし、節税ばかりに目が行って、収益物件としての事業計画や本来の目的が達成できないのでは意味がありません。アパートやマンションなどの収益物件は、毎月入ってくる家賃収入が一定以上なければ、当然収支がマイナスになるでしょう。
そうなると、物件を維持するための必要経費や納税のための資金が用意できないほど、赤字続きになってしまう可能性もあります。物件の購入に不動産投資ローンを利用している場合は、返済も難しくなってしまうかもしれません。
不動産投資を行う最終的な目的は収益を上げ、資産を形成することにあります。空室率が高い物件では節税ではなく、ただの損失になるリスクがあります。損失を出しているとリフォーム・リノベーションのための融資や不動産投資を拡大するための融資も、受けにくくなるでしょう。
将来的に売却したいと思っても、収益性の低い物件では希望する価格で売れないことも考えられます。節税効果を念頭に入れておく必要はありますが、不動産投資本来の目的を踏まえ、事業計画が難しい物件には手を出さないことが大切です。
融資枠を無駄に使わないようにする
不動産投資は、投資を始めるにあたって不動産を保有するための大きい資金が必要になります。自己資金で購入できる方もいるかもしれませんが、金融機関の融資を利用するケースが一般的でしょう。金融機関が融資を行う際、多くは投資家の属性によって融資枠が決められています。
アパートやマンションを一棟丸ごと購入する一棟マンション投資や一棟アパート投資の場合は、融資枠の関係で希望する資金調達が難しいケースもあります。
一方、マンションの1室だけを購入する区分マンション投資は融資を受けやすいメリットがあるものの、一般的に利回りが低い傾向にあります。特に都心部の物件は値上がりしていることもあり、価格が高額な分、利回りは低くなっています。利回りが高ければ必ず儲かるというわけではありませんが、不動産投資を成功させるためにはキャッシュフローが残る物件を選ぶことが重要です。
将来的な資産形成を考えると、節税だけを意識しすぎて利回りの低い物件を買い進めるのはマイナスになることもあります。せっかく融資を受けられるのなら、融資枠を無駄にしない物件を選ぶようにしましょう。
出口戦略を意識する

終の棲家として購入するマイホームとは違い、投資用の収益物件ではいつかは手放すタイミングが訪れます。もちろん、売却せず賃貸に出し続けるのも選択肢のひとつです。
しかし、建物は年数が経過すると劣化が進み、修繕コストがかかってくるうえ、いざ売却しようと思ったときは売却益が見込めない状態になる可能性が高くなります。入居者様がいてくれれば長期的な家賃収入を望めるメリットもありますが、入居率が低下するリスクも内包します。
戸建て住宅や区分マンション投資では、入居者様に購入してもらえるケースや自宅に転用できるケースもありますが、出口戦略として多い方法は売却です。ただ、節税目的で築古の木造物件を取得したときなどは、売却で苦労する場合があります。築年数が古いと金融機関の融資が下りにくく、買主様もかぎられるため、ババ抜きのジョーカー状態になってしまいかねません。
不動産投資では家賃収入を得て資産形成できるのがメリットですが、出口戦略を間違えるとせっかく蓄えてきた利益が消失してしまうことがあります。売却したとき、最終的な利益をプラスにして終われるよう、出口戦略を意識しておくことが大事です。
デッドクロスが見えたら次の投資判断を
デッドクロスとは、ローンの元金返済額が減価償却費を上回った状態です。減価償却ができる間は、実際の支出がないにもかかわらず会計上は減価償却費として費用として計上できるため、課税対象額を圧縮できるメリットがあります。一方でローンの元金返済額は現実的に支払いがありながら、費用計上はできません。
特に元利均等返済のローンを利用している場合は、年数が経つにつれて元金の割合が増えていくため、よりデットクロスが発生しやすくなっています。また、築古の物件はすでに耐用年数が近づいているか、すでに超えていることが多く、購入後の短期間で減価償却を終えます。その分、初期には利益を大幅に圧縮できますが、デッドクロスが訪れる時期も早いのが特徴です。
デッドクロスに入ると現実のキャッシュフローは変わらないにもかかわらず、帳簿上は黒字となります。帳簿上で利益が出ている分、所得税も上昇し、資金繰りが悪化して黒字倒産するリスクもあるため注意しましょう。デッドクロスが見えてきた物件は、収益性が下がるのは避けられません。売却準備を始める、新規物件の購入で新たな減価償却を取る、などの対策が必要です。
デッドクロスに関係する記事は以下も参照ください。
【事例付】アパート売却の流れと売却時期の見極め方!相続時の注意点も解説
【事例付】一棟アパート売却の成功術!売却時期と諸経費・税金を解説
まとめ 不動産投資は節税を含めた総合的な判断を

節税効果があるのは、不動産投資の大きなメリットです。しかし、どのような物件を選ぶか、どの程度の期間保有するかといった判断が、最終的な税負担や手残りに大きく影響します。そのため、節税だけに目を向けるのではなく、収益性や出口戦略まで含めて総合的に判断することが大切です。その手助けになるのが、賃貸経営の運営内容や税務面を把握している、信頼できる賃貸管理会社です。
【リロの不動産・リロの賃貸】では日常的な建物の維持管理や客付け、入居者様への対応に至るまで、収益物件の賃貸管理業務をトータルでサポートしています。加えて、税金対策の相談も経験豊富で専門家と一緒にサポートいたします。節税の効果を得ながらの不動産投資を検討している方は、ぜひ【リロの不動産】にご相談ください。
関連する記事はこちら
【保存版】不動産投資で節税する仕組み!節税が向いている方を徹底解説
アパート経営の節税戦略!減価償却・法人化・相続税対策の全てを解説
不動産投資に税理士への依頼は必要? 費用や不動産に強い税理士の見つけ方
おすすめのサービス
おすすめのお役立ち情報
この記事を書いた人
秋山領祐(編集長)
秋山領祐(編集長)
【生年月日】昭和55年10月28日。
【出身地】長野県上田市。
【趣味】子供を見守ること。料理。キャンプ。神社仏閣。
【担当・経験】
デジタルマーケティングとリブランディングを担当。
分譲地開発のPMや家業の土地活用などの経験を持つ。
リノベした自宅の縁の下に子ども達の夢が描かれている。





















