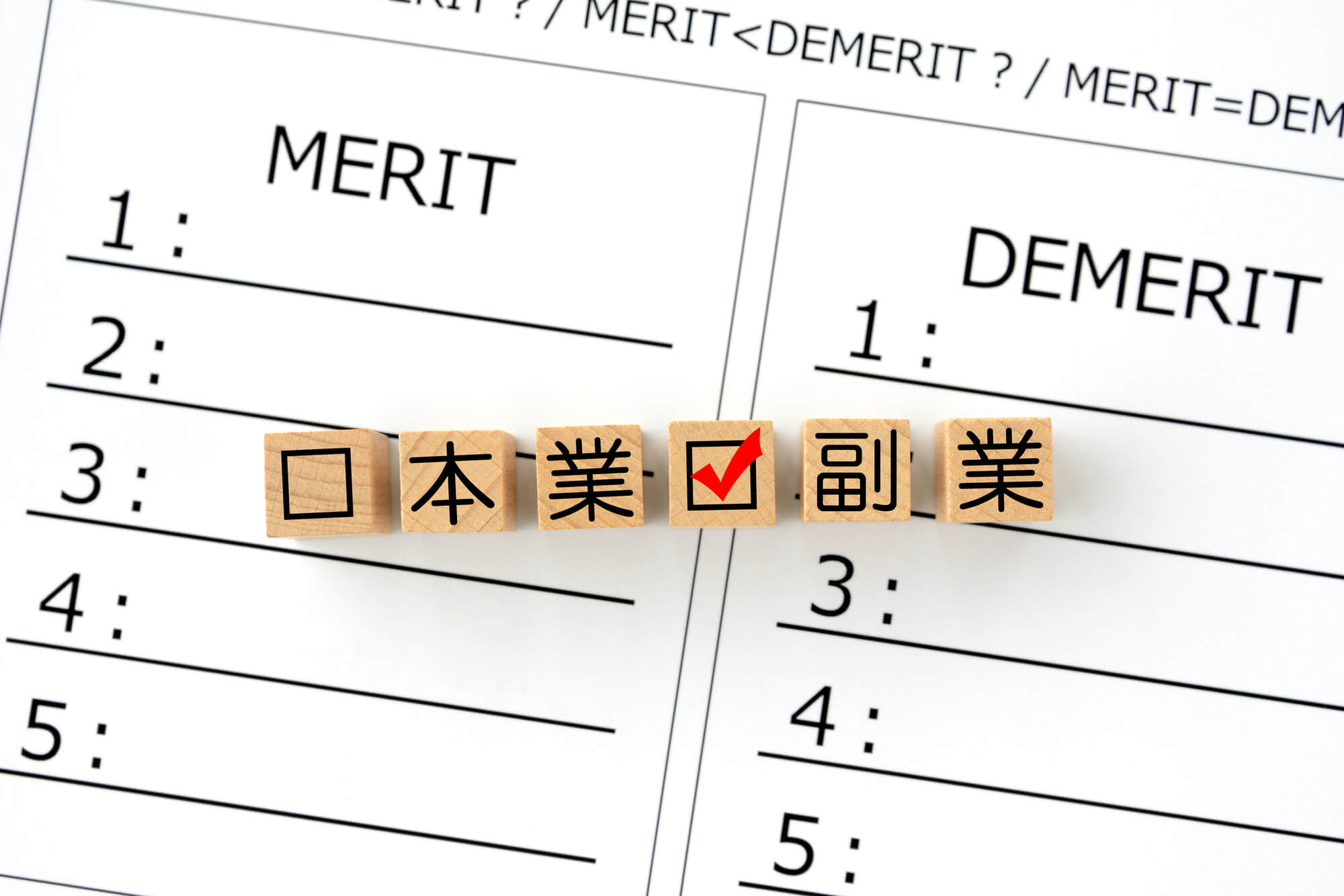転勤・海外赴任で自宅はどうする?期間限定の賃貸と売却、空き家を徹底解説!
2025.08.19
この記事では、転勤予定のある方に向けて、自宅である戸建や区分マンションを賃貸に出す際のメリットや手順、注意点を解説しています。売却か賃貸か、空き家か居住の判断は、将来の居住予定やライフプランに応じて決めるべきです。
転勤や海外赴任で一時的な賃貸を選ぶ場合は、転勤などで一定期間自宅を不在にする際に、その家を賃貸に出し、管理してもらうリロケーションサービスを活用することで安心して運用でき、帰任後もスムーズに再入居が可能です。
目次
転勤が決まったら──「賃貸・売却・空き家」3つの選択肢から考える自宅の扱い方

転勤が決まった際、多くの方が悩まれるのが「自宅をどうするか」という問題です。単身赴任であれば、家族がそのまま居住する選択もありますが、家族帯同で転居する場合、持ち家が空き家になるケースも少なくありません。
このとき、自宅については大きく以下の選択肢から検討することになります。
・賃貸に出して収益化する
・売却して資産を現金化する
・空き家管理を行う
どの選択肢にもメリット・デメリットがあり、ライフプランや転勤期間、資産状況などによって最適な判断は異なります。ここでは、「家族・住宅ローン・税務・維持管理コスト」の観点から、転勤時に検討すべき自宅に関する主なポイントを整理します。
家族や生活環境への影響
家族帯同での転勤か、単身赴任かによって自宅の取り扱いは異なります。家族がそのまま住み続ける場合は、日常の暮らしに大きな変化はありません。一方で家族全員が引っ越す場合、子どもの学校・生活環境の変化や地域コミュニティとの関係整理も必要になります。単なる物件の問題ではなく、家族全体のライフスタイルと将来設計も踏まえた選択が求められます。
自宅をどうするか(賃貸・売却・空き家)
▼選択肢の概要
・賃貸に出す(転勤貸し/定期借家契約など)
・売却する(転居先に応じた資産の組み替え)
・空き家として保有(将来的に戻る予定がある場合)
▼検討すべき注意点
・賃貸の場合、契約形態の選定(定期借家/普通借家)が重要
・売却を選ぶ場合は、税制優遇(居住用財産の3,000万円控除)の条件を確認する必要があります
・空き家の場合、防犯や維持管理、固定資産税の負担が継続
転勤や海外赴任の際、自宅をどう活用するかや、確定申告に関するポイントを詳しく知りたい方は、リログループの「リロの留守宅管理」が掲載するコラムをご覧ください。転勤期間中の留守宅賃貸を専門に扱うリロケーションサービスの専門家による情報を参考にしていただけます。
▼リロの留守宅管理 リロケーション基礎知識
海外赴任中の持ち家はどうする?売る・貸す・空き家のメリット・デメリットを解説
住宅ローンの取り扱い
現在住宅ローンの返済中であれば、特に注意が必要です。多くの住宅ローンは「自己居住用」が前提となっており、無断で賃貸に出すと契約違反になる可能性があります。金融機関によっては、「用途変更届」の提出が必要となるケースもあります。ローン残債がある状態での売却・賃貸には、事前に金融機関との確認が必須となります。
税務上の注意点と確定申告

転勤に伴い、賃貸または売却を行う場合、税務手続きにも注意が必要です。賃貸収入が発生する場合は、確定申告が必要になります。売却の場合は、譲渡所得に対して課税されますが、一定の条件を満たせば3,000万円の特別控除を利用できます。長期不在でも「空き家対策特例」や「住宅用地の軽減措置」などが対象外となることもあるため、税理士など専門家への相談を推奨します。
自宅の維持・管理コスト
長期間空き家にする場合には、以下のような管理上の課題が発生します。
・定期的な換気・通水・清掃・点検が必要
・火災保険・地震保険の契約内容の見直し(住居用→空き家用)
・郵便物の管理や草木の手入れ、防犯対策にも配慮が求められます。
適切な管理を怠ると、建物劣化や近隣トラブルにつながる恐れがあるため、空き家管理サービスの活用も選択肢のひとつに加えても良いでしょう。
■将来の生活設計と環境や状況の変化を検討する
転勤が一時的なものか、長期になるかによって、自宅の扱い方が変わります。
・転勤後に今後も自宅に戻る見込みが薄い場合は、「売却」による資産の組み替えが合理的です。
・お子さんの転校を避ける場合は、「単身赴任」の選択となります。
・自宅に戻る可能性があるなら「定期借家契約での賃貸」の選択肢が有力でしょう。
不動産市況や周辺の相場状況も加味し、中長期的な資産戦略としての出口設計をしておくことが重要です。
転勤を機に、自宅とライフプランを見直してみてください。転勤は生活の転機であると同時に、資産運用の見直しの好機でもあります。「今の自宅をどうすべきか?」を感情や惰性で決めるのではなく、将来を見据えた合理的な判断が求められます。自宅を貸すべきか、売るべきか、それともそのまま維持するべきか。次は売却について詳しく解説します。
転勤中に自宅の戸建や区分マンションを売却するメリットとデメリット

転勤をきっかけに、自宅マンションを売却するかどうかを判断するには、「資産としての価値」と「今後の使い道」の両面から冷静に整理することが大切です。ここでは、売却を選ぶ際の主なメリットとデメリットを分かりやすくご説明します。
■ 売却のメリット
1.売却益が得られる可能性がある
不動産市場や物件の条件によっては、購入時より高く売れるケースもあります。売却額から取得額を引いた差額(売却益)は、手元の現金資産として次の住まいや投資に充てることも可能です。
2.維持費の負担がなくなる
不動産を所有していると、転勤中で住んでいなくても「固定資産税」や「管理費」「修繕積立金」などのランニングコストがかかります。活用予定のない住まいであれば、売却によってこうした費用負担をなくすのは合理的です。
3.資産価値が下がる前に現金化できる
今後の市場動向(人口減少・地域の地価下落など)に不安がある場合は、早めに売却して資産を現金化しておくことで、リスク回避につながります。現金で保有すれば、別の価値ある資産へ柔軟に振り分けることも可能です。
■ 売却のデメリット
1.売却価格が購入時より下がるリスクがある
築年数や市場状況によっては、購入価格を下回る金額でしか売れないこともあります。その場合、売却によって損失が出る可能性があるため注意が必要です。
2.将来的な活用の機会を失う
一度売却してしまうと、その物件を将来「再び住む」「家族に住ませる」「タイミングを見て売却する」「賃貸で運用する」など、不動産としての自由な活用の選択肢はすべて失われます。これが売却における最大のデメリットといえるでしょう。
3.売却活動に時間や労力がかかることも
仲介で売却する場合は、買主が見つかるまでに時間がかかることもあり、転勤準備で忙しい時期に販売活動を並行するのは負担となる可能性があります。一方、買取業者に直接売却する方法もありますが、その場合は相場より低い金額になる傾向があるため注意が必要です。
▼売却は「今後の予定」と「不動産の活用価値」で判断を
転勤中に住まいを使う予定がなく、将来もその物件に戻る可能性が低いなら、「維持費をなくして現金化する」という目的で売却を選ぶのは合理的です。ただし、物件としての将来性や家族構成の変化、転勤後の生活スタイルも踏まえた上で、短期的な判断だけでなく中長期の視点も持つことが重要です。
転勤・海外赴任の際に自宅の戸建や区分マンションで賃貸経営するメリットとデメリット

転勤によって一時的に自宅を離れることになった場合、持ち家をどう活用するかは大きな課題です。特に、将来的に戻る予定がある場合や売却には踏み切れない場合、自宅を「貸す=賃貸経営をする」という選択肢が有力になります。
ここでは、転勤中に自宅(戸建て・区分マンション)を賃貸に出す場合のメリットとデメリットについて整理します。
■ 賃貸経営のメリット
- 家賃収入による収益化
自宅を空き家のまま保有しておくと、固定資産税や管理費といったランニングコストがかかる一方で、収益は生まれません。一方、賃貸に出せば毎月の家賃収入によって、そうした維持費用を相殺できるだけでなく、収益として手元資金を増やすことも可能になります。
- 売却せずに資産を活かせる
将来的に再び住む予定がある方にとって、売却は資産を手放すことになります。その点、賃貸に出せば、将来的に戻って再居住する可能性を残しながら、不在中は有効活用することができます。また、住宅は人が済まないと傷むものですが居住者がいる事で住宅の老朽化を低減することが期待できます。
- 犯罪被害の防止になる
賃貸に出すことは、犯罪リスクを減らすことにつながります。空き家のままにしておくと人の出入りがないため、不法侵入やゴミの不法投棄など犯罪のターゲットにされるリスクが高まります。たとえ一時的であっても近隣の迷惑になってしまい近隣トラブルまで発展してしまうかもしれません。
空き家ではなく賃貸に出していれば、犯罪リスクを大幅に減らすことができるでしょう。また入居者がいること自体、近隣の方とのコミュニケーションが自然に生まれるため、不審者が近寄りづらくなる効果があります。
賃貸に出すことで空き家にしないことは、犯罪被害防止の観点からも大きなメリットになるでしょう。
■ 賃貸経営のデメリット
- 入居者が見つからないリスク
エリアや物件の条件によっては、空室が続いて家賃収入が得られない可能性もあります。特に転勤直前に急いで募集を始めると、賃料設定や物件の魅力を十分に伝わらず、成約につながりにくいことがあります。逆に、適正賃料で入居が見込めたのを必要以上に安い賃料で募集してしまうケースにも注意が必要です。
- 原状回復や修繕対応の必要
入居者がいる以上、使用による劣化や破損は避けられません。退去時には原状回復やリフォーム費用が発生することもあり、賃貸経営を行う際の支出が利益を圧迫するケースもあります。
- 契約・管理の手間
入居者募集・契約・クレーム対応・家賃の管理など、不動産管理には一定の手間やコストが伴います。信頼できる管理会社と契約することで負担は軽減できますが、委託料なども必要になります。
- 自宅が自由に使えなくなる
賃貸中のご自宅には、当然ながら自分で住むことができません。仮に転勤が予定より早く終了して戻りたくなっても、契約期間中は入居者が優先されます。特に「普通借家契約」の場合は、正当な理由がなければ契約を解除できない点に注意が必要です。
■ 賃貸に出す前に検討したいこと
・契約形態の選定(定期借家契約か、普通借家契約か)
・賃料相場と収支のシミュレーション
・住宅ローンの契約内容(賃貸禁止条項の有無)
・管理会社の選定と委託内容の確認
・税務上の手続き(家賃収入の確定申告、減価償却など)
転勤や海外赴任でご自宅を貸す場合は、上記に注意してください。
次に、気を付けておきたいポイントを解説します。
転勤中にマンションを賃貸に出すメリット1 室内劣化の防止と防犯対策になる

転勤などで長期間不在となる自宅マンションを賃貸に出す最大のメリットの一つは、「室内の劣化防止」と「防犯対策」に繋がることです。
■室内の劣化防止
空き家の状態が続くと、住まいとしての機能が徐々に損なわれていきます。まず、日常的な換気や掃除が行われないことで、湿気がこもりやすくなり、カビやダニが繁殖しやすい環境になります。特にマンションのような気密性の高い構造では湿気が逃げにくく、内装材や壁紙、木部などの劣化を早める原因となります。また、水道が長期間使われないことで、排水管の封水(トラップ)が蒸発し、下水臭が室内に立ち込めたり、害虫が侵入しやすくなったりすることもあります。
さらに、住宅は「人が住むこと」を前提に設計・建築されているため、空き家として放置されると、換気不足による結露や設備の不具合、建具の歪みなどが生じやすく、想定以上に傷んでしまう可能性があります。
その点、賃貸に出せば、入居者が日常的に窓を開けて空気を入れ替えたり、掃除をしたり、設備を使用したりすることで、建物や室内設備の状態を良好に保つことができます。適度な使用と手入れがされることで、住まいの寿命を延ばし、将来ご自身が再び戻って住む際にも、大規模な修繕を必要とせずに済むケースが多いです。
■防犯対策
加えて、防犯面でも大きな安心があります。空き家は空き巣や不法侵入の標的になりやすく、特に郵便物の溜まり具合や夜間の明かりがないことなどから「無人」と判断され、犯罪に利用されるリスクが高まります。中には、詐欺グループの拠点として不正利用されるケースも報告されています。
一方で入居者がいれば、日常的な生活の気配が外部に伝わるため、防犯性が格段に向上します。不在時でも「誰かが住んでいる家」としての機能が保たれるため、空き家特有のリスクを大幅に軽減することが可能です。このように、賃貸に出すことで、単なる収益確保にとどまらず、大切な資産である自宅を守る手段にもなるのです。
転勤中にマンションを賃貸に出すメリット2 賃料収入が得られ、経済的負担を軽減できる

転勤中や海外赴任中に自宅マンションを賃貸に出すもう一つの大きなメリットは、「家賃収入が得られることによって、経済的負担を軽減できる」という点です。
多くの方は住宅ローンを組んでマンションを購入していますが、転勤が決まったからといってローンの返済が止まるわけではありません。たとえ一時的に自宅に住まなくなったとしても、これまで通りの返済が毎月発生します。さらに、マンションであれば共用部の維持管理費や修繕積立金も、所有者として継続して支払う必要があります。加えて、毎年発生する固定資産税も無視できないコストです。
そして転勤先では、会社の社宅制度や住宅手当があったとしても、多くの場合、何らかの形で新たな住居にかかる費用が発生します。つまり、「使っていない自宅」の維持費と、「転勤先の新居」の住居費が同時に発生する二重生活の状態となり、家計にとっては大きな負担が発生します。
こうした状況で自宅を賃貸に出し、第三者に貸し出すことができれば、入居者から毎月支払われる賃料が安定的な収入となります。この賃料を、住宅ローンの返済や固定費(管理費・修繕積立金・固定資産税など)に充てることで、経済的な負担を大幅に抑えることが可能になります。
賃料の方が上回っていれば、実質的な利益が生まれるケースもあります。たとえば、住宅ローンの月々の返済額が12万円で、毎月の賃料が15万円であれば、ローンだけでなく管理費や固定資産税分までまかなえる可能性があります。また、単に支出を抑えるだけでなく、「転勤期間中も資産である自宅を有効活用している」という安心感や満足感も得られます。空き家にして無駄なコストをかけるよりも、第三者に利用してもらうことで、家そのものが「収益を生む資産」として機能するようになるのです。
このように、賃料収入は転勤中の経済的負担を軽減するだけでなく、自宅という資産の価値を最大限に活かす手段にもなり得るのです。
転勤中にマンションを賃貸に出すメリット3 転勤が終わったあと、再び自宅に住める安心感がある

転勤中に自宅マンションを売却せず、賃貸として貸し出す最大の魅力の一つは、「将来的に再び自分の家に住める」という点です。
転勤を機にマンションを手放してしまった場合、仮に数年後に元の勤務地へ戻ることになっても、もはやその住まいは他人の所有物です。戻ったときには、新たな物件を探す手間や費用が発生するだけでなく、以前の暮らしの環境を再現できないことも少なくありません。子どもの通学区域、近隣との人間関係、駅までのアクセスや生活導線など、「住み慣れた場所に戻れないこと」は精神的にも負担となり得ます。
一方、所有権を維持したまま自宅を賃貸に出しておけば、転勤が終わった際には、入居者の退去後に再び自宅に住むことができます。これは、売却とは異なり、「一時的に他人に貸しているだけ」という状態だからこそ可能となる選択肢です。
特に将来的にまた自宅に戻ることを前提にしている場合は、「定期賃貸借契約」を利用することが重要です。これは、あらかじめ定めた契約期間が満了すれば、借主が退去しなければならないという契約形態で、貸主が戻る予定時期を明確にできるメリットがあります。たとえば「3年間の転勤予定がある」場合には、その期間に合わせて3年の定期賃貸借契約を結んでおけば、安心して自宅に戻れる仕組みがつくれます。
一方で、従来一般的な「普通賃貸借契約」では、借主に継続居住の権利があるため、貸主の都合で退去を求めることは原則できません。つまり、「戻ろうと思ったが借主が居座っていて戻れない」といった事態に陥るリスクがあるのです。
転勤期間が不確定な場合には、4年や5年といった余裕をもった期間で定期契約を結ぶことも有効です。仮に予定より早く帰任となった場合でも、契約期間満了までは別の住まいで暮らし、借主の退去後にスムーズに自宅へ戻ることができます。実家や社宅、一時的な賃貸住宅など、暫定的な住まいをうまく活用することで、自宅への再居住を現実的に計画することが可能です。
ただし、定期賃貸借契約にはいくつか注意点もあります。借主側にとっては「契約期間終了で必ず退去しなければならない」という制約があるため、一般の賃貸よりも敬遠されやすく、市場相場よりもやや低めの賃料設定が求められることがあります。また、契約期間を満了せずに早期退去されるケースもあり、その場合は新たな借主を募集する手間や空室期間による収入減少のリスクも考慮する必要があります。
このように、転勤後に自宅に戻れるという「将来の選択肢」を維持できることは、精神的にも大きな安心材料になります。売却と比較して流動性に制限はありますが、「一時的に貸して、また住む」ための手段として、信頼できるパートナーに依頼できるならば、転勤及び海外赴任中の賃貸活用は非常に合理的な選択肢の一つと言えるでしょう。
転勤時にマンションの賃貸借契約を行う手順

転勤が決まり、一定期間自宅を離れることになった際、所有している戸建や区分マンションをそのまま空き家にしておくのではなく、第三者に賃貸して有効活用するという選択をした際に慌てないように、自宅を賃貸に出すための流れを確認しましょう。
ここでは、自宅マンションを賃貸に出す際の基本的な流れを5つのステップに分けて、具体的に解説します。
依頼する不動産会社を決める
信頼できる不動産会社の選定が、賃貸成功の第一歩になります。転勤中に自宅マンションを賃貸に出す際、最初に取り組むべき重要なステップが「どの不動産会社に依頼するか」を決めることです。この選択が、入居者募集のスムーズさや賃貸中のトラブル対応、そして全体の収支や安心感にまで大きく影響します。
■ 不動産会社の業務は「仲介」と「管理」に大別される
賃貸運用における不動産会社の業務は、大きく分けて次の2つに分類されます。
1.仲介業務(入居者の募集・契約対応)
物件の賃貸情報をインターネットや店舗を通じて公開し、内見希望者の対応や物件案内を行い、契約成立までをサポートする役割です。入居者と貸主との間に立ち、契約書の作成や重要事項説明などの事務的な手続きを代行してくれます。
2.賃貸管理業務(貸出後の運営・入居者・物件の管理)
入居者との契約が成立し、物件を引き渡したあとの運用管理を担うのが賃貸管理業務です。代表的な内容は以下のとおりです。
・毎月の賃料・共益費の回収と送金
・借主からの問い合わせやクレーム(騒音、水漏れ、鍵の紛失など)への対応
・設備の故障対応や業者手配
・更新手続きや契約条件の調整
・退去時の立ち合い、原状回復の工事手配、敷金精算など
■ 転勤中は「仲介」と「管理」両方を依頼できる会社が安心
転勤中は遠方に住むことになるため、貸し出したマンションの管理や入居者対応をご自身で行うのは現実的ではありません。そのため、リロの不動産のように「仲介」と「賃貸管理」のどちらにも対応している不動産会社に一括して依頼することをおすすめします。
ワンストップで対応してくれる会社であれば、入居者募集から契約、賃貸中のトラブル対応、退去後の修繕・再募集まで、すべてのプロセスを一本化して任せられるため、貸主の手間が大幅に減り、想定外のトラブルにも迅速に対応してくれます。
また、転勤や海外赴任のサポートには、リログループの関連会社であるリロケーション・ジャパンが提供する「リロの留守宅管理」もおすすめです。1984年に転勤時の留守宅管理(リロケーション)を日本で初めて事業化し40年以上の実績があり、2025年3月末現在留守宅管理戸数が10,000戸超の国内最上位の実績を保有しています。
■ 不動産会社選びのチェックポイント
不動産会社を選ぶ際には、以下の点を事前に比較・確認しておくと安心です。
・その地域での賃貸実績・仲介力
・転勤など短期貸しや定期賃貸借契約への理解
・管理業務の対応範囲とサポート体制
・管理手数料(相場は賃料の3〜5%程度)や初期費用の明確さ
・入居者募集までのスピードと広告力
・トラブル発生時の対応体制(24時間対応の有無など)
また、実際に管理を任せる担当者との相性も非常に重要です。契約前に面談を行い、誠実さや説明のわかりやすさ、質問への対応力をしっかりと見極めましょう。
転勤中のマンション貸し出しは、「不在時でも大切な資産を守ってくれるパートナー選び」がカギになります。賃貸経営には、トラブル対応、空室リスク、法的知識など、専門的な対応が求められる場面も多いため、長期間の留守を安心して任せられる経験とノウハウが豊富な不動産会社を選ぶことが、安定した賃貸運用の第一歩にして最も重要なポイントになります。
▼関連コラム
リーシング・空室対策に強い賃貸管理会社とは?入居者募集力と仲介力から確認
賃貸管理会社の選定基準は手数料の安さか、収益性を高める管理か
【賃貸管理会社】大手と地域密着型のどっちがおすすめ?選び方とは
【トラブル事例】賃貸管理会社に求められる対応力とは? 起こりうるリスクも紹介
収支を確認する

家賃収入だけで安心しない。賃貸に伴う税金や経費も含めて「実際の手取り」を把握しましょう。転勤中にマイホームを賃貸に出せば、毎月一定の家賃収入が得られるため、一見すると「収入が増える」と感じるかもしれません。しかし、実際には家賃収入のすべてが自由に使えるわけではなく、経費や税金などが差し引かれたうえでの「手取り額」を正しく把握しておくことがとても重要です。
賃貸運用によって利益が出る場合、その金額は「不動産所得」として扱われ、給与所得などと合算されて課税対象になります。適切な収支管理を行わなければ、予想以上の税負担が発生し、結果的に赤字になってしまう可能性もあるため、事前に収支のシミュレーションを行うことで理想と現実のギャップが少なくなり数字でリスクを把握できます。
■ 家賃収入にかかる税金とは?
賃貸で得た家賃収入に対しては、以下の税金がかかります。
1.所得税
毎年の確定申告を通じて計算され、給与所得などと合算して課税されます。所得税は所得額に応じて5%〜45%の累進課税が適用されます。
2.復興特別所得税(2037年12月31日まで)
所得税に対して2.1%上乗せされる附加税です。
3.住民税
前年の所得に応じて、原則として10%が課税されます(自治体によって若干異なる場合あり)。
つまり、「賃貸で得た利益=収入-必要経費」に対して、これらの税金がかかることになります。
■ 経費として計上できる費用とは?
収入に対して課税されるのは「利益部分」であり、賃貸運営にかかった必要経費は差し引くことができます。代表的な経費には以下のようなものがあります。
・管理費、修繕積立金(マンションの場合)
・不動産会社への管理委託料、仲介手数料
・固定資産税、都市計画税
・火災保険、地震保険の保険料
・建物、設備の減価償却費
・ローン返済のうち利息部分(※元金返済分は経費になりません)
・修繕、クリーニング、設備交換費用 など
これらを適切に申告すれば、税負担を軽減することができます。ただし、経費として認められるかどうかは、支出の内容や証明書類の有無によって異なるため、領収書や契約書などは必ず保管しておきましょう。
■ 住宅ローン控除が使えなくなる点に注意
すでに住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けている場合は要注意です。この制度は、「本人が居住している住宅であること」が適用条件であるため、マイホームを賃貸に出した時点で、控除の適用対象外となります。
これにより、所得税からの控除額(通常は年末ローン残高の1%相当)がなくなるため、毎年の税負担が増えることになります。賃貸による収入と控除がなくなることで生じる負担を天秤にかけ、どちらが自分にとって有利かをシミュレーションしておくことが大切です。
■ 税金・経費・収入をトータルで把握しよう
転勤中の賃貸運用を検討する際は、以下のような視点で収支の見通しを立てるとよいでしょう。
・家賃収入(月額 × 契約期間)
・支出(管理費、固定資産税、修繕費など)
・所得税、住民税の増加見込み
・住宅ローン控除が外れる場合の影響
・空室リスクや修繕リスクの想定
こうした要素をあらかじめ整理しておくことで、「貸し出したのに思ったほど利益が残らない」「税金が増えて手取りが減った」といった後悔を防ぐことができます。
■賃貸収入は「手取りベース」で判断するのが正解
マイホームを賃貸に出すことで得られる家賃収入は魅力的ですが、それに伴う経費や税金、制度の変更点まで含めて総合的に判断することが必要です。
まずは、税理士や不動産会社に相談し、具体的な収支シミュレーションを作成してもらうことで、より現実的な判断ができるでしょう。大切な資産を無理なく運用するためにも、「収入」ではなく「実際に手元に残る金額」を軸に検討することをおすすめします。
▼関連コラム
賃貸管理会社の探し方と6つのポイント!賃貸経営の収支を握る管理とは
【必読】賃貸管理会社の選び方!運用益と出口戦略を見据える賃貸管理
【総集編】アパート経営の利回りの目安は?不動産投資の指標と注意点
金融機関や管理組合に報告する

転勤中に自宅マンションを他人に貸し出す場合には、賃貸に出す前に「金融機関」と「マンションの管理組合」へ報告・相談を行うことが非常に重要です。
どちらの手続きも怠ると、後々のトラブルや契約違反につながる恐れがあるため、早い段階での確認と準備が求められます。住宅ローンやマンションの管理規約に基づいた正式な手続きを行いましょう。
■ 金融機関への報告は「契約違反」を避けるために必須
住宅ローンを利用して購入したマンションの場合、多くのケースで「居住用住宅ローン(いわゆるマイホームローン)」が適用されています。これは「契約者本人およびその家族が実際に居住すること」を前提に、低金利で融資される制度です。そのため、転勤などで自宅を離れる際に「第三者に賃貸する」となると、ローンの契約条件に違反する可能性が出てきます。
特に、投資目的(収益目的)とみなされると、金融機関側から以下のような対応を求められることもあります。
・投資用ローンへの借り換え要請
・残債の一括返済要求(極めて稀ですが可能性あり)
・ペナルティ金利の適用 など
ただし、「転勤」というやむを得ない事情で一時的に貸し出す場合には、理解を示してもらえるケースも多く、契約条件の変更や金利の上昇を免れることもあります。重要なのは、事前に金融機関へ正直に相談し、正式な承諾を得ておくことが重要です。
報告の際には、転勤の辞令や転勤期間が記載された書類などを用意しておくと説明がスムーズです。また、口頭だけでなく、書面やメールなど記録が残る形でやり取りしておくと安心です。
■ 管理組合への届出で円滑な賃貸運用を
分譲マンションを賃貸に出す場合は、管理組合への届出も必要です。分譲マンションには管理規約があり、「区分所有者が所有住戸を賃貸に出す場合には、事前に管理組合に報告すること」が義務付けられているケースがほとんどです。
報告を怠ると、管理組合との信頼関係にヒビが入るだけでなく、入居者が管理会社や他の住民とトラブルを起こした際に、オーナーとしての連絡が届かず、対応が遅れるといった問題も生じかねません。
管理組合への届出の際には、次のような手続きを行うのが一般的です。
・入居者(借主)の氏名や連絡先の届け出
・賃貸開始日や契約期間の報告
・管理組合からの書類送付先の変更手続き(転勤先の住所へ)
・総会や重要決議への委任状提出方法の確認
特に、理事会や総会の案内、決議事項の通知、管理費の変更などはオーナーである限り関係のある内容です。そのため、通知書類が転勤先の住所にきちんと届くよう、郵送先の変更手続きも忘れずに行いましょう。
■ 金融機関と管理組合の手続きを正しく行うことが、安心・安全な賃貸運用の土台に
住宅ローンの融資条件を守り、マンション全体の管理体制に協力することは、貸主としての責任でもあり、トラブル回避の基本です。転勤というライフイベントにより一時的に賃貸運用を行う場合でも、こうしたルールを順守することで、自宅という資産を安全かつ有効に活用することができます。
どちらの手続きも、「やっておいて損はない」ものではなく、「やらなければならない」手続きです。万全の準備を整え、安心して転勤生活を送れるようにしておきましょう。
募集条件を決める

賃料設定から契約形態まで、自分に合った条件を整理しましょう。信頼できる不動産会社を選び、金融機関や管理組合への報告が済んだら、次は実際にマンションを「どのような条件で貸し出すか」を具体的に決めていくステップに入ります。募集条件の設定は、空室期間やトラブルの発生リスクを大きく左右する重要なポイントです。
ここでは、事前に決めておくべき主な要素を整理しながら、転勤時の賃貸に適した契約方法についても詳しく解説します。
① 募集条件(家賃・初期費用・入居条件など)を設定する
まずは入居者を募集する際に掲載する「募集条件」の設定から始めます。主な検討項目は以下のとおりです。
・月額賃料(家賃)
周辺相場や物件の築年数、立地、設備(オートロック・宅配ボックス・浴室乾燥機など)を加味して設定します。不動産会社の意見も参考にし、相場と乖離しすぎない価格が早期成約につながります。
・敷金、礼金の有無と金額
敷金は退去時の原状回復費用の担保、礼金はオーナーへの謝礼金です。最近では「礼金なし」で募集する物件も多く、競争力を高めるために柔軟な設定が求められます。
・共益費、管理費
マンション全体の共用部分の維持費として徴収される費用。毎月の家賃と併せて負担感を考慮します。
・ペット可否、喫煙可否
ペット飼育や室内喫煙を許可するかは、トラブルや汚損のリスクと表裏一体です。「小型犬1匹まで可」「バルコニー喫煙可」など、具体的に条件を設定しておくと良いでしょう。
・家具、家電付きか否か
既存の家具・家電をそのまま使用してもらう「家具付き賃貸」は、短期転勤の貸し出しに向いていますが、故障・破損時の責任や維持管理の手間も発生するため要検討です。
これらの条件は、借主の属性や生活スタイルにも大きく影響を与えるため、「どのような入居者に住んでほしいか」という視点からも考えることが大切です。
② 契約の種類と期間を決める

次に重要なのが「契約形態」と「契約期間」の設定です。賃貸借契約には大きく分けて次の2種類があります。
・普通賃貸借契約(普通借家契約)
一般的な賃貸契約で、契約期間は通常「2年」など比較的長めに設定されます。契約期間満了時は、借主側が希望すれば自動更新されるのが原則です。
貸主の都合による契約終了は原則不可で、「正当な理由」がない限り更新拒否はできません。この契約形態では、転勤終了後に自宅に戻りたくても、借主が居住を希望し続ける限り、オーナー側からの立ち退き要請ができないという大きなリスクがあります。
・定期賃貸借契約(定期借家契約)
契約時にあらかじめ終了日が決められており、その日をもって契約が終了する契約形態です。契約期間が終了すれば、借主は退去しなければならず、更新は借主にとって当然の権利とはなりません。終了の1年〜6か月前(契約内容による)には、貸主側から「期間満了による契約終了」の通知を出す必要があります。
転勤などで「○年後に戻る予定がある」場合には、この定期賃貸借契約を選ぶことで、確実に自宅へ再居住できる計画を立てやすくなります。不動産会社にもその意図を伝え、定期契約の取り扱い実績があるか確認しておきましょう。
■ 募集条件は「収益性」と「再居住の予定」を両立できる内容に
募集条件の設定は、単に「高く貸せる条件」を目指すのではなく、収益性とリスク、将来の住まいのバランスを見極めることが大切です。たとえば、家賃を高く設定しすぎると入居者が決まらず空室期間が長引いたり、トラブルを避けるために条件を厳しくしすぎると対象となる入居希望者が減ってしまったりすることもあります。
また、転勤期間が不確定な場合は「4~5年の定期契約+更新なし」とし、早期帰任の際には一時的に別の住まいを利用するなど、柔軟な運用も検討しましょう。
最適な募集条件は、オーナーのライフスタイルや物件の特性、地域の需要によって異なります。不動産会社とよく相談しながら、後悔のない契約内容を組み立てていきましょう。
▼関連コラム
入居者募集のコツとは?契約形態別のメリット・デメリットを解説!
空室を埋めるには適切な原因の特定と対策を! 改善事例で学ぶ賃貸経営の鍵
▼改善事例
競合物件が多いなら募集条件と掲載方法で一歩抜け出す入居者募集を!
入居者を探す(リーシング活動)

適切なリーシング活動が、早期成約と安定収益の鍵になります。募集条件が整ったら、いよいよ「入居者を探す=リーシング活動」のスタートです。
空室期間を最小限に抑え、信頼できる入居者と良好な賃貸関係を築くためには、計画的かつ効果的な募集活動が不可欠です。ここでは、入居者募集の流れとポイントについて詳しく解説します。
■ 不動産会社が行うリーシング活動とは?
入居者募集を不動産会社に依頼すると、オーナーに代わって以下のような一連の募集活動(リーシング)を代行してくれます。
・インターネット掲載(SUUMO、HOME’S、アットホーム等)
写真・間取り図・物件紹介文を用いた物件ページを作成し、広く募集します。
・店舗での接客・紹介
不動産会社の来店者や問い合わせ客に物件を提案し、見学の案内を行います。
・他業者との連携
自社での募集だけでなく、他の仲介業者とも情報を共有し、より広いネットワークで募集を展開します(いわゆる「客付け」)。
・物件写真・室内清掃・ホームステージングの提案
より魅力的に見せるために、室内清掃や家具・小物の設置を提案するケースもあります。
▼改善事例
競合物件が多いなら募集条件と掲載方法で一歩抜け出す入居者募集を!
■ 内見対応のポイントとオーナーの関わり方
入居希望者が現れた場合、多くは「内見(内覧)」を希望されます。これは実際に室内の雰囲気を確認し、住むかどうかの最終判断をするための重要なプロセスです。
転勤前で自宅にまだ居住している場合や、家具・家電が残っている状態の場合には、内見時の印象がそのまま成約率に直結することもあります。
このときの注意点として、以下のことを確認しておきましょう。
オーナーの立ち会いが必要かどうか
賃貸中の物件では不動産会社の担当者のみで内見を行うことが多いですが、自宅にまだ居住中である場合は、事前に日時調整や立ち会いの有無について不動産会社と相談しておく必要があります。
事前の片付け・掃除
内見者に好印象を与えるためには、室内を清潔に整え、生活感をできるだけ抑えることが効果的です。特に水回りや照明、カーテンの開閉など細かい部分が見られます。
必要に応じて退去・空室化してから募集することも検討
家具や私物が多く内見時の印象が悪い場合、退去後に空室として見せた方が成約率が上がることもあります。ホームステージング(家具や雑貨の演出)を取り入れると、さらに効果的です。
■ 良い入居者を見つけるための鍵は「魅せ方」と「スピード」
リーシングでは「物件をどれだけ魅力的に見せられるか」と「募集をどれだけ早く始められるか」が成否を分けるポイントです。特に都市部では空室の動きが早く、周辺に類似物件も多いため、写真の質や紹介文の工夫、募集タイミングの早さが差別化につながります。
また、不動産会社に物件の強み(角部屋、南向き、通勤アクセス、小学校区など)をしっかり伝えておくことで、より適したターゲット層への訴求が可能になります。
入居者を探すことは、単なる作業ではなく「資産を活かすための営業活動」です。不動産会社との連携を密にし、的確な戦略でスピーディに進めることが、転勤中の安定した賃貸運用につながります。
▼関連記事
空室の原因を解決する『4つの空室対策』とは?14種類の手法を徹底解説!
満室経営を4つの空室対策で実現!入居者満足度を高める賃貸管理とは
リーシング・空室対策に強い賃貸管理会社とは?入居者募集力と仲介力から確認
賃貸借契約を結ぶ

契約内容を十分に理解し、トラブルのない賃貸運用を始めよう
金融機関やマンションの管理組合への報告が完了し、募集条件に合う入居希望者が見つかったら、いよいよ賃貸借契約の締結です。
このステップは、貸主(オーナー)と借主(入居者)との法的な関係を正式に取り決める重要なプロセスであり、契約内容をしっかり理解したうえで慎重に進める必要があります。
■ 賃貸借契約とは?
賃貸借契約とは、貸主が物件を貸し、借主がその対価として家賃を支払うことを取り決めた法的な契約です。口頭の約束ではなく、契約書を作成して両者が署名・押印することで、明確なルールが成立します。
契約書には主に以下のような事項が記載されます
・賃貸物件の所在地・面積・設備の明細
・賃料・共益費・敷金・礼金の金額と支払い方法
・契約期間(開始日・終了日)と更新・再契約の条件
・契約の種類(普通賃貸借契約 or 定期賃貸借契約)
・禁止事項(ペット飼育・喫煙・楽器演奏など)
・原状回復のルール
・中途解約の条件や違約金に関する取り決め
・連帯保証人や保証会社の情報
これらの内容は、契約期間中のルールだけでなく、退去時のトラブルを防ぐためにも非常に重要なものです。
■ 契約前に必ず確認すべきポイント
契約書にサインする前に、以下の点を念入りに確認しましょう。
契約の種類と期間
転勤期間が決まっている場合は、再入居を見据えて定期賃貸借契約(定期借家契約)を選ぶのが一般的です。期間満了後に確実に契約が終了し、借主が退去することが明記されているかを確認してください。
賃料や敷金・礼金の条件
初期費用や毎月の支払い内容に抜けや誤りがないか、項目ごとにチェックしましょう。
原状回復のルール
退去時にどこまで修繕費を負担するかは、トラブルが起きやすい部分です。「通常損耗(経年劣化)」と「借主の過失による汚損」の区別が明記されているかを確認しましょう。
連帯保証人・保証会社の利用
万が一、入居者が家賃を滞納した場合に備え、家賃保証会社の加入や連帯保証人の明記があるかも要確認です。
禁止事項と特約
ペットやタバコ、DIYの可否、借主の転貸禁止など、暮らしに関する細かいルールは「特約事項」に記載されることが多いため、見落とさないよう注意が必要です。
■ 不明点は必ずその場で確認を
契約書に押印する前に、「少しでも不明な点」や「納得できない内容」があれば、その場で不動産会社の担当者に確認しましょう。特に初めて賃貸運用を行う方にとっては、専門用語や法的な制約が多く、戸惑う部分も少なくありません。
また、できる限り書面やメールでやり取りの記録を残しておくことで、万が一後からトラブルが発生した場合にも安心です。
■ 契約後の対応もスムーズに進めよう
契約書に署名・押印が完了したら、鍵の引き渡しや設備の最終点検、入居者からの問い合わせ対応などが発生します。これらのやり取りや入金確認などは、通常、不動産会社が代行してくれますが、オーナーとしての最終責任は自分にあることも忘れてはいけません。
賃貸借契約は「信頼関係を築くための出発点」です。しっかりと内容を把握し、納得のうえで契約を締結することで、転勤中の不在時も安心して賃貸経営を任せることができます。
▼関連記事
入居者募集のコツとは?契約形態別のメリット・デメリットを解説!
転貸借とは

転貸借(てんたいしゃく)とは、ある物件を借りている人(賃借人)が、その物件をさらに第三者に貸し出すことを指します。一般的には「又貸し(またがし)」という言葉のほうが馴染みがあるかもしれません。
例えば、あなたが賃貸マンションに住んでいて、その部屋を別の人に貸す――つまり、あなたは「転貸人」、新たに借りたその人は「転借人」となります。このように、賃借人が自ら借りた物件を、さらに他者に使用させる行為が転貸借です。
■ 転勤時の転貸借の活用例
たとえば、会社の社宅や借り上げ住宅、あるいは親や知人から借りている住宅に住んでいる人が、転勤などで一時的にその住まいを離れることになったとします。このとき、自分が契約上の借主であるにもかかわらず、その家をさらに別の人に貸す場合には、「転貸借契約」を結ぶ必要があります。
つまり、自分が所有者ではなく、借りている立場でも、正式に承諾を得ていれば、転貸によって物件を運用することが可能になるというわけです。
■ 無断転貸借は法律違反になることも
ただし、注意すべきは「無断で転貸借を行うことは原則として禁止されている」という点です。
民法第612条では以下のように定められています
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その物の使用及び収益を第三者にさせることができない。
(中略)
賃借人がこの規定に違反したときは、賃貸人は契約を解除することができる。
つまり、オーナーや管理会社の正式な承諾を得ないまま転貸した場合には、契約違反とみなされ、元の賃貸借契約そのものを解除される可能性があるということです。
無断転貸は「モラル上の問題」ではなく、契約法上の重大な違反行為として扱われるため、たとえ善意であっても慎重な判断が求められます。
■ 転貸借は「承諾」があれば可能
裏を返せば、賃貸人(オーナー)の明確な承諾があれば、合法的に転貸借を結ぶことは可能です。
実務上では、以下のようなケースで承諾付きの転貸借が行われています
・法人契約の社宅を社員が転勤中に別の社員へ貸す
・不動産オーナーがサブリース会社と契約し、サブリース会社が第三者へ転貸する
・借り上げ社宅として企業が借りた物件を従業員に貸す
いずれの場合も、オーナーが文書や契約書により明確に転貸を認めていることが前提条件となっています。あいまいな口頭の承諾だけでは、後のトラブルにつながる恐れがあるため、必ず書面での同意取得が必要です。
■ 転貸借を検討する際の注意点
転貸借を行う際には、次のような点にも注意が必要です。
原賃貸借契約(元の契約)の条件に反しないこと
例:契約で転貸禁止と明記されていれば、原則不可能です。
転貸借契約の内容を明文化すること
家賃、契約期間、退去時の原状回復、禁止事項などを明記した転貸契約書を必ず作成しましょう。
入居者トラブルや損害発生時の責任は、転貸人(=あなた)が負う
オーナーにとって契約相手はあくまで「元の借主(転貸人)」であるため、新しい入居者によるトラブルも、元の借主が責任を負う構造になっています。
転貸借は一見複雑に感じるかもしれませんが、正しい知識と手続きを踏めば、転勤時の住宅活用の一つの有効な手段となります。まずは元の契約内容をよく確認し、オーナーや管理会社としっかりと相談のうえ、必要な手続きを進めるようにしましょう。
転貸借のメリットは?

リスクと手間を大幅に軽減できる「安心のしくみ」が転貸借のメリットです。マンションや戸建てを転勤中に賃貸に出す場合、その方法として「代理委託方式」と「転貸借方式」の2つがあります。その中でも、転貸借方式には、オーナーにとって大きなメリットが複数あるのが特徴です。
以下では、一般的な代理委託方式と比較しながら、転貸借の主なメリットをわかりやすく解説します。
■ 代理委託方式と転貸借方式の比較:オーナーが「当事者」になるかどうか
まず「代理委託方式」とは、オーナーが不動産管理会社に賃貸の仲介や管理を委託する形態で、入居者と直接契約を結ぶ方式です。この場合、万が一トラブルが発生したときは、契約当事者であるオーナー自身が対応の責任を負うことになります。
たとえば以下のようなケースです
・入居者が家賃を滞納した
・設備トラブルを巡って入居者と揉めた
・退去時に敷金精算でトラブルになった
・入居者から訴訟を起こされた(敷金返還請求など)
これらの問題が起きた際、不動産会社はあくまで「管理の代行者」に過ぎず、法的な当事者ではないため、最終的な責任はオーナーが引き受ける必要があります。トラブルの対応や裁判手続きなどは、想像以上に手間とストレスを伴います。
■ 転貸借方式なら「契約当事者」は不動産管理会社
一方、転貸借方式では、オーナーが不動産会社に物件を貸し、不動産会社がさらに第三者(入居者)に貸すという二段構えの契約構造になります。つまり
・オーナー ⇔ 不動産会社(第1の契約)
・不動産会社 ⇔ 入居者(第2の契約)
となるため、入居者と直接契約を結ぶのは不動産会社(たとえばリロケーション会社)であり、オーナーは法的な当事者から外れる形になります。
その結果、以下のようなメリットが得られます
■ 転貸借の主なメリット
トラブル発生時にオーナーが前面に出なくてよい
入居者との契約トラブル(例:家賃滞納、近隣クレーム、設備の破損、敷金返還請求など)が起きた場合でも、すべての窓口は不動産会社が担い、対応・交渉・解決も管理会社側が行います。オーナー自身が交渉の場に出る必要はありません。
法的手続き(明渡訴訟や滞納督促など)も代行可能
たとえば入居者が家賃を長期間滞納した場合、通常であればオーナー自身が内容証明の送付や訴訟手続きに関与しなければなりません。しかし、転貸借では不動産会社が当事者として家賃催促や明渡訴訟を行うことが可能です。法的対応を任せられることで、オーナーの精神的・時間的負担は大幅に軽減されます。
入居者との訴訟リスクが最小限に
例えば「敷金の返還が不当だ」として入居者が訴訟を起こす場合でも、契約当事者は不動産会社であるため、訴えられる対象は不動産会社であり、オーナーではありません。自身が裁判に巻き込まれるリスクを大きく下げることができます。
遠方に住んでいても安心して賃貸運用ができる
転勤先が遠方であっても、不動産会社が一貫して入居者対応を行ってくれるため、地理的なハンディキャップを気にせず賃貸を継続できます。海外赴任や長期出張などでも、不動産会社が実質的なオーナーとして対応するので意思決定が早まることで借主への安心感、管理委託よりもオーナーの手間を減らした賃貸運用が可能です。
■ 「責任を任せる=安心して任せられる」仕組み
転貸借方式では、不動産会社が一部のリスクや義務を引き受ける代わりに、オーナーは賃料を受け取ることに集中できます。まさに「管理とトラブルの盾を構えてくれる存在」が間に入ることで、転勤中の賃貸運用がぐっと現実的かつ安心な選択肢になります。
もちろん、転貸借には不動産会社によって内容や条件(保証範囲、家賃設定など)に違いがありますので、導入を検討する際は信頼できる管理会社と契約内容をよく確認することが大切です。
転貸借のデメリットは?
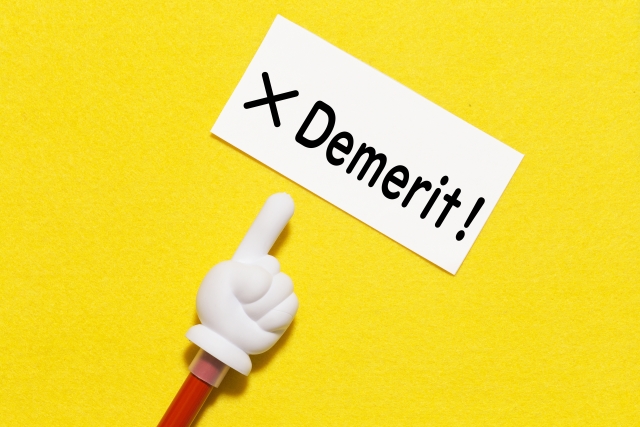
先ほどはメリットに焦点を当てましたが、注意すべきデメリットも確認しておきましょう。
■ 想定より家賃が低くなる可能性がある
転貸借方式では、不動産会社が空室リスクや入居者トラブルを負担する分、オーナーに支払われる賃料は、相場よりも抑えられるケースが少なくありません。特に人気エリアや築浅物件など「高めに貸せそう」と期待していた物件の場合は、賃料にギャップを感じることもあるでしょう。
■ 契約内容の自由度が下がる
入居者との契約は不動産会社が行うため、オーナーが細かい条件を指定するのが難しくなります。「ペット不可にしたい」「外国籍の方はNGにしたい」といった個別の要望が反映されにくいこともあります。
また、万が一、予定よりも早めに自宅へ戻ることになった場合でも、入居者様との契約期間中はすぐに物件を空けてもらえないケースもあるため、将来の予定が不透明な方には注意が必要です。
■ 契約や対応範囲の不明確さによるトラブルの可能性
一見すべての内容を不動産会社に任せられるように見える転貸借方式ですが、契約内容によっては「どこまでが不動産会社の責任か」が不明瞭な場合もあります。たとえば、給湯器の交換や外壁の修繕など、建物の維持管理に関して費用負担の線引きが曖昧で予期せぬトラブルになるケースもあります。
契約書をよく確認せずに進めてしまうと、後々「思っていたより負担が多い」と感じる可能性があるため注意しましょう。
■ 不動産会社の対応力に左右されやすい
転貸借方式では、不動産会社が「契約当事者」としてすべての入居者対応を行うため、その会社の誠実さや対応力が物件運用の質を大きく左右します。入居者への対応が雑だったり、トラブル処理が遅かったりすると、退去後の評価や再募集に悪影響が出ることもあります。どの会社に任せるかを慎重に見極めることが非常に重要です。
■ 解約・終了の柔軟性が低い
転勤や海外赴任が予定より早く終了した、あるいは売却の話が出たなど、オーナー側の事情で早期に契約を終了させたい場合でも、転貸借では簡単に中断できないことがあります。不動産会社がすでに入居者と契約している以上、途中解約には違約金が発生したり、解約時期を調整しなければならないケースもあるため、柔軟な運用にはやや不向きです。
転貸借方式は、オーナー自身がリスクや手間から解放され、安心して自宅を貸し出せる点で非常に魅力的な仕組みです。一方で、「自由度の低さ」や「収益性の抑制」、「契約の複雑さ」などの側面もあるため、事前に契約内容を十分に確認し、信頼できる不動産会社と提携することが不可欠です。
物件の特性やご自身のライフプランによっては、代理委託方式など他の手法も検討する価値があります。どの方式が最適かは、ご状況に応じて丁寧に比較・判断していくことが大切です。
サブリースと転貸借の違いは?

■サブリース=転貸借を含む「保証付きサービス」の総称
サブリースとは、不動産会社がオーナーから建物や部屋を一括で借り上げ、その物件を第三者(入居者)に貸し出す仕組みを指します。この構造そのものは、法律的に言えば「転貸借」に該当します。
つまり、
・オーナー ⇔ 不動産会社(第1の契約)
・不動産会社 ⇔ 入居者(第2の契約)
という二段構えの契約関係が成立しており、不動産会社は借主でありながら貸主にもなるという構造です。
ただし、日本では「サブリース」という言葉が、単なる転貸借以上に「空室時の家賃保証」や「一括管理サービス」などを含む独自のパッケージ型サービスとして普及しています。
そのため、実務では以下のような違いが認識されています。
転貸借:法的には「借りた物を他人に貸す」シンプルな構造を指す
サブリース:転貸借をベースに、不動産会社が「空室時の家賃保証」「退去時の原状回復サポート」などを含めた包括的な運用サービスを提供する仕組み
特にサブリースでは、入居者がいない間もオーナーに一定額の賃料が保証されるのが大きな特徴であり、長期的な収益安定を求めるオーナーにとっては安心材料となります。一方で、家賃設定や契約条件に制限が出ることもあるため、契約時には十分な確認が必要です。
転勤時の「賃貸」か「売却」、結局どちらが正解?賃貸を選ぶなら、信頼できるプロへの相談が安心

転勤に伴って持ち家をどうするかは、多くの人が悩むテーマです。「賃貸に出すか、それとも売却するか?」この選択は、単に資産活用の方法というだけでなく、今後の暮らし方やライフプラン全体に関わる重要な判断です。
結論からいえば、賃貸と売却のどちらが正しいという答えはなく、最適な選択はオーナー自身の状況や意向によって異なります。以下に、それぞれの選択肢が向いているケースを整理してみましょう。
■ 売却を選ぶ方がよいケース
・転勤期間が長期または無期限になる可能性がある。
・今後は現在の物件に戻る予定がない。
・転勤先で新たに住宅を購入したいため、資金を作りたい。
・マンションの築年数や相場から見て、今が高く売れるタイミング。
このような場合は、転勤を機に売却を行うことで、将来的な資産リスクを回避し、スムーズに住み替えへ移行することができます。
■ 賃貸を選ぶ方がよいケース
・「いずれは自宅に戻って住みたい」という明確な希望がある。
・短期転勤(例:1年〜5年程度)の予定で、将来が見えている。
・自宅を活用して家賃収入を得たい。
・空き家のまま放置せず、劣化や防犯の対策をしたい。
このように、「一時的に家を空けるが、いずれ戻る予定がある」方にとっては賃貸が有力な選択肢になります。転勤中の収入源となるだけでなく、住まいとしての機能を維持することにもつながります。
転勤中に自宅を賃貸に出す場合は、契約や入居者対応など専門的な対応が求められるため、信頼できる不動産会社に相談することが重要です。遠方や海外からの対応は現実的ではなく、プロに任せることで安心して運用できます。
また、売却との比較や将来の選択に迷っている方も、まずは専門家に相談することで、不安を解消し、自分にとって最適な判断ができるでしょう。大切な資産を守るために、早めの行動が将来の安心につながります。
転勤や海外赴任のサポートには、1984年に転勤時の留守宅管理(リロケーション)を日本で初めて事業化し40年以上の実績があり、2025年3月末時点で、留守宅管理戸数が10,000戸超の国内最上位の実績を保有しているリロケーション・ジャパンが提供する「リロの留守宅管理」もおすすめです。また、転勤や海外赴任に関する情報は「リロの留守宅管理 転勤コラム」で多数紹介しておりますので、ぜひご一読ください。
賃貸や売買、工事といった賃貸管理に必要な業務だけではなく、資産活用や相続・節税までトータルサポートをいたします。賃貸経営に関するお悩みについてはどんなことでも、リロの不動産にお気軽にご相談ください。
おすすめのサービス
おすすめのお役立ち情報
この記事を書いた人
秋山領祐(編集長)
秋山領祐(編集長)
【生年月日】昭和55年10月28日。
【出身地】長野県上田市。
【趣味】子供を見守ること。料理。キャンプ。神社仏閣。
【担当・経験】
デジタルマーケティングとリブランディングを担当。
分譲地開発のPMや家業の土地活用などの経験を持つ。
リノベした自宅の縁の下に子ども達の夢が描かれている。