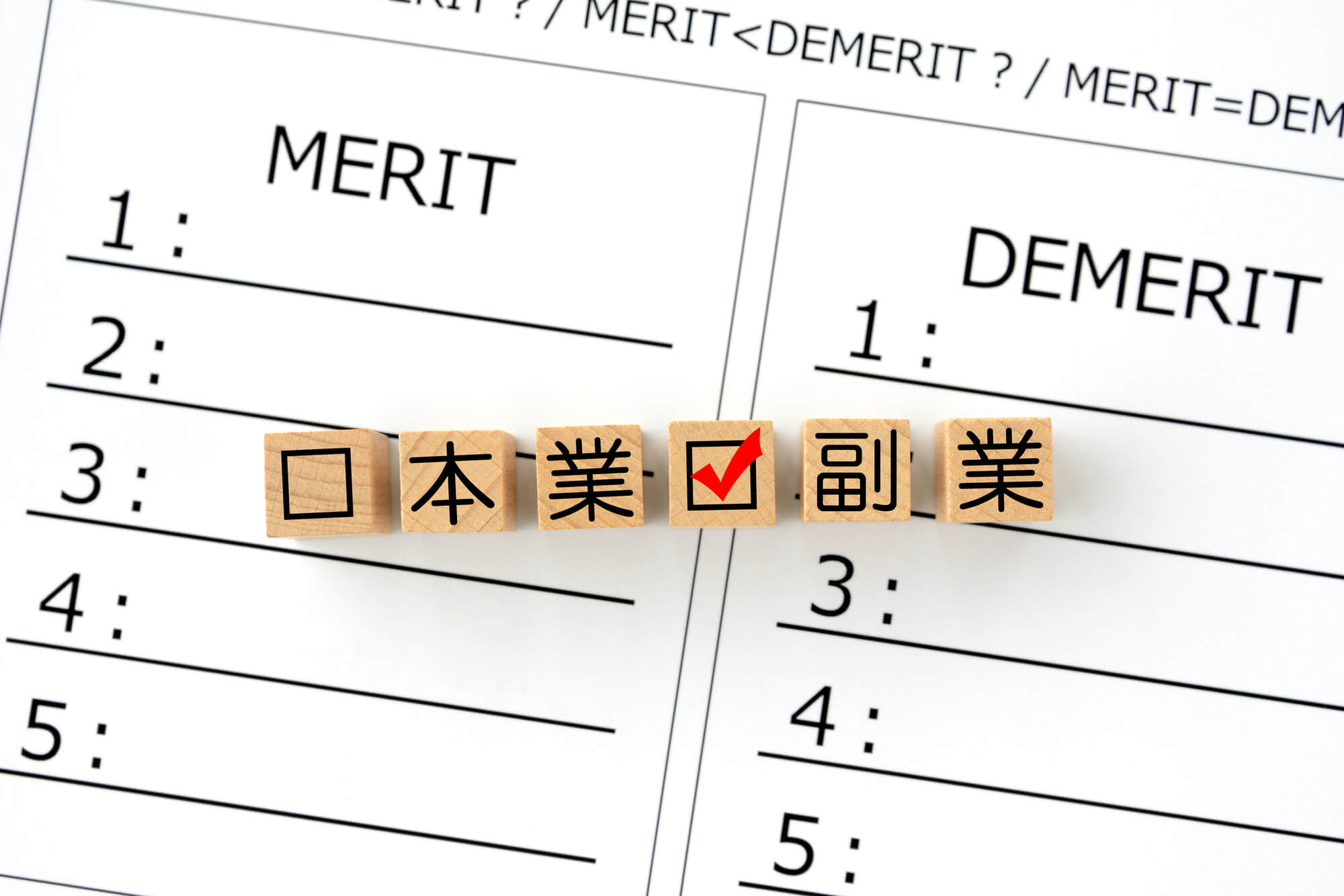【事例付】アパート一棟買いで失敗しない重要ポイントを徹底解説!
2025.10.19
不動産投資にはさまざまな手法があります。現物不動産へ投資する手法のうち、アパート全体を購入して賃貸経営を行うのがアパートの「一棟買い」です。一棟買いによる投資は賃貸する戸数が多い分、入居率を高められれば高収益を見込める一方で、知識不足や準備不足だと大きな損失を招くケースもあります。
そこでこの記事では、アパートの一棟買いで考えられるリスクとその回避法を解説します。アパート一棟買いで成功した事例も紹介するので、不動産投資の手法選びに迷っている方はぜひ参考にしてください。
アパートの購入事例に関しては、以下の事例もあわせてご覧ください。
▼この記事の内容
●アパート一棟買いとは、一棟アパート投資のことを指す。
●一棟アパート投資と一棟マンション投資を比較すると、一棟マンション投資は資産規模も大きくなり、一般的にはキャッシュフローも潤沢になるが、投資総額が大きくなるため融資のハードルが高く、問われる属性も厳しくなる。
●一棟アパート投資と区分マンション投資を比較すると、区分マンション投資は比較的少額から始められるため、融資が受けやすい点。ただし、新築は利回りが低く、投資不適格となるケースが多い。1戸のみの所有の場合は、空室が発生すると家賃収入が途絶えてしまう。
●一棟アパート投資と戸建て賃貸住宅投資を比較すると、戸建て賃貸住宅投資はファミリー層がターゲットになり、長く住む傾向にあるため、安定した家賃収入が期待できる。ただし、中古物件の場合融資が難しいため、レバレッジはかけられず資産形成のスピードは遅くなる。
●アパート一棟買いで失敗する理由としては、①立地が悪い、②過剰な借入金になっている、③表面利回りだけで判断している、④家賃滞納・入居者トラブルが発生する、⑤節税だけが目的となっている、⑥修繕費用が負担になる、⑦サブリースに依存している、⑧出口戦略を考えていない、⑨相続対策ができていない、⑩賃貸管理会社の質が悪い、が考えられる。
●アパート一棟買いに失敗する人の特徴は、自己資金が足りない、不動産投資に関する勉強を怠っている、他人の意見に流されやすい、などが挙げられる。
目次
アパートの「一棟買い」とは
まずは、アパートの「一棟買い」とはどのような不動産投資の手法を指すのか、概要を見ていきましょう。同じ現物不動産への投資である一棟マンション投資、区分マンション投資、戸建て賃貸住宅投資との違いについても解説します。
アパートの購入に関しては、以下の記事もあわせてご覧ください。
▼関連記事
アパート購入と賃貸経営の流れ! アパート経営成功のポイント【保存版】
収益物件の買い方!不動産投資の物件購入は目的設定と情報収集が重要な理由
収益物件購入時の注意点とは? 収益物件の種類とリスクへの対策を解説
アパートの「一棟買い」とは一棟アパート投資を指す

アパートの「一棟買い」とは、読んで字のごとくアパートを一棟単位で購入し、運用する投資手法のことです。所有している土地や新たに購入した土地にアパートを新築するケースと、すでに建築されている中古アパートを購入して運用するケースがあります。
アパート一棟を丸ごと購入するので、初期投資やメンテナンス費用はかかるものの、全戸から家賃収入を得られるため、高収益を狙える点が特徴です。しかし、投資額の大きさから、失敗したときのリスクが大きい点には要注意。アパートの一棟買いを始めるにあたっては、事前の知識習得と入念な準備を怠らないようにしましょう。
一棟マンション投資との違い
「一棟買い」での不動産投資は、アパートの一棟買い以外に一棟マンション投資があります。これも同じように、マンション一棟を丸ごと購入し、入居者様へ賃貸することで家賃収入を得る投資手法のことです。
アパートとマンションというと、物件規模の大きさの違いを思い浮かべるかもしれません。たしかにアパートのほうが小規模、マンションは比較的規模が大きめという傾向はあります。しかし、それ以外にも節税効果の大きさや融資の受けやすさなど、投資の性格に違いが見られます。
アパートとマンションの違いとは

アパートの一棟買いと一棟マンション投資の違いを考えるにあたり、そもそもアパートとマンションがどう違うのかを理解しておく必要があります。2つを厳密に分ける法的な決まりはないものの、次のような基準で区別されるのが一般的です。
アパートとマンションの一般的な違い
| 階数・戸数の傾向 | 建物構造 | |
| アパート | 2〜3階、戸数は少なめ | 木造・鉄骨造が中心 |
| マンション | 3階以上、戸数は多め | 鉄筋コンクリート(RC)造・鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造が中心 |
建物構造が違えば、法定耐用年数も当然異なります。法定耐用年数は木造22年、鉄骨造(3mm超4mm以下)27年、RC造・SRC造47年となっており、マンションはアパートに比べて、2倍程度耐用年数が長いと考えてよいでしょう。
一棟マンション投資が優位な点
アパート一棟買いと比較して一棟マンション投資が優位な点としては、資産規模の大きさが挙げられます。アパートに比べてマンションは物件規模が大きく、毎月得られる家賃収入が大きくなります。マンションは強固な構造かつ共用設備が充実している傾向にあるため、1戸ごとの家賃水準も高めに設定でき、一般的にキャッシュフローも潤沢になりやすいでしょう。
一棟の資産規模が大きいため、時間をかけず一気に資産拡大を狙いたい方にとっては、アパートよりもマンションが向いているといえます。
一棟マンション投資が劣る点
一棟マンション投資は大きな初期投資を必要とするため、融資のハードルが高いという問題点があります。中規模のマンションでも億単位の投資が必要になるケースも多く、融資の際に求められる属性も当然厳しくなるでしょう。そのため、一棟マンション投資に取り組めるのは一部の方に限られているのが実情です。
また、先述したとおり、マンションはアパートに比べて法定耐用年数が長い傾向にあります。法定耐用年数が長くなるほど、1年ごとに計上できる減価償却費は小さくなるため、所得税や住民税の節税効果を狙う場合は、アパートのほうが有利といえるでしょう。
▼関連記事
賃貸マンションの一棟買いはあり? アパート経営・区分マンション経営との徹底比較
アパート一棟買い・マンション一棟買いを数字で判断!一棟投資成功に向けたポイントを解説
マンション一棟買いの成功ポイントと指標にする利回り!メリット・デメリットや注意点
区分マンション投資との違い

次に区分マンション投資との違いを見ていきましょう。区分マンション投資とは、マンション(区分所有建物)の1室もしくは複数室を所有し、入居者様へ賃貸することで家賃収入を得る投資手法のことです。
一棟マンション投資と異なり、1室単位での投資なので、初期投資を抑えられるのが魅力です。共用部の管理は物件所有者や賃貸管理会社に任せられるため、日常的な管理の手間がほとんどかからない点も特徴となっています。その反面、期待できる収入額は小さめで、空室リスクの影響が大きいといった点には注意が必要です。
以下では、アパート一棟買いと比較した場合の、区分マンション投資が優位な点・劣る点を詳しく見ていきましょう。
区分マンション投資が優位な点
区分マンションがアパート一棟買いに比べて優位な点としては、まず投資のハードルの低さが挙げられます。区分マンション投資は、アパートを一棟丸ごと購入するのに比べれば少額で始められるため、ある程度の収入があれば融資も受けやすいでしょう。一定割合で自己資金を準備するとしても、もとの物件価格が安価なので、それほど大きな負担になりません。
また、立地のいい区分マンションであれば、アパート一棟買いより流動性が高いというメリットもあります。アパート一棟買いの場合、購入希望者が投資家などに限られる一方、1室単位の区分マンションなら実需層もターゲットになるからです。
ただし、資産価値が見込めない物件だと、不動産投資ローンの残債が物件価格を上回ってしまい、キャピタルロスが発生するケースもあるので注意しましょう。
区分マンション投資が劣る点
比較的少ない初期投資で始められる区分マンション投資ですが、新築物件の場合は価格が高くなる傾向にあり、利回りが低くなりがちです。物件価格の割に家賃収入が見込めないと、投資不適格となるケースもあるでしょう。
また、区分マンション投資は1室単位で所有するため、空室が発生すると家賃収入が途端にゼロになってしまうというリスクもあります。入居者様が入れ替われば、ある程度の空室期間は発生するため、収益が不安定になりやすいというのもリスクです。
加えて、区分マンションのオーナー様が管理するのは専有部分のみであり、建物全体の管理は、建物所有者が指定する別の賃貸管理会社に委託されます。そのため、オーナー様の経営自由度が低いというのもデメリットです。
▼関連記事
戸建て賃貸住宅投資との違い

戸建て賃貸住宅投資は、取得した戸建て住宅を入居者様に賃貸し、家賃収入を得る不動産投資のスタイルです。近年では、郊外や地方の中古戸建て住宅を低価格で購入し、DIYでリフォームしたうえで入居者様へ貸し出すやり方が人気となるなど、高利回りで運用しやすいという特徴があります。
アパートやマンションの賃貸物件に比べ、戸建て住宅の賃貸物件は少ないというのもポイント。「マイホームを購入するほどではないけれど、戸建て住宅に住みたい」という層にアプローチできるので、戸建てニーズのある地域であれば、比較的入居者様が見つかりやすいでしょう。
戸建て賃貸住宅投資が優位な点
アパート一棟買いと比較した場合の戸建て賃貸住宅投資のメリットとしては、中古物件であれば初期投資が安くてすむことが挙げられます。先述のように、近年は郊外や地方の中古戸建てを購入して、リフォームしたうえで貸し出す投資手法が注目を集めています。
立地によっては数百万円で物件を購入できるケースもあり、ローンを組まずに自己資金で投資するというのもそれほど難しくありません。毎月のローン返済がなければ、家賃水準が低めでも十分な収益を見込めます。
また、戸建て賃貸住宅はファミリー層をターゲットにするケースが多いのも特徴です。子育て世帯の入居者様は、一度入居すると学区の関係で長期間にわたって住み続ける傾向にあるため、入居者様さえ見つかれば、長期的に安定した家賃収入を期待できるのも魅力といえます。
区分マンションと同様、売却時には一般の実需層もターゲットになります。おまけに、リフォームで内装が整った中古戸建て住宅は物件数が限られるため、流動性の面でも有利でしょう。
戸建て賃貸住宅投資が劣る点
特に中古戸建て住宅は物件価格が安い分、担保価値も低いため、築古になると融資を受けること自体が難しいケースも少なくありません。こうなると自己資金で投資するのが前提となるので、不動産投資の大きなメリットであるレバレッジ効果が見込めず、資産形成のスピードが遅くなりがちです。
戸建て賃貸のニーズは立地に左右されにくいものの、地域のターゲットに合った物件かどうかが大きなポイントになります。そのため、マンションやアパートとは異なる目利きが求められる点にも注意が必要です。
高い利回りを求めて中古戸建て住宅を購入する場合、リフォームを行うことが前提になります。通常のリフォーム会社を利用すると、物件価格よりもリフォーム費用が高くなりかねないので、手頃な価格で施工してくれる会社を探したり、オーナー様がDIYで仕上げたりといった工夫も必要になるでしょう。
アパート一棟買いで失敗する10の理由
区分マンション投資や戸建て賃貸投資に比べて、大きな収益が見込めるアパート一棟買いですが、その分失敗したときのリスクも大きいといえます。アパート一棟買いで失敗につながりやすい10の理由を知って、リスク回避に活かしましょう。
立地が悪い
アパート経営において最も大きなリスクの一つが「空室リスク」です。空室の多い状態が長く続けば、期待していた家賃収入が入らなくなり、経営が成り立たなくなる恐れもあります。アパート経営で損失が生じやすい立地としては、次のようなものが挙げられるでしょう。
・都市部において最寄り駅から遠い
・周囲に商業施設や病院などの生活利便施設がない
・小学校、中学校などの教育機関がない
・周辺の治安が悪い
立地に関しては、地域で狙うべきターゲット層によっても良し悪しが変わります。例えば、都市部で若者の一人暮らしをターゲットにしたアパートであれば、駅からの距離や飲食店の充実度などが重要です。一方、地方でファミリーをターゲットにするなら、駅からの距離よりも商業施設や駐車場の充実度、学校までの距離などがポイントになるでしょう。
周辺地域のマーケット分析が不足していると、立地に対する判断を誤り、アパート経営に失敗するおそれが高まります。
過剰な借入金になっている

アパート一棟買いを含む不動産投資は、初期投資の多くをローンでまかなえるというのが魅力です。ローンがもたらすレバレッジ効果により、投資額に対して、さらに大きなリターンを狙うことができます。
しかし、自己資金を抑えようとして借入比率を高くしすぎると、毎月のローン返済が重くなり、家賃収入を圧迫しかねません。期待どおりの家賃収入を得られている間は、何とか収支をプラスに保っていても、空室率が高まった瞬間に手出しが発生する可能性もあります。
近年は金利上昇の兆しも見えており、ローンを変動金利で借り入れた場合、返済期間中に借入金利が上がることも考えられます。金利上昇で毎月返済額が増えると、アパート経営自体が立ち行かなくなるかもしれません。
物件購入費用にローンを充当できるからといって、それに頼りすぎることなく、不測の事態に備えた一定の自己資金を準備するとともに、堅実な資金計画を立てることが重要です。
表面利回りだけで判断する
不動産広告などで見かける「利回り」は、多くの場合「表面利回り」です。表面利回りは次の計算式で求められます。
表面利回り(%) = 年間家賃収入 ÷ 物件価格 × 100
この式から分かるとおり、表面利回りは、満室時の家賃収入を物件価格で割っただけの簡易的な指標に過ぎません。おまけに、アパート経営にかかる固定資産税などの税金、管理費用、メンテナンス費用といった経費も一切考慮されていないのです。
アパート一棟買いを選択する方の中には、利回りの高さに魅力を感じるケースも多いかもしれませんが、表面利回りだけで物件を選ぶのは推奨できません。あとで紹介するように、実質利回りや自己資本利回り(CCR)、イールドギャップなどの指標も参考にして、判断を誤らないようにしましょう。
不動産投資の利回りに関しては、こちらの記事で詳しく解説しています。
▼関連記事
【総集編】アパート経営の利回りの目安は?不動産投資の指標と注意点
【徹底解説】不動産投資の利回り計算! 賃貸経営を成功に導く指標とは
家賃滞納・入居者トラブルが発生する
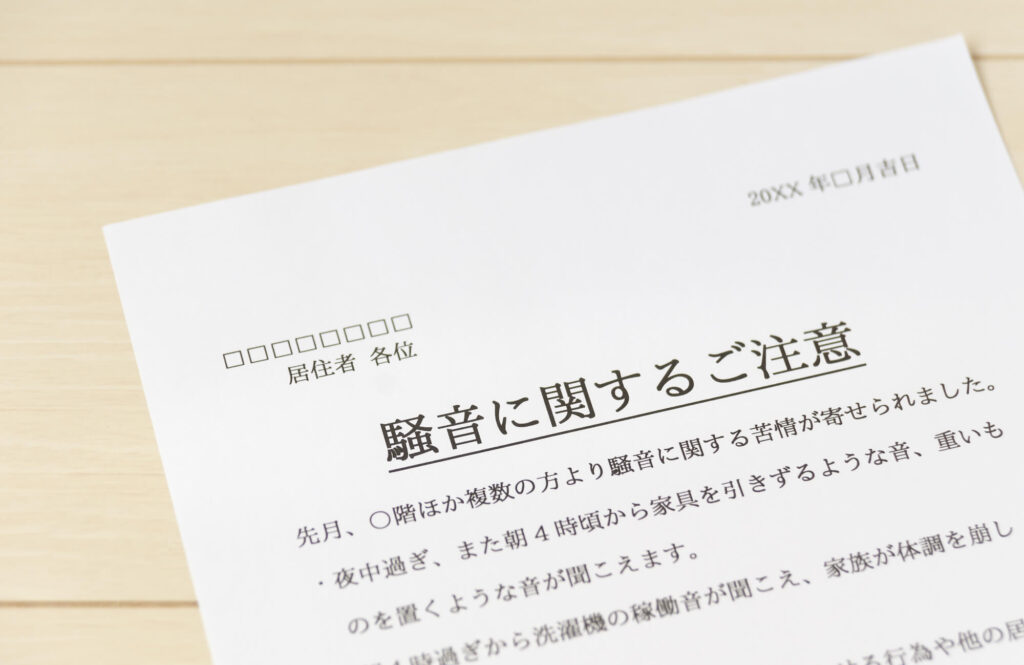
アパート経営でよくあるリスクとして空室リスクを紹介しましたが、空室リスク以上に厄介なのが、入居者様が家賃を支払わない「家賃滞納リスク」です。家賃滞納が発生すると、入居状態であるにもかかわらず家賃収入が入らなくなってしまいます。
空室であれば新たな入居者様を募集すればいいですが、家賃滞納の場合、現在の入居者様が退去しないかぎり、入居者募集をかけることもできません。しかも、賃貸借契約を解除するには「信頼関係の破壊」が条件とされ、退去に応じなければ建物明け渡し請求訴訟を裁判所に提起しなくてはならないのです。このように、家賃滞納は大きな損失につながるリスクを秘めています。
入居者様の質に問題があると、騒音やゴミ出しなどをめぐって、ほかの住民とトラブルを起こす危険性も高まります。トラブルが発生すると物件の評価が下がり、空室増加や家賃下落を引き起こすこともあるので注意が必要です。
節税だけが目的となっている
先述のとおり、アパートは木造や軽量鉄骨造が中心のため、RC造・SRC造のマンションに比べて法定耐用年数が短いという特徴があります。法定耐用年数が短いほど、1年で計上できる減価償却費が大きくなることから、節税目的でアパート一棟買いを選択する方も多いでしょう。
法定耐用年数を超過した築古物件は、減価償却期間を「法定耐用年数×20%」で計算する決まりになっています。木造アパートの法定耐用年数は22年なので、築22年以上の物件は「4年」で減価償却できるのです。
しかし、節税だけを目的として物件を選んでしまうと、物件自体の収益性や維持管理にまつわるリスクを見落とす危険性があります。築年数が古ければ、家賃水準が相場よりも低くなり、相場を維持しようとすればリフォームの必要も生じます。設備や配管も老朽化しているので、維持管理費も多くかかるでしょう。
節税を主な目的として投資する場合でも、長期的な収益性や修繕リスクを十分考慮したうえで物件を選ぶべきです。
修繕費用が負担になる

前の理由にも通じますが、修繕費用が大きな負担となって収支が悪化した結果、アパート経営が立ち行かなくなるケースも見られます。当然、築年数が経過している物件ほど、給排水管や外壁、防水、屋根など大がかりな修繕が必要です。
こうした配管や設備は20〜30年に1回程度、全体的な修繕が求められるため、資金計画にあたっては当初から費用を見込んでおかなければなりません。修繕費を見落としていると、キャッシュフローに大きな影響を与えるでしょう。
また、大規模修繕に限らず、築古の物件では突発的な不具合や故障が生じるリスクもあります。資金計画に余裕がないと、想定外の修繕費に対応できず、キャッシュフローが悪化するかもしれません。大規模修繕に向けた積み立てに加え、突発的な修繕に使える予備費も見込んでおいたほうが安全です。
サブリースに依存している
アパート経営特有の空室リスクや家賃滞納リスクへの対策として、賃貸管理会社とサブリース契約を締結するケースも少なくありません。サブリース(一括借上)契約とは、賃貸管理会社に物件を転貸し、運営管理をすべて任せる契約形態のことです。サブリース契約を締結したオーナー様は、賃貸管理会社から毎月一定のサブリース賃料を受け取ることができます。
サブリース契約は、たしかに安定した収入を確保するには効果的です。しかし、リスクがあることも認識しておかなければなりません。
というのも、サブリース契約ではオーナー様が貸主となり、転貸されている賃貸管理会社側が借主となります。不動産賃貸の根拠法である借地借家法は、立場の弱い借主を保護する性質の法律であるため、借主の権限が強く認められているのが特徴です。そのため、サブリース契約においても、賃貸管理会社から一方的に家賃の減額を請求されたり、契約解除に応じてくれなかったりといったトラブルが起こり得ます。
サブリース契約に依存していると、こうしたトラブルが要因で、アパート経営が立ち行かなくなることもあるでしょう。
出口戦略を考えていない
アパート経営の収益の柱は、毎月の家賃収入によるインカムゲインです。しかし、アパート経営の最終的な目的は、投資期間全体を通じて収支をプラスにすることのはずです。毎年のインカムゲインがプラスで推移しても、物件売却時に売却価格が購入価格を大きく下回ってしまい、大きなキャピタルロスが発生するようでは、長年の投資が無駄になってしまいます。
こうした事態を防ぐためにも、購入時に資金計画を立てる時点で、出口戦略をしっかり考えておく必要があります。
出口戦略を考えるにあたっては、物件の経年劣化や不動産市場の変動のほか、デッドクロスの発生も見込んでおきましょう。デッドクロスとは、ローン返済のうち元金分が減価償却費を上回る状態のことをいいます。減価償却費は経費計上できる一方、元金返済は経費として扱えないため、デッドクロスを迎えると帳簿上の黒字幅が大きくなってしまい、一気に所得税・住民税が上昇し、キャッシュフローが悪化してしまいます。
なお、節税目的で築古アパートを購入する場合、デッドクロスの到来は避けられないものであるため、あらかじめ売却の対策を講じておくことが重要です。
相続対策ができていない
アパート経営は数十年にわたるケースも少なくないため、経営をしている間に相続の発生も予想されます。資産価値の高いアパートは、相続財産としての評価もそれなりに高くなることが想定されるため、事前の相続税対策や相続人の間での調整が必要不可欠です。
気をつけなければならないのが、アパートは現物分割が難しいということ。アパートを分割して複数の相続人に相続することができないため、一人の相続人が相続し、それ以外の相続人に代償金を支払うといったケースが考えられます。このとき、誰がアパート経営を承継するか、代償金をいくらにするかをめぐって相続人同士の争いに発展するおそれがあるのです。
また、相続人同士で共有名義にするというのも、後々トラブルを引き起こす可能性があり、あまり現実的ではありません。相続をめぐる争いを避けるため、オーナー様が亡くなったあとのことも想定して、必要な対策を講じておきましょう。
賃貸管理会社の質が悪い
アパート経営の運営管理業務は多岐にわたるため、オーナー様が自主管理ですべて対応するのは難しく、多くの場合、賃貸管理会社に業務を委託することになります。賃貸管理会社はオーナー様と二人三脚でアパート経営を行うパートナーであるため、会社の質が悪いと、アパート経営もうまくいかない可能性が高いでしょう。
賃貸管理会社は、日々の清掃や点検などの物件管理から、入居者募集や入居者様からのクレーム対応といった入居者管理、家賃回収に至るまで幅広い業務を担います。これらの業務の質は入居者様の満足度に大きく関わるため、業務の質が悪いと、空室率の上昇につながりかねません。
さらに、賃貸管理会社からの報告が不透明な場合、オーナー様がトラブルにいち早く気づくことができず、トラブルが深刻化したり長期化したりするおそれもあります。
アパート一棟買いの失敗を回避する10の対策
前章で述べたアパート一棟買いの失敗を回避するには、どのような対策が効果的なのでしょうか。ここでは、アパート一棟買いのリスクを低減し、成功へと導くための10の対策を紹介します。
アパート経営は立地がすべて

アパート経営において重要なのは物件選びであり、その中でも特に重視すべきは立地です。アパートに限らず、不動産は立地がすべてであり、立地なくして不動産投資の成功はありません。
駅からの距離、商業施設や病院、学校といった生活インフラの充実度、周辺の治安、周辺地域における将来の都市開発計画などを総合的に評価し、将来にかけて収益性が見込めるかどうかを見極めましょう。このことが空室リスクや家賃下落リスク、物件価格下落リスクへの何よりの対策になります。
また、地域によっては大学のキャンパスや大規模工場など、特定の学生や社会人に向けたニーズで賃貸マーケットが成り立っているところもあります。こうした地域の物件を選ぶ場合、ターゲットとなる施設が縮小したり移転したりすれば、一気に賃貸ニーズが消失するかもしれません。大学や工場の動向に不安があるなら、ほかの地域の物件を探したほうがよいでしょう。
適正なレバレッジ比率で運用する
レバレッジ効果を狙えるのが不動産投資の大きな魅力ですが、自己資金を準備せずに借入比率を高すぎてしまうと、毎月のローンの返済負担が大きくなり、資金繰りが厳しくなると考えられます。そもそもレバレッジ効果を高めるには、家賃収入からローン返済や経費を除いた手取りを増やす必要があるため、ローン返済によって手取りが減ってしまうのでは意味がありません。
また、ローンを変動金利で借り入れる場合、将来の金利上昇リスクにも配慮すべきです。金利上昇にともなう毎月返済額の増加によって、当初見込んでいただけのレバレッジ効果が得られなくなる可能性もあるからです。
十分なレバレッジ効果を得るには、一般的に借入比率を物件価格の70%程度までにするのがいいとされます。30%程度の自己資金を準備することで、毎月のローン返済を抑えられるうえ、金利が上昇したとしても十分な効果が期待できるでしょう。ローンに頼りすぎず、余裕のある返済計画を立てることがアパート経営を成功させる秘訣です。
表面利回り以外の指標も参考にする
先述のとおり、不動産広告などに記載される表面利回りは、満室時の年間家賃収入をベースに計算されるものであり、空室の発生やローン返済、経費などが一切考慮されていません。アパート経営の根底となる物件選びでつまずかないためには、表面利回り以外の指標も参考にしましょう。表面利回り以外でチェックしたい重要指標は次のとおりです。
| 指標 | 内容 | 計算式 |
| 実質利回り | 年間家賃収入において空室率を考慮し、各種経費を差し引いた利回り | (年間家賃収入−年間経費)÷物件価格×100 |
| 自己資本利回り (CCR) | 購入時の自己資金に対する利益の割合を表す利回り | 年間キャッシュフロー÷購入時の自己資金(自己資本)×100 |
| イールドギャップ | 投資利回りと借り入れているローンの金利差を示す指標 | 実質利回り−ローン定数(年間ローン返済額÷総借入額) |
これらの指標を組み合わせてチェックすることで、より精緻で安全サイドの資金計画を立てることができるでしょう。
厳格な入居審査を行う
先述のとおり、家賃滞納や入居者トラブルはアパート運営に大きな影響を与えます。家賃滞納が続けば、期待していた家賃収入が入って来ないだけではなく、強制退去のための訴訟に大きな費用と手間・時間がかかる恐れがあります。また、入居者トラブルが発生すると近隣の入居者様が退去したり、新しい入居者様がなかなか決まらなかったりして、空室率の増加につながるおそれもあるでしょう。
家賃滞納や入居者トラブルを未然に防ぐには、入居審査を厳格に行うのが効果的です。入居希望者の収入や職業、過去の滞納履歴などをしっかり確認し、家賃の支払い能力が十分にあるか、問題行為を起こす恐れがないかを慎重にチェックします。
とはいえ、審査だけでは見抜けないこともあります。とりわけ家賃滞納に関しては、家賃保証会社を利用したり連帯保証人の確認を行ったりして、万が一滞納してしまったときに備える対策を講じておくことも重要です。
節税だけでなく収益性を考慮する

減価償却による節税目的でアパート経営を行うケースでは、減価償却効果の見込める、築古の中古物件を選びがちです。法定耐用年数を超過した物件なら、1年あたりに経費計上できる減価償却費が大きく、新築よりも大きな節税効果が見込めます。
しかし、物件の収益性が低く、キャッシュフローがマイナスになってしまうようでは元も子もありません。節税目的で物件を選ぶときでも、物件自体の収益性が十分かどうかしっかり見極めるようにしましょう。
節税目的で中古アパートを購入する場合では、デッドクロスを迎える時期も必然的に早まるため、早めの売却を盛り込んだ出口戦略を立てる、利回りの高い物件を選ぶなど、事前に対策を考えておくことも大切です。
▼関連記事
【事例付】中古アパートを購入するときの注意点と対策を事例と一緒に徹底解説
不動産購入は法人と個人どっちがお得?法人化するタイミングも解説
修繕積立金を準備する
不動産は築年数が10〜15年経過した時点で、1回目の大規模修繕が必要になってきます。また、その後も10〜15年おきに定期的な大規模修繕の時期を迎えるのが一般的です。
こうした修繕は計画的に行うものなので、予測される修繕費を事前にシミュレーションし、月々の家賃収入から一定額を積み立てておくことが求められます。時間をかけて無理なく大規模修繕積立金を準備しておけば、キャッシュフローに影響を与えることなく、必要な時期に修繕を施すことができるでしょう。大規模修繕を適切な時期に行っておけば、長い期間にわたって建物をいい状態に保つことができ、資産価値の維持や家賃収入の安定にもつながります。
なお、アパートの修繕には、国や自治体が実施する補助金制度を活用できる場合があるので、最新情報をチェックしておきたいところです。2025年度の国の制度では「長期優良住宅化リフォーム推進事業」が利用できるほか、高効率給湯器への交換については「賃貸集合給湯省エネ2025事業」も活用できます。
参照:国土交通省 令和7年度長期優良住宅化リフォーム推進事業
参照:経済産業省資源エネルギー庁 賃貸集合給湯省エネ2025事業
サブリース契約のリスクを知る

空室リスクや家賃下落リスクへの対策として効果的なサブリース契約は、オーナー様が貸主であり、サブリースを行う賃貸管理会社が借主となります。先ほども紹介したとおり、賃貸借契約の根拠法である借地借家法は貸主保護を目的とした法律のため、サブリース契約においては賃貸管理会社が保護される立場です。よって、オーナー様からの契約解除には正当事由が求められるため、十分に注意しましょう。
この立場を利用して、一方的にサブリース賃料の減額を求めてくる賃貸管理会社も少なからず存在します。借地借家法上、オーナー様から賃貸管理会社側へ契約解除を求めるのはハードルが高いので、多くの場合、減額要求を飲まざるを得ません。結果的に期待していた収入を得られなくなり、キャッシュフローが悪化してしまうのです。
サブリース契約は、賢く利用すればリスクを軽減できる有用なものですが、依頼する賃貸管理会社は慎重に判断する必要があります。
出口戦略を定めておく
アパート経営は、物件売却という出口を迎えてはじめて、成功か否かがはっきりとします。運用期間中のキャッシュフローがいくらプラスでも、売却価格が購入価格を大きく下回って巨額のキャピタルロスが生じてしまうと、不動産投資全体で見た場合には損失超過となってしまうのです。
最終的にアパート経営を成功させるためには、物件購入時から出口戦略を描いておくことも重要でしょう。
まず、どの時点で売却するのか、目標を決めておく必要があります。「長期譲渡所得」となる所有期間5年を超えた時点ですぐ売却するのか、さらに長期運用を行って安定的な収入を確保するのかなど、投資の狙いや将来のビジョンにそって、適切な売却タイミングを定めておきたいところです。
加えて、売却価格をなるべく高くする工夫も求められます。例えば、将来にかけて高い賃貸ニーズが見込める立地を選定する、空室を減らして利回りを高める、修繕やリニューアルを適切に行って資産価値を維持するといった対策が有効です。
▼関連記事
アパート経営に必要な自己資金はいくら? 成功に導く出口戦略と資金計画
アパート購入費用はいくら? アパート経営の費用と注意点を徹底解剖
一棟アパート購入から始める不動産投資!成功者が確認する指標と利回りも解説
木造一棟アパートの購入から始める不動産投資!メリット・デメリットと投資戦略
土地購入から始めるアパート経営!土地選びの方法や注意点を徹底解説
相続対策を準備する

長期にわたることも多いアパート経営では、相続に向けた準備も必要です。購入したアパート以外の財産の評価額も計算し、将来の相続発生時にどれくらいの相続税が発生するのか、しっかりと予測を立てておきましょう。
アパートに限らず、不動産は相続対策に有効な資産とされます。土地は相続税路線価、建物は固定資産税評価額をベースに相続税評価額を計算するため、額面どおりに評価される現預金などの金融資産に比べ、評価額が低くなる傾向にあるからです。アパートのように第三者へ賃貸している家屋には借地権割合・借家権割合・賃貸割合が適用されるので、評価額がさらに圧縮されます。
また、一定面積までの宅地に対して評価額の減額が適用される「小規模宅地の特例」などの優遇措置も用意されています。こうした特例は、自ら申請しないかぎり適用されないため、事前にリサーチしておきましょう。
アパートなどの収益物件の相続においては、経営をめぐって相続人同士で争いになることも予想されます。親族内での争いを未然に防ぐためにも、遺言書の準備や生前贈与、資産管理会社の設立なども検討しておくとよいでしょう。相続に向けた準備には専門知識が求められるため、弁護士や税理士などの専門家に協力を仰ぐことをおすすめします。
信頼できる賃貸管理会社に依頼する

アパート経営の運営管理業務は多岐にわたるため、オーナー様一人ですべてをこなすのは至難の業です。ほとんどの場合、賃貸管理会社に業務を委託することになるでしょう。賃貸管理会社は、日常的な清掃や入居者対応、クレーム処理、家賃回収、修繕や点検の手配など、運営管理に関するあらゆる業務を担当します。そのため、賃貸管理会社の質が経営の安定性に直結するといえるのです。
賃貸管理会社を選定する際は、過去の運営管理の実績を確認するとともに、担当者の対応、報告体制、手数料体系なども総合的にチェックしましょう。信頼できる賃貸管理会社に委託することが、アパート経営を成功させるための重要な鍵となります。
アパート経営を成功・改善した事例を紹介
リスクを回避する適切な対策を講じれば、アパート経営を成功に導くことができます。ここでは、物件選びや運営管理の工夫により、アパート経営を成功・改善した事例を5つ紹介しましょう。
【事例1】杉田にて土地を購入、アパートを新築

横浜市磯子区の杉田で土地を購入し、その後、請負契約を締結してアパートを新築した事例です。新築物件のために借入期間を長く設定できたことから、毎月のローン返済額を低く抑えられ、十分なキャッシュフローを確保できました。
また、オーナー様はほかにも不動産を所有しており、共同担保として担保提供できたのもポイントです。結果として、融資額5,250万円に対して自己資金を100万円まで抑えられ、高いレバレッジ効果を実現しました。
▼アパート一棟の購入事例
杉田新築アパートの購入事例|不動産投資・投資用不動産・収益物件
【事例2】沼袋で築2年の一棟アパートをアメリカ・ファンドから購入

こちらは、中野区沼袋にある築2年の築浅アパートの事例です。銀行の積算評価が購入価格を大幅に上回っていたため、融資比率を高めることができました。
都心部の好立地でありながら利回りも高く、優位性の高い物件でした。当然人気も高く、買付が3本以上重複していたものの、オーナー様と金融機関、【リロの不動産】の三者が緊密に連携してスピーディに行動した結果、購入を勝ち取りました。
▼アパート一棟の購入事例
マルチプレックス沼袋の購入事例|不動産投資・投資用不動産・収益物件
【事例3】ペット共生住宅の募集条件を工夫し周辺相場より10,000円アップ

千葉県八千代市にあるこちらのアパートは、ペットの飼育が可能なペット共生住宅です。募集条件も「ペット可」という強みを前面に押し出した広告を展開。オーナー様と相談し、飼育できるペットの種類や頭数に関する条件も緩和しました。
その結果、ペット飼育を希望する層からの注目度が高まり、新たな対策費用をかけることなく、周辺相場よりも10,000円高い家賃を実現しました。
▼アパートの空室対策・収益改善事例
ペット共生住宅の募集条件を工夫し周辺相場より10,000円アップ
【事例4】ネット広告の見直しで長期空室をすぐに改善!
次に紹介するのは、仙台市若林区に立つアパートです。設備は比較的充実しているにもかかわらず、長年空室が埋まらないという悩みを持つオーナー様よりご相談を受け、インターネット広告の見直しを実施しました。
具体的には、研修で技術を高めた写真撮影、地域情報などにもこだわり、質の高い物件情報を提供。結果として、インターネット掲載の見直しからあまり時間を置かずに満室稼働を達成しました。
▼アパートの長期空室改善事例
【事例5】新築なのに決まらない。諸条件を見直しキャンペーンと入居者募集を強化

最後に紹介するのは、埼玉県上尾市の新築アパートにおける事例です。当物件は最寄り駅から徒歩9分の新築という好条件ながら、3ヶ月経っても入居が決まりませんでした。
改善の依頼を受けた【リロの不動産】は、オーナー様と相談のうえ、募集条件の見直しやフリーレントなどのキャンペーンを実施。インターネットへの情報掲載の強化や、同業他社への積極的な情報紹介も並行して行った結果、追加費用をかけることなく満室を実現できました。
▼アパート入居者募集の改善事例
新築なのに決まらない。諸条件を見直しキャンペーンと入居者募集を強化
アパート一棟買いに失敗する人の特徴
ここまで見てきたように、物件選びを慎重に行って必要な対策を講じれば、アパート経営を成功に導くことができます。しかし、次のような特徴に当てはまる方は失敗する可能性が高いので注意が必要です。
自己資金が足りない
先述のとおり、アパート経営を始めるにあたっては、借入比率を物件価格の70%程度までに抑えるのがいいとされています。十分な自己資金が用意できないからといって、ローンに依存するのはリスクが高い行為です。
もちろんフルローンで購入するという手法もありますが、融資の審査は当然厳しくなります。また、借入比率が高まるほど毎月の返済額も大きくなるため、キャッシュフローを圧迫することになり、資金がショートするリスクも高まるでしょう。
一定の資金力がある中、あえて借入比率を高めるのであればいいですが、手元にも自己資金がない場合、突発的な不具合や故障が発生したときに対応ができません。修繕が遅れると入居者様の不満につながり、退去や空室率の上昇を招くおそれもあります。
物件購入にローンを活用するのは前提としても、最低限の自己資金が準備できない方は、アパート経営に取り組むべきではないでしょう。
▼関連記事
賃貸アパートの値段はいくら? 一棟買いのメリットと不動産投資ローンの基本を解説
アパートローンを上手に利用するコツと注意点|住宅ローンとの違いは?
現金一括購入とローン活用によるアパート経営の違い!不動産投資判断のポイントを解説
不動産投資に関する勉強を怠っている
アパート経営は、不動産投資会社や賃貸管理会社などのプロの意見を参考にしながら進めることができます。しかし、オーナー様にも投資の基本知識、法律に関する知識、建築に関する知識、税金に関する知識などがなければ、適切な判断を下すことはできません。利回りや収支といった数字を見て、状況を整理したり対策を考えたりする論理的思考能力も求められるため、常に学習する姿勢が求められます。
パートナーである不動産投資会社や賃貸管理会社に任せきりで、学習する姿勢のない方はアパート経営でつまずくリスクが高いといえるでしょう。
他人の意見に流されやすい
不動産投資は賃貸経営です。アパート経営のオーナー様も一人の経営者であり、場面ごとに経営者としての判断が求められます。ときには第三者の意見を聞き入れることも大切ですが、最終的には自分の問題であり、自分の責任で決断しなければなりません。
例えば、物件購入時、不動産販売会社の担当者の営業トークに流され、自分で考えることを怠ると物件選びがうまくいかない可能性が高まります。運営管理においても、空室がなかなか埋まらない場面で賃貸管理会社の言い分にばかり耳を傾けていては、いつまでも状況は改善されません。
プロの意見は参考にしつつも、自分なりの意見や信念を持てる方でないと、アパート経営はうまくいかないでしょう。
まとめ

「アパート経営はやめておけ」といわれることもありますが、成功させるための方法を身につけて実践できれば、安定的かつ大きな収益を上げることは可能です。ただし、そのためには事前の情報収集と慎重な判断が欠かせません。加えて、物件の立地、管理体制、資金計画に至るまで、綿密に組み立てることが求められます。
とはいえ、アパート経営はオーナー様一人で完結するものではありません。リスクを回避するためには、信頼できる賃貸管理会社をパートナーに迎えることも重要です。
【リロの不動産】は、豊富な実績により蓄積された賃貸経営データをもとに、物件探しからトータルでサポート。徹底した運用フォローで満室経営を実現するとともに、出口戦略もしっかりとご提案いたします。アパート経営に向けて物件探しをご希望の方は、ぜひ【リロの不動産】までご相談ください。
おすすめのサービス
おすすめのお役立ち情報
この記事を書いた人
秋山領祐(編集長)
秋山領祐(編集長)
【生年月日】昭和55年10月28日。
【出身地】長野県上田市。
【趣味】子供を見守ること。料理。キャンプ。神社仏閣。
【担当・経験】
デジタルマーケティングとリブランディングを担当。
分譲地開発のPMや家業の土地活用などの経験を持つ。
リノベした自宅の縁の下に子ども達の夢が描かれている。