アパート経営 法人化の完全ガイド|節税・融資・相続・タイミングを徹底解説!
2025.07.20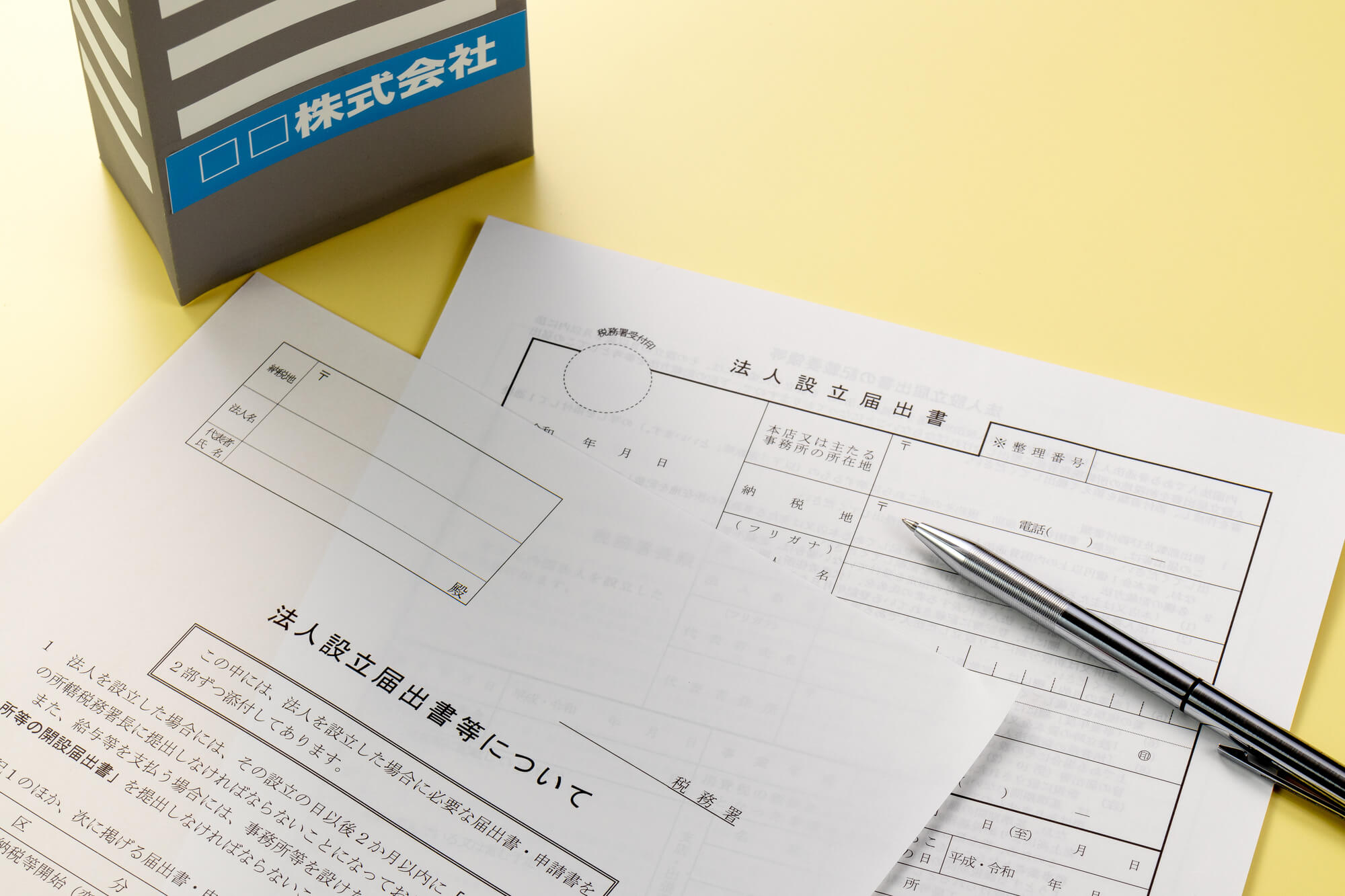
アパート経営が順調に進み、収益の規模が拡大してくると、法人化を検討する場面が出てきます。
どのタイミングで法人化すればいいのか、どういうケースが法人化に向いているのか、詳しくは分からないという方もいるのではないでしょうか。
この記事では、アパート経営の法人化についてメリット・デメリットはもちろん、具体的な手順や注意すべき点などを詳しく解説しますので参考にしてください。
▼この記事の内容
●アパート経営を法人化すると、①節税効果がある、②経費計上の幅が広がる、③欠損金の繰越期間が長い、④融資の面で有利になる、⑤認知症対策になる、⑥相続対策になる、というメリットがある。
●一方、①初期費用がかかる、②維持費用がかかる、③売却時税金が高くなるケースがある、④決算・申告が必要になる、⑤税務調査が入る確率が高まる、などのデメリットもある。
●個人から法人へ不動産の名義変更をする方法として、贈与、売買、現物出資がある。
●アパート経営法人化で注意すべきポイントとして、借入金がある場合は金融機関との協議が必要、会社員・公務員は慎重に対応する、専門家にアドバイスを求める、という点がある。
アパート経営の法人化については、こちらの記事もご覧ください。
■アパート経営の法人化に関連する記事
不動産購入は法人と個人どっちがお得?法人化するタイミングも解説
不動産投資は法人化がお得?節税対策につながるメリット・デメリット
目次
アパート経営の法人化とは
アパート経営の法人化とは、新たに法人(会社)を設立し、個人事業主として行っていたアパート経営をその法人が行う経営形態を指します。
アパートの経営自体は、個人でも行うことが可能です。その際、購入したアパートはオーナー様の名義となり、家賃は入居者様からオーナー様に毎月入ってきます。
法人によるアパート経営では、アパートの所有者は法人です。オーナー様は法人役員という立場になり、収入は役員報酬として受け取る形になります。また、家族を役員にすれば、家賃収入を家族にも分散させられるメリットがあります。
ほかにも、アパート経営の法人化には、税制上の優遇や経営の効率化が期待できるのもメリットです。アパート経営の法人化で期待できるメリットについては、後の段落で詳しく後述します。
アパート経営の法人化の2つのタイプ

アパート経営の法人には、大きく分けて「管理型法人」と「所有型法人」の2つのタイプがあります。所有権が個人と法人のどちらにあるのか、どのようなケースに向いているのかなど違いもあるため、まずは詳細を把握しておきましょう。
管理型法人
管理型法人は、土地や建物の所有権を個人に残したまま、管理業務は法人が行う形態です。アパート経営では、建物管理や入居者管理などの管理業務が発生しますが、管理型法人ではこの管理業務を行う部分を法人化します。
オーナー様は得た家賃収入のうち、一定部分を設立した法人に管理手数料として移転できます。また、実際の管理業務については、専門の賃貸管理会社に再委託する方法も可能です。
管理型法人としてアパート経営をする選択肢として、法人がアパートを一括借上し、第三者に転貸(サブリース)する方式もあります。
所有型法人
所有型法人とは、法人がアパートそのものを所有して経営を行う形態です。所有型法人には建物のみ法人で所有する方法と、土地・建物の両方を所有する方法があります。
土地・建物の両方を所有する方法の場合、家賃収入はすべて法人のものとなり、オーナー様へは役員報酬として支払われます。建物のみ法人で所有する方法では、家賃収入からオーナー様へ地代が発生します。
所有型法人は管理型法人に比べ、オーナー様個人から法人へ所得が大きく移転しますので、節税効果が大きくなります。また、建物のみ法人で所有するか、土地・建物の両方を所有するかの判断については、個人から法人への不動産の移転時に譲渡所得税や贈与税が大きく変わり、相続の際にも手続きが変わりますので、専門家の意見を取り入れて行うようにします。
アパート経営法人化のメリット
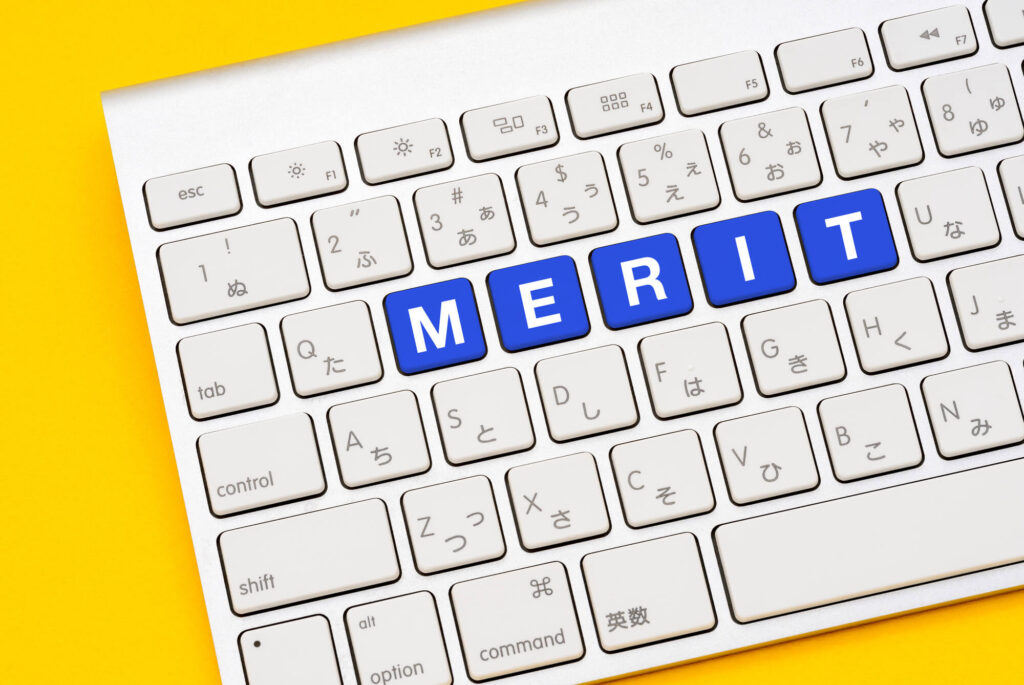
アパート経営を法人化すると、具体的にはどのようなメリットがあるのでしょうか。メリットになる部分を把握しておくことで、より効率的なアパート経営が可能です。6つのメリットを挙げ、それぞれ詳しく解説していきます。
アパート経営法人化のメリット①節税効果がある
アパート経営を法人化する大きなメリットは、節税効果です。
個人の所得税は、課税所得が大きくなるほど税率も高くなります。所得税率は課税所得900万円未満ならば23%(控除額63万6,000円)ですが、900万円以上になると33%(控除額153万6,000円)になります。さらに1,800万円以上では40%(控除額279万6,000円)、4,000万円以上になると45%(控除額479万6,000円)です。
一方で、法人税率は原則23.2%です。これは法人の所得がどんなに大きくなっても税率はかわりません。さらに、中小法人については軽減措置があり、年800万円以下の所得金額の部分については、税率が15%となります。
個人では課税所得が900万円以上になると一気に税率が33%に上がるため、法人化したほうが節税になるのがわかります。
ただし、課税所得は家賃収入とイコールではありません。不動産所得は、家賃収入から固定資産税などの税金や減価償却費、保険料、管理委託費などの必要経費を差し引いた分で、家賃収入の合計ではありません。
また、給与所得や事業所得など不動産所得以外にも所得がある場合、すべてを合算しそこから所得控除を行った金額が所得税を計算するもととなる課税所得になります。ほかの収入と合算して課税所得が900万円以上になれば節税効果が期待できるため、法人化を検討するタイミングだといえるでしょう。
アパート経営にかかる税金については、以下の記事もご覧ください。
■アパート経営の税金に関係する記事
家賃収入にかかる税金はいくら?設備投資と損益通算で考える節税対策
【事例付】不動産売却の譲渡損失の損益通算!基本知識と注意点を解説
アパート経営法人化のメリット②経費計上の幅が広がる

法人は経費として認められる費用の範囲が広い点も、アパート経営を法人化するメリットです。個人で事業を行っていると、経費計上できる範囲は限定的です。
一方で、法人は基本的に利益を追求して事業を展開している存在であることから、経費として認められる範囲が広くなっています。法人化すると、オーナー様や役員となっているご家族に対する役員報酬や給与の支払いができるため、「所得の分散効果」もあります。その役員報酬は、経費として計上できる項目です。
アパート経営のために、社長が出張した際の旅費交通費や日当も経費計上が可能です。経費を多く計上できれば、その分だけ課税所得の額を下げられるため、節税につながります。
アパート経営法人化のメリット③欠損金の繰越期間が長い
繰越欠損金を繰り越しできる期間が長いのも、アパート経営を法人化するメリットです。課税所得がマイナス、つまり赤字が出た場合、税務上は赤字になったときの金額を欠損金といいます。
法人税(正確には法人税・法人事業税・地方法人税・特別法人事業税の4種)の税額は課税所得の金額で決まってくるため、赤字になった年は全額免除となります。翌年も基本的には、またその年の課税所得に応じて法人税が課されますが、所定の要件を満たすと、欠損金を翌年以降に繰り越せる繰越欠損金制度を利用できます。
例えば欠損金が100万円ある状態で、翌年は黒字が40万円あったとすると、相殺してもまだ翌年の課税所得がマイナス60万円の赤字です。さらに次の年の黒字が10万円だった場合、相殺しても課税所得はまだマイナス50万円で、赤字が残っています。繰り越してその年の黒字と相殺しても課税所得が赤字のうちは、法人税が課されません。
個人の場合は繰越期間が3年しか取れないため、その期間が過ぎると欠損金が残っていても、4年目からは相殺できないことになります。一方で、法人は繰越期間が10年あるため、長期的な節税が可能です。ただし、繰越欠損金制度を利用するためには、欠損金が生じた年に青色申告をしている必要があります。
アパート経営法人化のメリット④融資の面で有利になる
一般的に、個人事業主に比べて、法人のほうが社会的信用度は高いとされています。法人として登記されると、社会的には公的機関に存在を確認された組織になるからです。第三者にとっては公的機関に認められた組織という点が安心感につながり、信用も得やすくなります。
また、法人になると複式簿記による帳簿付けを行い、毎年決算書類を整えて申告しなければなりません。そのため、同じアパート経営をしていても、金融機関側からすると法人のほうが財政状態や経営状況を確認しやすいのです。その分、金融機関からの融資も有利に働く場合があります。
アパート経営法人化のメリット⑤認知症対策になる
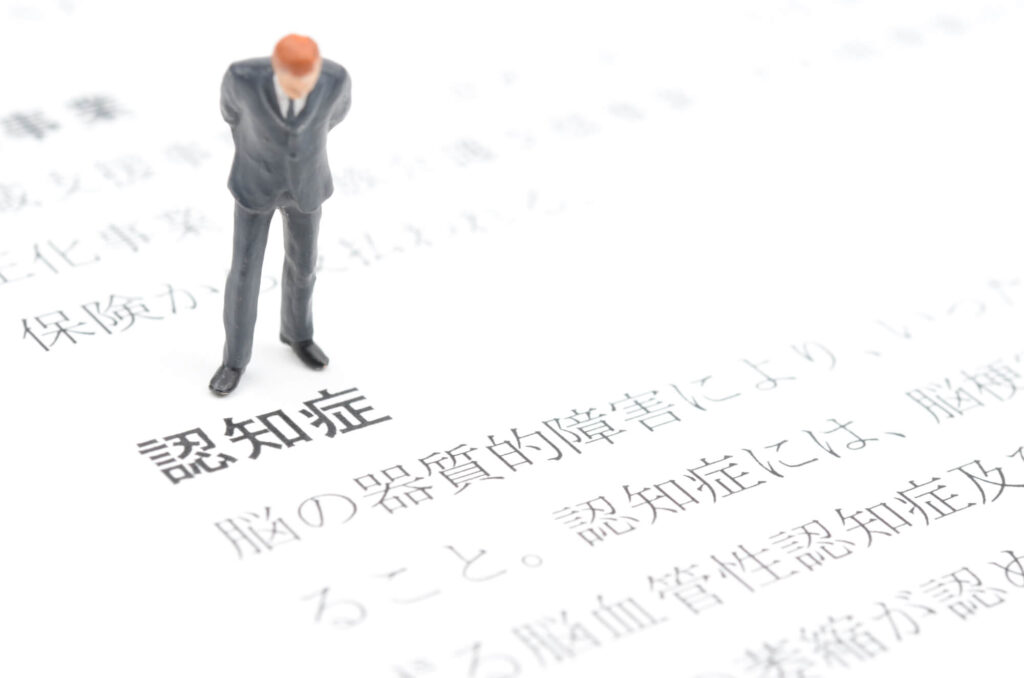
アパート経営を法人化しておくメリットとして、万が一、オーナー様が認知症を発症したときの備えになることも挙げられます。認知症を患うと財産の管理が難しくなるのはもちろん、法律行為もできなくなるからです。不動産売買契約、賃貸借契約ができないばかりか、更新契約・家賃交渉・リフォームの発注すらできなくなります。
個人の名義になっているアパートでは、たとえ子どもであっても代理の権限がなければ、資産を動かす手続きはできません。もし、修繕費用をオーナー様の口座から出金したいと思っても、出せないのです。
オーナー様以外の第三者に財産の管理を委ねるためには、成年後見制度を利用する必要があります。しかし、実際に認知症を発症してしまってからさまざまな手続きをしていると、アパート経営が滞る可能性もあるでしょう。
アパート経営を法人化して家族が役員になっていると、オーナー様が認知症になっても、役員が法人の口座から修繕費用を出せます。法人化することで、ほかの役員によって通常どおりの経営が続けられるため、認知症対策としても有効です。
アパート経営法人化のメリット⑥相続対策になる
アパート経営を法人化するメリットの6つめは、相続対策としても有効なことです。相続対策については、相続税の節税と遺産分割、事業承継の3つにそれぞれ的を絞り、各場面でどのようなメリットがあるのか掘り下げて解説します。
相続対策については、以下の記事もご覧ください。
■アパートの相続対策に関連する記事
【高額納税者必見】高所得者向け節税対策とは? 不動産投資と資産管理会社
不動産投資が相続税対策に選ばれている理由は?5つの節税対策も紹介
アパート経営は相続対策に有効!資産管理会社の活用でメリット拡大
相続税の節税
個人の名義でアパートを所有していると、毎年得られる不動産所得はオーナー様の財産になります。使わずにいると毎年財産は蓄積されていき、いざ相続が発生した際にはすべてが課税対象となり、多額の相続税がかかってくる可能性もあるでしょう。
一方で、アパート経営を法人化し、配偶者や子どもなどの将来相続人になる家族を役員にしておけば、不動産所得を役員報酬という形で分散させられます。年数をかけて財産を移動させておくことで相続税の節税になるのはもちろん、相続人が相続税の納税準備ができたり、資産形成にもなったりします。
法人の相続では、相続財産は法人の株式になります。株式は非上場株式なので、法人全体の資産評価にもとづいて株価が決められます。法人の評価を下げることによって、相続税評価額を圧縮できます。
評価の下げ方としては、借入金を増やして純資産を減らす、役員退職金を支給する、法人向け保険商品を活用するなどの方法があります。
遺産分割が容易になる

オーナー様が個人で財産を所有している場合、相続が発生すると経営しているアパートも遺産分割の対象になります。遺産分割協議によって相続財産を相続人が分割するのですが、土地や建物などの実物資産は現金や株式などのように、等分に分割することができません。そのため、相続人の間で不平等が生じることも考えられます。
アパート経営を法人化していると、財産は不動産から株式になっているため、遺産分割では株式を各自の相続分に応じて分けやすく、遺産分割がスムーズに進みます。例えば、法人の株式が400株あり、相続人が配偶者と子2人であれば、配偶者200株、子が100株ずつ相続すれば法定相続通りの遺産分割になります。
事業承継にも有効
アパート経営が法人化されていれば、スムーズな事業承継にも役立ちます。将来相続人となる家族を法人の役員とし、報酬や給与の形で支払えば、生前贈与にはあたらないため贈与税も発生しません。(ただし、アパート経営に関する勤務実態がないのに、報酬・給与を拠出すると違法行為になります。)
アパート経営を事業承継させたい相続人が決まっている場合にも、法人は役に立ちます。例えば事業承継される相続人を長子とすると、長子には普通株式を相続させ、そのほかの相続人には譲渡制限付株式や議決権制限株式を相続させます。そうすると、相続発生後もアパート経営について意見が紛糾せず、長子のイニシアティブで事業が承継されます。
また、個人の所有にしていると、入居者様との賃貸借契約や水道光熱費の契約、預貯金の名義などもすべてオーナー様名義になっています。法人化していれば、名義は法人であるため、名義変更などに手間や時間をかけることもありません。
アパート経営法人化のデメリット
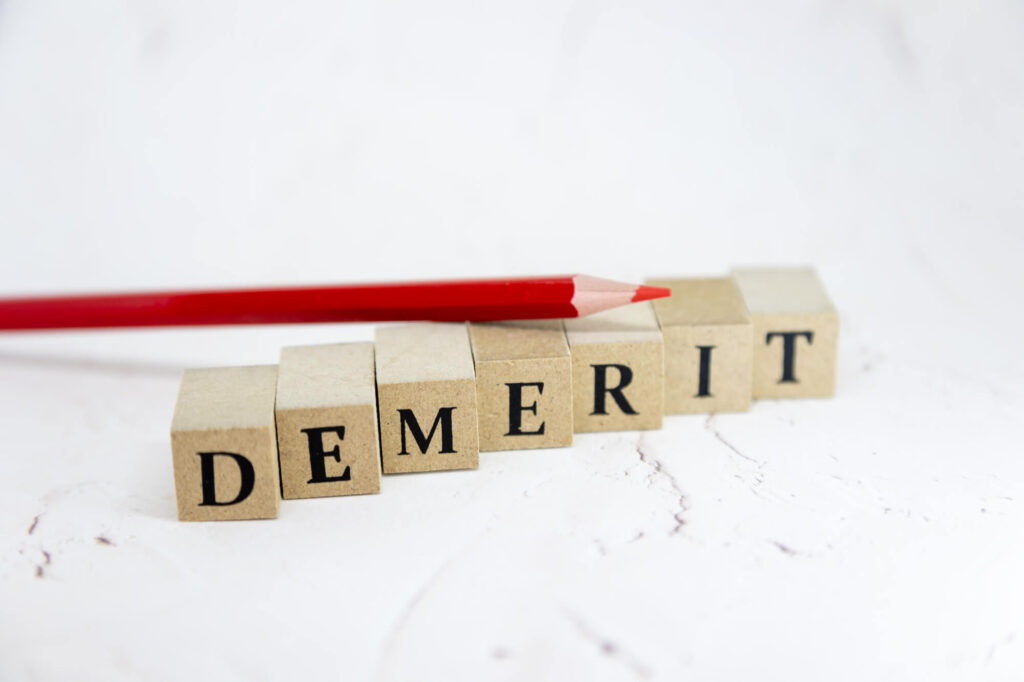
アパート経営の法人化にさまざまなメリットがあることを解説してきましたが、デメリットがないわけではありません。法人化を考えるためには、デメリットもふまえておく必要があります。
主に考えられる5つのデメリットについて解説します。
アパート経営法人化のデメリット①初期費用がかかる
法人の設立には初期費用がかかります。費用は、登録免許税や定款認証費、印紙代や謄本手数料などです。法人を設立する際は、設立する場所を管轄する法務局に申請し、登記を行わなければなりません。
例えば株式会社を設立する場合、登録免許税の金額は15万円または資本金の額に1,000分の7を掛けた金額のうち、大きいほうの額です。
合名会社・合資会社の登録免許税は6万円、合同会社は6万円または資本金の額に1,000分の7を掛けた金額のうち大きいほうの額になります。
ほかにも定款の作成が必須です。そのため、定款認証費として3万円または5万円、印紙代に4万円(電子定款の場合は不要)がかかります。謄本手数料として数千円程度も必要です。
手続きを司法書士に依頼すると、5~10万円程度の司法書士報酬も発生します。不動産をオーナー様の個人名義から法人名義に変更した段階で、不動産の登録免許税や不動産取得税の支払いも必要になってきます。
アパート経営法人化のデメリット②維持費用がかかる
法人の設立後も、維持費がかかってくるのはデメリットになります。どの形態の会社であっても、基本的に法人として事業を営んでいれば、法人税のほか、法人事業税や法人住民税なども納めなければなりません。
税金の金額は所得や資本金の金額によって決まりますが、特に注意する必要があるのは法人住民税です。法人住民税は、不動産所得が赤字だったとしても課されます。税額は資本金の額や従業員数によって区分が分かれており、都道府県民税・市町村民税を合わせて最低でも7万円は課税されます。
また、従業員を雇う場合は、厚生年金保険料や健康保険料などの費用も考慮に入れておかなければなりません。維持費用を上回る節税効果が見込めないようなら、経費倒れになる可能性があります。
アパート経営法人化のデメリット③売却時税金が高くなるケースがある
アパート経営では、出口戦略も考えておく必要があります。いくらアパート経営が順調だったとしても、売却時に大きな損失がでれば積み上げてきた収益が吹き飛んでしまい、不動産投資としては成功したとはいえません。そのため、最終的に所有している物件を売却した際、トータルでプラスがでるかどうかが重要です。
不動産を売却すると、譲渡所得税がかかってきます。個人名義の不動産の場合は、所有期間(基準日が譲渡年の1月1日)が5年以下か、5年を超えるかで税率が変わってきます。所有期間5年以下で売却すると短期譲渡所得となり、税率は住民税と2037年まで課される復興特別所得税を含めて39.63%になります。
一方で、所有期間が5年を超える長期譲渡所得に該当する時期になってから売却すると、譲渡所得の税率は20.315%です。しかし、法人の場合は所有期間に関係なく法人の事業として得た所得となり、税金も法人税として課されます。
ケースによっては法人のほうが税金が高くなるため、注意してください。
アパート経営法人化のデメリット④決算・申告が必要になる
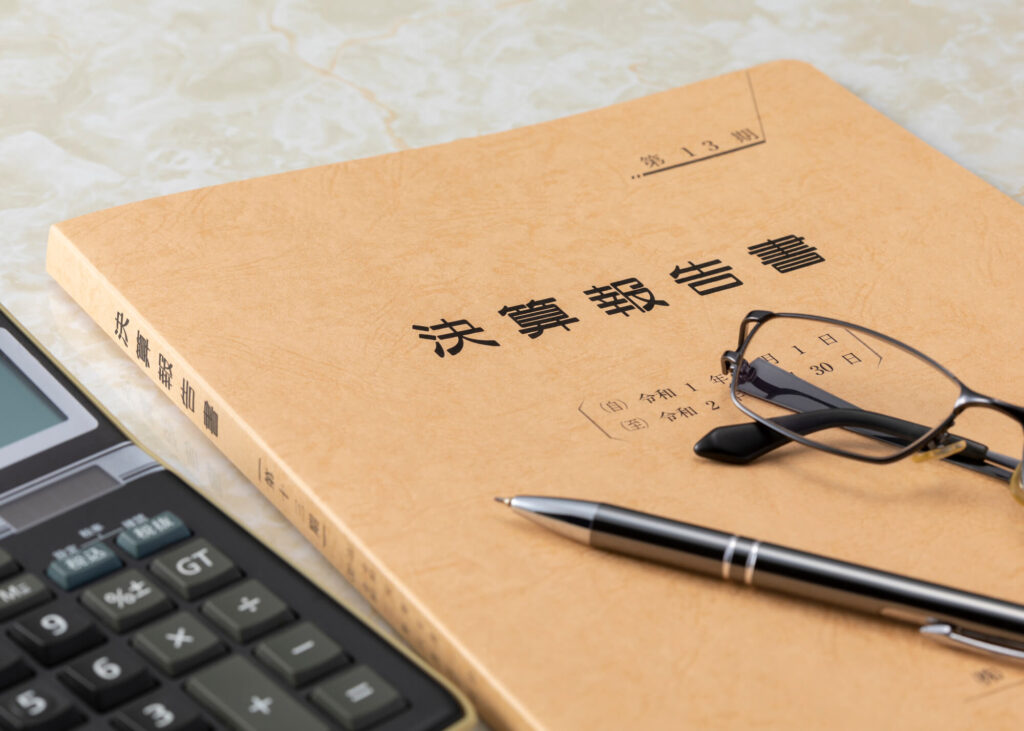
アパート経営を法人化すると、当然ながら法人としての運営が求められます。会計処理においても個人事業主とは違い、まず日々の取引は複式簿記で帳簿を作成しなければなりません。事業年度ごとに損益計算書や貸借対照表などの決算書類も作成する必要があるため、会計処理の手間は増えるでしょう。
また、納める税金は法人税や法人住民税、法人事業税などに変わります。個人の場合は収支を計算して確定申告を行いますが、法人になると事業年度ごとに所得額を計算し、事業年度終了日から2ヶ月以内に法人税の申告をしなければなりません。
個人が納める所得税や住民税などとは申告方法が変わるうえ、計算方法も複雑になるため、決算や税務申告に関連する専門的な知識が必要です。会計処理をスムーズに行うためには、会計ソフトなどを導入するのも選択肢のひとつでしょう。
税理士との間で顧問契約を結ぶ必要もでてくるため、年間20~50万円程度のコストが発生します。
アパート経営法人化のデメリット⑤税務調査が入る確率が高まる
個人事業主よりも法人のほうが、税務調査を受ける確率が高いとされています。もちろん、個人でアパート経営をしていても税務調査が入ることはありますが、割合は0.3%程度です。一方で、法人になると約10倍の3%程度の割合になり、個人でアパート経営しているよりも税務調査が入る可能性は高くなっています。
黒字であるほど、また事業規模が大きいほど、税務調査の対象になりやすい傾向です。多すぎる役員報酬を経費として計上していないか、明確な理由がない支出を接待交際費として計上していないかなど、注意すべき点はいくつかあります。
万が一、帳簿などに不備があると、追徴課税されるケースもあるため注意してください。日頃から正確に帳簿を作成し、正しく保管しておきます。また、専門家である税理士に毎月チェックしてもらい、密に連携を取っていればリスクの回避につながります。問題があったとしても、早めに把握できれば対処もできるでしょう。
法人化のタイミング

法人化に踏み切るには、適切なタイミングがあります。効果的に法人化を図るためには、法人化するのに向いているタイミングを知っておかなければなりません。アパート経営法人化のタイミングとして考えられるのは、主に以下の3パターンです。
アパート経営法人化のタイミング①不動産所得が1,000万円を超える
答えからいうと、アパート経営の所得が1,000万円を超えたあたりが、法人化を検討する目安のひとつになります。理由は所得が上がると、法人税の税率よりも所得税の税率のほうが高くなってしまうからです。
法人税の税率は、法人所得が高くても23.2%です。個人の所得税を見ると、課税所得が695万円から900万円未満までの間は税率が23%で、まだ法人税の税率を超えていません。しかし、900万円以上になると所得税の税率は33%になり、法人税の税率を超えてしまいます。
個人の所得税は課税所得が大きくなるほど税率も高くなる累進課税制度が取られていることもあり、そのまま所得が上がっていくと、さらに多くの税金を支払わなければならなくなります。
不動産所得が1,000万円程度になることが見込まれる場合は、選択肢のひとつとして法人化を考えてみましょう。ただし、法人化すると個人経営のときには必要がなかったコストも発生するため、法人化によってかえって赤字になることがないかどうか、タイミングは見極めなければなりません。
アパート経営法人化のタイミング②相続を控えている

子どもなどに所有しているアパートを相続させることが決まっているのであれば、時期をみてアパート経営を法人化しておくのが有効です。アパート経営法人化のメリットでも挙げたように、法人化は相続対策になります。
個人事業主としてアパート経営を行っている場合、オーナー様所有の財産が多いほど、相続税の税額も大きくなります。実際に相続が発生した際、あまりに相続税が高くなると、相続人に負担をかけてしまう可能性もあるでしょう。
アパート経営を法人化しておくと、アパートの所有者は法人です。将来的に相続が発生しても、アパートは被相続人個人の財産ではないため、相続人にはその分の相続税がかかりません。相続が控えている場合は、相続税対策として株式を利用するのが有効です。法人化する際にあらかじめ相続人を株主にしておくことで、相続税の圧縮が可能になります。
アパート経営法人化のタイミング③相続直前の法人化は注意が必要
アパート経営の法人化は、相続対策として有効であるのは間違いありません。ただし、タイミングを間違えると、かえって相続税が高額になる可能性があるため注意が必要です。
個人から法人へ不動産を移転した場合、移転から3年以内は当該不動産は相続税路線価・固定資産税評価額ではなく、時価で評価されます。
アパートが時価で評価されると自社株の評価額も高まり、相対的に相続税も高額になります。アパートの購入から3年経過すると時価よりも低い相続税評価額を用いることができますが、それまでに相続が発生すると、相続人が納めるべき税金は高くなる恐れがあります。
もちろん、相続がいつ発生するか正確に予測するのは不可能です。しかし、持病があって体調がすぐれないなど、3年を超えないうちに相続が発生するリスクが高い状況ならば、法人化は慎重に進める必要があるでしょう。
個人から法人へ不動産の名義変更をする方法
アパート経営を法人化する際、不動産の名義は個人から法人に変更しなければなりません。名義変更にも3つのパターンがあり、必要な手続きや手順が違ってきます。以下で「贈与」と「売買」、「現物出資」の3つの方法について解説します。
贈与
不動産の名義を個人から法人へ変更する方法として、贈与という選択肢があります。贈与は民法549条において、「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」と規定されています。
手続きでは、まずは利益相反承認決議が必要です。利益相反とは、ある行為が一方にとっては利益になるものの、他方には不利益になることを指します。つまり、贈与ではアパートを譲るオーナー様にとっては利益を手にすることがないため、利益相反を承認する必要があるのです。その後は贈与契約を結び、法人名義で不動産登記を行います。
個人から法人への名義変更では、後述する売買や現物出資に比べて手続きは分かりやすいかもしれません。ただし、贈与された金額が1年間で110万円以下ならば贈与税はかかりませんが、不動産を贈与する場合は金額が大きくなる可能性があります。ケースによっては多額の贈与税が発生することも考えられるため、利用する際は注意してください。
売買
売買は個人が法人に不動産を売却し、設立した法人がオーナー様からアパートを購入する方法です。もともとアパートの所有者であるオーナー様とオーナー様が代表者を務める法人との間の契約では、売買価格が適正であるかどうかに注意しなければなりません。
一般的な不動産売買では価格を決める際、近隣の類似物件の価格なども参考にしながら、あまり相場とかけ離れない金額を設定します。しかし、法人設立をきっかけにオーナー様から法人にアパートを売却する場合は、実質的には「自分で自分に売る」ようなものです。そのため、明確な基準がなく、極端に安い金額にしても取引としては成立してしまいます。
ただし、あまりにも適正価格とかけ離れた低い金額にすると、税務署の監査で贈与とみなされる可能性があるため、適正価格に近づけることが大切です。手続きでは贈与と同様に利益相反承認決議を行ったうえで売買契約を結び、不動産登記を行います。なお、売買によって譲渡所得が発生した場合は、譲渡所得税がかかります。
現物出資
現物出資は法人の代表者である個人が、金銭のかわりに不動産を出資する形式を取る方法です。現物出資を原因として不動産の所有権がオーナー様から法人に移り、名義変更が可能になります。売買の手続きでは売買の価格を自由に決められますが、現物出資では出資する財産の価値を評価することが求められます。
不動産に関しては、不動産鑑定士による不動産鑑定評価と税理士の証明書が必要です。顧問税理士がいるのであれば、税理士の証明書は顧問税理士に依頼すればいいでしょう。しかし、不動産鑑定評価は専門の国家資格を持つ不動産鑑定士にしかできないため、別途依頼する必要があります。
また、現物出資では不動産を法人に出資したことになり、資本金も増加します。そのため、現物出資の方法を取る場合は不動産の名義変更だけではなく、資本金増資の商業登記も行わなければなりません。現物出資では不動産鑑定士や税理士など、専門家に依頼するためのコストがかかる点をふまえておいてください。
会社形態の種類と特徴
法人を設立する際は、会社形態も決めなければなりません。アパート経営の法人化で考えられるのは「株式会社」と「合同会社」、「合資会社」と「合名会社」の4つです。それぞれの会社形態について、特徴を詳しく解説します。
株式会社
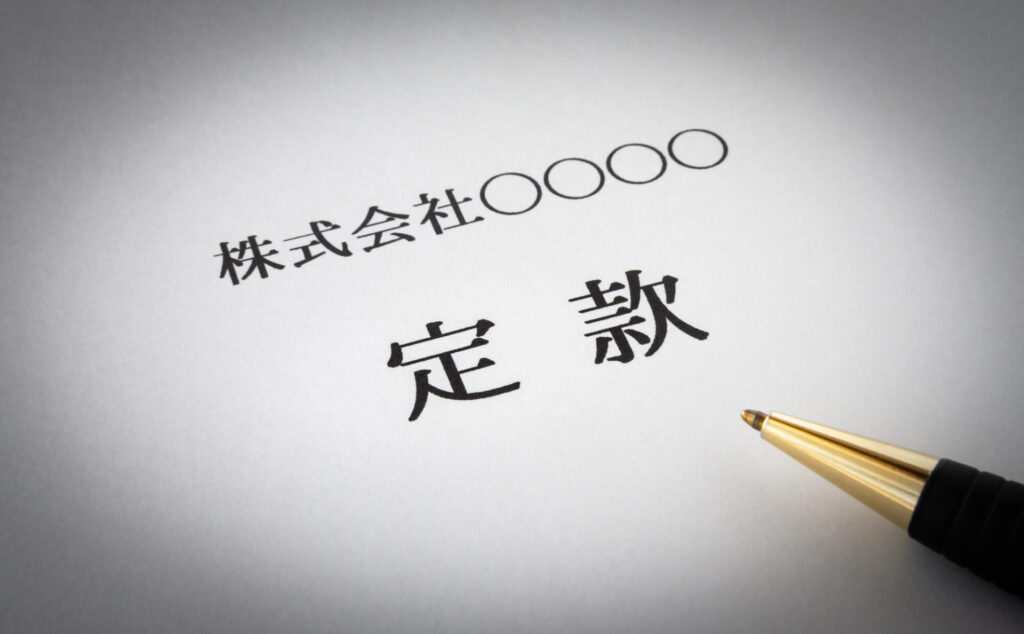
株式会社は株式を発行することによって資金調達が行える会社の形態です。出資者は株主と呼ばれ、1名以上の株主と資本金1円以上があれば、株式会社が設立できます。株式会社では、所有と経営が分離されているのが特徴です。
株主が開く株主総会で選ばれた人物が経営者として事業を行い、利益が出れば株主に配分できるのはメリットでしょう。独立性が高く、法人としては継続性が高い会社形態です。また、株式を公開すれば、より多くの投資家から資金を調達できることもあり、大規模経営に適しています。
出資者は有責責任であり、出資した範囲においてビジネスに責任を負う仕組みです。株式会社には毎年決算公告の義務を負い、株主などに経営状況や財政状態を明らかにする義務があります。
合同会社
合同会社は株式会社とは違い、持分会社(もちぶんがいしゃ)という形態です。出資者全員が経営者として決定権を持つ形で、2006年の会社法改正で新しく設けられました。設立費用が安価であることから、小規模経営に向いています。
設立時に定款の認証を受ける必要がなく、決算公告の義務もないため、設立までのハードルも低いというメリットがあります。出資者と経営者が一致していることで事業にスピード感があり、かつ柔軟な運営が可能です。
利益分配なども自由に決められます。出資者の立場は有限責任で、出資した以上の金額を弁済する責任は負っていません。また、特に役員の任期には定めがないため、継続して役員でいることができます。上場はできませんが、合同会社設立後に株式会社に組織を変更する道はあります。
合資会社
合資会社も小規模事業に適している持分会社の会社形態です。合同会社と同様に手続きが比較的簡単で、設立時にかかる費用やランニングコストが抑えられるのはメリットでしょう。決算公告の義務もなく、資本金も不要です。
有限責任社員と無限責任社員の両方で構成されている特徴があるため、会社を設立するためには最低2名が必要です。万一、倒産した場合、有限責任社員は出資した金額の範囲内でしか責任を負いませんが、無限責任社員はすべての責任を負わなければならず、負担が大きくなる可能性があります。
合名会社
合名会社は、無限責任社員だけで構成される持分会社の会社形態です。合同会社や合資会社と同じく、会社を設立するハードルが低く、設立費用も低く抑えられます。最低出資者数は1名です。
出資者が無限責任を負うという点では、個人事業主と同じであるといえるでしょう。2名以上の出資者がいる合名会社では、複数の個人事業主が共同で会社を作っているようなイメージです。出資者が経営者でもあり、ひとり一人の個性が重視される特徴があります。
アパート経営を法人化する流れ
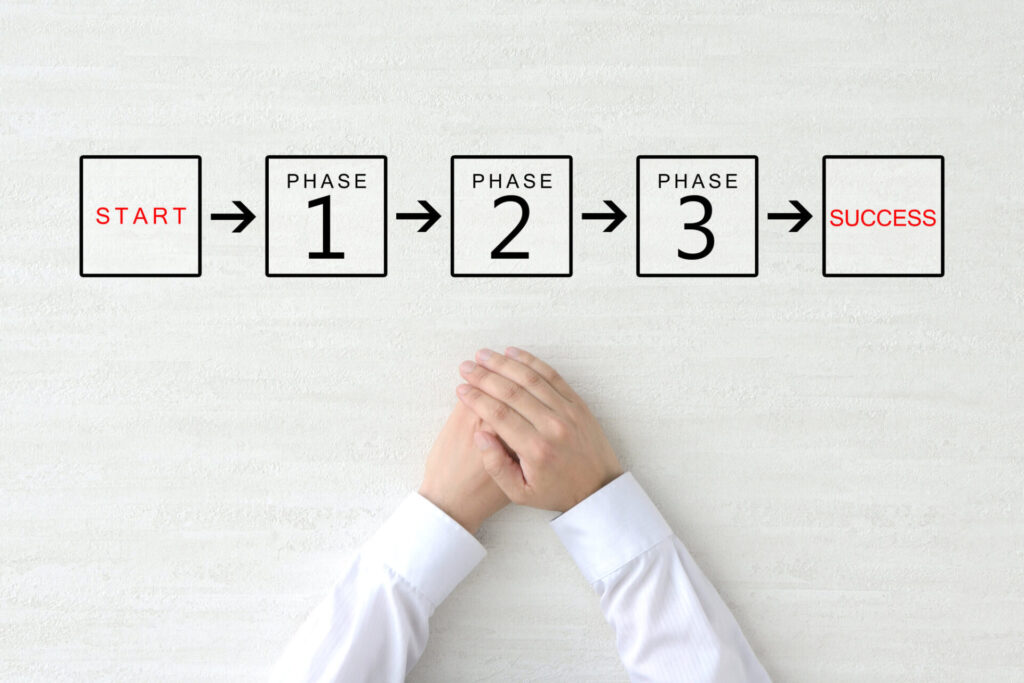
では、アパート経営を法人化することが決まったら、具体的にどのような手続きを踏めばいいのでしょうか。所有方式や会社形態を決めるところから運用開始まで解説しますので、手続きをスムーズに進めるためにも流れを把握しておきましょう。
所有方式を決める
アパート経営を法人化する際、これから設立する法人の基本的な情報を検討するところから始めましょう。まず、所有方式はどうするのがオーナー様の状況に合っているでしょうか。アパート経営の法人化には、大きく分けて管理型法人と所有型法人の2つのタイプがあることをすでに解説しました。
管理型法人はアパートの土地・建物はオーナー様の所有のままで、管理業務を法人が行う形態、所有型法人は法人が不動産を所有して賃貸経営を行う形態です。
管理型法人では管理手数料が法人の売上になり、オーナー様はその分を必要経費として差し引けるメリットがありますが、節税効果が限定的です。
所有型法人にする場合、土地・建物を所有する方法と建物だけを所有する方法があります。管理型法人と所有型法人の特徴を再確認し、オーナー様の経営スタイルに合った方式を選択してください。
会社形態を決める
法人をどのように運営していくのか、株式会社や合同会社などの会社形態も選択しなければなりません。会社形態は先述したように、株式会社・合同会社・合資会社・合名会社の4種類ありますが、登記されている会社で圧倒的に多いのは株式会社です。
持分会社の合同会社・合資会社・合名会社のうちでは、合同会社が多くなっています。合資会社と合名会社は知名度も低く、2006年の会社法施行で合同会社が新たな会社形態として加わって以降、あまり選ばれていません。よって、アパート経営を法人化する場合、株式会社または合同会社を選択するのが一般的です。
株式会社は出資を募って大規模に事業を展開しやすい会社形態ですが、初期費用やランニングコストがかかるうえ、手続きに手間もかかります。合同会社は比較的設立しやすく、小規模事業に向いている会社形態です。経営の規模や資金調達の必要性などを考慮し、オーナー様のアパートの経営状況に応じて選んでください。
法人設立の準備と設立登記

所有方式と会社形態が決まったら、法人の名称や資本金額を決定し、事業目的の設定と役員構成の検討を行いながら、必要書類もそろえて準備を進めましょう。
法人を設立するためには、基本的なルールを定めた定款を必ず作成しなければなりません。株式会社を設立する場合は、公証役場で定款の認証手続きを経る必要があります。合同会社や合資会社、合名会社は認証が不要です。法人の設立登記のために、登記申請書や資本金の払い込み証明書などの必要書類も用意してください。
登記の手続きは法務局の窓口や郵送に加え、オンラインでも申請できます。オーナー様が自分で手続きを行うことも可能ですが、申請書類に不備があると再提出しなければならなくなる可能性もあり、余計な手間がかかるでしょう。
さまざまな手続きを自分でするのが難しいようならば、司法書士や税理士などの専門家に依頼するのがおすすめです。その分、諸費用はかかってしまいますが、複雑な手続きは専門家に任せて、オーナー様はほかの手続きや本業に専念できます。
所有権を移転する
所有型法人を選択したケースでは、アパートの所有権を法人名義に変更する手続きを行う必要があります。不動産の所有権が新たな所有者に移ったことを明確にするための手続きが、所有権移転登記です。
不動産を個人名義から法人名義に変更する方法には、贈与と売買、現物出資の3つがあると解説しましたが、いずれにしても所有権移転の手続きはしなければなりません。所有権移転登記を行い、新たに不動産を取得すると、登録免許税や不動産取得税などの税金がかかってきます。
登録免許税は登記の手続きと同時に納める国税です。不動産取得税は都道府県民税で、不動産の取得から数ヶ月経ったころに納税通知書が送付されてくるため、期限までに納めます。
所有権移転登記の手続きも、オーナー様が自分ですることは可能です。しかし、法人の設立登記と同様に、必要書類を集めたり、申請書類を準備したりするには手間も時間もかかるため、司法書士報酬などの諸費用はかかりますが、専門家に依頼するのも選択肢でしょう。
契約の変更
アパートの所有者が変わったら、それまでオーナー様名義の契約だった部分を法人名義に変更してください。具体的には、入居者様、賃貸管理会社、保険会社、家賃保証会社などとの契約を変更する必要があります。
アパートの所有者が法人に変わったら、あらためて入居者様と新たに設立した法人との間で賃貸借契約を締結し直し、新しい家賃の振込先も伝える必要があります。
長く住み続けてもらいたい入居者様への対応には、特に細心の注意を払ってください。アパートの所有者がオーナー様個人から法人に変更される旨をしっかり説明し、生活に大きな変化がないことを伝えましょう。入居者様に不安を抱かせないためにも、丁寧な対応が大事です。
運営開始
法人設立や所有権移転登記の手続きが完了し、各種契約の変更を終えたら、いよいよ法人名義での運営を開始できます。個人名義から法人名義にアパートを変更すると、登記のほかにもしなければならない初期の運営手続きがあるため、順次対応していきましょう。
税務署には、開業届を提出する必要があります。届出には法人設立届出書のほか、状況に応じて給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書や源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書、青色申告の承認申請書などの書類が必要です。資本金または出資金が1,000万円以上ならば、消費税の新設法人に該当する旨の届出書も必要になります。
それぞれ提出期限が定められているため、期限内に提出できるように準備しなければなりません。なお、個人事業主としての届出をしている場合は、個人事業主の廃業届も提出する必要があります。法人としてアパートを運営していくために、役員報酬の設定や社内規定の整備、銀行口座の開設や経理システムの構築などの体制も整えてください。
アパート経営法人化で注意すべきポイント
ここまでアパート経営法人化についてメリット・デメリットや法人化のタイミング、名義変更や会社形態、法人化の流れなどを解説してきました。ここまで解説してきたこと以外の注意すべきポイントについて、3つを解説します。
借入金がある場合は金融機関との協議が必要

アパート経営を始めるにあたって、その資金をアパートローンなどの融資でまかなっているケースが多いのではないでしょうか。ローンを活用することでレバレッジを効かせ、自己資金だけでは叶わない大きなリターンを得られるのが不動産投資の醍醐味です。ただし、ローン返済中の物件を個人名義から法人名義に変更するためには、借り換えが必要になります。
ローンが完済されていなければ、アパートには金融機関の抵当権が付いています。その状態で変更を加えるためには、そもそも金融機関に了承してもらわなければなりません。また、ローンの名義もオーナー様個人から、法人に変更する必要があります。
具体的な手続きとしては、ローンを個人名義から法人名義に借り換え、以後は法人がローンの残債を返済していくという形になるでしょう。なお、手続きにともない、アパートローンの解約手数料や借り換え先ローンの事務手数料などの費用が発生します。ローン返済中のアパートを法人化する場合は、融資を受けている金融機関と協議し、手続きを行ってください。
会社員・公務員は慎重に対応
会社員や公務員としての本業がある方の場合、アパート経営の法人化には注意すべきポイントもあります。最近では副業を認める企業なども増えてきましたが、まだまだ副業を認めていないところが多いかもしれません。しかし、副業禁止の会社員や公務員でも、事業的規模未満であれば、不動産投資は認められます。
親などからアパートを相続するケースもあり、アパート経営のような不動産投資は必ずしも副業には該当しないからです。ただ、一定以上の規模になると事業だとみなされてしまう可能性があるため、法人設立が事業的規模に該当するか否かを判断する必要があります。
基本的にはアパートの規模が5棟10室より小さい規模、家賃収入が年間500万円未満、管理業務を自分で行わないなどの条件を満たしていれば事業的規模にはなりません。会社員の方は就業規則、公務員の方は担当部署で念のため確認しましょう。オーナー様本人が代表になって法人を設立するのが難しい場合は、家族を代表にするなどの対策が必要になります。
専門家にアドバイスを求める

実際にアパート経営を法人化しようとすると、さまざまな手続きにおいて法律上、または税務上の専門的な知識が必要になります。アパートの名義を法人に変更する際は、贈与契約や売買契約を締結する手続き、現物出資では不動産鑑定士や税理士に必要書類を作成してもらうなど、さまざまな場面で専門家の協力は必須です。
不動産の所有権移転登記や法人の設立登記の申請も、オーナー様が自分ですることも可能だとはいえ、実際には大変な労力がかかるため、実務上は司法書士に依頼することになります。法人化手続きの過程でさまざまな分野の専門家にアドバイスを求め、協力してもらう必要があるでしょう。
まとめ

アパート経営の法人化は、所得税の節税や相続対策として効果が得られるのは大きなメリットです。しかし、実際に法人化する際は、設立コストや運営にかかる手間を考慮する必要があります。法人化のタイミングも十分検討しなければ、かえって経営を悪化させてしまうかもしれません。
法人化すると経営はもちろん、相続にも大きな影響を与えます。法人化には時間や手間がかかるため、税理士や司法書士などの専門家に相談したほうがスムーズに手続きが進むでしょう。アパートを健全に管理するためには、信頼できる賃貸管理会社の協力も重要です。
【リロの不動産】は4つの空室対策や安心の管理対応で、賃貸経営をサポートしています。アパート経営の法人化を検討しているのなら、相続対策を踏まえた資産活用にも対応している【リロの不動産】にご相談ください。
関連する記事はこちら
【アパート経営・賃貸経営入門】メリット・リスク・成功の秘訣をわかりやすく解説!
アパートローンを上手に利用するコツと注意点|住宅ローンとの違いは?
【総集編】アパート経営の利回りの目安は?不動産投資の指標と注意点
アパート経営の失敗体験談9選と回避方法!よくある失敗事例から学ぼう
アパート経営に必要な自己資金はいくら? 成功に導く出口戦略と資金計画
アパート経営の年収と暮らしとは?アパート経営の収入を上げる方法
失敗しない中古アパート経営とは? メリット・リスク・対策方法を解説
公務員はアパート経営できる? 公務員が不動産投資を始める意外なメリット
【事例付き】地主のアパート経営が資産保全・税金対策に有利な理由と注意点を解説
【事例付】アパート経営の成功率とは? 賃貸経営の手順とリスク対策
サラリーマン・会社員が副業で始めるアパート経営 メリット・デメリットから成功の秘訣まで
アパート経営・マンション経営で必要なメンテナンス!費用と注意点を解説
【事例付】アパート経営に必要な工事と実施時期!工事の依頼先と注意点
おすすめのサービス
おすすめのお役立ち情報
この記事を書いた人
秋山領祐(編集長)
秋山領祐(編集長)
【生年月日】昭和55年10月28日。
【出身地】長野県上田市。
【趣味】子供を見守ること。料理。キャンプ。神社仏閣。
【担当・経験】
デジタルマーケティングとリブランディングを担当。
分譲地開発のPMや家業の土地活用などの経験を持つ。
リノベした自宅の縁の下に子ども達の夢が描かれている。





















