収益物件の買い方!不動産投資の物件購入は目的設定と情報収集が重要な理由
2024.06.11
収益物件の購入は不動産投資の第一歩。不動産投資が成功するかどうかは、収益物件選びの段階で決まるといっても過言ではありません。しっかりと目的意識を持ったうえで、ご自分の投資プランに合った購入計画を立てる必要があります。
そこで今回は、不動産投資家が収益物件を購入するまでの心構えや注意点、実際の物件購入の流れなどを中心に解説しましょう。
収益物件購入の前に準備すること
不動産投資を始めるにあたって収益物件購入の前に準備するべきことは何か、基本となるポイントを4つ挙げてみましょう。
不動産投資の目的設定

不動産投資に限らず、何事もまずは行動の目的を設定しなければ、やるべきことが分からず迷走してしまいます。特に不動産投資では大きな金額が動きますので、安易な行動で間違った行動を取るわけにはいきません。
不動産投資の目的を明確にする理由は、目的によって購入する不動産の種類や規模が違ってくるためでもあります。例えば不動産投資の最終目的としては、以下のようなケースが想定できます。
・生活を少し豊かにする程度のキャッシュフロー獲得
・所得税・住民税の節税
・相続税対策
・老後のための資産形成
・FIRE(経済的自立)を視野に入れた資産形成
副収入程度の家賃収入を目指すのであれば、中古の戸建て賃貸住宅投資、中古の区分マンション投資から始めるという選択肢もありえますし、所得税・住民税の節税が目的なら築古の木造アパート一棟購入が適しているでしょう。
大きな資産を持ちたいのであれば、一棟アパート・一棟マンションを買い進めることになります。こうした資産は相続税対策にもなります。
資産形成の目的や規模に応じて投資すべき不動産の種類、規模、時期、さらに融資戦略が変わります。まずは何のために不動産投資を始めるのかについてを明確にして、不動産投資家としてのスタートラインに立ちましょう。
投資目的に合った物件の選び方についてはこちらで解説していますので、ぜひお読みください。
■投資用不動産・収益物件の選び方に関連する記事
賃貸マンションの一棟買いはあり? アパート経営・区分マンション経営との徹底比較
失敗しない中古アパート経営とは? メリット・リスク・対策方法を解説
マンション一棟買いの成功ポイントと指標にする利回り!メリット・デメリットや注意点
不動産投資の勉強
不動産投資について勉強しないまま大金を投じてしまうのは、リスクが高い行為と言わざるをえません。不動産投資のために勉強すべきことは膨大ですが、まずは基本となる知識を広く浅く網羅してください。基本的な知識があれば初歩的な事柄でつまずく確率は減りますし、不動産選びでも学んだ情報が役立ちます。
勉強内容は、
・法律(宅建業法・賃貸管理業法・建築基準法など)
・金融(ローンや金利の仕組みなど)
・建築(建築材や防災に関する知識)
・会計・簿記(帳簿付けの基本・税金の知識など)
・リスクマネジメント(空室対策、建物管理など)
を中心に、それぞれの分野ごとに分けて徐々に知識を身に付けるといいでしょう。最初から難しいことを理解する必要はないので、各分野の基本的な内容から学習することをおすすめします。
勉強方法は書籍、スクール、Web、セミナーなどの活用が便利。特にコスパがいいのは書籍や不動産投資の専門サイトです。
当サイトの『賃貸経営HACK』でも不動産投資に関する情報を一通り網羅しておりますので、一通りお読みいただくと効率よく不動産投資について学ぶことができます。
これから不動産投資を始めたい方は、まずはこちらの記事で不動産投資の基礎を学びましょう。
■賃貸経営・不動産投資・収益物件・アパート経営・マンション経営に関連する記事
アパート購入と賃貸経営の流れ! アパート経営成功のポイント【保存版】
失敗しない不動産投資の秘訣とは?メリットとリスクを徹底検証!
【必読】不動産投資の初心者向けに基礎知識を網羅!注意点も徹底解説
【マンション経営入門】失敗から学ぶマンション経営成功のポイント
【保存版】不動産投資の損益分岐点で着目するポイントは運用と売却!
自己資金を貯める

不動産は高額ですから、基本的に自己資金だけで購入費用を調達できません。ほとんどのケースで、アパートローンなどの融資を受けて収益物件を購入します。ただ、投資家としての実績のないオーナー様の場合、頭金なしでいきなりフルローンを受けることは難しいのが実情です。ある程度の自己資金を準備したうえで、金融機関からの借入れを申し込むことになります。
頭金の相場は物件価格の10~30%ほどですが、自己資金は頭金以外にも必要です。例えば突発的な修繕工事・リフォーム工事費用。安めの築古物件を購入したにもかかわらず、結局リフォーム費用がかさんでしまい、持ち出し費用が増えてしまうケースも少なくありません。
したがって、頭金ギリギリではなく、多少余裕をもって予算を組めるだけの自己資金を準備することが重要です。そのためには、まず現金を貯めることが最優先。お金が貯まるまでの時間は不動産投資の勉強に充てましょう。資金集めと勉強を並行して行えば、収益物件を購入する段階で十分知識のついた状態からスタートできます。
自己資金の貯め方、資金計画の立て方についてはこちらでも詳しく解説していますので、ぜひ参考にお読みください。
■投資用不動産・収益物件の資金計画・出口戦略に関連する記事
アパート経営に必要な自己資金はいくら? 成功に導く出口戦略と資金計画
収益物件購入のための情報収集
不動産投資の目的を決め、基本的な知識が十分身に付いてきたら、収益物件についての情報収集を始めましょう。ここでは具体的に希望する収益物件のスペックにフォーカスし、マクロな情報とミクロな情報を取り入れながら、多角的に情報を集めます。
例えば購入したい立地が決まったのなら、その地域で売りに出ている物件をリストアップし、家賃相場ごとに比較してみます。希望する家賃収入が得られそうな地域といった観点から、条件に合う物件を絞り込んでみるのも上手な探し方です。
大まかな立地や家賃相場の傾向をつかんだら、具体的に購入したい物件も探しましょう。物件情報は「健美家」や「楽待」などの収益物件ポータルサイト、不動産会社からの紹介などで集めると効率的です。
住宅情報サイト(SUUMO・HOME‘S・at-home)も利用できます。圧倒的な物件情報数があり、検索画面なども使いやすく工夫されていて、収益物件にも役立ちます。
収益物件を買うまでの流れ
収益物件を買うまでの流れについて解説しましょう。ここでは、中古の一棟アパート・マンションを購入するケースを想定します。
物件の現地調査・内見を行う
購入したい物件が出てきたら、不動産仲介会社に連絡を取り、その物件に関する現地調査や内見をさせてもらいます。特に立地や周辺環境については、実際に足を運んで確かめます。地図上ではわからない細かな生活動線や入居者様の様子、周辺からの騒音、車の乗り入れ状況などを把握するためです。現地で注目するポイントを挙げておきましょう。
・共用部分の管理状況(郵便受けや駐車場、駐輪場などもチェック)
・建物のメンテナンス状態(外壁や雨樋、配管など)
・日当たり(周囲の建物の影になっていないかなど)
・コンビニや郵便局、スーパー、駅からの動線
・建物周りの環境、治安状況
空室があって室内を見られる場合は、内装や水回りを中心に設備状況などもしっかり見ておきましょう。また、レントロール(賃貸借条件一覧表)を取り寄せ、入居者様の属性、家賃の支払い状況なども確認し、入居者様に何か問題がないかも確かめなければなりません。
物件の購入申し込みをする
購入したい物件が決まったら、不動産仲介会社に買付申込書を提出します。買付申込書とは売主様に対して購入意思を示すもので、購入したい物件の名称、所在地、買付希望金額、支払方法などを記載し、署名・捺印をして作成します。
買付申込書は契約書ではなく、あくまでも買付けの条件を相手方に示して購入意思を示すための書類です。手付金の有無、値引き交渉の条件、ローン特約(ローンが下りたら買付るなどの特約)などの条件があれば、買付申込書ですべて提示します。
なお、買付申し込み後のキャンセルは可能ですが、理由もなくキャンセルとすると先方だけでなく不動産仲介会社にも迷惑がかかるのでお気をつけください。
買付けの申し込みで注意したいのが「スピード感」です。人気物件だと数日も経たないうちに複数の買付けが入ることも少なくありません。希望通りの物件が現れたら即買付けるくらいの行動力が求められますので、普段から購入条件の絞り込みや資金調達の準備を整えておくことが大切です。
不動産投資ローンの事前審査を受ける
買付申込書を提出したら、金融機関に対し不動産投資ローンの事前審査の申し込みをします。現段階で手に入る物件情報資料(地図やレントロールなど)、事業計画書、自分の年収確認資料や資産情報、本人確認情報などの必要書類を準備します。事前審査といえどもほぼ本審査と同じ内容です。
実質的にローンが下りるかどうかは事前審査の段階で決まるといっても過言ではありません。必要な準備はすべて整えたうえで、本審査のつもりで審査に臨みます。
また、同一条件であっても審査に通る金融機関と通らない金融機関がありますので、複数の金融機関に事前審査を申し込むこともおすすめです。事前審査段階なら複数の金融機関に相談してもかまいません。提示される融資額や諸条件を金融機関ごとで比較してみましょう。
不動産投資ローンの審査基準について、注意点や住宅ローンの違いなどを知りたい方はこちらの記事をぜひお読みください。
■投資用不動産・収益物件の不動産投資ローン(アパートローン)の関連記事
不動産投資ローンと住宅ローンの違い!審査基準や注意点を徹底解説
不動産売買契約を結ぶ

売買交渉が成立したら不動産売買契約書の締結です。売買契約に際しては、宅地建物取引士から重要事項説明があります。いずれも収益に直結する重要な内容が含まれているので、中身をしっかり読んでおくことが大事。後から契約内容や物件設備について知らないことがあると困りますから、少しでも疑問点があればその場で積極的に質問しましょう。
特に問題点がなければ、いよいよ契約書の締結です。ここで手付金を支払います。通常、手付金は売買価格の5~10%ほどで、ほとんどが現金払いです。
また、万が一融資が下りなかった場合に備えて「融資特約」も結んでおきます。融資特約とは融資が通らなかった際に売買契約を解除できる特約のこと。融資が下りなかったにもかかわらず購入代金を支払わなければならないリスクを回避できます。
賃貸管理会社を選ぶ
不動産の運用が始まるまでの間に、パートナーとなる賃貸管理会社を選びましょう。オーナー様自ら物件を管理することも可能ですが、管理物件の規模が大きくなればなるほど膨大な業務量と高い専門性を要求されます。
現実的には賃貸管理会社に物件運用をおまかせすることになるので、ここでの会社選びはきわめて重要です。パートナーとなる賃貸管理会社の能力次第で、入居者様の満足度や収益効率はかなり変わってきます。
ただ、賃貸管理会社と一言で言っても、その得意分野や業務への取り組み方は会社によって千差万別です。会社を選ぶときは、管理実績や会社としての専門性や強みにも注目してください。できれば実際に担当者と会ってみて、会社の雰囲気や希望するサービスを提供してくれそうかどうかも吟味してみましょう。
■投資用不動産・収益物件の管理会社の選び方に関連する記事
【必読】賃貸管理会社の選び方!運用益と出口戦略を見据える賃貸管理
【賃貸管理会社】大手と地域密着型のどっちがおすすめ?選び方とは
賃貸経営を成功に導く不動産管理とは? 信頼できる管理会社の選び方を解説
不動産投資ローンの本審査を受ける
事前審査の段階で融資が下りるかどうかはほぼ決定していますが、本審査の開始は売買契約の締結後です。事前審査時の提出書類に加えて、不動産売買契約書や実印、印鑑証明書なども提出します。本審査の期間はおよそ2週間ほどです。審査が通ると金銭消費貸借契約(ローン契約)を締結します。必要な場合は団体信用生命保険(団信)の加入なども行います。
融資実行が決まれば金利や返済期間、そのほかの特約の条件なども変えられないので、疑問点などは事前審査時に解消しておきましょう。
物件の引渡し
ローンの実行と購入残代金の決済、物件の引渡し、登記手続きは、基本的に同日に行います。場所は金融機関の一室で行うのが一般的です。売主様と買主様、金融機関の担当者、不動産仲介会社、司法書士の立会いのもと、売主様と買主様の意思確認と本人確認を行い、ローンが実行されます。その後、司法書士が所有権移転登記、抵当権設定登記などを行います。
決済がすむと物件に関する書類、鍵、設備の保証書などの一式を受け取り、物件の引き渡しは完了です。一連の手続きが終わると、購入したアパート・マンションは晴れてオーナー様の所有物となります。
収益物件購入時にかかる諸費用
収益物件の購入では購入価格以外にもさまざまな費用がかかります。予想よりも大きな金額となることが多いので、どのような費用が必要なのかしっかり把握しておきましょう。
不動産仲介手数料
物件を購入する際に不動産会社に仲介してもらった場合は不動産仲介手数料を支払います。仲介手数料は法律で上限額が決まっていますので、上限を超えて請求されることはありません。計算式は次の通りです。
不動産仲介手数料の上限(物件価格400万円超の場合)
(物件価格×3%+6万円)×消費税率(1.1)
例えば物件価格4,000万円の中古アパート一棟を購入したとすると、
仲介手数料の上限は
(4,000万円×0.03+6万円)×1.1=138万6,000円
となります。
仲介手数料は上限額の範囲内で不動産仲介会社が設定します。通常は上限額いっぱいの手数料設定となることがほとんどです。
登記費用

不動産の購入では主に2種類の登記が必要と理解しておきましょう。まず、不動産を取得して所有権を手に入れたことを示す所有権移転登記です。
所有権移転登記の申請時には国に「登録免許税」を納めます。登録免許税額の計算は次の通りです。
不動産移転登記の登録免許税額
【土地部分】
不動産の固定資産税評価額×1.5%
【建物部分】
不動産の固定資産税評価額×2.0%
もう1つ必要なのが不動産投資ローンの債権を担保する抵当権の設定登記です。こちらの税率は次のようになります。
抵当権設定登記の登録免許税額
債権額×0.4%
これに加え、申請の代理を依頼する司法書士に対する報酬が発生します。司法書士によって報酬設定は変わりますが、だいたいは5~10万円前後といったところです。
印紙税
不動産取引などで作成する契約書などは「課税文書」といわれ、取引時に収入印紙を貼る形で課税されます。
課税額に関しては2024年3月31日までの作成文書に対して軽減率が適用されます。主な税額は次の通りです。

印紙代は売主様と買主様で平等負担となるのが通例です。なお、売買契約書を紙ではなく電子契約で行った場合、印紙税がかかりません。今後は電子契約が広がる可能性もありますので、予備知識として押さえておきましょう。
固定資産税・都市計画税(日割り)
中古物件の場合は、売主様と買主様で固定資産税・都市計画税を日割りで折半するのが一般的です。固定資産税は各年度1月1日時点で不動産を保有する方に対して課税されます。多くのケースでは、引き渡しを基準に1月1日から引き渡し日までを売主、引渡し日以降を買主で固定資産税・都市計画税を日割り計算します。
ちなみに折半方法はあくまでも売主様と買主様の契約で決まるので、どちらか一方が全額負担しても構いません。固定資産税・都市計画税の納税額は不動産所得に計上し、必要経費として処理できます。
不動産取得税
不動産購入時に1回だけかかる地方税です。税額は固定資産税評価額をベースに計算します。
不動産取得税の税率(原則)
宅地の固定資産税評価額×4%
建物の固定資産税評価額×4%
なお、宅地や宅地と評価を受けた土地、住宅については軽減措置が取られています。2024年度の税制改正で2026年3月31日までに取得した不動産が対象となりました。
軽減措置適用後の税率
宅地の固定資産税評価額×1/2×3%
住宅の固定資産税評価額×3%
火災保険料
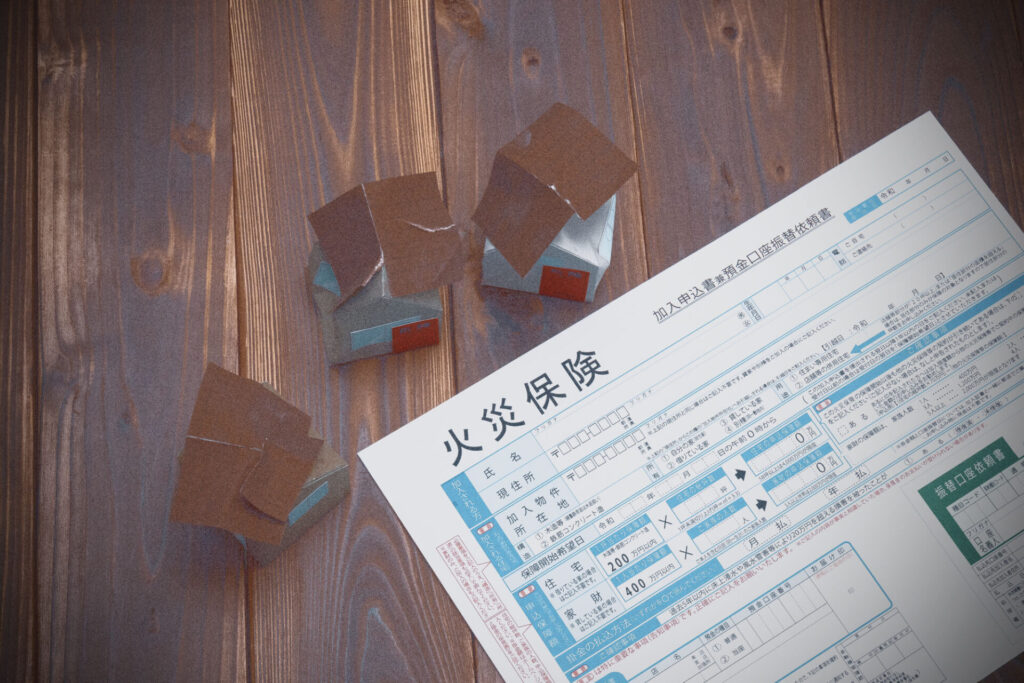
通常のワンルームマンションの購入での火災保険料は、各種オプションに地震保険を追加したとしても年間2~3万円程度です。しかし、一棟アパート・マンションといった規模になると火災保険料は無視できない金額となってきます。
一般的に一棟アパートでの火災保険料は年間10~15万円ほどです。もちろん、火災保険料は保険会社や追加オプションの有無によってもかなり差が出ますので、あくまでも参考程度とお考えください。
火災保険料は補償内容をよく確認して内容を決めることが大事です。中身を気にせずコストだけにこだわってしまうと、いざという時に必要な補償が出ないなどの不測の事態も考えられます。立地から考えられる個別リスクにきちんと対応できるよう、各保険内容をよく比較し、内容重視で選びましょう。
ローンに関連する諸費用
不動産投資ローンを設定するときにかかる費用には事務手数料、ローン保証料、金銭消費貸借契約にかかる印紙代などがあります。一般的な相場としては、ロ―ン手数料は借入金額の1~3%ほどです。保証料に関しては保証会社に別途保証料を払う方式と、金融機関にローン手数料を払って金融機関に保証料を負担してもらう方式があります。
また、ローン設定に関連する費用としては先ほど解説した抵当権設定に関する登記費用、ローン契約書(金銭消費貸借契約書)にかかる印紙税なども必要です。ローン設定時に団体信用生命保険(団信)に加入する場合はその保険料もかかります。
なお、ローン手数料や保証料、団信の保険料などはローン金利に上乗せするかたちで負担するケースも多く、コスパ良く運用するにはローンの組み方についてしっかり学ぶ必要があります。
こちらの記事では不動産投資での利回りやローンの組み方についても細かく解説していますので、合わせてお読みください。
■投資用不動産・収益物件の利回りやローンの組み方に関連する記事
【徹底解説】不動産投資の利回り計算! 賃貸経営を成功に導く指標とは
【総集編】アパート経営の利回りの目安は?不動産投資の指標と注意点
アパートローンを上手に利用するコツと注意点|住宅ローンとの違いは?
まとめ

収益物件選びは不動産投資での成功を大きく左右します。しっかりとした情報収入を継続することで、希望に合った物件が見つかる可能性は高くなるでしょう。そして、万全の準備が整ったら迅速に行動することも大切。いい物件は常に競争相手がいますし、運用や売却に関しても素早く判断する局面が増えてきます。
このように高い専門知識や経験のもとで的確な判断を行うためには、パートナーとなる専門家や不動産会社の存在が不可欠です。物件探しから賃貸管理、売却や相続などの出口前略までを一気通貫で提供してもらえるパートナーがいればなお心強いでしょう。
【リロの不動産】は安定した収益拡大を目指すオーナー様にとってのベストパートナー。日本トップクラスの管理実績のもと、全国各地でオーナー様の賃貸経営をサポートしております。不動産投資に関して少しでもわからない点がございましたら、ぜひ一度【リロの不動産】までご相談ください。
関連する記事はこちら
失敗しない不動産投資の秘訣とは?メリットとリスクを徹底検証!
アパート購入と賃貸経営の流れ! アパート経営成功のポイント【保存版】
賃貸マンションの一棟買いはあり? アパート経営・区分マンション経営との徹底比較
マンション一棟買いの成功ポイントと指標にする利回り!メリット・デメリットや注意点
木造一棟アパートの購入から始める不動産投資!メリット・デメリットと投資戦略
アパート一棟買い・マンション一棟買いを数字で判断!一棟投資成功に向けたポイントを解説
土地購入から始めるアパート経営!土地選びの方法や注意点を徹底解説
現金一括購入とローン活用によるアパート経営の違い!不動産投資判断のポイントを解説
アパート購入費用はいくら? アパート経営の費用と注意点を徹底解剖
賃貸アパートの値段はいくら? 一棟買いのメリットと不動産投資ローンの基本を解説
収益物件購入時の注意点とは? 収益物件の種類とリスクへの対策を解説
【事例付】中古アパートを購入するときの注意点と対策を事例と一緒に徹底解説
おすすめのサービス
おすすめのお役立ち情報
この記事を書いた人
秋山領祐(編集長)
秋山領祐(編集長)
【生年月日】昭和55年10月28日。
【出身地】長野県上田市。
【趣味】子供を見守ること。料理。キャンプ。神社仏閣。
【担当・経験】
デジタルマーケティングとリブランディングを担当。
分譲地開発のPMや家業の土地活用などの経験を持つ。
リノベした自宅の縁の下に子ども達の夢が描かれている。





















