家賃収入は副業になる? 不動産投資で副収入を得る方法と投資規模別のリスクを解説
2025.11.13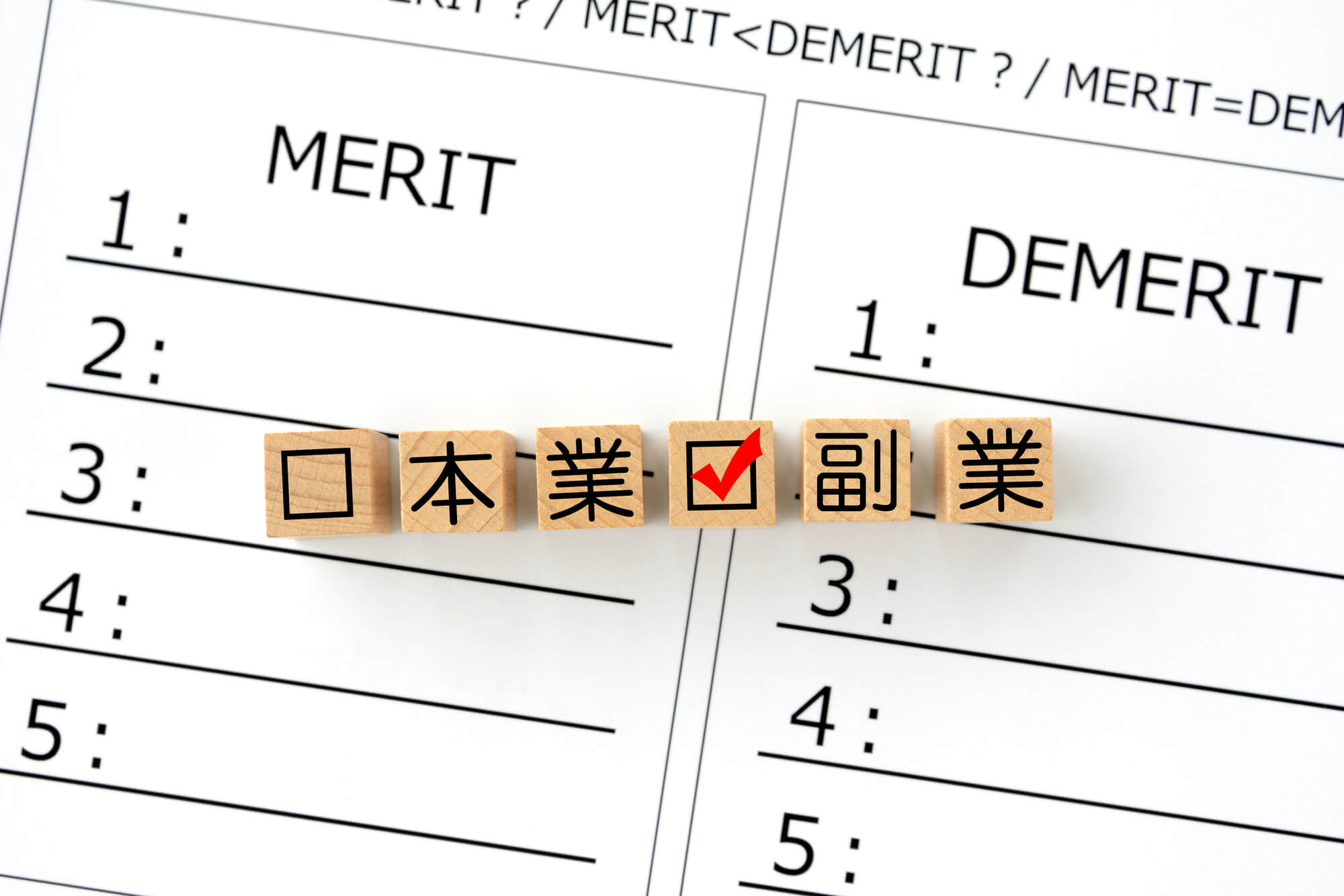
会社員や公務員として本業がある方でも、相続でマンションやアパートなどの収益物件を取得することがあります。また、突然の転勤でマイホームを離れることになり、借家として貸し出して家賃収入を得るケースもあり得ます。
ただ、公務員であったり、副業禁止の会社に勤めている方の場合、家賃収入が副業に該当するのかどうか、心配になることがあるのではないでしょうか。この記事では家賃収入と副業について、副業を取り巻く状況も交えて詳しく解説します。
▼この記事の内容
●家賃収入が副業に該当するかは、会社によって見解が異なる。不動産投資は副業には当たらないとする会社が多いが、認めない会社もあるため、会社の就業規則を確認する。
●働き方改革の一環として、副業解禁の流れが強くなってきている。原則として、日本国憲法では国民に職業選択の自由を保障している。ただし、公務員は法律上の制限がある。
●会社に副業が発覚する原因としては、住民税の通知が行った、確定申告をしなかった、副業を同僚・上司などに話した、などがある。
●副業として家賃収入を得るメリットとしては、安定した収入を得られる、融資が有利になる可能性、賃貸管理会社に委託することで本業に支障はない、節税を行いながら資産形成ができる、生命保険代わりになる、インフレに強い資産を得られる、相続税対策として有効がある。
●家賃収入を副業とするリスクとしては、空室リスク、家賃滞納リスク・入居者信用リスク、修繕リスクなどがある。
目次
家賃収入は副業になるのか
そもそも家賃収入が副業に該当するかについては、一概に断言できません。勤務している会社によって、副業をどう規定しているかが異なるからです。
会社の就業規則を確認する

副業の捉えかたについては、会社によって見解が異なります。副業を認める、認めないの判断も会社次第であるため、まずは会社の就業規則を確認しましょう。会社が副業を認めていれば問題はありません。
そもそも副業を持つこと自体は法律などで禁止されているわけではなく、あくまでも会社がそれぞれ基準を決め、就業規則で定めているに過ぎないからです。何をもって副業とするのかは各社の考え方によります。
副業を一切認めていないところもあれば、一定の規模までなら認めているところもあります。副業が認められていたとしても、実際に行う場合に申請する必要があるのかどうかも、確認しておかなければならないでしょう。
就業規則を確認しても判断がつなかいようならば、自分が行おうとしている内容が副業にあたるのかどうか、どのくらいの規模ならば大丈夫なのかなど、あらかじめ会社に相談してください。特に公務員や金融機関などは、副業に関しての規定が厳しいケースが多いため要注意です。
家賃収入は副業に当たらないケースが多い
結論からいうと、不動産投資によって得る家賃収入は副業には当たらないとする会社が多い傾向です。企業が副業を禁止する理由には、安全配慮義務や秘密保持義務、競業避止義務などが根幹にあると考えられます。会社は社員が安全かつ健康に働けるよう配慮する義務を負っています。
しかし、社員が副業を行うことで本業に影響をおよぼす事態になった場合、本人だけの問題にとどまらず、会社やほかの社員の安全が図れない状況にもなりかねません。
また、会社にとって自社が持つノウハウなどが外部に漏れることは大きな問題です。特に業務に関連する副業は情報漏洩のリスクが高く、意識していなくても起こる可能性があります。そのため経営側の判断として、副業の禁止はリスクを回避するための方法として妥当です。会社の不利益になる行為を行わないようにするために、就業規則で競業避止義務を定めている場合もあります。
不動産投資や賃貸経営については、これらの義務には該当しないとするところがほとんどです。ただし、本業に支障がでることを考慮して事業規模を問題にする会社もあります。就業規則だけでは判断が難しい場合、会社の法務部門に問い合わせてみるといいでしょう。
社会で進む副業解禁の流れ
これまでは副業を禁止している企業が多かったのですが、現在では副業解禁の流れが強くなってきています。次に、副業解禁が進んでいる理由と公務員の副業について解説します。
働き方改革の一環として

副業解禁を後押ししている理由のひとつが働き方改革です。2018年に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立し、政府はさまざまな取り組みを進めています。その一環として推進しているのが副業の解禁です。
厚生労働省は「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を策定し、2022年には改訂版が発表されました。ガイドラインでは副業・兼業促進の方向性や企業の対応、労働者の対応などが示されています。労働者が副業を通じてスキルや経験を得ることで、主体的にキャリアを形成できるとされている点がポイントのひとつです。
労働者にとっては離職せずに副業ができることで、経済的なリスクを負わずにやりたいことにチャレンジできるメリットがあります。副業することで新たな知識を得たり、スキルを磨いたりできれば、キャリアの幅も広がるでしょう。
会社側にとっても社員が辞めてしまうことを防ぎ、定着率をアップさせられるなど、労働力の確保にも有効です。副業・兼業で得た知識やスキルが本業に還元されれば、会社にとってもプラスになります。実際に副業・兼業する際は留意する点があるものの、基本的に会社は副業・兼業を認める方向が適当だとされているのがポイントです。
憲法は職業選択の自由を保障している
従来は多くの企業が副業や兼業を禁止してきましたが、憲法で社員の副業が認められていることが副業解禁の根拠のひとつになります。日本国憲法の第22条1項では「何人も、公共の福祉に反しないかぎり、居住、移転及び職業選択の自由を有する」と謳われています。
日本国憲法で職業を自由に選択することが保障されているということは、副業を持って複数の職業に就くことも基本的に認められるべきということです。実際に、副業は法律で禁止されているわけではありません。
一般的に副業が禁止されているのは、あくまでも安全配慮義務や秘密保持義務、競業避止義務などを理由として、会社が独自に就業規則で定めているだけです。憲法の解釈によれば、就業時間外などで本業に支障をきたさないのであれば、副業を行うのは個人の自由です。
ただ、会社側にとっても社員が副業をすることでリスクになるようなことは避けなければならないため、これまでは就業規則で副業に関して禁止とするところが少なくありませんでした。
働き方改革の推進もあり、徐々に社員の副業を認める会社が増えています。ただし、後述するように公務員は民間企業とは違い、副業や兼業に関しては法律で一定の制限があります。
公務員は法律上の制限がある
民間企業に勤務する会社員の場合は、憲法で職業選択の自由が認められています。しかし、公務員は国家公務員法や地方公務員法によって副業には法律上の制限があるため、家賃収入を得るような不動産投資を行う際は注意が必要です。
国や地方自治体の職務は国民や住民の信頼があってこそ成り立つものであることから、公務員には守秘義務や職務に専念する義務、私企業からの隔離などが法律で規定されています。それらの法律を根拠に、公務員の副業には制限があります。
人事院規則14-8によると、不動産の賃貸に関しては5棟10室以上、独立家屋以外の建物では居室数が10室以上、家賃収入の年間金額が500万円以上ある場合は営利を主目的とした副業と判断されます。言い換えれば、4棟9室まで、家賃収入の年間金額が500万円未満なら、公務員でも家賃収入を得ることが可能です。
規模が大きいケースでも、収益物件を相続した場合や転勤などでやむを得ず自宅を賃貸に出す場合などは、申請すれば認められるケースがあります。
公務員の不動産投資については、こちらもご参照ください。
公務員はアパート経営できる? 公務員が不動産投資を始める意外なメリット
公務員の副業に不動産投資は向いているのか?メリットと注意点を解説!
公務員の副業はなぜ禁止?できる範囲と不動産投資が公務員に有利な理由
会社に副業が発覚する原因
就業規則で副業が禁止されている会社に勤めていても、どうしても副業をしたいのであれば、会社に内緒で副業を行うことになります。会社に副業が発覚する原因は、おおよそ以下の3点になります。
住民税の通知
所得税を源泉徴収されている給与所得者の場合、多くは住民税も会社で天引きされています。源泉徴収された所得税は税務署に、天引きされた住民税は市区町村に、会社がそれぞれ納めているため、会社員は自分で手続きをする必要がありません。
住民税の税額は前年の所得の額によって決まります。副業によって所得が増えれば住民税も高くなるため、結果的に会社側に発覚するきっかけになります。不審に思った経理担当者などに事情を聞かれることもあり得るでしょう。
住民税の徴収方法には、会社で天引きされる「特別徴収」以外に「普通徴収」という方法もあります。普通徴収では、市区町村が発行する納付通知書にしたがって自分で住民税を納付することになります。納付のタイミングは年4回となります。
住民税の納付方法を普通徴収に変更することで、住民税の金額が変わっても会社には知られないことになります。変更方法は、確定申告時に「主給与以外の所得を普通徴収で支払う」の欄にチェックを入れるだけです。
ただし、給与所得者は特別徴収が一般的なため、市町村のほうで点検漏れが発生することもありえます。念のため、市町村の担当部署に電話を入れておくと完璧です。
確定申告をしなかった
副業によって本業とは別に所得を得ながら確定申告をしないでいると、税務署から勤務先に問い合わせが入ることもあります。会社員の場合は、年間で20万円を超える所得があれば、確定申告をしなければなりません。
無申告のまま追徴課税にも応じないでいると会社に連絡がいき、副業が発覚することがあります。もし、就業規則で副業を禁止している会社ならば、降格処分や減給、訓戒などの処分が下される可能性があります。
大前提として、一定の所得を得ているならば、適正な納税を行うことは国民の義務となります。副業の収入が発覚するのを恐れて、申告しないのは法律違反になる可能性もあります。万が一、申告漏れが発生する場合は追徴課税が課されるなど、法的にもペナルティを負うことになりかねません。
なお、確定申告が必要になる所得20万円を超える金額とは、家賃収入などの売上から物件の運営に関わる減価償却費や固定資産税などの経費を差し引いた金額です。例えば、家賃収入が23万円あったとしても、かかった費用が5万円なら差し引きは18万円になります。この場合は20万円以下にとどまっているため、確定申告の必要はありません。
副業を同僚・上司などに話した

実は意外と多いのが、副業していることを同僚や上司などに話したことで発覚するケースです。賃貸経営が軌道に乗って家賃収入が増えてくると、嬉しくなったり気持ちが大きくなったりして、つい周囲の人間に自慢してしまうことがあります。
話を聞いているときは和やかに会話を楽しんでいるように見えても、実は自慢話を不愉快に思っているかもしれません。思わぬ妬みから告げ口をされて発覚することもあるため、信頼している相手であっても簡単に話さないほうがいいでしょう。
また、直接話した相手は内緒にしてくれていたとしても、実は近くで偶然耳にしてしまった人が噂を広めてしまう可能性も捨てきれません。「人の口に戸は立てられぬ」という言葉があるように、一度広まってしまった噂が予期しない事態を招くことも考えられます。
近年ではSNSへの投稿も注意が必要なところです。匿名ならば大丈夫だろうと考えるかもしれませんが、油断していると身元が発覚することもあります。就業規則に違反しない範囲で副業をするのであれば問題ありませんが、そうではない場合は副業を行っていることを話すのは避けておきましょう。
不動産収入は副収入として最適
不動産の運用で得た収入は、本業を持っている方の副収入として最適です。その理由として主に以下の3つが挙げられます。
安定した収入を得られる

賃貸経営が軌道に乗れば、長期にわたって安定的に家賃収入を得られます。本業とは別の収入源を確保しておくことで、何か想定外のことが起こったときのためにも備えられるでしょう。
同じ不動産投資でもオフィスビルなどのような事業系の物件の場合は、景気の影響を受けやすく、テナントとして入居している企業の経営判断によって短期での撤退は日常茶飯事といえます。また、一度空室が発生すると、長期間埋まらないという状況も珍しくありません。
一方で、アパートやマンションなど住居系の物件は景気に左右されることが少なく、比較的安定した経営が可能です。入居者様にとっては生活の基盤となる場所であるため、劇的に外部環境が変わらないかぎり短期間で退去することはありません。入居者様の入れ替わりで短期間空室が発生することはありますが、堅実に経営を行っていれば継続して家賃が入ってきます。
融資が有利になる可能性
自己資金のみで不動産投資を行う方もいますが、大きなお金が動く不動産投資は金融機関からの融資を活用して行うのがスタンダードな手法になります。不動産を購入する際に、マイホームを購入するときに利用する住宅ローンではなく、不動産投資の場合は不動産投資ローン(アパートローン)という事業用のローンに申し込むことになります。
融資する側の金融機関にとっては、融資した金額分が滞りなく回収できるかどうかが大事なポイントになります。ローン返済の原資が賃貸経営の収益に関わってくるため、物件の資産価値や収益性も審査の対象になります。
事業用ローンである不動産投資ローンは住宅ローンに比べて審査項目が多く、住宅ローンに比べると審査のハードルは高いのが特徴です。賃貸経営の収益性以外にも、年収や資産、勤務先や勤続年数など、本人の属性も重視されます。
安定した職業に就いている会社員や公務員が不動産投資を行う場合、金融機関の属性評価が高くなる可能性があります。年収が高い、保有する金融資産がある、上場企業に勤めているなどの条件があれば、融資の審査が有利に働く可能性が高くなります。
賃貸管理会社に委託することで本業に支障はない
副業を行ううえで、本業への支障を心配している方もいるでしょう。確かに、所有している物件の管理を自ら行おうとすれば、かなりの労力がかかります。
例えば、設備に不具合が発生すれば、修理の手配などを行う必要があります。入居者様とも連絡を取り、作業できる日程の調整もしなければなりません。空室が出た際の募集業務は、ノウハウがなければ新たな入居者様を見つけるのが難しい可能性があります。家賃の滞納が発生したときの督促も、適切な対応をしなければトラブルになることもあり得ます。
公務員の場合は、自分で所有している物件といえども、自主管理をすると職務専念義務違反になります。
手間のかかる管理業務を信頼できる賃貸管理会社に委託すれば、本業に支障をきたすことなく不動産投資が可能です。管理手数料はかかるものの、ノウハウを持ったプロに任せることで適切に管理でき、賃貸経営や不動産投資のリスク対策を任せられるのは大きなメリットと言えます。
節税を行いながら資産形成ができる

高所得の方は毎年納める税金も高額になるため、不動産投資による節税が可能です。副業として賃貸経営を行っている方の場合、会社員ならば給与所得、自分で事業を行っている方ならば事業所得など、本業による収入があるでしょう。
不動産投資で得た所得は、給与所得や事業所得など他の所得と損益通算できます。もし、賃貸経営で赤字が出た場合は本業の所得から赤字分を差し引けるため、所得税の圧縮が可能です。
特に物件を購入した初年度はさまざまな初期費用がかかります。また、減価償却を計上している間も帳簿上赤字になるケースが多く、節税の効果が期待できます。減価償却は不動産のように何年も使用でき、かつ高価なものを購入した際、何年かに分けて費用計上する仕組みです。
減価償却費は帳簿上、費用として計上されますが、実際にお金が出ていくわけではありません。帳簿上は赤字になっていても実際には手元に残る分があるため、節税しながら資産形成できるのが魅力です。
生命保険代わりになる
不動産投資ローンを活用すると、団体信用生命保険(団信)に加入できるのもメリットのひとつです。不動産投資ローンは数十年など、ある程度まとまった期間で組むため、ローンの返済期間中に不測の事態に陥らないとはかぎりません。
団信に加入していると、契約者が死亡または高度障害を負った場合、その時点の残債が完済される仕組みになっています。保険料は利息に組み込まれていることが一般的なため、別途保険料の支払いが発生することはありません。
団信に加入していればオーナー様に万が一のことがあったとしても、相続人にローンが完済された状態の収益物件を遺すことが可能です。遺族に不動産という資産を遺せる団信は、生命保険の代替手段となります。
インフレに強い資産を得られる

アパートやマンションなどの不動産は実物資産であり、インフレに強いとされています。インフレが進むと、現金の実質価値はどんどん下がっていきます。
例えば、インフレで物価が10%上昇すると、1,000円で買えた商品が1,100円に上がり、逆に現金の実質価値は10%下落します。現在の超低金利下、預貯金の金利では物価上昇率に追いつくことができません。現金や預貯金はインフレの進行によって、実質価値が目減りするのです。
一方で、不動産は物価の上昇で物件価格が上がり、大きく下落するリスクが少なくなります。家賃上昇の流れも生まれており、事実好立地の収益物件では家賃上昇が続いています。
このように、不動産を保有しているとインフレ耐性を備えた資産形成が可能なのです。
相続税対策として有効
将来相続が発生した際、不動産を保有していることで相続税の節税に役立つのもメリットです。現金が課税対象になる場合、相続税の計算は現金の金額100%が相続税評価額となります。
一方、不動産の場合は現金とは異なり、土地は相続税路線価によって、建物は固定資産税評価額によって定められます。相続税路線価・固定資産税評価額ともに時価よりも低く設定されているのです。なお、相続税路線価が定められていない地域では、固定資産税評価額に一定の倍率をかけた評価がなされます。
賃貸アパート・賃貸マンションには借地権割合・借家権割合・賃貸割合が適用されるため、相続税評価額がさらに減額される仕組みもあります。
不動産投資の成功確立を高める記事については、こちらもご参照ください。
【必読】不動産投資・賃貸経営の目的が明確なほど成功確率が上がる理由
【完全ガイド】賃貸経営の成功法則!不動産投資で稼ぐための全知識
【徹底解説】不動産投資の利回り計算! 賃貸経営を成功に導く指標とは
【事例付】アパート経営の成功率とは? 賃貸経営の手順とリスク対策
【総集編】アパート経営の利回りの目安は?不動産投資の指標と注意点
家賃収入を副業とするリスク
不動産投資で家賃収入を得る場合は特有のリスクがあるため、副業として行う際はリスク管理が不可欠です。ここでは、空室リスク、家賃滞納リスク・入居者信用リスク、修繕リスクという不動産投資で重要な3つの視点から解説します。
アパート経営や不動産投資のリスクについては、こちらもご参照ください。
アパート経営のリスク完全ガイド!失敗を防ぐ対策を成功事例で徹底解説
不動産投資のリスクとは? リスクを正しく認識すればヘッジはできる
空室リスク
空室リスクは、不動産投資最大のリスクといえるものです。賃貸アパートや賃貸マンションなどの収益物件は、ある程度入居者様が入れ替わるのは避けられないため、空室が発生してもすぐに新たな入居者様が決まれば大きな問題にはなりません。
しかし、空室であっても、物件を維持するための管理費用やローン返済は発生し続けます。万が一、空室が多数・長期間埋まらない状態が続くと家賃収入は大きく下落し、賃貸経営の悪化につながります。
空室リスクを減らすためには、投資先の物件を選定する際に賃貸需要のある地域かどうか、交通や生活の利便性がいいかどうかなどを見極める必要があります。単身者向けに需要があるのか、ファミリー層が多いのかなど地域の賃貸需要動向を把握したうえで、物件の選定と入居者募集の戦略が必要とされます。
空室の改善事例については、こちらもご参照ください。
家賃滞納リスク・入居者信用リスク
賃貸経営では、入居者様の家賃滞納も賃貸経営に大きな影響を与えるリスクになります。形の上では満室経営であっても、滞納されると家賃収入が得られません。借地借家法上、家賃を滞納しているからといってただちに退去してもらうのは不可能なため、家賃の回収に時間や手間をかけなければならないのは大きな負担です。
また、近隣に迷惑をかける方が入居してしまう入居者信用リスクもあります。騒音を発生させる、ゴミ出しのルールを守らないなど、たった一人の入居者様のマナー違反でも、ほかの入居者様が退去してしまうケースもあるのです。
家賃滞納リスクや入居者信用リスクを避けるためには、家賃保証会社の利用や入居審査の厳格化など、適切な対応を取る必要があります。
家賃滞納リスク・入居者信用リスクについては、こちらもご参照ください。
修繕リスク

修繕リスクは、収益物件の修繕費が高額になってしまうリスクです。アパートやマンションなどの建物は、経年劣化が進むのは避けられません。築年数が経過するにつれて修繕の必要な箇所が増え、その都度費用が発生します。
入居者様が退去するタイミングでは原状回復工事も行われるため、入居者様の入れ替わりが多い物件ではオーナー様の負担も大きくなりがちです。突発的な修繕が必要になる事態も想定しておく必要があります。
日常的に適切な修繕やメンテナンスを行っていても、12~15年に一度は大規模修繕を実施しなければなりません。大規模修繕では一度に多大な費用がかかってくるため、あらかじめ修繕積立金を貯めていくなど、将来を見据えた資金計画を立てる必要があります。
修繕リスクについては、こちらもご参照ください。
副業として安定的に家賃収入を得るポイント
副業として安定的に家賃収入を得るためには、どのような点に気をつければいいのでしょうか。賃貸経営を成功させるために大事な3つのポイントについて、それぞれ詳しく解説します。
投資目的をはっきりさせる
不動産投資では、投資目的によって採用すべき戦略が変わってきます。不動産投資を行っているオーナー様によって、なぜ投資をするのか事情はそれぞれ違うでしょう。月々のキャッシュフロー目的なのか、老後対策として資産を構築しておきたいのか、子どもに資産を遺したいのか、節税したいのかなど、目的をはっきりさせておくことが重要です。
例えば節税が目的ならば、減価償却費を大きく取れる築古の木造一棟アパートを選び、損益通算で所得税や住民税を抑えると節税効果が高くなります。また、月々のキャッシュフローは少なくても構わないから将来に大きな資産を残したいなら、レバレッジ比率を高めてRC造一棟マンションに投資する戦略もあります。
投資目的別の不動産投資の戦略については、こちらもご参照ください。
【必読】不動産投資・賃貸経営の目的が明確なほど成功確率が上がる理由
自身のリスク許容度を確認する

ハイリスク・ハイリターンといわれる株式投資やFXとは違い、不動産投資はミドルリスク・ミドルリターンだとされています。不動産投資を行う際はオーナー様のリスク許容度を客観的に把握し、ふさわしい投資を行うことが求められます。
リスク許容度は投資家の年齢、年収、保有資産、家族構成、投資経験、性格などで決まります。例えば、年齢が若く、年収や保有資産が多い方は、多少の損失が出てもある程度カバーできるため、リスク許容度が高いとされます。一方、扶養家族が複数いて、投資経験があまりないという方はリスク許容度が低いとされます。
一見リスク許容度が高そうな条件を備えている方でも、損失やリスクに対して慎重な性格であればリスク許容度は低いかもしれません。オーナー様がどれくらいまでならマイナスが出ても受け入れられるかを確認しておいてください。
不動産投資のリスクについては、こちらもご参照ください。
資産運用の基本とは? 節税効果の高い不動産投資をおすすめする理由
不動産投資のリスクとは? リスクを正しく認識すればヘッジはできる
アパート経営のリスク完全ガイド!失敗を防ぐ対策を成功事例で徹底解説
信頼できる賃貸管理会社を味方につける
不動産投資では、信頼できる賃貸管理会社を味方につけることも重要なポイントです。アパートやマンションの管理業務はオーナー様が自分で対応するのも可能ですが、入居者管理や建物管理などをすべてオーナー様が行うのは現実的ではありません。そのため、管理業務は専門の賃貸管理会社に依頼するのが一般的です。
定型的な入居者募集業務や建物管理業務だけでなく、融資戦略や出口戦略、税金対策や相続対策まで賃貸経営をサポートしてくれる賃貸管理会社もあります。不動産投資にまつわる悩みに一気通貫で対応でき、トータルで任せられる賃貸管理会社は非常に心強い存在です。
不動産投資の成功の鍵は、信頼できるパートナーいかんにかかっています。具体的にどのくらい賃貸管理業務を行っているのか実績を確認し、信頼できる賃貸管理会社に委託しましょう。
家賃収入をシミュレーション

最後に、副業として家賃収入を得るシミュレーションを行ってみます。家賃収入を手取りで年間100万円得るケースと500万円得るケース、1,000万円得るケースの3パターンを考えてみましょう。
なお、税金に関わる部分など詳細は計算は割愛します。副業で100万円、500万円、1,000万円のキャッシュフローを得るには、どのくらいの投資規模になるかを大雑把にイメージしてもらうシミュレーションです。
家賃収入を手取りで100万円得る
中古一棟アパートを以下の条件で購入した場合のシミュレーションをしてみます。
物件価格(土地・建物):5,600万円
初期費用:400万円
想定家賃収入:504万円(表面利回り:9%)
自己資金:1,000万円
借入金:5,000万円
金利:2%(元利均等方式)
返済期間:20年間
運用経費:100万円
年間の想定家賃収入504万円から運用経費と借入金の返済額を差し引いて、年間キャッシュフローを求めます。
この物件の購入では、5,000万円を金利2%、返済期間20年で借り入れているため、まず年間の返済額を計算します。返済方法を元利均等方式とすると、元金・利息を合わせた年間の返済額は約303万円です。ここでは、日本政策金融公庫の「事業資金用 返済シミュレーション」に条件を入力して算出し、端数は省きました。
結果「504ー100-303=101(万円)」となり、年間キャッシュフローは101万円となりました。
家賃収入を手取りで500万円得る
次に中古一棟マンションを、以下の条件で購入する場合のシミュレーションです。
物件価格(土地・建物):3億円
初期費用:2,100万円
想定家賃収入:2,100万円(表面利回り:7%)
自己資金:7,100万円
借入金:2億5,000万円
金利:2%(元利均等方式)
返済期間:30年間
運用経費:450万円
この物件の購入では2億5,000万円を金利2%で借り入れているため、上記のケースと同様に年間の返済額を計算すると、1,100万円となります。
年間の想定家賃収入から運用経費と借入金返済額を差し引くと、「2,100-450-1,100=550(万円)」となり、手取りで年間500万円以上を得ることが可能です。
家賃収入を手取りで1,000万円得る
次に、中古一棟マンション2棟を以下の条件で購入した場合のシミュレーションです。
物件価格(土地・建物):6億円(3億円×2)
初期費用:4,200万円
想定家賃収入:4,080万円(表面利回り:6.8%)
自己資金:1億4,000万円
借入金:5億200万円
金利:1.8%
返済期間:30年間
運用経費:860万円
このケースでは5億2,000万円の借入金を返済期間30年、金利1.8%で返済するようになっています。返済金額をシミュレーションしてみると、年間の返済額は2,240万円となりました。
年間の想定家賃収入から運用経費と借入金返済額を差し引くと、「4,080-860-2,240=980(万円)」となります。今回のシミュレーションでは1,000万をわずかに下回っていましたが、同規模の不動産投資を行うと、ほぼ手取りで1,000万円を得られる結果となっています。
まとめ

家賃収入は多くのケースで副業に当たらないとされています。不動産投資は会社で認められている場合や、公務員が規定の制限内で行う場合、副収入を得る方法として最適です。ただし、賃貸経営を成功させて安定した副収入を得るためには、信頼できる賃貸管理会社の経営サポートを受けることが重要です。
【リロの不動産】では原状回復工事や日常的な建物の清掃・設備のメンテナンス、入居者様のサポートや空室対策、資産活用や節税対策、相続対策に至るまで、賃貸経営をトータルでサポートしています。本業に支障を出さず、適切に賃貸経営を行うためにも、【リロの不動産】におまかせください。
関連する記事はこちら
【アパート経営・賃貸経営入門】メリット・リスク・成功の秘訣をわかりやすく解説!
【マンション経営入門】失敗から学ぶマンション経営成功のポイント
不動産オーナーになる方法!仕事内容や収入、メリット・リスク、注意を解説
【保存】不動産経営の種類や収支を学ぶ!リスク回避する成功の秘訣とは?
【事例付き】地主さんが行う賃貸経営での資産の増やし方とトラブル回避術
公務員の副業はなぜ禁止?できる範囲と不動産投資が公務員に有利な理由
アパート経営の年収と暮らしとは?アパート経営の収入を上げる方法
不労所得の種類とおすすめの人を紹介! 不動産投資が選ばれる理由とは
おすすめのサービス
おすすめのお役立ち情報
この記事を書いた人
秋山領祐(編集長)
秋山領祐(編集長)
【生年月日】昭和55年10月28日。
【出身地】長野県上田市。
【趣味】子供を見守ること。料理。キャンプ。神社仏閣。
【担当・経験】
デジタルマーケティングとリブランディングを担当。
分譲地開発のPMや家業の土地活用などの経験を持つ。
リノベした自宅の縁の下に子ども達の夢が描かれている。




















